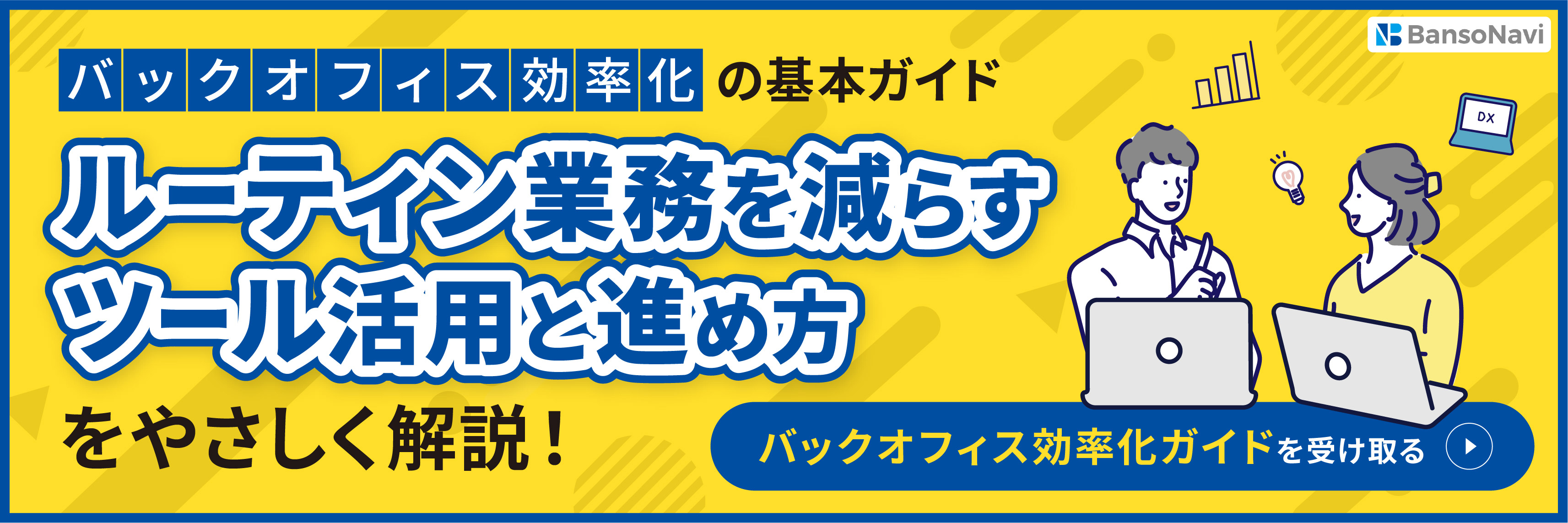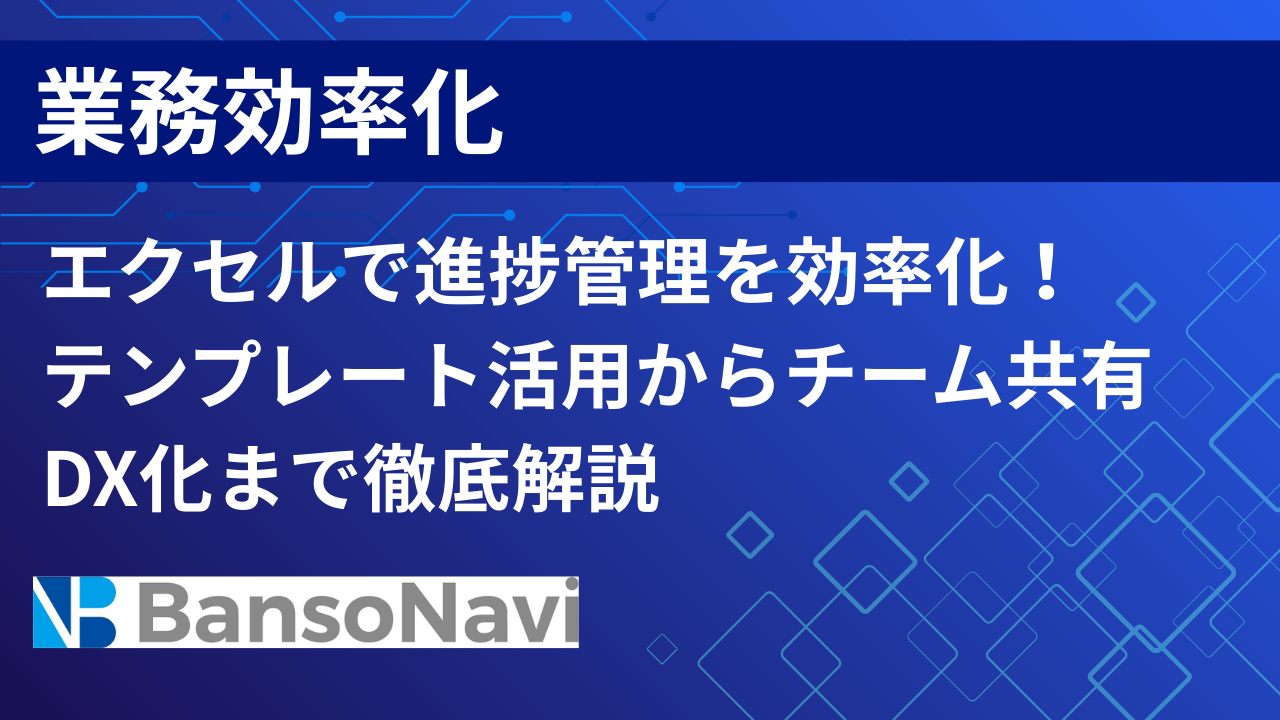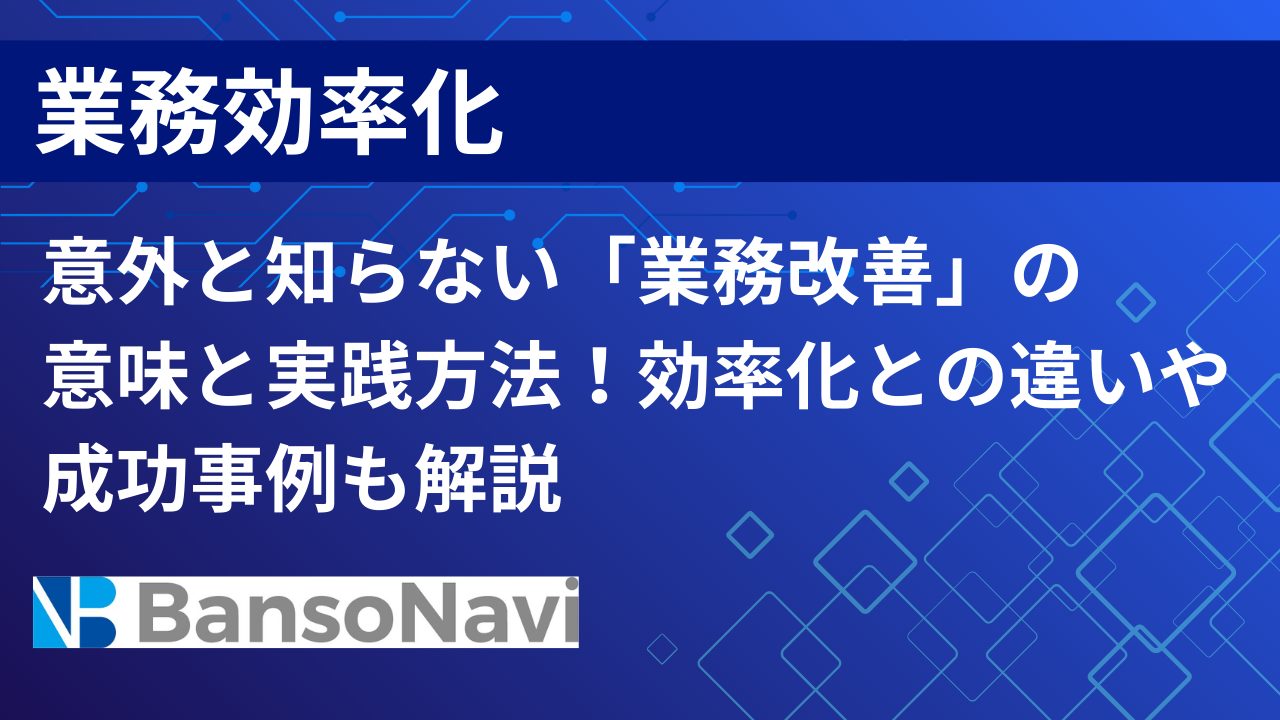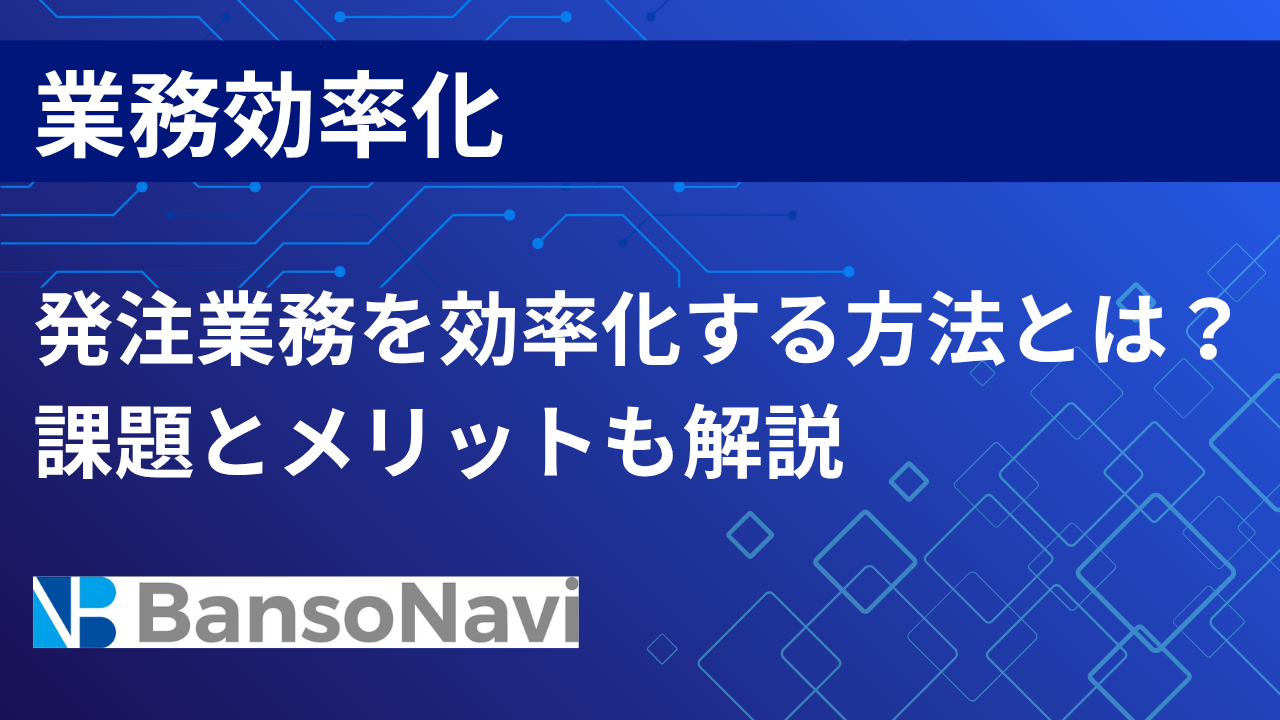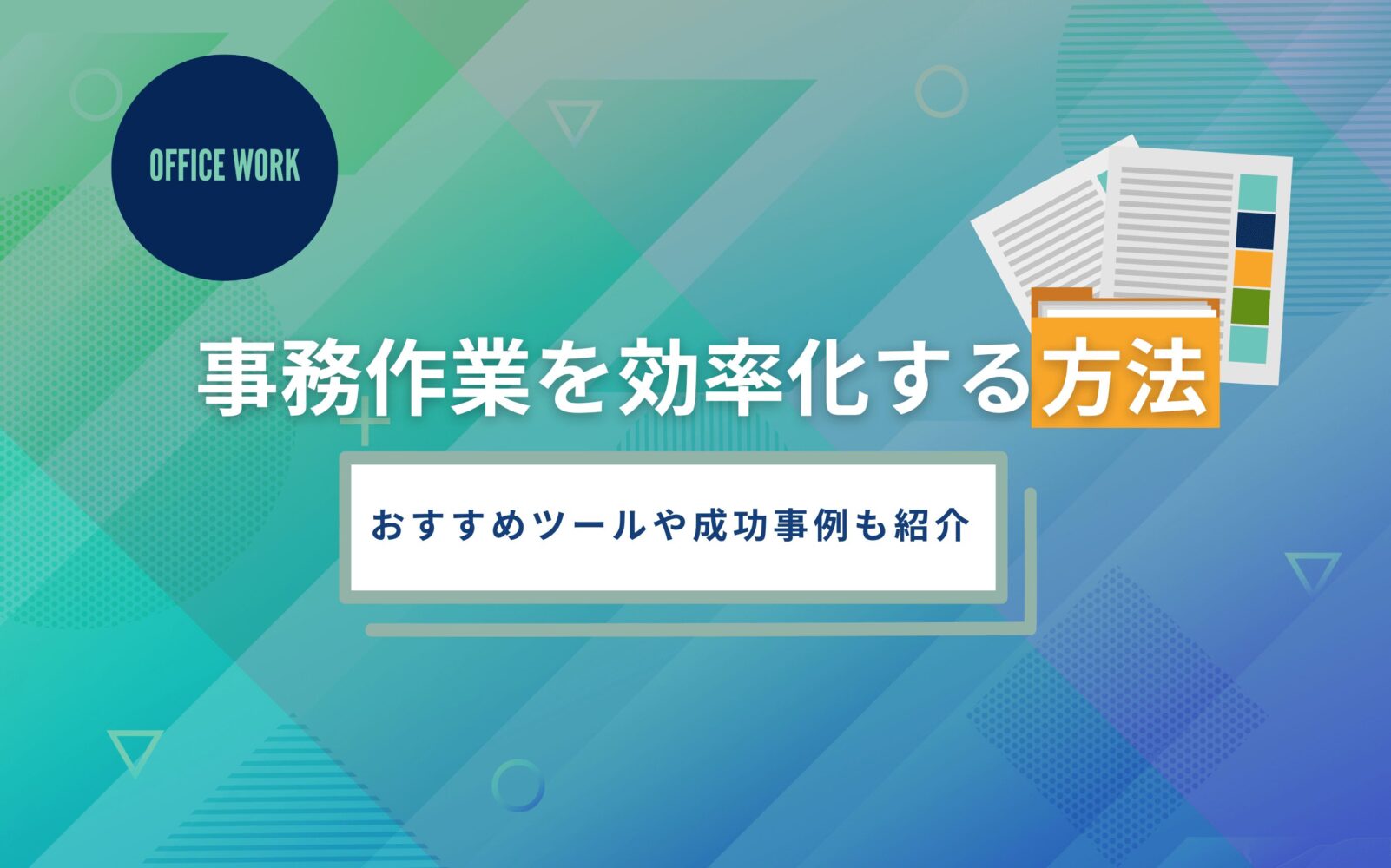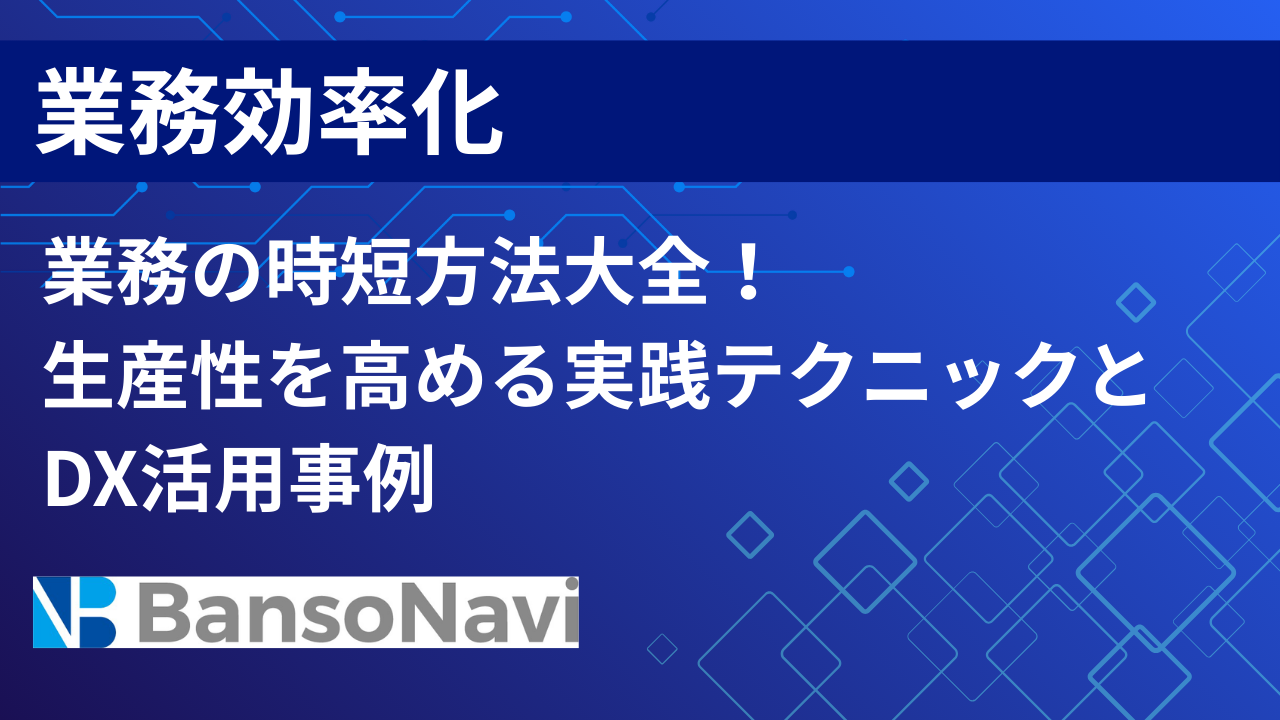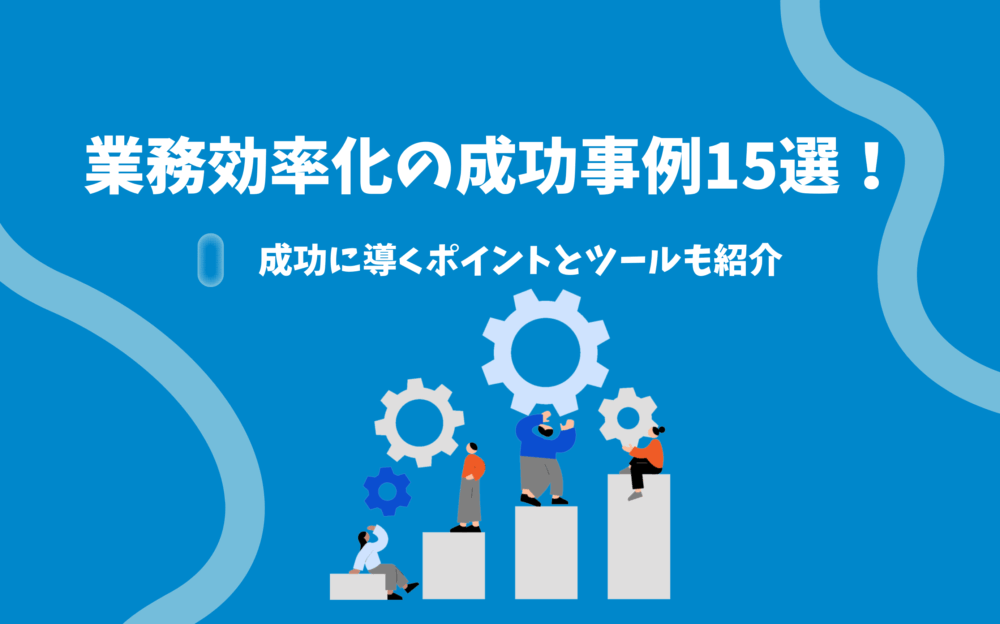非効率な業務を徹底見直し!原因分析から改善事例までわかる完全ガイド
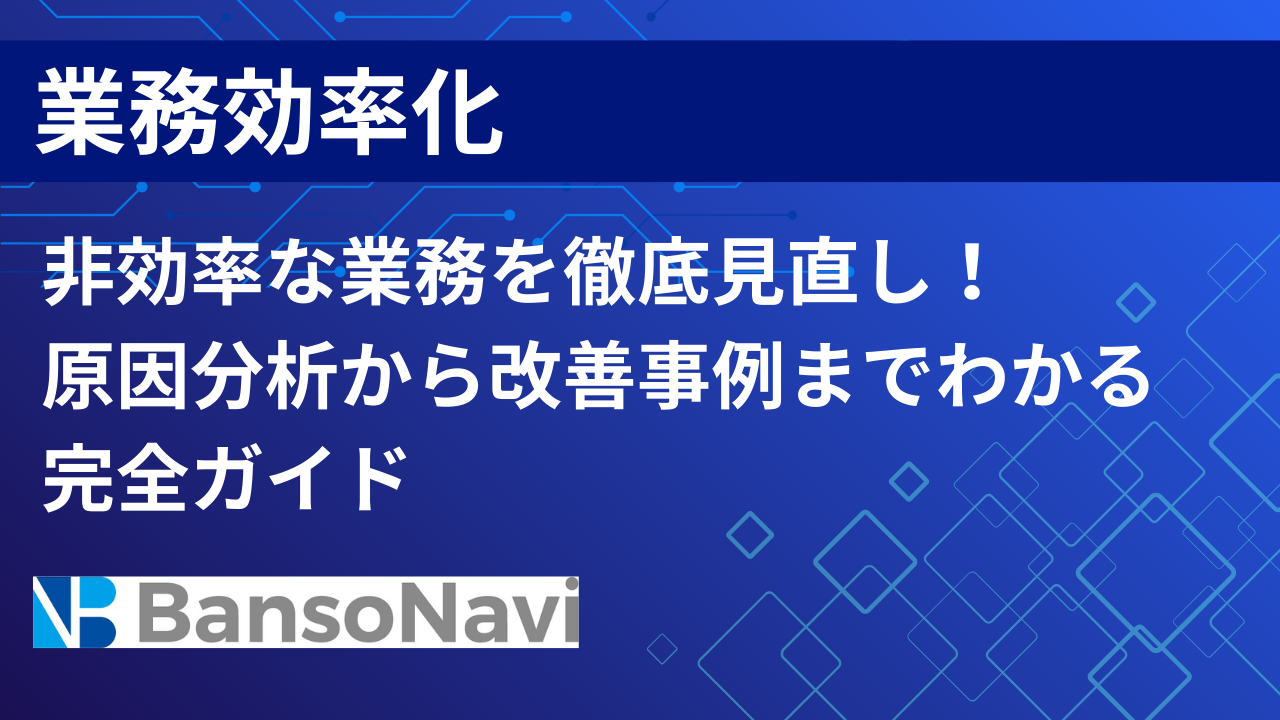
「業務がなんだか回らない…」「会議や報告に時間ばかり取られて本来の仕事が進まない…」そんな悩みを抱えていませんか?非効率な業務は、生産性を下げるだけでなく、社員のモチベーション低下や顧客満足度の低下にもつながります。
本記事では、非効率業務を見直すための原因分析方法から改善手順、具体的なツール活用事例までをわかりやすく解説します。読むだけで「どこから手を付ければいいのか」が明確になり、すぐに改善に着手できるようになります。
目次
なぜ業務が非効率になるのか?原因を正しく理解する

業務が非効率になる背景には、単なる「やり方の悪さ」だけではなく、組織の仕組みや文化、情報の流れ、ツールの選定ミスなど複合的な要因が絡んでいます。原因を正しく理解せずに対策を進めると、改善のつもりが逆効果になることもあります。
ここでは、非効率業務の典型的な特徴と、見えにくい原因を整理する方法を解説します。
よくある非効率業務の特徴とサイン
非効率な業務にはいくつかの共通するサインがあります。
例えば、同じ情報を何度も入力する「二重作業」、関係者全員にメールを送っても返信がバラバラに返ってくる「情報の分散」、承認フローが複雑すぎて決裁が遅れる「意思決定の停滞」などです。また、会議が多すぎる、資料作成に過剰な時間をかける、属人化が進み一部の人しか業務内容を理解していないといった状態も要注意です。
こうした現象が続くと、現場の負担が増え、顧客対応や新しい施策に割ける時間が削られてしまうため、組織全体の成長スピードが落ちます。まずはこうした「非効率の兆候」を洗い出すことが、業務見直しの第一歩です。
人・仕組み・ツールのどこに原因があるかを見極める方法
非効率の原因を突き止めるには、まず業務プロセスを「人」「仕組み」「ツール」の3つの視点から分解してみましょう。
人に原因がある場合:スキル不足や役割の不明確さが多く、属人化やコミュニケーション不足に繋がる
仕組みに原因がある場合:承認ルートの複雑化、業務ルールの形骸化、責任の所在不明などが発生する
ツール面に原因がある場合:複数システムの連携不足や古いソフトの利用が作業効率を阻害する
重要なのは、1つの業務に対して複数の要因が絡むことを前提に分析することです。そのため、部署横断でヒアリングを行い、全体像を見ながら原因を特定していくことが欠かせません。
現場で気づきにくい“隠れムダ”の見つけ方
一見スムーズに回っているように見える業務の中にも、実は時間やコストを浪費している“隠れムダ”があります。
例えば、複数人が同じ資料を別々に作成している、紙での承認とデジタル承認が二重になっている、過去の慣習で続けているが意味を失った報告作業などです。
これらは当事者が慣れすぎているため、外から指摘されないと気づきにくいものです。見つけるためには、実際の作業時間を可視化し、作業工程ごとに「本当に必要か?」を問い直すことが有効です。また、外部の視点や他部署との比較から、改善の余地を洗い出す方法も効果的です。
業務見直しの基本ステップと成功のコツ
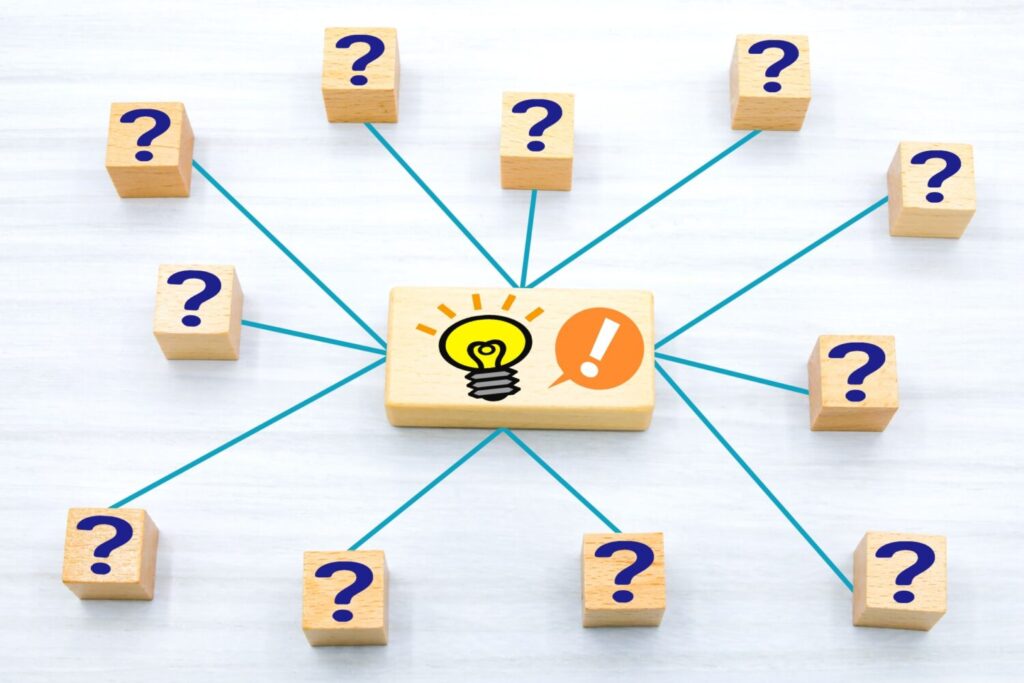
非効率な業務を改善するには、やみくもに手を付けるのではなく、現状を把握→課題を整理→優先度を決め→改善計画を立て→実行と検証を行うという流れを踏むことが重要です。
この手順を守ることで、改善効果が測定しやすく、社内の理解や協力も得やすくなります。
ここでは、業務見直しの基本ステップと、成功に導くためのコツを紹介します。
現状把握と課題抽出のためのフローチャート作成
業務見直しの最初のステップは、現状を正確に把握することです。
現場の感覚や記憶に頼るのではなく、業務フローを図解した「フローチャート」を作ることで、作業の流れや関係者、情報のやり取りが明確になります。例えば、受注処理の流れを可視化すれば、「ここで二重入力が発生している」「この承認ステップが遅延の原因になっている」といった課題が浮かび上がります。作成の際は、現場担当者からヒアリングし、実際に行っている作業手順をできるだけ細かく書き出すことが大切です。見える化が進むと、改善対象が具体的になり、社内での共通理解も得やすくなります。
優先順位のつけ方と改善計画の立て方
改善ポイントが複数見つかったら、全てを同時に手を付けるのではなく、優先順位を付けましょう。
優先度を決める基準としては「影響度の大きさ」「改善の難易度」「緊急性」の3軸がおすすめです。
例えば、日常的に発生し、多くの社員が関わる非効率業務は影響度が高く、優先して改善すべきです。改善計画は、いつまでに・誰が・どのように改善するかを明確にし、関係者に共有します。ここで曖昧な計画だと、改善が進まなかったり、途中で頓挫するリスクが高まります。計画段階で必要なツールや外部支援の検討も行うことで、実行フェーズがスムーズになります。
短期間で成果を出すための小さな改善の積み重ね
業務改善というと、大掛かりな改革をイメージしがちですが、現場に負担をかけすぎると反発や疲弊を招きます。そこで効果的なのが、小さな改善を短期間で繰り返すアプローチです。
例えば、会議の資料フォーマットを統一する、承認ルートを1段階減らす、情報共有をチャットツールに一本化するといった小規模な変更です。これらは即効性が高く、改善効果を早く実感できます。小さな成功体験が積み重なることで、社内に「改善はやればできる」という空気が生まれ、より大きな改革にも取り組みやすくなります。短期成果→評価→次の改善というサイクルを意識すると、継続的な改善文化が根付きます。
非効率業務を改善する具体的な手法とツール

非効率な業務を改善するには、単に作業手順を変えるだけでなく、デジタルツールの導入や情報共有の仕組みづくり、業務プロセスの自動化など多面的なアプローチが必要です。近年は低コストで導入できるクラウドサービスも増えており、中小企業でも本格的な改善が可能になっています。
ここでは、現場で実際に効果を上げている改善手法と、それを支えるツールの活用事例を紹介します。
業務プロセスの自動化とデジタル化
手作業や紙ベースの業務は、人為的なミスや時間の浪費を招きやすいです。
例えば、毎回手入力している請求書作成や在庫管理を、クラウド会計ソフトや在庫管理システムに置き換えるだけで、作業時間を大幅に削減できます。さらに、RPA(Robotic Process Automation)を活用すれば、データ入力や定型レポート作成などの単純作業を自動化できます。
自動化のメリットは、単に時間短縮だけでなく、作業の正確性向上や担当者の負担軽減にもつながることです。また、デジタル化によりデータが蓄積されるため、分析や改善の精度も高まります。まずは、繰り返し発生する単純作業から自動化に着手すると効果が見えやすいでしょう。
コミュニケーションロスを減らす情報共有の仕組みづくり
業務の非効率化には、情報共有の不十分さも大きく影響します。
例えば、メールのやり取りだけでは必要な情報を探すのに時間がかかり、最新情報がどれか分からなくなることがあります。そこで効果的なのが、チャットツールや社内ポータルを活用したリアルタイム情報共有です。
SlackやMicrosoft Teamsなどを使えば、部門やプロジェクトごとにチャンネルを分け、議論や資料を一元管理できます。さらに、Google WorkspaceやSharePointなどのクラウドストレージを併用すれば、資料の最新版を誰でもすぐに確認できる環境が整います。ポイントは、情報を「探す」時間を極限まで減らすことです。その結果、意思決定が早まり、業務全体のスピードが上がります。
kintoneを活用した内製化・DX化の事例紹介
kintoneは、プログラミング知識がなくても自社の業務アプリを作成できるクラウドサービスです。
例えば、紙で行っていた顧客管理や日報提出をkintoneアプリに移行すれば、リアルタイムで情報が共有され、集計や分析も自動で行えます。また、社内の要望に応じてアプリをカスタマイズできるため、業務の変化にも柔軟に対応できます。
実際に伴走ナビが支援した企業では、kintone導入によりExcel管理の属人化を解消し、データ入力時間を半減しました。さらに、外部ツールとの連携機能を活用すれば、営業管理から請求処理まで一気通貫でデジタル化が可能です。内製化によって改修コストを抑えつつ、継続的な改善が行えるのも大きな魅力です。
業務改善を定着させる仕組みと継続のポイント

せっかく業務改善を行っても、一時的な取り組みで終わってしまうと、すぐに元の非効率な状態に逆戻りしてしまいます。
改善を社内文化として根付かせるためには、効果測定・課題再設定・社内巻き込み・外部支援の活用といった継続の仕組みが欠かせません。ここでは、改善を持続させるための実践ポイントを解説します。
改善後の効果測定と次の課題設定
改善は「やりっぱなし」にしてはいけません。実行後は、必ず効果を数値や事実で測定し、改善の成否を判断します。
例えば、作業時間の短縮率、エラー発生数の減少、顧客満足度の変化などが指標になります。これらを月次や四半期ごとに定期測定することで、改善の効果を客観的に評価できるのです。そして、測定結果を踏まえて次の課題を設定します。改善によって新たな業務課題が見えることも多く、改善は常に進化していくプロセスです。効果測定→課題設定→再改善のサイクルを回し続けることが、真の定着につながります。
社内の巻き込み方とモチベーション維持策
業務改善は、担当者や一部の部署だけで進めると限界があります。全社的に協力を得るには、改善の目的や成果を共有し、「自分たちの仕事が楽になる」実感を持ってもらうことが重要です。
例えば、改善前後の作業時間の比較や、成功事例を社内ミーティングで発表するのも有効です。また、小さな成功を表彰制度やインセンティブで評価することで、現場のモチベーションが維持されます。加えて、改善に対する意見や提案を募る仕組みを作ると、社員が主体的に改善活動に参加する文化が醸成されます。
失敗しないための外部支援・伴走型サポート活用法
業務改善を社内だけで完結させようとすると、どうしても知識やリソースが不足する場合があります。そこで有効なのが、外部のコンサルタントや伴走型支援サービスの活用です。
伴走ナビのような支援サービスでは、現状分析から改善計画、ツール導入、内製化支援まで一貫してサポートします。特に、初めてのDX化やツール導入では、失敗事例やつまずきポイントを事前に回避できるメリットがあります。また、外部支援を活用しながら社内メンバーがノウハウを吸収すれば、次回以降は自走型の改善が可能になります。外部と社内の役割をうまく分担することが、長期的な成功の鍵です。
伴走ナビの事例から学ぶ、業務改善のリアルな成果
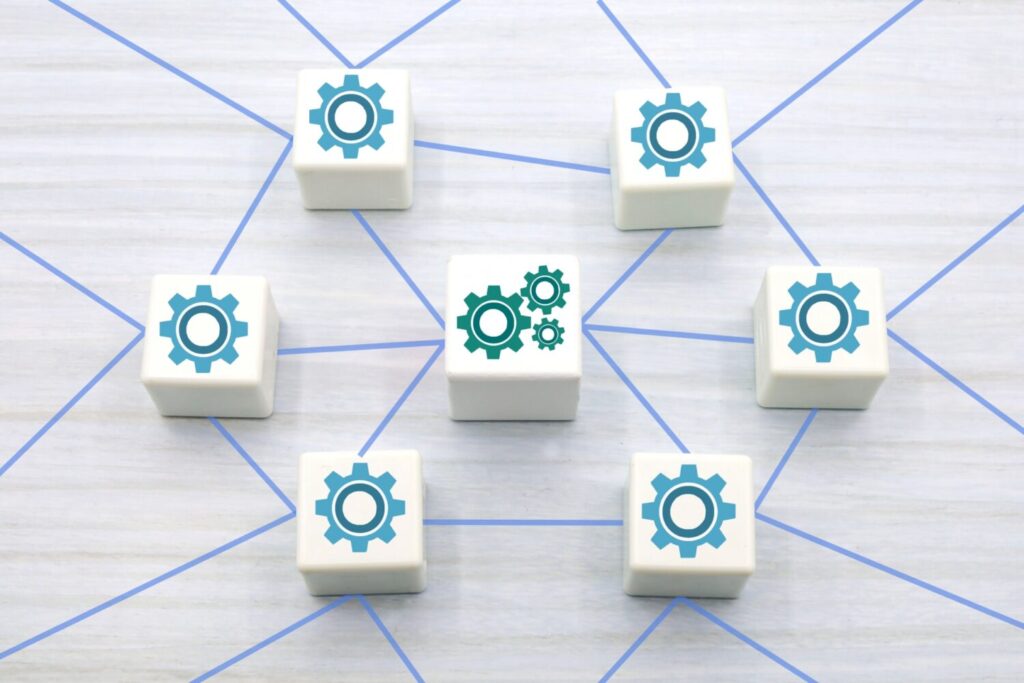
業務改善の成功例を知ることは、自社の取り組みを具体的にイメージする大きな助けになります。
伴走ナビでは、kintoneの活用や業務プロセスの再設計を通じて、多くの企業が短期間で成果を上げています。ここでは3つの代表的な事例を紹介します。
紙やExcel中心だった企業が3ヶ月で脱・非効率化
ある製造業の企業では、受注や在庫管理をすべて紙とExcelで行っていました。その結果、データの二重入力や転記ミスが頻発し、情報更新にも数日かかる状態でした。
伴走ナビの支援により、kintoneを基盤とした受注・在庫管理アプリを構築。過去のExcelデータも移行し、リアルタイムでの情報共有が可能になりました。導入からわずか3ヶ月で、事務作業時間を40%削減し、ミス発生率をほぼゼロに。現場からは「もう紙には戻れない」という声が上がり、全社的なデジタル活用の意識も高まりました。
部署間の連携不足を解消したワークフロー改善事例
あるサービス業の企業では、営業部とバックオフィス間の連携がうまく取れず、案件進行が遅れることが課題でした。原因は、情報共有がメールと口頭に依存していたため、最新状況の把握に時間がかかることでした。
伴走ナビは、kintone上で案件進行管理アプリを設計し、案件のステータスや担当者、進捗を全員がリアルタイムで確認できる仕組みを構築。結果として、案件処理スピードが30%向上し、部署間のやり取りに費やす時間が半減しました。改善後は、新規案件の対応スピードが競合他社より早まり、顧客満足度も向上しました。
現場主導でのDX内製化に成功した中小企業のストーリー
IT人材が少ない中小企業でも、内製化によって業務改善を継続できるようになった事例があります。伴走ナビは、まず現場担当者が自分たちでアプリを作れるよう研修を実施。その後、既存業務のアプリ化を一緒に進め、3ヶ月で5つの業務をデジタル化しました。結果として、現場主導での改善サイクルが回り始め、外部依存のコストが大幅に削減されました。
この成功体験により、社員が自ら改善アイデアを出す文化が定着し、会社全体の業務効率と柔軟性が向上しました。
まとめ|改善は一度きりではなく、文化として根付かせることが大切
非効率な業務を見直すには、原因を正しく分析し、優先度を決めて改善を進めることが欠かせません。そして、改善の効果を数値で測定しながら、小さな改善を積み重ねることで、大きな成果につながります。
ツール導入や外部支援の活用は、改善のスピードと成功率を大きく高める手段です。
伴走ナビのように、現場に寄り添いながらDX化や業務見直しをサポートするサービスを活用すれば、短期間で確実な変化を実感できます。改善は一度きりのイベントではなく、組織文化として継続することが、長期的な競争力の源泉になります。