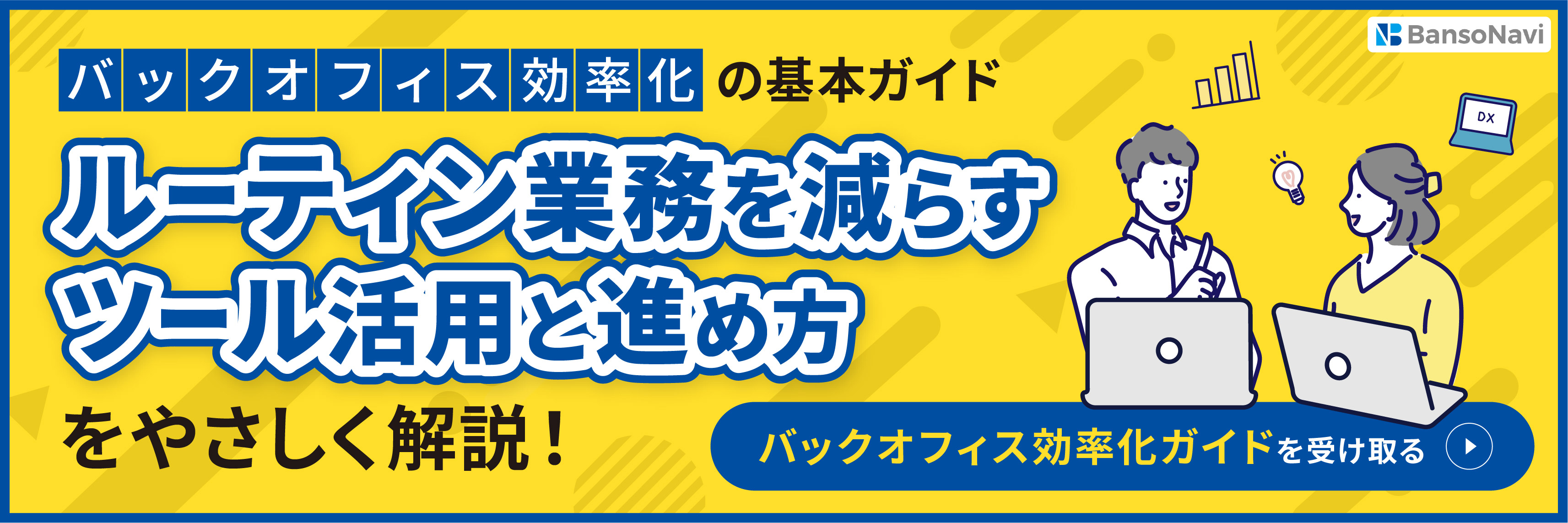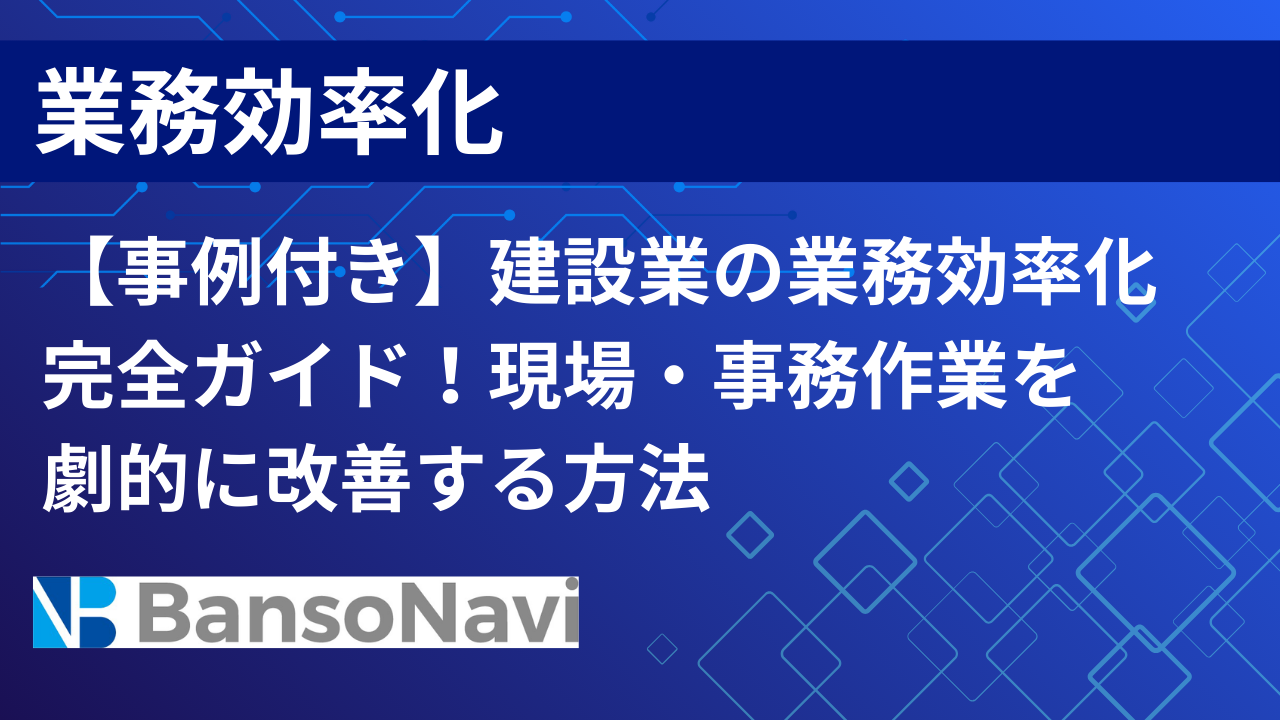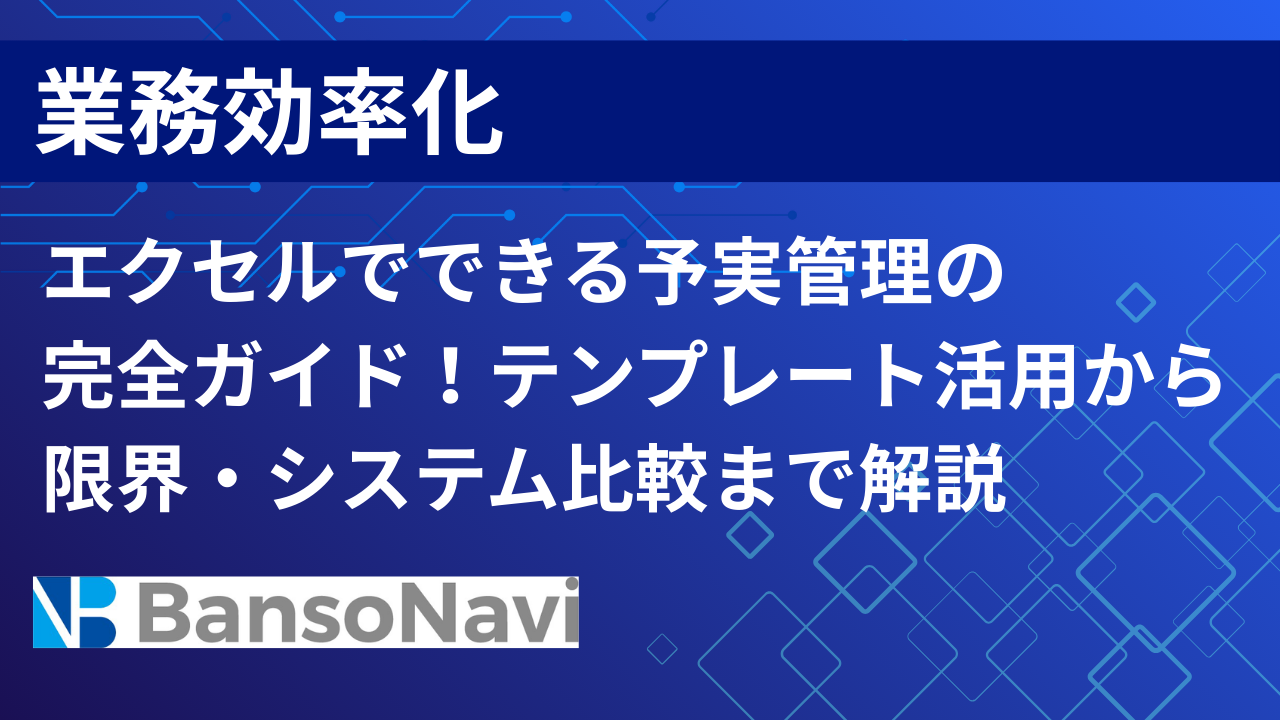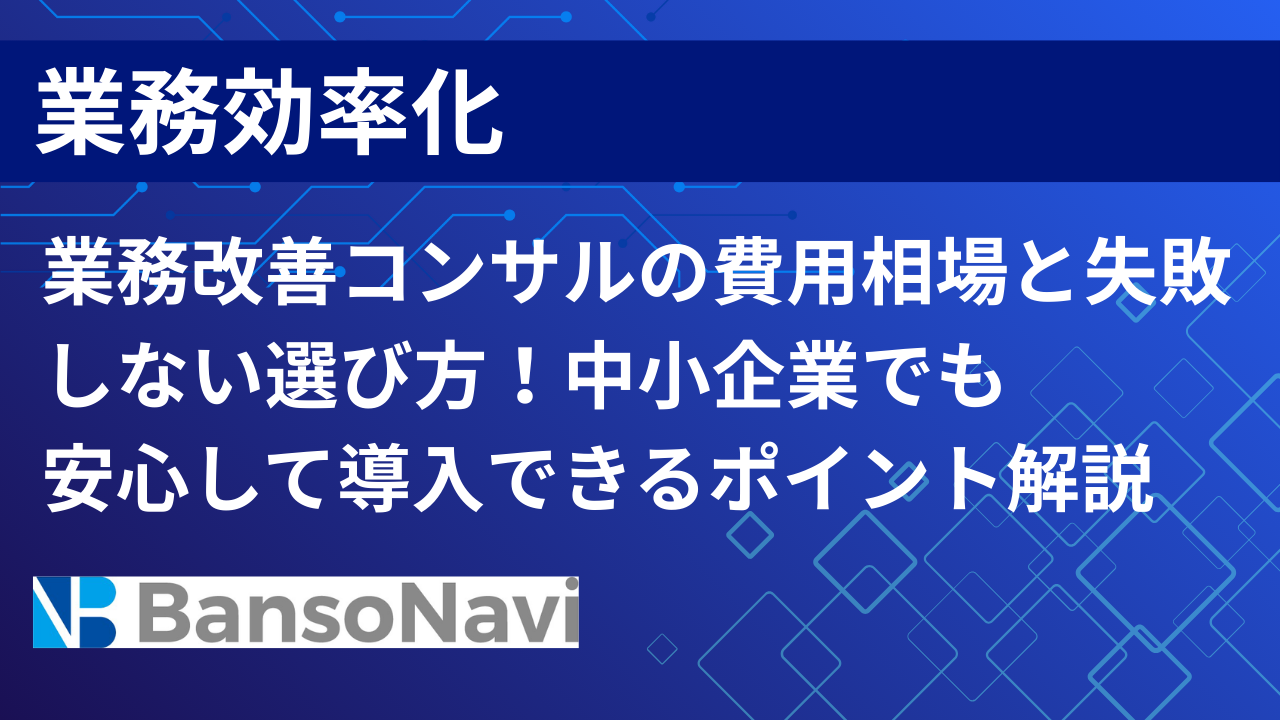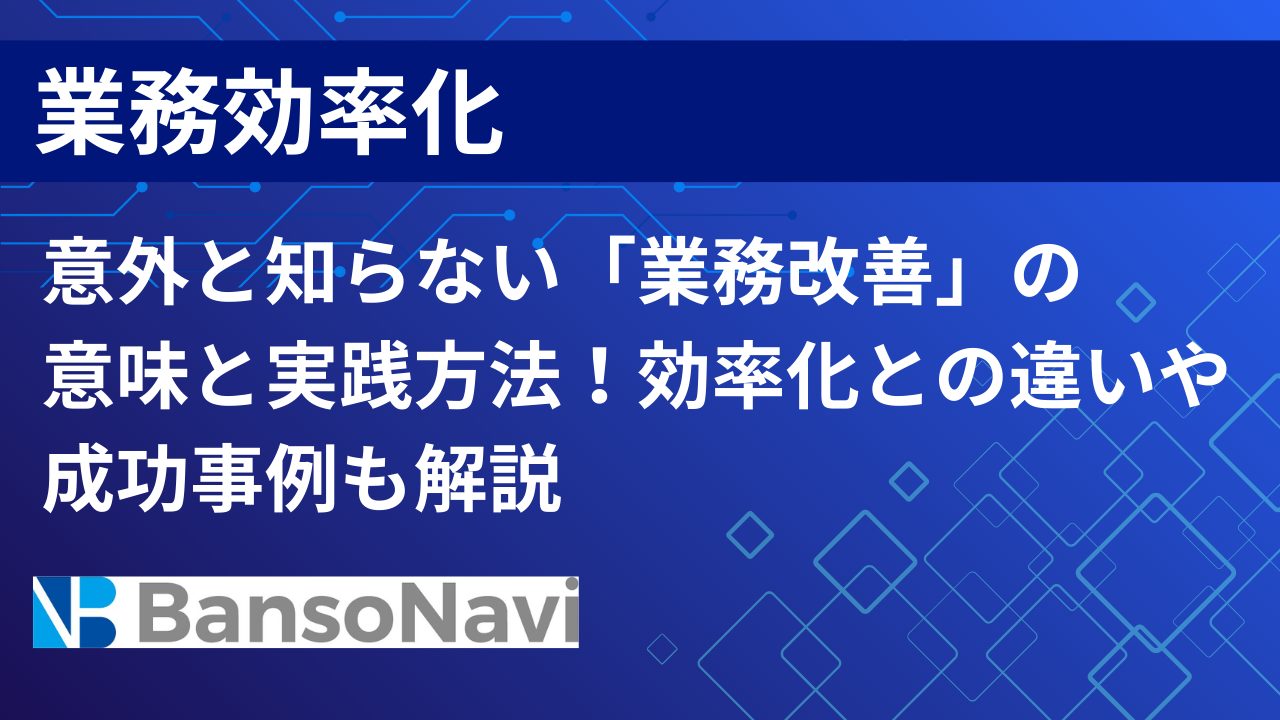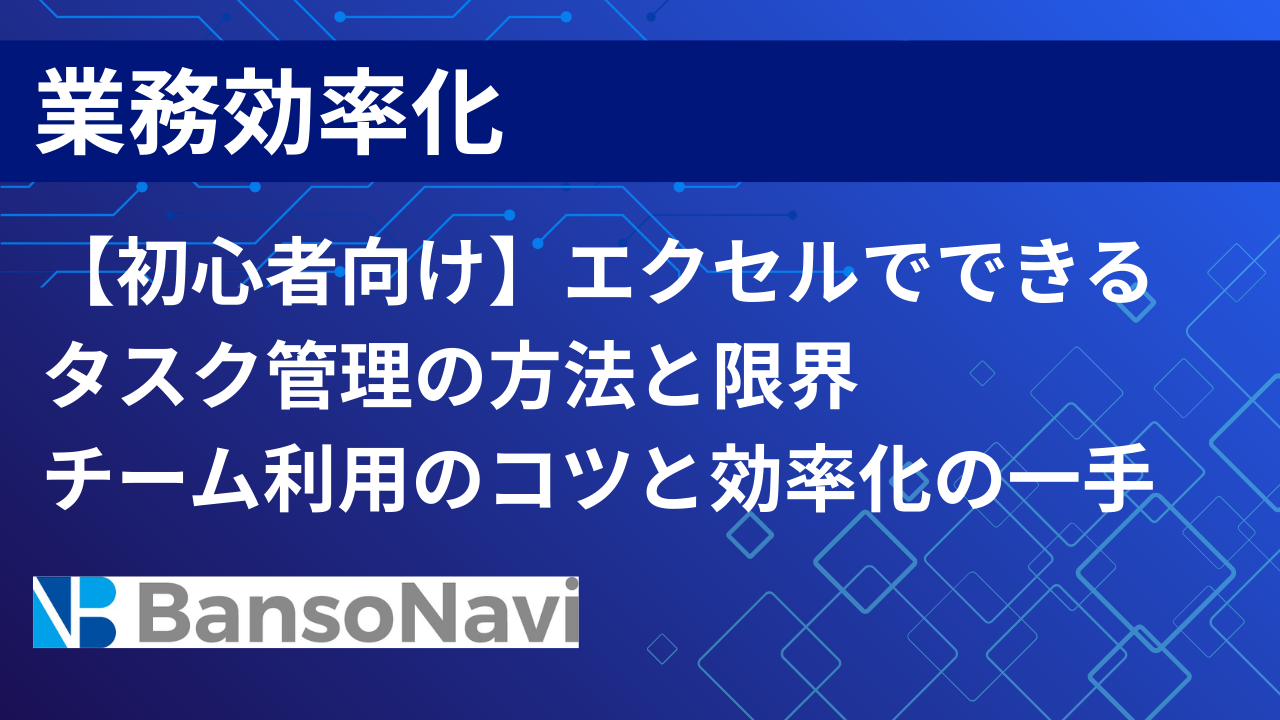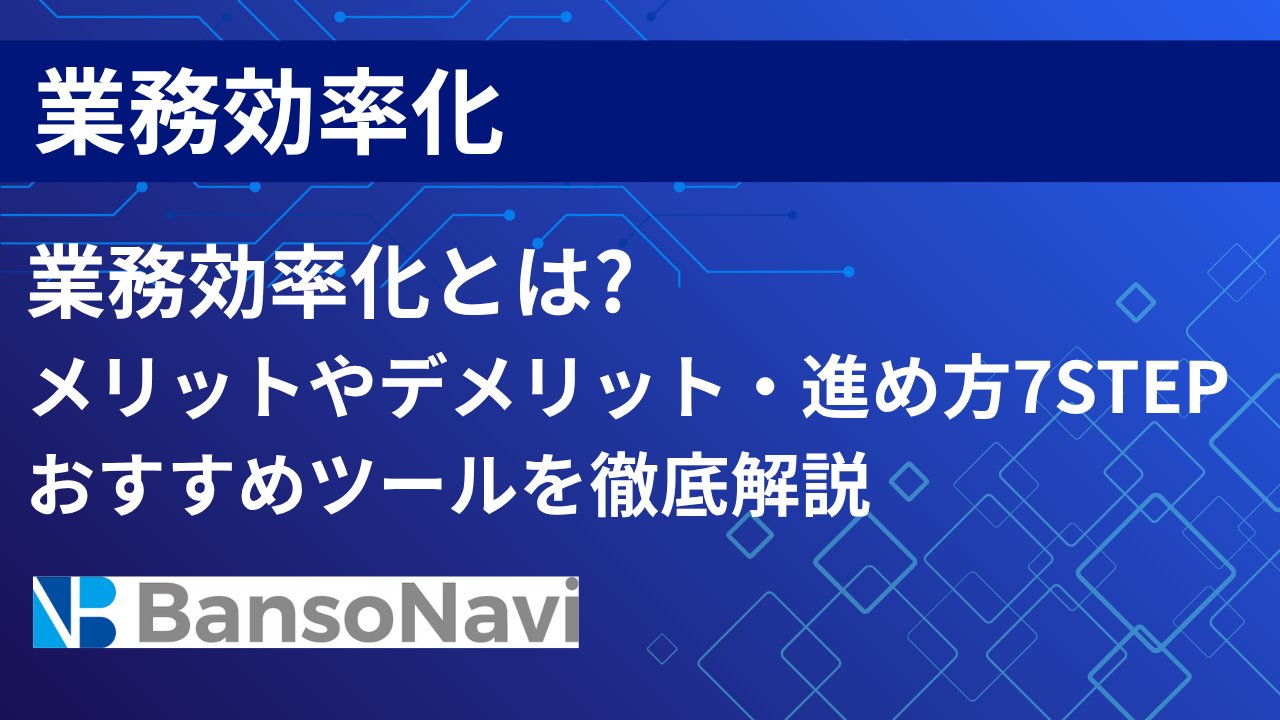発注業務を効率化する方法とは?課題とメリットも解説
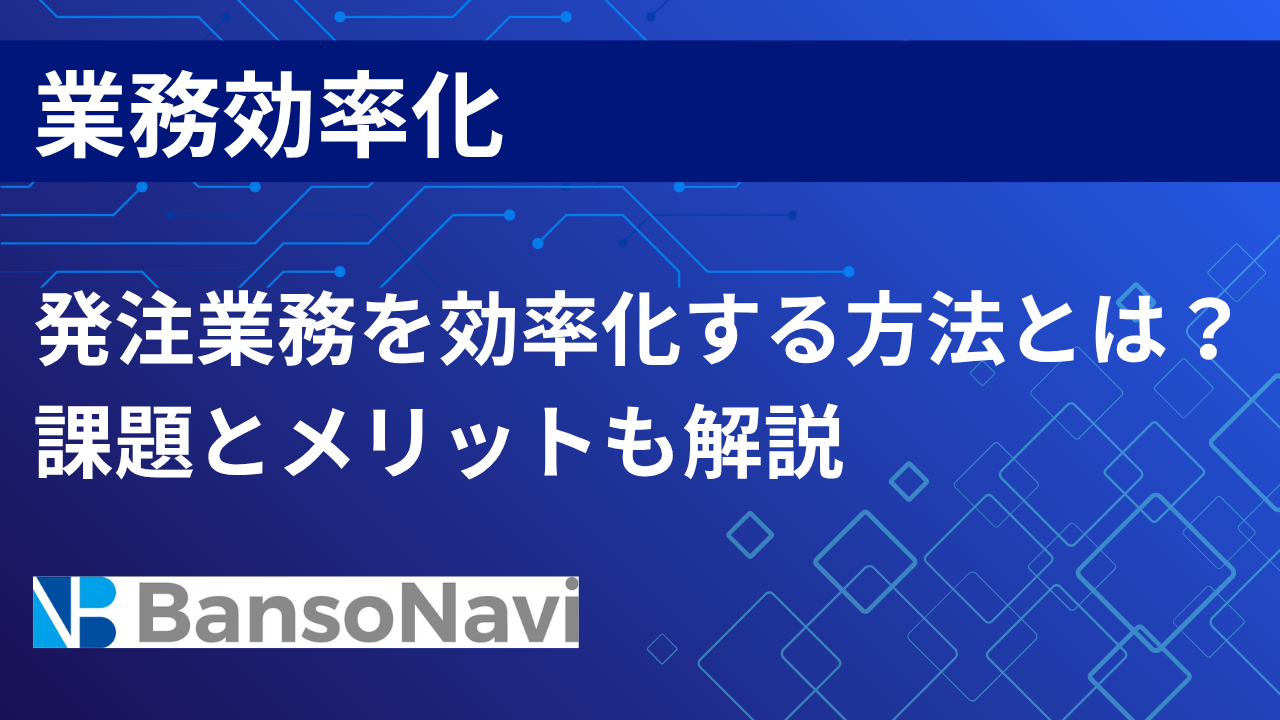
「受発注業務にミスが多く、手間ばかりかかってしまう」
「人手不足で発注処理が追いつかない」
発注業務に関わる悩みを抱えている企業担当者も多いでしょう。これらの課題を解決するには、システム導入やRPA活用などの実践が欠かせません。
本記事では、発注業務における課題を整理し、業務効率化につながる具体的な対策を解説します。
効率化によって得られるメリットや実行手順にも触れているので、発注業務の見直しを検討している方は、参考にしてください。
■この記事でわかること
- 受発注業務でよくある課題
- 受発注業務を効率化する方法と具体的な手順
- 業務効率化によって得られるメリット
■こんな人におすすめの記事です
- 受発注業務の見直しを検討している総務・経理・購買担当者
- 人手不足や属人化に悩んでいる中小企業の管理部門担当者
目次
受発注業務とは?

発注業務とは、企業がモノやサービスの取引を行う際に発生する「注文」と「受注」に関する一連の業務を指します。たとえば、見積書のやり取りや発注書の発行、納品確認、請求処理などが含まれます。
この業務は、営業・調達・経理など複数の部署をまたいで行われるのが一般的です。そのため、情報の伝達が不十分な場合、納期遅延や誤発注などのトラブルを招くおそれがあります。
また、近年はテレワークの普及やDX推進を背景に、従来の紙やExcel中心の運用から、システムを活用した一元管理へと移行する企業が増えています。業務の属人化を防ぎ、効率的な情報共有を実現するためには、受発注フローの見直しが欠かせません。
受発注業務の7つの課題
受発注業務は、人手に依存した作業が多く、部署間で情報が分断されることも少なくありません。業務の効率化を妨げる要因は多岐にわたり、対応を後回しにすると納期遅延や顧客離れといった大きな損失につながるおそれもあります。
ここでは、受発注業務でとくに多くの企業が抱えている7つの課題を紹介します。
- 入力ミスや確認漏れなどの人的ミスが多発している
- 他部署との情報共有がスムーズに進まない
- 担当者に業務が偏り、引き継ぎが困難である
- フローが複雑化し、作業に時間と手間がかかる
- 社外から業務を行えず、柔軟な働き方に対応できていない
- 紙書類が中心で、データの活用や検索が難しい
- 営業対応が後回しになり、顧客満足度の低下を招いている
それぞれ自社の課題と照らし合わせてみてください。
ヒューマンエラーがなくならない
受発注業務では、数量や納期、取引先名の入力ミス、送信先の選択ミスなど些細な操作ミスが大きなトラブルに発展するケースがあります。とくにExcelやメール、FAXなど複数の手段を組み合わせて運用している企業では注意が必要です。なぜなら、手作業での確認や転記が多く、人的ミスが避けられないからです。
たとえば、商品の発注単位を間違えて必要量より多く手配してしまうケースや、納期の欄を更新せずに、古い情報のまま送信して混乱を招く恐れがあります。どれも担当者の確認ミスによるもので、このようなエラーが日常的に発生している企業も少なくないのです。
関係する部署と連携しづらい
受発注業務は、営業・調達・在庫管理・経理など、複数の部門が関与する業務です。しかし、各部門が独立して管理していると、進捗状況や最新情報の共有が遅れがちになります。
たとえば、営業が変更した納期を購買側に伝え忘れると、発注タイミングがズレて納品遅れが生じることも。Excelファイルをメールでやり取りしているケースでは、ファイルのバージョン違いや誰が最新情報を持っているのかが曖昧になり、トラブルの原因になります。部署間の認識にズレが起きやすく、情報がスムーズに流れないことで業務の非効率化を招いています。
業務が属人化する
受発注業務では、特定の担当者が顧客対応から発注処理、納期確認までを一手に引き受けている傾向があります。長年その業務を担ってきたベテラン社員が独自のルールやフォーマットで運用しており、ほかの社員が業務を把握していないケースも少なくありません。
その結果、担当者不在の際には対応が止まり、取引先からの問い合わせに即答できない問題が発生します。加えて、業務の全体像が見えないことで、社内でも改善の提案が出にくくなります。結果として、「あの人しか把握していない仕事」が増え、組織としてのリスクが高まるでしょう。
作業工程が複雑である
見積依頼・発注・納期調整・在庫確認・請求処理など、受発注業務は多くのプロセスで構成されています。それぞれの工程が手作業中心の場合、工程ごとの確認や承認に時間がかかり、全体の業務スピードが落ちるでしょう。
また、工程ごとに別々のツールやフォーマットが使われていると、情報の連携が取れず、同じ内容を何度も記入・確認する手間が発生します。たとえば、発注内容を一度紙でまとめたあと再度Excelに転記し、さらにメールでも確認するなど、ムダな作業が日常化している例もあります。
テレワークや在宅勤務に対応できない
受発注業務では、いまだに紙伝票やオフィス内の共有サーバーへのアクセスが必須とされるケースが多く、社外からの作業が困難です。とくに、FAXや電話によるやりとりが中心な企業では、在宅勤務中の担当者が発注書の確認や返信を行えず、業務が滞ってしまいます。
また、セキュリティ上の制約から、社内ネットワーク以外では重要な情報にアクセスできない場合も多く、働く場所を柔軟に選べない状況に陥っています。このような構造がテレワーク普及の妨げになり、業務継続性の面でも課題が残っているといえるでしょう。
紙の脱却に苦戦し、データを活用できない
多くの企業では、受発注に関する書類を紙やPDFでやり取りしており、情報の蓄積や分析が困難です。過去の発注履歴を確認する際も、書庫を探し回ったり、PDFを1件ずつ開いて内容を確認したりする必要があり、担当者の負担が大きくなりがちです。
また、紙帳票では情報の再利用が難しく、在庫管理や仕入れ分析などにも活かせません。たとえば、どの時期にどの商品の注文が集中したのかを把握するにも、手作業による転記・集計を要し、リアルタイムに判断できないでしょう。
営業活動の妨げとなり顧客満足度が下がる
受発注に関する事務処理に時間が取られると、本来優先すべき顧客対応や提案活動がスムーズに進みません。たとえば、入力作業や進捗確認に追われると、見積書の提出が遅れたり、納期の確認が後回しになったりします。
このような対応の遅れが続くと、顧客からの信頼を失うだけでなく、競合他社に取引を奪われる原因になるため注意が必要です。とくに、リピート率が重要な業種では、迅速かつ丁寧な対応が成果に直結します。そのため、営業活動が制限されると、売上に大きな影響を与えるでしょう。
受発注業務を効率化する6つの方法

紙や手作業中心のフローではスピードや正確性に限界があり、業務負荷の増加やミスが続く原因になりがちです。このような状況を打破するには、業務プロセス全体の見直しとあわせて、最新のツールや外部リソースを活用する視点が求められます。
ここでは、受発注業務の効率化に有効とされる6つの具体策を紹介します。
- 業務全体を一元管理できる専用システムを導入する
- 定型的な処理を自動化できるRPAツールを活用する
- 人員や作業時間の再配置により業務負荷を見直す
- 発注書や納品書のやり取りをデジタルで完結させる
- 紙の帳票を読み取ってデータ化できるOCRを導入する
- 一部の業務を外部企業に委託し社内リソースを軽減する
それぞれ参考にしてください。
システムを導入する
受発注業務を効率化するには、まず業務全体を一元管理できるシステムの導入が効果的です。手作業での入力や確認が続くと、ヒューマンエラーが頻発し、情報の行き違いによる納期遅延や誤発注につながるためです。また、複数部署で異なるツールを使っている場合、進捗状況の把握やデータの整合性に時間を要し、業務全体のスピードと精度が低下します。
一方、専用システムを導入すれば、発注処理・在庫情報・納期状況などがリアルタイムで可視化され、確認や集計の手間も大幅に削減可能です。データの検索性や共有性も高まり、社内全体でスムーズな意思決定が実現するでしょう。
中でもおすすめなのが、ノーコードで柔軟なアプリ作成機能を搭載した「kintone(キントーン)」です。自社の業務フローに応じて受発注管理アプリを構築できるため、現場に即した運用がしやすく、部署間の情報共有も円滑に行えます。コメント機能やカスタマイズ性も高く、属人化の解消や拠点間の連携にも役立ちます。
なお、受発注業務におけるkintoneの活用方法を知りたい方は、こちらをご覧ください。
参考|kintoneで受注管理するメリットは?受発注業務を効率化するプラグインや事例も紹介
RPAを活用する
RPA(Robotic Process Automation)とは、人がパソコンで行っている定型的な操作をソフトウェアロボットが代行する仕組みです。マウス操作やキーボード入力、ファイルのコピー&ペースト、メールの送受信などルール化された繰り返し作業を高速かつ正確に処理できます。人手による確認や転記に頼っていた業務をRPAに置き換えることで、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減が期待されます。
たとえば、受注データをメールやFAXで受け取り、それを基幹システムへ手入力していた場合、この一連の作業の自動化が可能です。また、夜間や休日の処理も無人で実行されるため、対応スピードも格段に向上するでしょう。
さらに、最近ではkintoneとRPAを連携させた活用が注目されています。kintoneに登録された受注情報をRPAが他システムへ自動転記したり、kintoneで申請されたデータをもとに請求書を自動作成したりと、異なる業務ツール間の橋渡し役として機能します。これにより、kintoneの柔軟なデータ管理とRPAの処理能力を組み合わせた、より高度な業務自動化が実現することは間違いありません。
kintoneとRPAの連携の詳細を知りたい方は、こちらも参考にしてください。
参考|サイボウズ株式会社「kintone×RPAでかんたん開発!劇的改善!」
リソースの配分を最適化する
一部の担当者に注文処理が集中していたり、業務量が部署間でアンバランスだったりする場合、処理遅延や属人化のリスクが高まります。とくに、繁忙期や急な欠員が出た際には、業務全体が滞ってしまうことも珍しくありません。
たとえば、受注内容の確認から発注入力、在庫の照会、納期連絡までを1人で抱えていると、どれか1つの遅れが他業務にも波及し、全体の効率を下げてしまいます。このような状況を防ぐには、業務の優先度や作業ボリュームに応じて、タスクや人員の再配分の検討が必要です。
業務ごとの負荷の「見える化」により、誰がどこにどれだけ時間をかけているかを把握でき、適切な人員配置につながります。
企業間取引を電子化する
企業間の受発注業務では、これまでFAXや電話、紙帳票を用いたやり取りが主流でした。しかし、アナログ手法は情報の転記ミスや処理の遅延を招きやすく、業務全体のスピードと精度を損なう原因になります。そこで注目されているのが、取引情報をデジタルデータでやり取りする「企業間取引の電子化」です。
電子化とは、発注書・納品書・請求書などの帳票を、EDI(電子データ交換)やWeb受発注システムを通じて送受信し、すべての記録をデータとして管理することを指します。これにより、紙の印刷や郵送が不要になり、入力作業や確認作業が大幅に削減されます。
たとえば、発注データが自動で基幹システムに取り込まれれば、再入力の手間が省けるだけでなく、処理のスピードも上がるでしょう。また、過去の取引履歴も瞬時に検索でき、トレーサビリティや監査対応にも効果を発揮します。
OCRを活用する
OCR(光学文字認識)とは、紙に印刷された文字や手書きの内容をスキャンし、テキストデータとして認識・変換する技術です。注文書や納品書などを手入力する手間を省き、業務の正確性とスピードを向上させる手段として注目されています。
たとえば、FAXで届いた注文書をOCRで読み取れば、そのままシステムに取り込んで処理を進めることが可能です。とくに、取引先が紙媒体を使い続けている場合でも、自社内だけで自動化や効率化を図れる点は大きな利点です。
アウトソーシングを活用する
受発注業務の一部または全体を外部に委託することで、社内の業務負荷を軽減し、人的リソースを有効に活用できます。とくに、注文データの入力や納期確認、帳票作成などの定型作業は、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業に依頼しやすい業務です。
たとえば、繁忙期に受注件数が急増する企業では、アウトソーシングの活用により業務の遅延を防げるうえに、対応品質も維持されます。また、社内のスタッフはより戦略的な業務や顧客対応に集中でき、全体の生産性向上にもつながるでしょう。コスト面と品質面のバランスを見ながら、導入範囲を検討することが重要です。
受発注業務を効率化する手順

効率化を進める際、いきなりツールを導入するのは得策ではありません。まずは業務の全体像を把握し、問題のある工程や非効率な部分の明確化が重要です。そのうえで、最適な手段を検討・導入し、社内に浸透させていく段階的なアプローチが成功につながります。
ここでは、受発注業務の効率化を実現するための6つの手順を紹介します。
- 現在の受発注フローを整理・可視化して現状を把握する
- 作業の遅延やミスが多い工程を見つけて原因を深掘りする
- もっとも効果的な解決策を選び、実行可能性を検討する
- 一部の業務から新しい方法を試し、改善点を明確にする
- 全社的な導入に向けて関係部署と共有・説明の場を設ける
- 本番運用に切り替え、定着と継続的な改善を図る
順に見ていきましょう。
1.受発注フローを見直す
まず取り組むべきは、業務の全体像を可視化することです。日々の作業が当たり前になっていると、どの工程が非効率なのか見えづらくなるからです。
たとえば、受注から納品までに何人が関与し、どのツールを使っているかを図式化することで、ムダや重複が明らかになります。また、部署ごとの役割や判断ポイントが分かると、業務の流れを俯瞰でき、改善の出発点が見えてくるはずです。
2.ボトルネックを洗い出し、解決策を練る
業務フローを整理したら、次は問題が集中している箇所を特定します。遅延が発生している工程やエラーが頻出する業務には、何らかの課題が潜んでいます。
たとえば、「在庫確認に時間がかかる」「発注の承認に数日かかる」などの事象は改善のヒントとなるでしょう。そのうえで、どのような対策が現実的かを検討し、複数案を比較してください。
3.解決方法を決定する
課題に対して複数の解決策が決定したら、コスト・導入期間・定着のしやすさなどを踏まえて、最適な方法を選定します。全体最適を意識し、単なるコスト削減だけでなく、現場の使いやすさや運用負荷も重視することが大切です。
たとえば、属人化を防ぐにはマニュアル整備だけでなく、誰でも使えるツールの導入が必要です。また、現場との意見交換も欠かせません。
4.テスト的に運用し、改善点を得る
本格導入の前に、限定的な範囲で新たなフローやシステムを試します。小規模なテスト運用を通じて、実際の使い勝手やトラブルの有無を確認してください。
たとえば、特定の取引先だけに新しい発注システムを適用し、問題点を洗い出す段階的な進め方が有効です。現場からのフィードバックをもとに改善を重ねることで、導入後の混乱を防げるでしょう。
5.社内に周知する
新しい業務フローやシステムを導入する際は、現場への浸透が成否を分ける重要なポイントです。単に通知するだけではなく、なぜ変更が必要なのか、どう使えばよいのかを丁寧に伝えることが求められます。とくに、ITツールを用いる場合は、社員一人ひとりのITリテラシーの差を考慮しなければなりません。
そのため、操作方法を共有するだけでなく、社内研修を通じた知識の底上げが効果的です。全員が同じ理解レベルで運用に参加できる環境を整えられると、トラブルや混乱を未然に防げます。
なお、システム運用をする前には社内の理解も必要です。外部リソースによるリスキリング講習を利用するのもよいでしょう。講習に興味のある方は、ぜひこちらよりお問い合わせください。また、リスキリングに関する情報はこちらの一覧も参考になります。
6.本番運用を始める
全体的な準備が整ったら、いよいよ本番運用のフェーズです。あらかじめ想定したスケジュールに従って切り替え、実際の業務に適用していきます。
この段階では、導入効果を測定するための指標(処理時間、エラー件数、対応スピードなど)を設け、定期的な振り返りも重要です。また、運用後も改善の余地は残されているため、現場の声を取り入れながら継続的な見直しを図りましょう。
受発注業務を効率化する5つのメリット

受発注業務が効率化されると、単に作業時間が短縮されるだけではありません。人手によるミスや属人化のリスクが減り、業務全体の生産性が大きく向上します。
ここでは、受発注業務の見直しにより得られる代表的な5つのメリットを紹介します。
- 入力ミスや確認漏れなどの人為的エラーが減少する
- 発注から納品までの対応が迅速かつスムーズになる
- 過不足のない在庫管理がしやすくなる
- 単純作業が減り、本来の業務に専念しやすくなる
- 無駄な手間やコストが削減され、経営効率が高まる
それぞれ見ていきましょう。
ヒューマンエラーが減る
効率化によってもっとも顕著に改善されるのが、作業ミスの削減です。手作業で行っていた入力や確認業務のシステム化により、数量間違いや記載漏れなどのヒューマンエラーの発生率が大幅に下がります。
たとえば、注文内容をExcelで転記していた工程を自動化すれば、数字の打ち間違いや項目のズレが防げます。処理の正確性が上がれば、業務全体の信頼性も向上し、取引先からの評価にも好影響を与えるでしょう。
発注から納品まで迅速に対応できる
業務の流れを見直し、フロー全体の簡素化により処理スピードが格段に上がります。複数の部門や承認ステップを経ることで時間がかかっていた発注業務も、ワークフローの自動化や情報共有の効率化によって短縮可能です。
たとえば、在庫情報と連携した発注システムを導入すれば、残数の確認から注文送信までを一連の流れで完結できます。対応が早くなると、顧客満足度も高まるはずです。
適正な在庫を維持できる
受発注業務が効率化されると、在庫状況をリアルタイムで把握しやすくなります。これにより、過剰な仕入れや在庫不足などの問題が起こりにくくなり、無駄なコストの発生も抑制されます。
たとえば、一定の在庫水準を下回った際に自動で発注をかける設定を導入すれば、タイミングを逃すこともありません。適正在庫の維持は、安定供給やキャッシュフロー改善にも貢献するため重要です。
コアな業務に集中できる
反復的な入力や確認作業に追われる状況が改善されると、社員は本来の業務に時間を割けます。たとえば、営業職であれば、書類対応ではなく顧客提案や関係構築に注力できるでしょう。
管理部門でも、トラブル対応に追われる日々から脱却し、業務改善や分析などの付加価値の高い仕事に時間を使えます。人的リソースを最大限に活かすことが、生産性向上のポイントです。
コスト削減につながる
無駄な作業の削減は、最終的にコスト低減につながります。たとえば、紙の帳票を使った処理では、印刷代・保管スペース・郵送費など目に見えるコストがかかりますが、電子化によってこれらを大幅に削減可能です。
また、人手によるミスが減ると、修正対応にかかる工数や人的リスクも抑えられます。継続的に改善すれば、長期的にも大きな経費節減効果を得られるでしょう。
まとめ:受発注業務の効率化にはkintoneとRPAの活用がおすすめ
本記事では、受発注業務における代表的な課題と、その解決策となる効率化手法を解説しました。とくに、属人化やヒューマンエラー、情報共有の非効率などの問題は、多くの企業に共通する悩みといえるでしょう。
このような課題に対しては、業務を可視化し、適切な手順を踏んで改善に取り組むことが重要です。中でも、柔軟なアプリ作成が可能な「kintone」と、定型業務を自動化できる「RPA」の併用は、高い効果を得られます。
受発注のスピードと正確性を向上させ、コア業務に集中する体制を整えるためにも、ぜひ自社に合った活用法を検討してみてください。
なお、kintoneの導入を検討されている方は、ぜひペパコミの伴走サービスをご覧ください。御社の現場に合ったkintone活用方法を提案いたします。