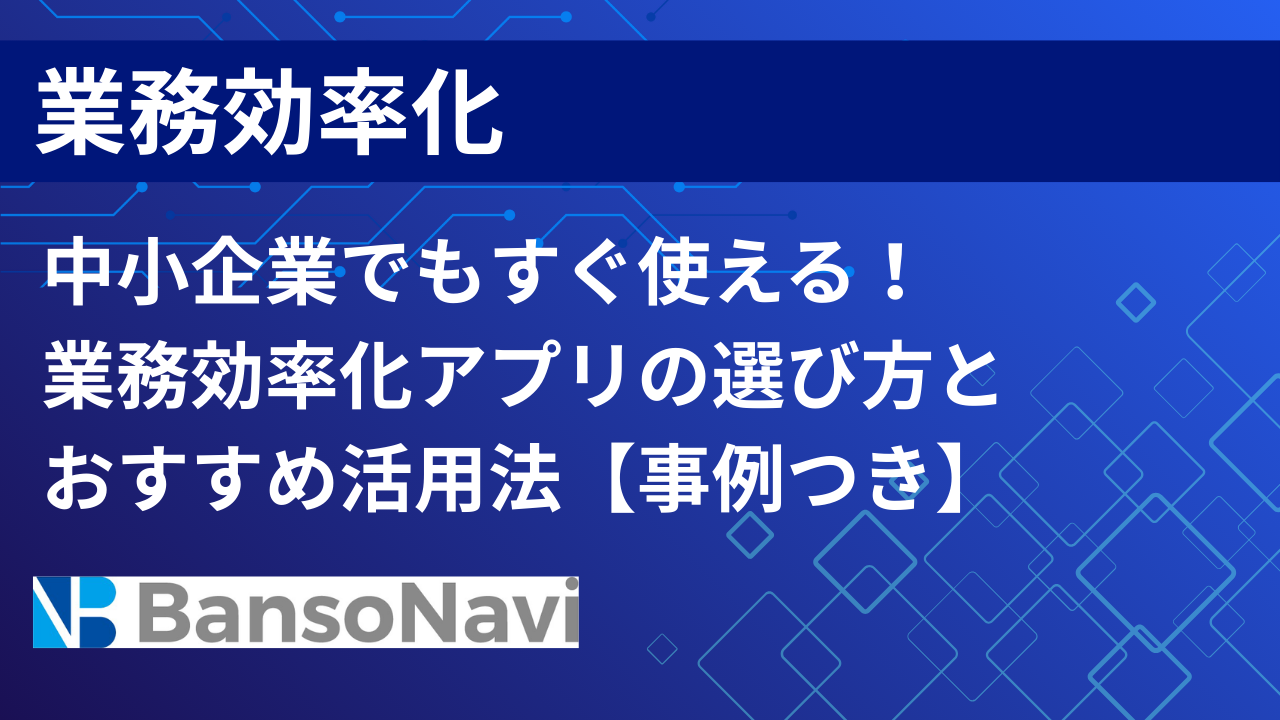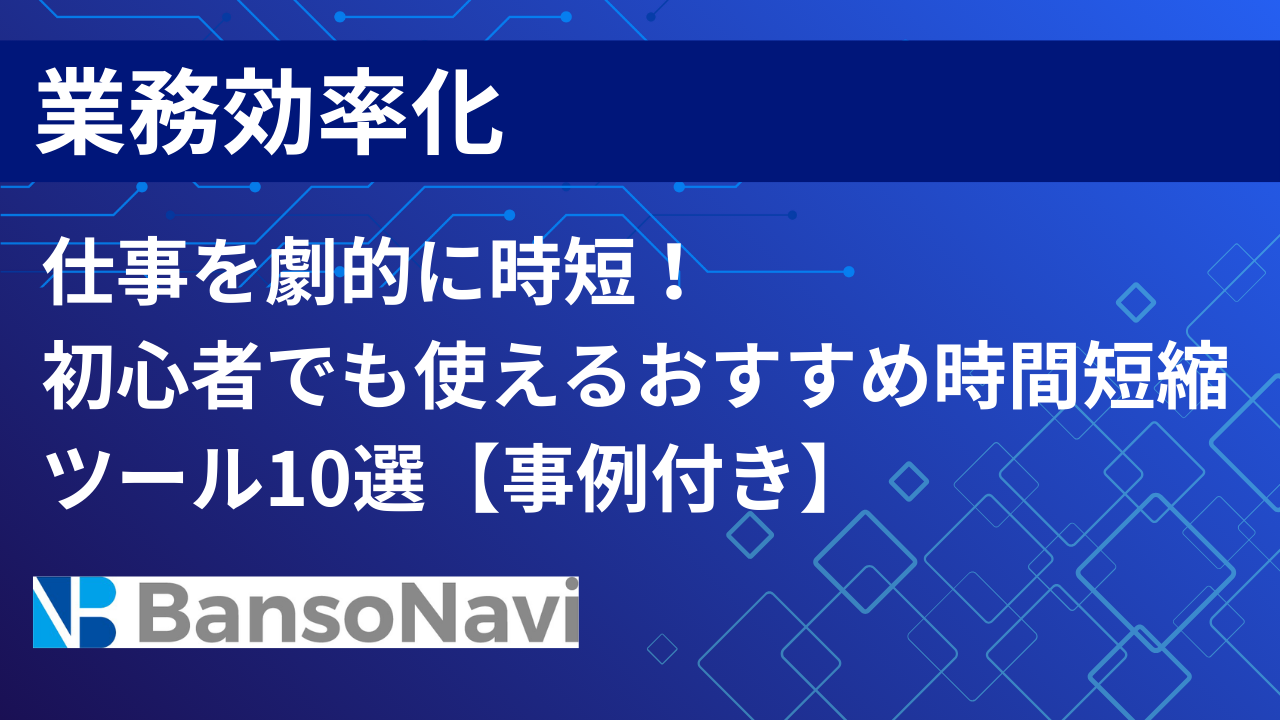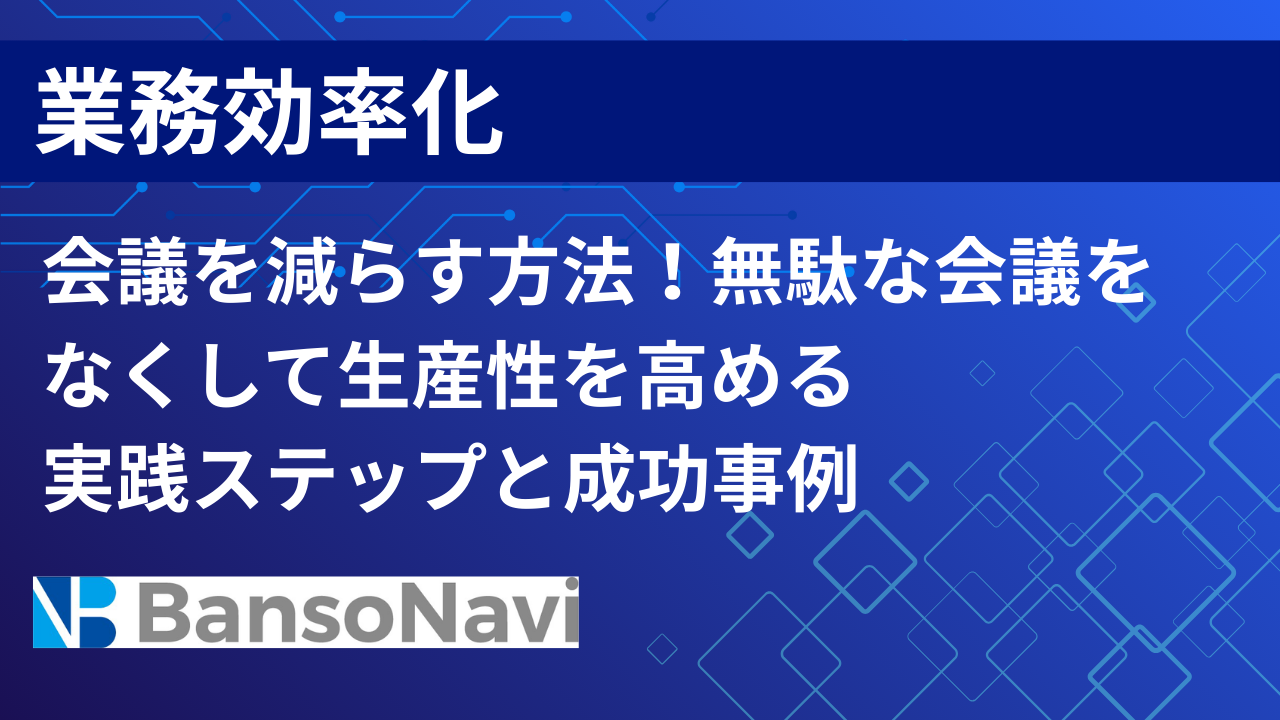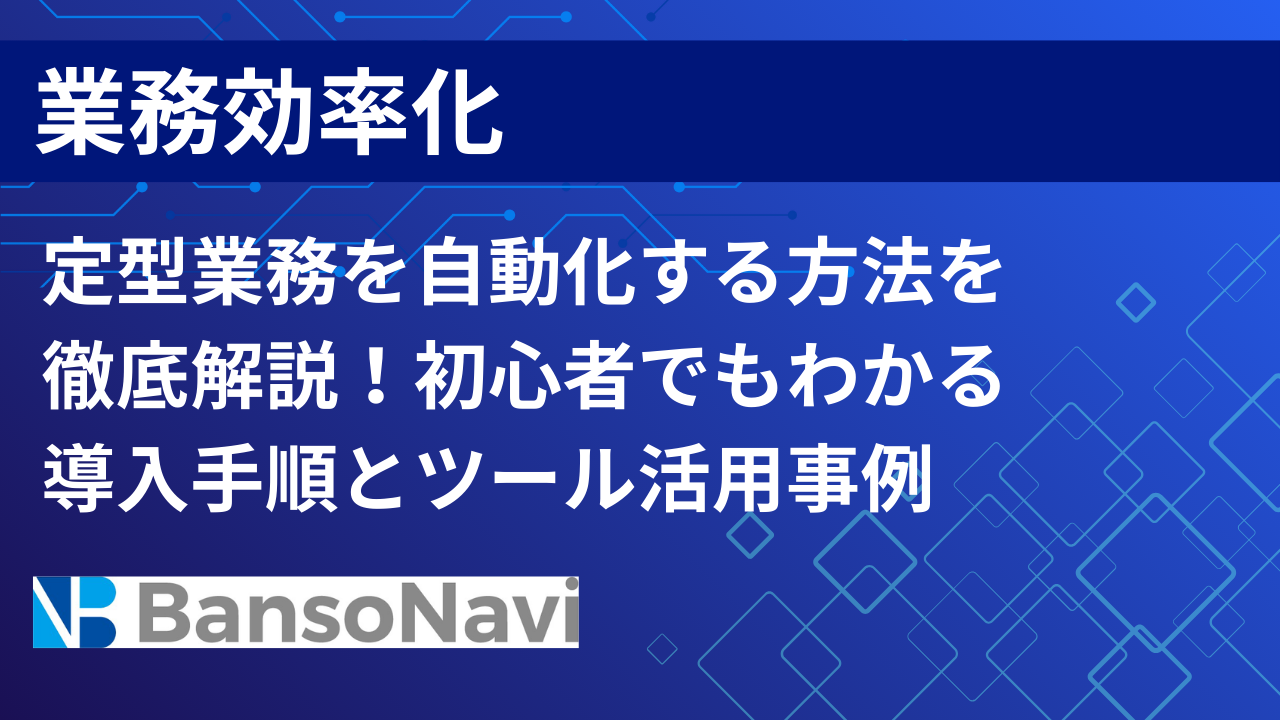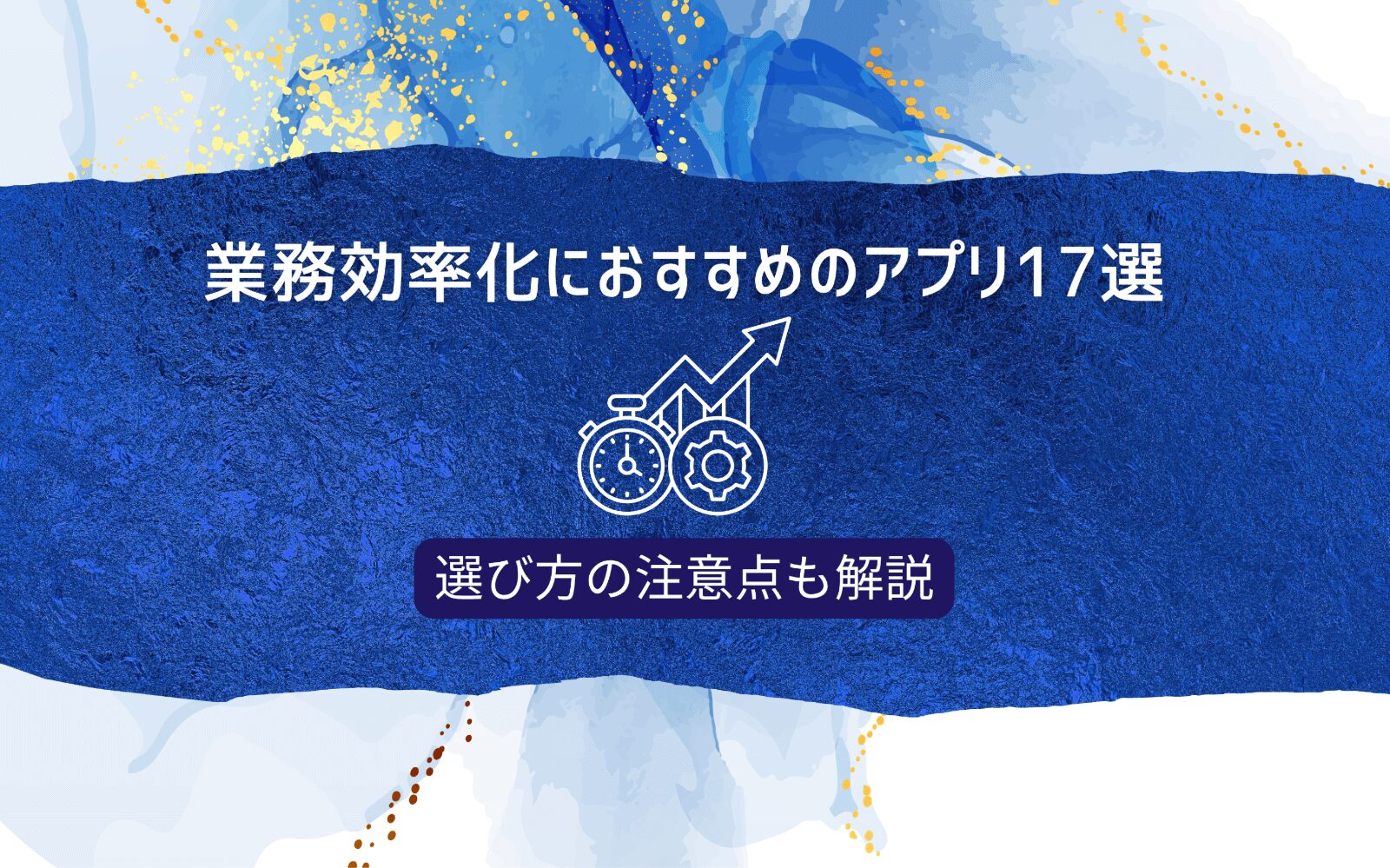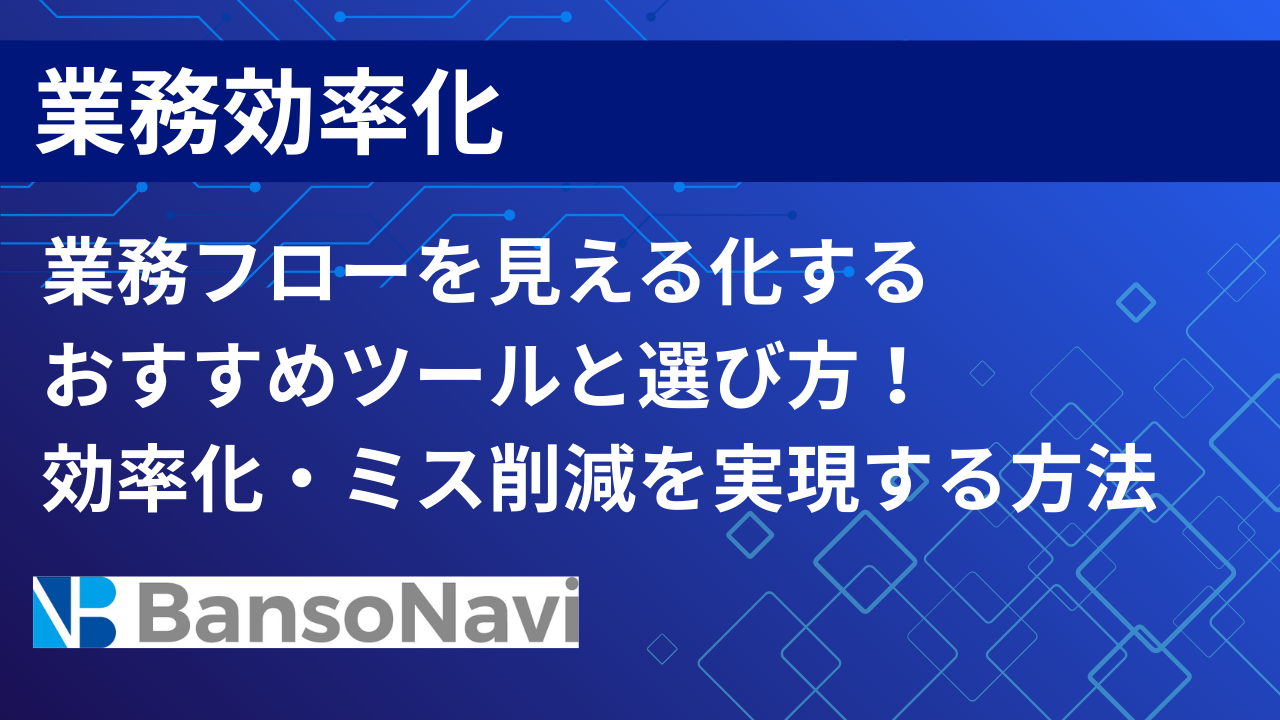業務マニュアルの作り方は?マニュアル作成のコツや運用時の3つの注意点を解説
「業務マニュアルの作り方が知りたい」
「わかりやすいマニュアルを作成するコツや、運用で失敗しないための注意点は?」
このようにお思いではないでしょうか。
業務マニュアルは、業務の標準化や品質向上に不可欠ですが、いざ作成するとなると何から手をつければよいか迷うものです。
本記事では、業務マニュアル作成の基本的な5つのステップから、メリット・デメリット、そして誰が読んでもわかりやすいマニュアルにするための6つのコツまで、網羅的に解説します。
本記事を読めば、マニュアル作成の目的が明確になるほか、すぐに活用できるマニュアル作成の実践的な知識が身につきます。業務マニュアルの作り方に関するお悩みは、「伴走ナビ」にご相談ください。
目次
業務マニュアルの作り方【5STEP】
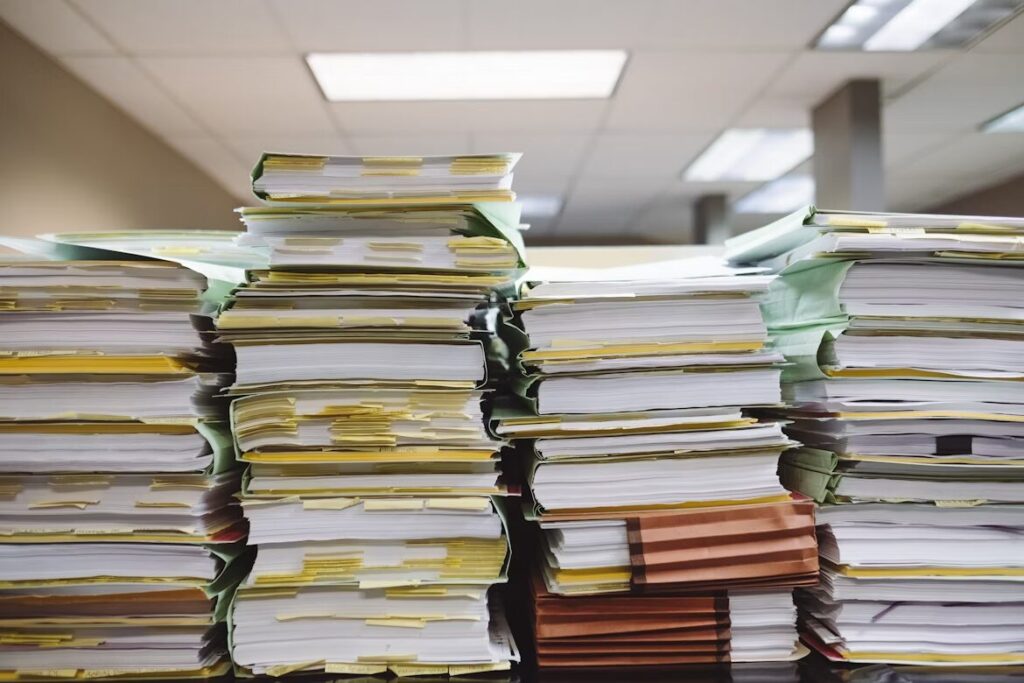
業務マニュアルを効果的に作成し、現場で活用されるものにするためには、計画的に進めることが重要です。ここでは、誰でも実践できる業務マニュアル作成の基本的な5つのステップを解説します。
- 目的や適用範囲を明確にする
- スケジュールを決める
- 業務内容や作業手順を整理する
- マニュアルの構成・フォーマットを決定する
- マニュアルを作成・運用する
この手順に沿って進めることで、抜け漏れがなく、わかりやすいマニュアルを作成できます。
1.目的や適用範囲を明確にする
まず「誰のために、何のために」マニュアルを作成するのかを明確に定義しましょう。新入社員向けの研修用なのか、部署全体の業務標準化のためなのかで、記載すべき内容の深さや専門性が変わるためです。
目的や対象読者を具体的に想定することで、作業の無駄がなくなり、内容のブレを防げます。目的が曖昧なまま作成を進めると、結局誰にも使われない「形だけ」のマニュアルになってしまうリスクがあります。
2.スケジュールを決める
次に、マニュアル作成の全体像を把握し、具体的なスケジュールを立てましょう。いつまでに誰が何を行うのか、計画から完成、承認までの各工程を洗い出し、無理のないタイムラインに落とし込みます。
関係部署や担当者と事前にスケジュール感を共有しておくことで、認識のズレによる手戻りやトラブルを防げます。特に、初めてマニュアルを作成する場合は、想定よりも時間がかかりやすいため、修正や改善の時間を見越して余裕のある日程を設定するとよいでしょう。
3.業務内容や作業手順を整理する

マニュアルに記載する業務の実際の流れや手順を詳細に洗い出します。担当者に直接ヒアリングを行ったり、実際の作業の様子を観察したりして、現場の実態に即した情報を集めることが重要です。
集めた情報は、業務の開始から終了までの一連の流れがわかるように整理し、誰が読んでも同じように作業を再現できるレベルまで手順を明確化します。この工程を丁寧に行うことで、マニュアルの品質が大きく向上します。
4.マニュアルの構成・フォーマットを決定する
マニュアルの全体像を決め、読み手が情報を探しやすい構成を考えます。まず目次や大まかな見出しを先に作成し、全体の骨子を固めることで、内容に一貫性を持たせます。次に、利用する環境に応じて、PDF形式で配布するのか、Webページとして公開するのかといったフォーマットを選択します。
近年では、デザインや更新作業が簡単な専用ツールも多く存在します。特に、ノーコードで業務アプリやシステムを開発できるkintoneのようなツールは、マニュアルの作成・管理にもおすすめです。
kintoneについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:kintoneとは?特徴や業務への活用事例をわかりやすく解説
5.マニュアルを作成・運用する
計画に沿って、マニュアルの本文を作成しましょう。文章は専門用語を避け、図や画像を組み合わせながら、誰が読んでも理解できるように簡潔でわかりやすい表現を心がけてください。
完成後は、必ず複数の関係者に読んでもらい、内容が正確か、わかりにくい点はないかフィードバックをもらって修正します。マニュアルは一度作って終わりではなく、業務内容の変更に合わせて定期的に内容を更新し、常に最新の状態を保つことが重要です。
業務マニュアルを作成する4つのメリット
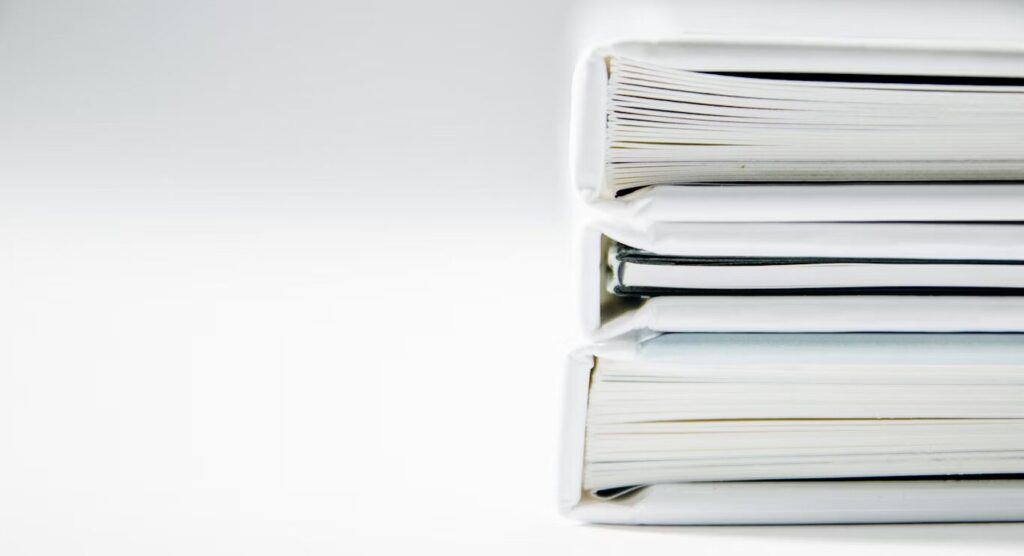
業務マニュアルを作成することは、単に作業手順を記録するだけでなく、企業に多くのよい影響をもたらします。業務マニュアル作成の代表的な4つのメリットを解説します。
- 作業工数を削減できる
- 業務品質の向上が期待できる
- 属人化を防止できる
- ノウハウ共有や引継ぎを円滑にできる
業務マニュアル作成のメリットを理解し、マニュアル作成の目的をより明確にしましょう。
作業工数を削減できる
業務マニュアルによって業務が標準化されると、作業の重複や無駄がなくなり、全体の作業工数を削減できます。誰が作業しても同じ手順で進められるため、自己流の非効率なやり方がなくなり、全体の生産性が向上します。
新人教育の際にも、マニュアルがあれば指導者がつきっきりになる必要がなくなり、教育にかかる時間を大幅に短縮可能です。手順が明確になることで、一つひとつの作業もスムーズに進められます。
業務品質の向上が期待できる
業務マニュアルは、従業員の経験やスキルに関わらず、業務の品質を一定のレベルに保つための指標となります。マニュアルを参照しながら業務を進めることで、作業の抜け漏れやミスを減らせます。
特に、顧客対応や製品の品質管理など、高い品質が求められる業務において、マニュアルは安定したサービス提供に欠かせません。業務マニュアルの作成は、企業全体の信頼性向上にもつながります。
属人化を防止できる
「特定の担当者しかやり方がわからない」といった業務の属人化は、多くの企業が抱える課題です。業務マニュアルを作成することで、業務のプロセスが可視化され、誰でもその業務を担当できる体制を構築できます。
急な担当者の不在時にも業務が滞ることなくスムーズに進められます。業務が個人に依存しなくなることで、組織として安定した業務遂行が可能になります。
ノウハウ共有や引継ぎを円滑にできる
個人の頭の中にしかなかった優れた技術や知識をマニュアルにまとめることで、ノウハウの共有や引継ぎを円滑に進められます。
ベテラン社員が持つ貴重なノウハウが組織に蓄積され、従業員全体の業務品質向上につながります。異動や退職に伴う業務の引継ぎも、マニュアルがあればスムーズかつ正確に行え、引継ぎ漏れによるトラブルを防げます。
業務マニュアルを作成するデメリット

業務マニュアルには多くのメリットがある一方で、作成と運用には相応の労力がかかります。マニュアルを作成する際、業務の洗い出しから整理、執筆、レビューといった多くの工程があり、担当者には大きな負担がかかります。
一度作成しても、業務内容の変更に合わせて更新し続けなければ、情報が古くなり、形骸化したマニュアルになるおそれがあります。この継続的な更新作業が、新たな負担となる可能性も考慮しなければなりません。
わかりやすい業務マニュアルにするための6つのコツ

せっかく作成したマニュアルも、分かりにくくては意味がありません。ここでは、誰が読んでも理解しやすく、現場で本当に役立つマニュアルにするための6つのコツを紹介します。
- 初心者でも理解できる表現を使う
- 5W1Hを明確化する
- 図・表・画像を活用する
- 目次や見出しで全体像を整理する
- 運用しながら定期的に更新・改善する
- ITツールを活用する
業務マニュアル作成のコツを意識するだけで、マニュアルの品質は格段に向上します。
初心者でも理解できる表現を使う
マニュアルを作成する際は、その業務をまったく知らない初心者が読むことを想定し、専門用語や社内用語の使用はできるだけ避けましょう。誰が読んでもわかるような、平易で簡潔な言葉を選ぶことが大切です。
どうしても専門用語を使う必要がある場合は、注釈をつけたり、巻末に用語集を作成したりするなど、意味を補足する工夫をしましょう。読み手の知識レベルを具体的に想定することが、分かりやすいマニュアル作成のポイントです。
5W1Hを明確化する
業務手順を説明する際には、「5W1H」を意識して情報を整理すると、内容が格段に明確になります。5W1Hは以下の6つの要素で情報を整理するフレームワークです。
- 誰が(Who)
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 何を(What)
- なぜ(Why)
- どのように(How)
5W1Hの要素を盛り込むことで、作業の背景や目的が明確になり、読み手の誤解を防ぎ、具体的な行動に直結する、より実践的なマニュアル作成につながります。
図・表・画像を活用する

文章だけの説明では、複雑な作業手順やシステムの操作を伝えるのは困難です。フローチャートやイラスト、実際の画面のスクリーンショットといった視覚的な情報を活用することで、読み手は直感的に内容を理解できます。
視覚的な情報は、記憶に残りやすいという利点もあります。情報の正確性は当然ながら、いかに「伝わりやすく」するかという視点を持つことが、質の高いマニュアル作成には不可欠です。
目次や見出しで全体像を整理する
マニュアルを読む人が、必要な情報にすぐにたどり着けるように工夫することも重要です。マニュアル全体の構成がひと目でわかる目次を作成し、情報を整理しましょう。
内容の区切りごとに適切な見出しをつけることで、読み手は自分の知りたい情報がどこにあるかを簡単に見つけられます。情報を階層的に整理し、関連する内容をグループ化することで、全体の構造が理解しやすくなり、検索性も向上します。
運用しながら定期的に更新・改善する
業務マニュアルは、一度作ったら終わりではありません。業務のやり方や使用するシステムは日々変化するため、マニュアルも変化に合わせて随時アップデートする必要があります。
更新作業の担当者を一人に限定せず、複数人でレビューする体制を整えることで、属人化を防ぎ、継続的なメンテナンスが可能になります。現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、常に最新かつ最適な状態を維持することが、形骸化を防ぐ鍵です。
ITツールを活用する

マニュアルの作成や更新、共有を効率的に行うためには、ITツールの活用が非常に有効です。専用のマニュアル作成ツールやクラウドサービスを利用すれば、フォーマットが統一され、誰でも簡単に見栄えのよいマニュアルを作成できます。
クラウド上で管理すれば、関係者はいつでもどこからでも最新版にアクセスでき、更新も容易になります。特に、ノーコードで業務システムを開発できるkintoneのようなツールは、マニュアル管理の基盤としても活用できます。
業務マニュアルとして活用できるkintoneのデータベース機能について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事:kintoneはデータベースとして利用可!アクセスやエクセルとの機能の違いについても解説!
業務マニュアルを運用する際の3つの注意点

マニュアルを効果的に運用し続けるためには、いくつかの注意点があります。業務マニュアルを組織に定着させるための3つの注意点を解説します。
- 変更点を必ず関係者に共有する
- 効果を定量的・定性的に測定する
- 原本を保存しておく
業務マニュアルを運用する際の注意点を押さえることで、マニュアルの価値を最大限に引き出せます。
変更点を必ず関係者に共有する
業務マニュアルの内容を更新した際は、その変更点をすべての関係者への共有を徹底してください。十分にマニュアルの変更点を周知しないと、業務の進め方を統一できず、現場で混乱が生じる可能性があります。
変更履歴をマニュアル内に記録し、いつ、誰が、どこを、なぜ変更したのかを明確にすることも重要です。更新内容を共有する際に、従業員からフィードバックをもらう機会を設けることで、より現場の実態に合ったマニュアルへと改善できます。
効果を定量的・定性的に測定する
マニュアルを導入した効果を定期的に測定し、改善に役立てましょう。効果測定には、作業時間の削減率やエラーの発生率といった「定量的」な視点と、従業員の使いやすさや理解度といった「定性的」な視点の両方が必要です。
数値データは客観的な改善点の発見に役立ち、アンケートやヒアリングで得られる定性的な意見は、数値では見えない課題を浮き彫りにします。この両面からの評価を繰り返すことが、マニュアルの品質向上に効果的です。
原本を保存しておく
マニュアルを更新する際には、誤って重要な情報を削除してしまったり、変更内容に誤りがあったりする可能性があります。万が一の事態に備えて、必ず更新前の原本(バックアップ)を保存しておきましょう。
原本を参照できる体制を整えておくことで、更新に伴うトラブルを未然に防ぎ、安心して改訂作業を進められます。バックアップデータは、不正なアクセスやデータ消失のリスクを避けるため、セキュリティ性の高い環境で管理しましょう。
業務マニュアル作成は外部の専門家による支援がおすすめな理由

業務マニュアルの作成は、高品質なものを目指すほど多くの工数がかかります。DX支援などを手掛ける外部の専門家による支援の活用も有効な手段です。
専門家は、豊富な経験と実績に基づき、わかりやすく、業務の実態に即した高品質なマニュアル作成を支援してくれます。外部の客観的な視点から、社内だけでは気づきにくい業務プロセスの課題点を指摘し、改善提案をもらえるメリットもあります。
専門家に作成を依頼することで、自社の従業員は本来のコア業務に集中でき、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。
業務マニュアルの作り方のお悩みは「伴走ナビ」にご相談ください

業務マニュアルは、目的を明確にし、計画的に作成・運用することが重要です。業務マニュアルを作成することで業務効率化や品質向上、属人化防止などのメリットが期待できますが、その一方で作成・更新には相応の負担がかかります。
分かりやすい表現や図表の活用、定期的な更新を徹底し、必要に応じて専門家の支援も視野に入れることで、その効果を最大限に引き出せます。
業務マニュアルの作り方についてお悩みであれば、ぜひ「伴走ナビ」にご相談ください。