顧客情報を一元管理する必要性とは?顧客管理システム(CRM)の4つの選び方も解説
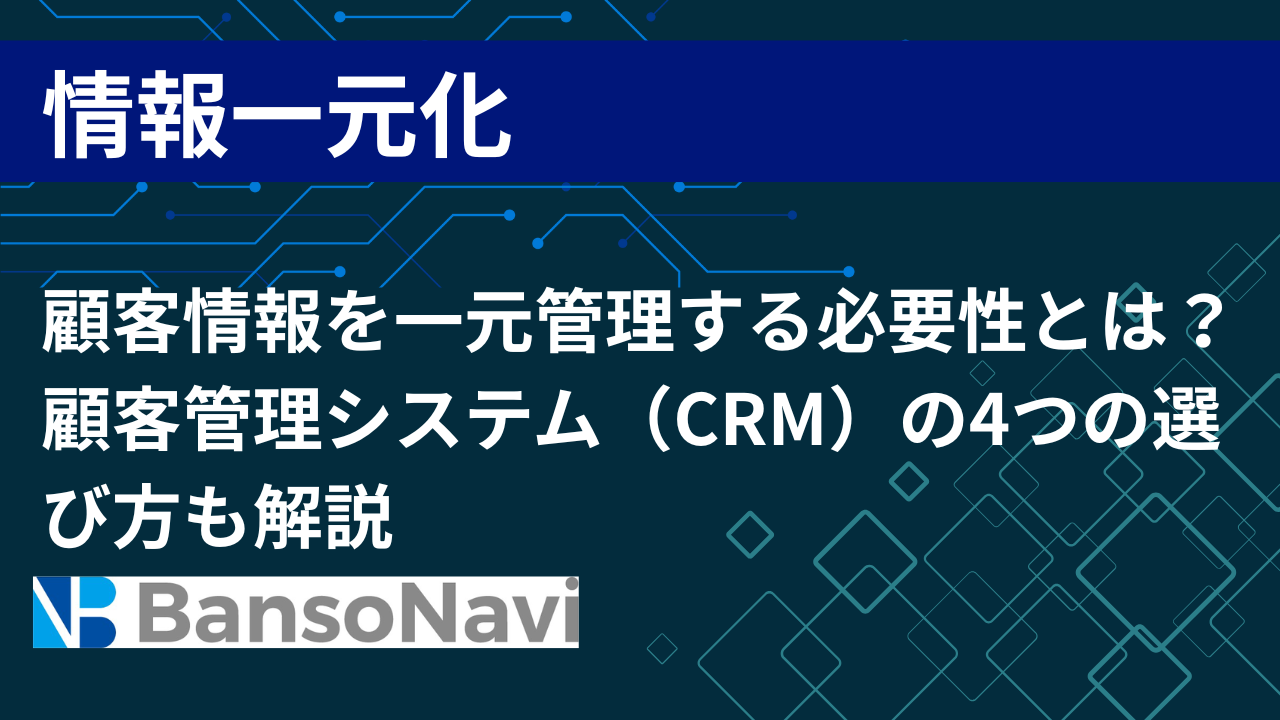
顧客情報がメールや表計算、名刺アプリなどに散らばっていると、最新状況が見えにくくなり、抜け漏れや重複連絡が起きやすく、受注までの道のりも長くなりがちです。そのため、まずは顧客情報を一元管理する必要性を把握するのが大切になります。
そこで本記事では、顧客情報を一元管理する必要性やメリット、注意点から顧客管理システム(CRM)の選び方を解説します。
また、伴走ナビなら導入設計や要件整理を短時間で固めたい場合、要件定義からツール比較、移行設計まで支援します。これから顧客管理の一元管理を実施したい企業は、最適な進め方を一緒に描きましょう。
目次
顧客情報を一元管理する必要性

顧客情報が部署やツールごとに散らばると、最新の状況を追うだけで時間が奪われ、重複対応や見落としも起きやすくなります。
そこで、まずは一元管理の狙いと期待できる変化を整理し、何から着手するかの判断軸を明確にしましょう。
- 顧客ニーズに応じたアプローチできるため
- 顧客情報を分散管理するよりセキュリティ性が強化されるため
以下の観点を押さえると、集約の意義が数字目標や現場の動きに結びつきやすくなります。
顧客ニーズに応じたアプローチできるため
一つの画面で問い合わせ履歴や検討段階、よく閲覧された資料を横並びで見られると、次に届ける情報が明確になります。
例えば、新規見込み顧客には全体像や導入の事例、既存顧客には活用の深掘りと追加提案を用意しやすい状態に変わります。
顧客との会話の流れと資料の順番がそろうため、意思決定までのやり取りが短くなり、失注理由の分析を行うことが可能です。また、過去の接点と直近の反応を結び、次回行動の理由を一言で説明できるようになる点も重要です。
顧客管理を一元管理すれば、担当者が交代しても提案の狙いが継続しやすく、資料の使い回しや重複連絡が減少します。
その結果、商談の質とスピードが同時に高まり、受注後の活用提案にも展開しやすくなります。
顧客情報を分散管理するよりセキュリティ性が強化されるため
顧客情報の保存先がメールや個人の端末などに分散してしまうと、最新性の確認やアクセスの追跡が難しくなります。しかし、保管場所を統一し閲覧権限の最小化や操作ログの記録を徹底すれば、誤送信や無断持ち出しのリスクが低減します。
さらに、退職や異動の停止手続きも手軽に完了するため、監査や点検の手順を均一化させることが可能です。また、重要度ごとの分類や外部共有の期限設定などとあわせて運用すると、確認漏れや管理不足によるデータ損失などの事故の防止にもつながります。
そのため、企業でセキュリティ性を強化し信頼や信用を獲得するためにも、顧客情報の一元管理は重要です。
顧客情報を一元管理する方法

顧客情報の集約には、複数の手段があります。そのため、導入コストや運用のしやすさ、連携の柔軟さなどを比較し、自社に適した方法を選定するのが大切です。
これから顧客情報の一元管理方法を検討している企業は、以下の表を参考にしてみてください。
| 手順 | 強み | 注意点 |
| CRM | 顧客の基本情報と履歴をまとめて扱える | 運用設計が甘いと入力が続かない |
| Excel/スプレッドシート | 着手が早い。集計の自由度が高い | 人数が増えると更新が衝突しやすい |
| MA | 反応データを集約し、育成を自動化できる | 事前のシナリオ設計が不可欠 |
| SFA | 商談や案件の見通しを全員で共有できる | 項目設計と入力ルールが要点 |
| 名刺管理 | 接点情報を素早くデータ化できる | 顧客マスタとの突合が必要 |
顧客管理システム(CRM)を活用して管理する
顧客管理システム(CRM)を導入すると、顧客台帳や対応履歴や契約情報が一つのツールに集約されます。
さらに、メールや商談メモや請求の仕組みと連携すれば、入力の重複が減り更新遅延も抑えることが可能です。また、画面上で顧客との接点の流れを時系列に追えるため、次回の連絡内容や提出資料が即座に判断できます。
顧客管理システムのほとんどは、権限設定と操作ログで閲覧範囲を絞れるため、初めてでも操作が手軽に行えます。そのため、ダッシュボードで失注理由や滞留案件を見つけ、取引履歴から再提案の時期を導き出す活用も進みます。
Excelやスプレッドシートで管理する
Excelやスプレッドシートなどの表計算ツールは準備が早く、列の並びや集計方法を自由に調整できます。
顧客名や担当者や最終接点や次回行動を列でそろえることで、条件付き書式で期限超過の強調が可能です。さらに、共有は編集者を限定し、更新日時と更新者を必須にすれば可能です。
ただ、顧客情報が増加するほど動作が重くなりやすいため、ファイル分割やデータベース移行を検討するようにしましょう。
MA(マーケティングオートメーション)
MA(マーケティングオートメーション)は、Web閲覧やメール反応やフォーム送信などの接点データを集め、関心度を数値で示します。
それぞれのスコアに応じて内容や頻度を切り替え、関係が深い見込み顧客には比較情報、検討前の見込み顧客には課題整理の資料を届けます。さらに、配信停止の窓口や同意の管理を台帳化し、追跡の範囲を明確にできるため、わかりやすい管理が可能です。
商談化した見込み顧客であれば、SFAやCRMへ自動連携すれば、引き継ぎの速度と品質をそろえられます。
SFA(営業支援システム)
SFA(営業管理システム)は、営業活動の記録と案件の段階管理を一枚のパイプラインで共有できます。
主に、面談や電話の記録と次回行動を管理し、担当者が交代した場合でも会話の内容や流れが一目で把握が可能です。さらに、成約確度や見込み額を統一基準で入力すれば、予測とレポート精度が向上します。
また、CRMやMAとの連携すれば、期日超過の自動通知やモバイル入力で滞留を減らし、重複入力を避けられます。
名刺管理ツール
名刺管理ツールは、紙の情報を短時間でデジタル化するため、重複の防止と情報の検索性が向上します。
部署横断で顧客との接点が可視化できるため、紹介依頼や同席調整の判断が早めることが可能です。
例えば、展示会で集めた名刺を当日中に全社共有すれば、名刺交換後の初回連絡が遅れにくくなります。また、外部交換機能やスキャン端末を活用すれば、CRMの顧客情報と照らし合わせて新規登録へつなげられます。
顧客情報を顧客管理システム(CRM)で一元管理する3つのメリット

CRMで情報を集約すると、提案の質、連携の速さ、引き継ぎのしやすさがそろって向上します。現場の体感が変わるため、入力の継続にもつながります。
ここでは、顧客情報を顧客管理システム(CRM)で一元管理する3つのメリットを紹介します。
- 一元管理した顧客情報を活用して営業活動ができる
- 顧客情報の共有がリアルタイムで実現できる
- 顧客情報管理の属人化を解消できる
顧客情報の管理を一元化したいと考えている方は、ぜひご参考ください。
一元管理した顧客情報を活用して営業活動ができる
顧客管理システム(CRM)で顧客情報を一元管理すると、提案の筋道が明確になり成約率の向上が見込めます。
主に、購入履歴や商談履歴、問い合わせ履歴などを同じ画面で比較し、顧客の関心の高さと検討段階を見極めることが可能です。
そして、次回行う連絡の内容と時期を具体化し、資料の順番を明確化させられます。さらに、セグメントごとに訴求軸を切り替え、新規顧客には全体像、既存顧客には活用拡張を提示するなどします。
また、ダッシュボードで滞留案件や失注理由を可視化し、再アプローチの順番を定めることで、顧客満足度の向上や、商談の往復感覚の短縮が可能です。
顧客情報の共有がリアルタイムで実現できる
顧客管理システム(CRM)では、顧客情報の保存と同時に更新が反映されるため、場所や時間を問わず全員に最新状態を共有できます。
活動履歴や担当者、次回行動や見積が即時にそろうため、判断と業務連携をスムーズに進められるようになります。さらに、パソコン以外にもモバイル入力で外出先から記録できるため、帰社後のまとめ作業の削減が可能です。
表計算ツールでは、同時編集をした場合に競合や保存失敗が発生しやすいですが、CRMならアクセス権と操作ログで更新者を明確にでき、会議前の確認の往復をも削減できます。
その結果、顧客からの問い合わせに応答するまでの時間が短縮し、機会損失を抑えることが可能です。
顧客情報管理の属人化を解消できる
顧客管理システム(CRM)の標準項目と入力ルールを使用すれば、個人のノウハウやスキルに頼る管理体制から脱却できます。
顧客管理システムを使用し、案件の段階や関係者、決裁フローや商談メモを同じ形式で保存できるため、誰が見ても状況の把握が容易です。
表計算ツールでは、独自関数や隠し列に依存しやすいため、属人化しやすく引き継ぎの際にかかる負担が大きくなります。一方、顧客管理システムでは必須項目でデータ抜けを防ぎ、テンプレートで記録のばらつきを抑えます。
さらに、権限設定と通知でレビューの流れを固定し、欠員や異動があった際でも品質が一定に保たれるような体制を整えることが可能です。
顧客情報を顧客管理システム(CRM)で一元管理する3つの注意点

顧客管理システム(CRM)は、導入だけで成果が出るわけではありません。運用の型づくりと権限設計まで含めて準備します。
ここでは、顧客管理システム(CRM)で一元管理する際の注意点を紹介します。
- 成果を得られるまでに時間がかかる
- 社内で運用が定着しない場合がある
- 社内でのセキュリティ対策が疎かになる場合がある
顧客管理でつまずかないためにも、それぞれ確認していきましょう。
成果を得られるまでに時間がかかる
顧客管理システム(CRM)の導入直後は、データ入力や設計などに時間や手間がかかります。
特に、段階ごとの必須項目・入力の締め切り・集計の粒度などをあらかじめ決め、四半期単位で指標を追う必要があります。そのため、導入直後はほとんど成果を得られないことがありますが、しっかりと運用すれば案件化率や受注率の改善・向上が実現可能です。
そのため、顧客管理システムを導入した際は焦らずに手順を固め、少しずつ範囲を広げていきましょう。
社内で運用が定着しない場合がある
顧客管理システム(CRM)は、使いにくい画面や過剰な項目がある場合、社内で運用が定着しない場合があります。そのため、役割ごとに必要な表示に切り分け、現場の作業に合う順番で並べ替えるようにしましょう。
例えば、朝夕の入力時間を短くするために、テンプレートとショートカットを用意するなどの対策がおすすめです。また、運用ルールのマニュアル化や最初の一週間の並走、週次のチ確認をセットで実施し、定着するまで徹底管理しましょう。
社内でのセキュリティ対策が疎かになる場合がある
顧客管理システム(CRM)の機能に依存せずに、社内の運用体制を整えることも大切なポイントです。
例えば、閲覧権限の最小化や外部共有の期限、退職時の停止手順を具体化するのが効果的な方法になります。さらに、持ち出しの監査とアクセスログの確認を月次で実施し、違和感が出た場合は即時の調査体制を決めるようにします。
保存データの分類も定義し、重要度に応じて保護の強さを変えることで、社内でのセキュリティ体制を強固に保った状態で運用が可能です。
顧客管理システム(CRM)を選ぶ際の4つのポイント

顧客管理システム(CRM)を選ぶ際は、人気や知名度などを確認するだけでなく、しっかりと自社に適した機能性や費用対効果か確認することが大切です。
ここでは、顧客管理システム(CRM)を選ぶ際の4つのポイントを紹介します。
- 機能性が充実しているか確認する
- 操作しやすいか確認する
- セキュリティ対策が充実しているか確認する
- 費用対効果を確認する
それぞれ、解説していきます。
機能性が充実しているか確認する
顧客管理システム(CRM)を選ぶ際は、機能性が充実しているか確認するのが大切です。
例えば、顧客台帳・履歴・案件・レポートの基本機能などに加えて、他のツールと連動できるかなどを確認します。また、見積や請求、メールの連携を通じて更新の重複を減らせるかを確認するのも大切なポイントです。
自社に最適な機能性か判断するためには、自社の必須項目を洗い出し、導入前に設定の再現性を確認しましょう。この時、機能性が十分でないと感じた場合は、追加での開発やツール連携などで補えるかを確認します。
操作しやすいか確認する
操作しやすいか確認するのも、顧客管理システム(CRM)を選ぶ際に大切なポイントの1つです。
特に、ツールで行う顧客情報の入力の流れが現場の作業順か・新規登録から履歴の追加・案件の更新までのクリック数・検索の挙動・スマホでの扱いやすさなどを確認します。
また、画面表示の切り替えや並び替えが分かりやすいほど、社内での運用が定着しやすくなります。
そのため、導入する際は事前にお試しとして数日運用し、朝夕の入力にかかる時間を実測しましょう。
セキュリティ対策が充実しているか確認する
顧客管理システム(CRM)を導入する際は、セキュリティ対策が充実しているかも確認しておきましょう。
主に、多要素認証・権限の細分化・操作ログの記録・暗号化の有無を確認し、外部共有リンクの管理・保存期間の設定・監査のレポート出力がそろっているかを確認します。
セキュリティ対策が充実しているツールであれば、顧客情報の漏洩や不正アクセスなどのリスクを削減できるため、とても重要なポイントです。
費用対効果を確認する
顧客管理システム(CRM)は、月額費用だけでなく、初期設定や教育、移行にかかる費用や負担を含めて見積もりを行いましょう。
さらに、入力時間の短縮・重複対応の削減・案件化までの期間短縮などの効果を金額に置き換え、三か月と一年の二軸で比較すると、より正確に費用対効果を図ることが可能です。
これから導入する際は、費用だけでなく機能性などを考慮して、導入するルールを選ぶようにしましょう。
顧客情報の一元管理に関する相談なら「伴走ナビ」へ相談しよう!

顧客情報の集約は、重複対応や記録の抜けを減らし、商談の進み方をそろえます。
部門横断で最新の接点と履歴を見渡せるため、引き継ぎの負担が軽くなり、担当が替わっても提案の質を保てます。一方で、導入直後から成果が得られることはあまりありません。
顧客管理システム(CRM)は、入力項目の設計や権限の整理、移行準備に時間がかかることを考慮しておきましょう。
また、顧客情報の一元化が進むほど権限の穴や情報持ち出しの危険性も可視化できるようになるため。運用ルールと監査手順を先に固める姿勢が必要不可欠です。
システム選びで悩んでいる場合は、機能性や操作性、セキュリティ性や費用対効果を確認するようにしましょう。
また、伴走ナビは現場の課題整理から要件定義、ツール比較や移行・教育、ダッシュボード設計まで一気通貫でサポートします。これから顧客情報の一元管理を実施したいと検討している企業は、伴走ナビに相談しましょう。








