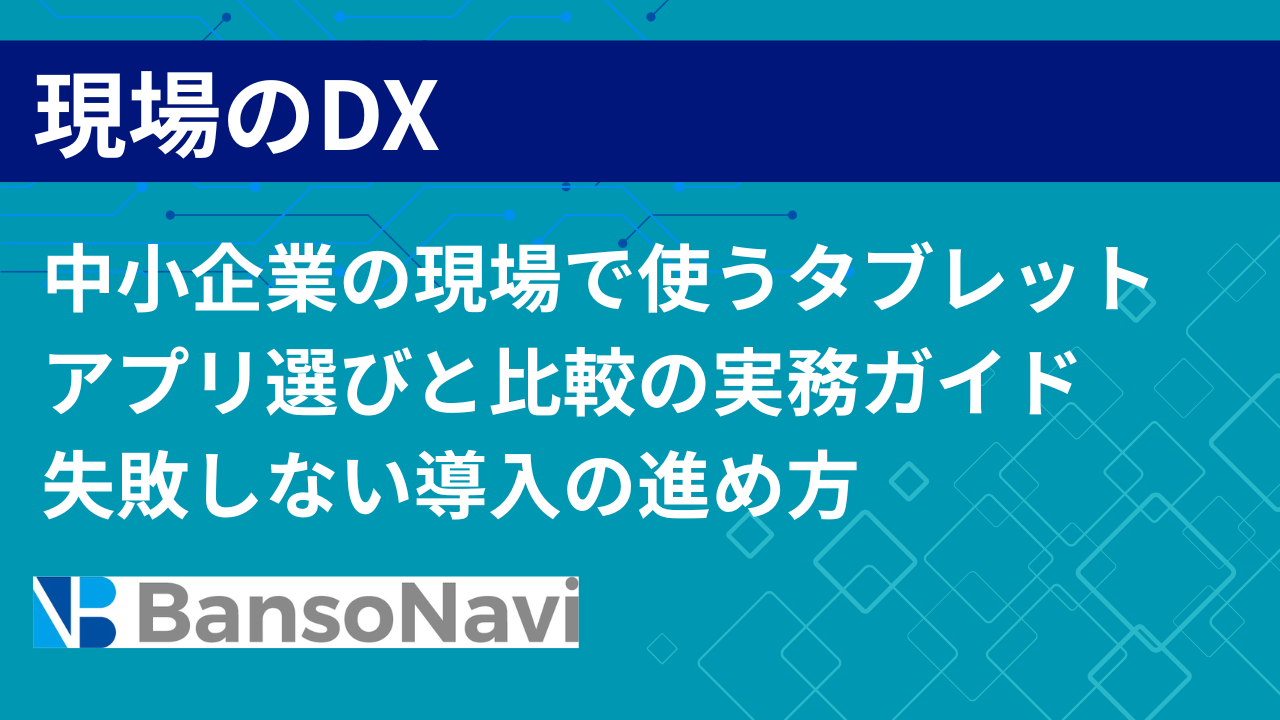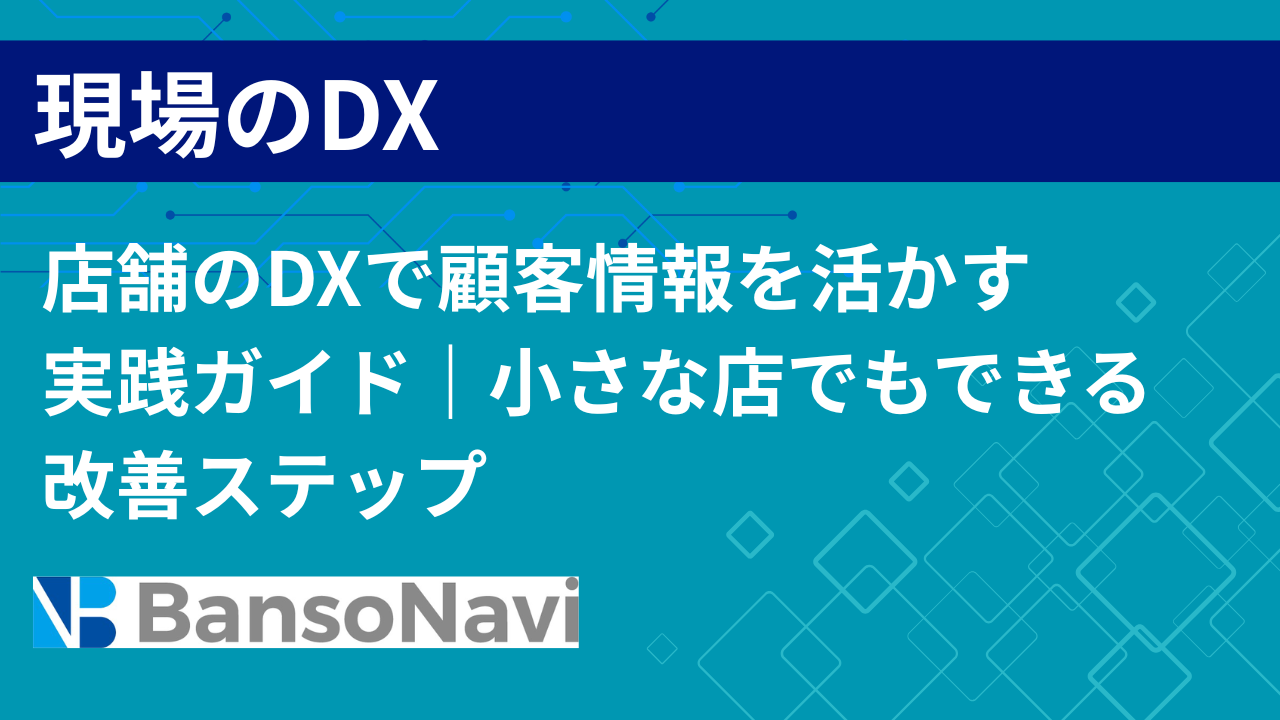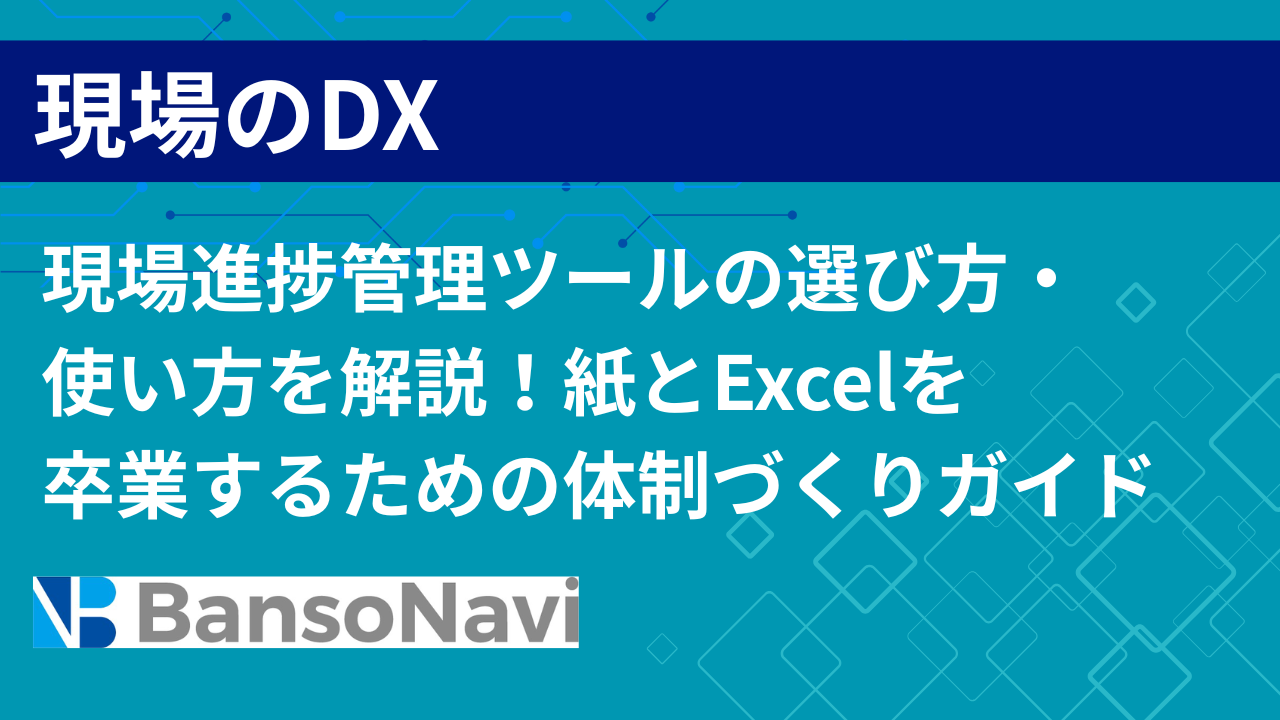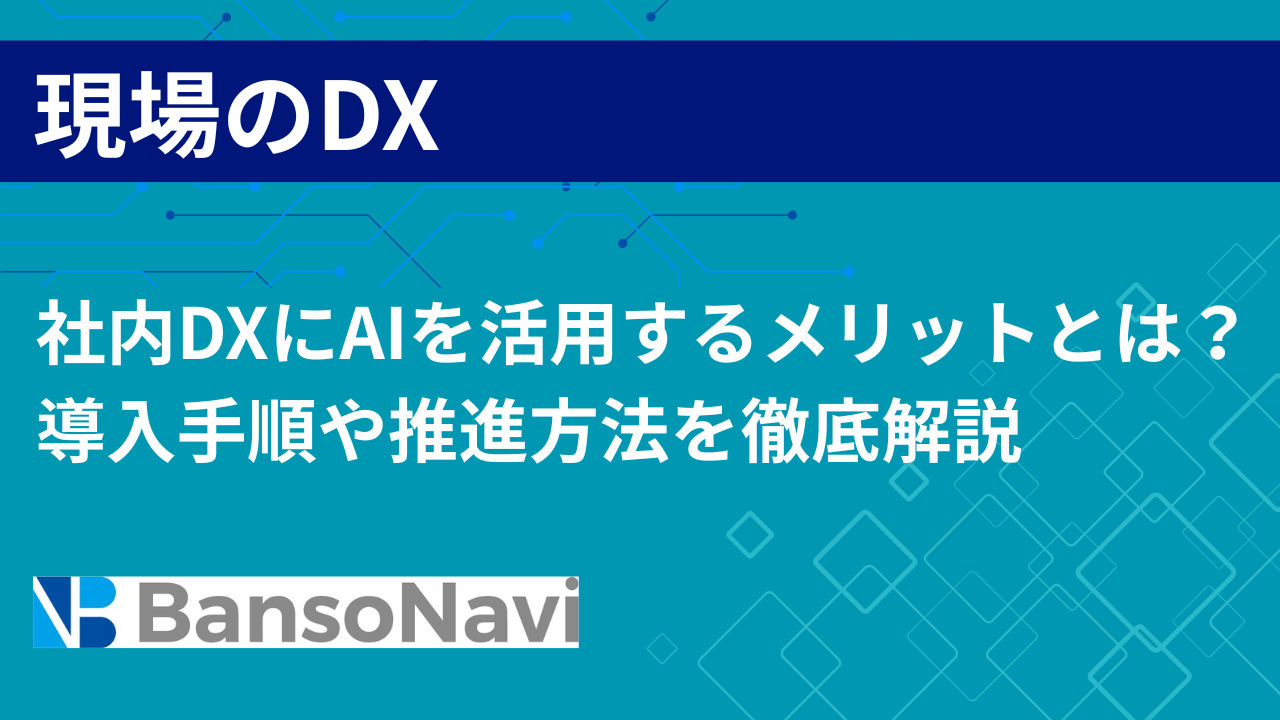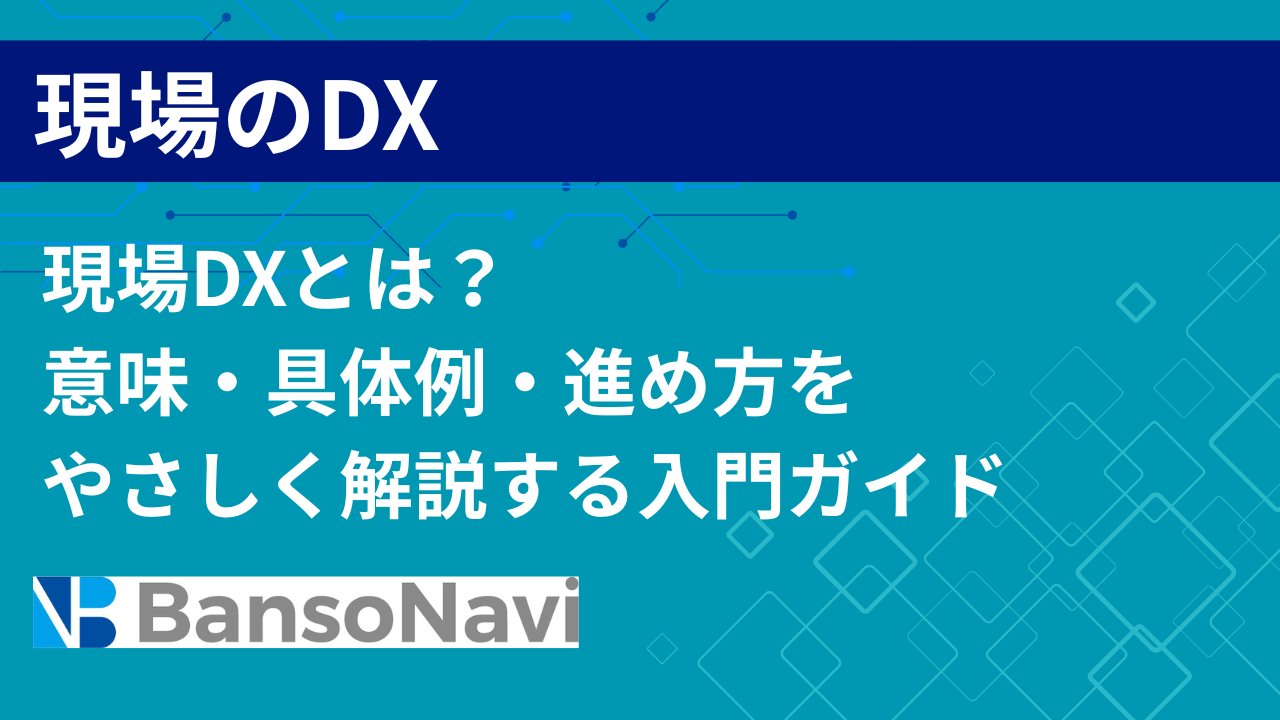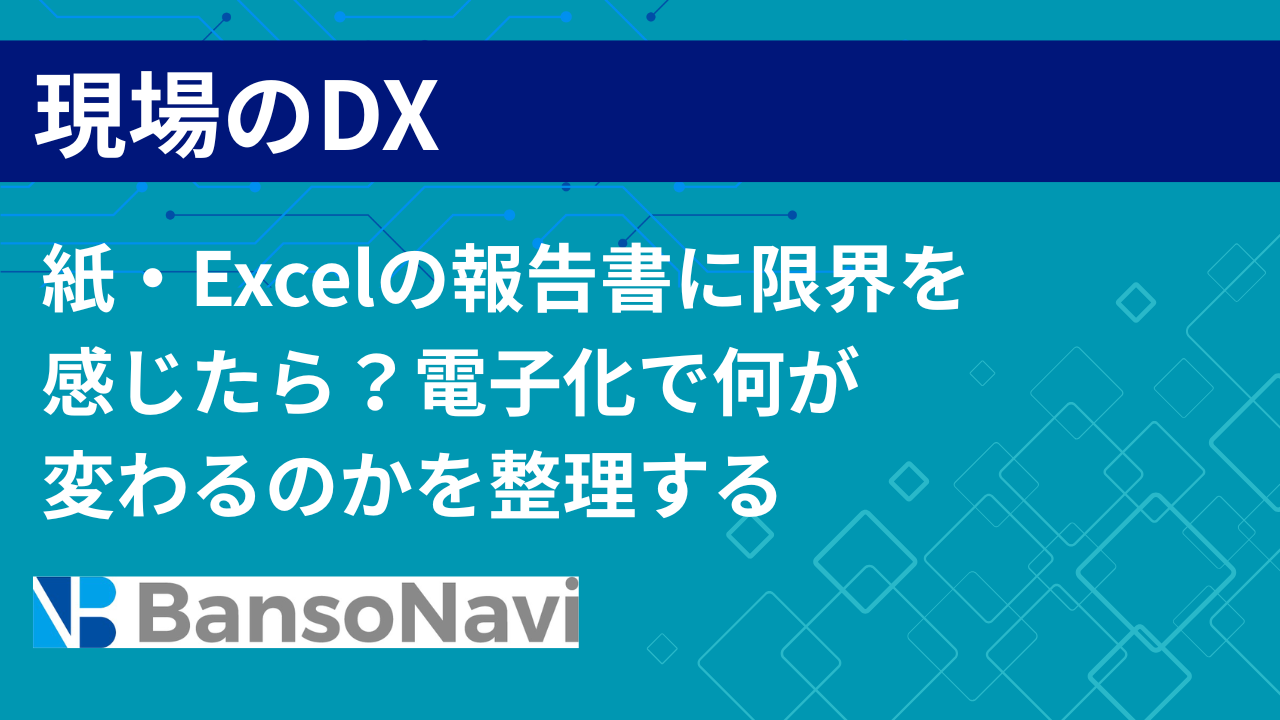DXで小売現場はここまで変わる!今から始める“ムリしないDX 小売”入門と成功イメージガイド
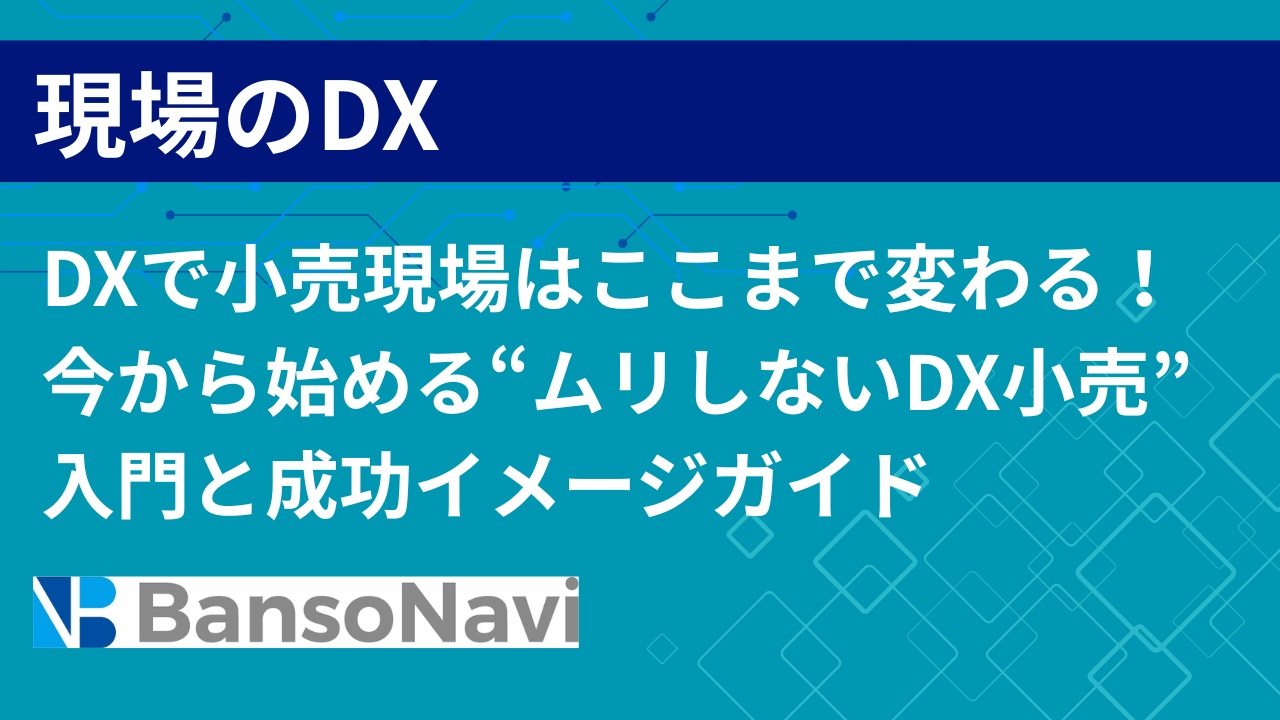
「DXが大事と言われるけれど、正直よく分からない」「うちみたいな小さな小売でもDX 小売なんて必要?」と感じている方は多いと思います。ニュースやセミナーではかっこいい事例が並びますが、目の前には紙の発注書やExcel、レジ締めやシフト調整など、毎日の業務が山積み。どこから手を付ければいいのか分からないのが本音ではないでしょうか。
本記事では、DX 小売で検索している方が知りたいであろう次のポイントを、できるだけ専門用語をかみ砕いて解説します。「そもそもDXとは何か」「小売現場のどこから始めれば良いか」「どんなツールがあるか」「失敗しない進め方」「導入後にどう変わるのか」を一通り押さえたうえで、最後に、伴走ナビが得意とするDXの内製化支援やkintone活用を、押しつけにならない形でご紹介します。読み終えた時に、「まず社内でこの話をしてみよう」「一度無料相談や資料請求で話を聞いてみよう」と思ってもらえることをゴールにしています。
目次
小売業でDXが必要と言われる本当の理由

DX 小売と聞くと、「AIレジ」「ロボット」「フル自動の倉庫」のような派手なイメージが先に浮かび、「うちには関係ない」と感じる方も多いはずです。でも現場に目を向けると、人手不足、紙とExcelだらけの管理、属人化した発注、在庫ロスや機会損失など、どの小売業でも似たような悩みがあります。DX 小売とは、こうした悩みをデジタルの力で少しずつ減らし、売上や利益、働きやすさにつなげていく取り組み全体だと捉えると、ぐっと身近に感じられます。
DXとIT導入の違い
DXという言葉はあちこちで聞きますが、「結局何なの?」という状態のままの人も多いと思います。ざっくり言えば、DXとは「デジタルの力を使って、ビジネスや働き方そのものを良い方向に変えていくこと」です。単に新しいシステムを入れるだけでは、まだDXとは言えません。
例えば、「紙の発注書をやめて、タブレットで入力するようにした」というだけなら、これはデジタル化に近い話です。しかし、そのデータを自動集計して「店舗ごとの在庫の偏り」や「欠品しやすい商品」を見える化し、発注ルールや棚の見せ方を変えるところまで行くと、それは仕事のやり方そのものを変えるDX 小売の取り組みになってきます。
小売現場でよくあるのは、「新しいPOSレジに入れ替えたから、うちはDXできている」という勘違いです。レジを入れ替えても、売上データを誰も見ていない、毎日CSVを出してExcelに手打ちしている、という状態だと、現場の負担がむしろ増えてしまうこともあります。大切なのは、「システムを入れたかどうか」ではなく、「そのおかげで現場のムダやモヤモヤが減ったかどうか」という視点です。
またDXは、一度プロジェクトをやって終わりではなく、少しずつ改善を続けていくマラソンのようなものです。最初から完璧を目指す必要はなく、「まずは紙とExcelの中で一番つらい業務をひとつラクにする」ことから始めても、立派なDX 小売の第一歩になります。
小売業が直面している現場の課題
多くの小売現場では、「とにかく毎日店を回すだけで精一杯」という状況が続いています。発注書は紙、棚卸しは手書き、日報はノート、シフト希望はLINEや口頭、クレームメモは付箋、売上管理は店舗ごとのExcel…。こうした形で、情報があちこちに散らばり、誰か一人の”頑張り”に頼った運営になっているケースがとても多いです。
こうした状態には、次のようなリスクがあります。
- 担当者が急に休むと、誰も代わりに対応できない
- ミスが起きても、どこで間違ったのか追いかけるのが大変
- 店舗ごとの数字がすぐに分からず、勘と経験で判断してしまう
- 同じ内容を紙→Excel→別システムと何度も入力して、時間が消えていく
DX 小売の取り組みは、こうした「なんとなく続けているやり方」を見直し、デジタルの仕組みを使って“手作業のムダ”と”属人化のリスク”を減らしていくことです。例えば次のようなイメージが分かりやすいでしょう。
- 棚卸しをタブレット入力にし、その場で在庫数が集計される
- 発注の判断に、売上と在庫のデータが自動でひも付く
- 店舗別の売上や粗利が、自動でグラフ化されて本部で見える
- シフト希望と勤怠打刻がクラウドで一元管理される
どれも、いきなり巨大なシステムを導入しなくても、ノーコードツールやkintoneのようなプラットフォームを活用すれば十分に実現可能な世界です。「すごいことをやる」のではなく、「現場の困りごとに直結した小さな改善を続ける」ことがDX 小売の本質と言えます。
よくある三つの誤解
DX 小売のご相談を受けていると、共通して出てくる誤解がいくつかあります。代表的なものを三つ挙げてみます。
一つ目は、「DX=自社ECを立ち上げること」というイメージです。もちろんECは重要なチャネルですが、実店舗側の在庫管理や出荷体制が整っていない状態でECだけ増やすと、「売れたのに発送が遅れる」「在庫が足りずキャンセルになる」など、現場に大きなストレスを生んでしまうことがあります。DX 小売は、必ずしも華やかな新サービスから始める必要はなく、足元の店舗運営を整えるところからでも十分な価値があるのです。
二つ目は、「DX=最新のAIやロボットを導入すること」というイメージです。AIによる需要予測やレコメンドは魅力的ですが、その前提として、売上・在庫・顧客などのデータがきちんと整っていることが欠かせません。データがバラバラで穴だらけの状態では、高度なツールを入れても効果が出にくく、「高いおもちゃ」になってしまいます。まずは日々の業務の中で、正しく・抜け漏れなくデータが集まる仕組みを作ることこそ、DX 小売の土台づくりと言えます。
三つ目は、「DXはITに詳しい人がいないと無理」という思い込みです。今は、ノーコードツールやkintoneのように、画面操作中心でアプリを作れるサービスが増えています。最初の設計や考え方は専門家のサポートがあると安心ですが、運用していく中での項目追加や画面の調整などは、現場の担当者が自分で触れるようになった方が、スピードも定着も圧倒的に良くなります。伴走ナビは、最初から「内製化」を見すえ、現場がDX 小売を自走できる状態まで一緒に育てていくことを大切にしています。
何から手を付けるべきか:「小さな一歩」の見つけ方

「DX 小売をやらなきゃいけないのは分かったけれど、具体的にどこから手を付ければいいか分からない」。おそらく、一番多い悩みがここだと思います。やりたいことを全部挙げようとすると、「発注も在庫もECも顧客管理も…」とキリがなくなり、結局動き出せないまま時間だけが過ぎてしまいがちです。そこでおすすめなのが、現場の業務を一度棚卸しし、「時間がかかる」「ミスが多い」「担当者が限られる」という三つの軸で優先順位をつけるやり方です。
現場業務の棚卸しから始める
DX 小売の第一歩は、難しい分析ではありません。やることはシンプルで、「紙」「Excel」「口頭」で行っている業務を、できるだけざっくり書き出していくだけです。例えば次のようなものが出てくることが多いです。
- 発注書、棚卸し表、入荷チェックシート
- 日報、クレーム対応メモ、引き継ぎノート
- シフト希望表、手書きの勤怠記録、休み希望メモ
- 売上報告用のExcel、本部に送る集計ファイル
書き出す時のポイントは、単に「棚卸し」「発注」などと名前だけ並べるのではなく、「誰が」「いつ」「どのくらいの時間をかけて」「どんな手順で」やっているかも簡単にメモすることです。例えば、「毎月末に店長が一人で在庫を数えて、深夜までかかる」「毎日閉店後にレジ締めと売上報告で30分以上かかる」「スタッフが紙でシフト希望を書き、本部がExcelに転記している」などです。
この棚卸しは、店長だけで抱え込まず、スタッフや本部も交えてざっくり行うのがおすすめです。「実はこの作業が一番大変なんです」「ここをもう少し楽にしたい」という現場の本音が出てきますし、DX 小売が”トップダウンの難しい話”ではなく、”みんなの働き方を良くするための話”なのだと共有できる良いきっかけにもなります。完璧さを目指す必要はなく、「大変そうな業務リスト」が作れれば十分です。
優先順位をつける三つの軸
業務の棚卸しができたら、次は「どこからやるか」を決めていきます。ここで役立つのが、「時間がかかる」「ミスが多い」「担当者が限られる」という三つの軸で業務を眺めてみることです。このどれかに当てはまる業務は、DX 小売による改善効果が出やすく、「最初の一歩」として取り組む候補になります。
例えば「時間がかかる」業務の代表は、レジ締め、売上集計、棚卸しなどです。毎日や毎月、かなりの時間を取られている場合が多く、アプリ化や自動集計を取り入れることで、目に見えて時間が空くケースがよくあります。「ミスが多い」業務としては、手書きの数量入力、紙からExcelへの転記、値札の貼り替えの指示などが挙げられます。人が目で見て数えたり写したりする作業はどうしてもヒューマンエラーが起こりやすく、デジタルの仕組みで置き換えやすい部分です。
「担当者が限られる」業務も見逃せません。例えば、「店長しか発注ロジックを知らない」「一人の社員しか複雑なExcelを触れない」といった状態だと、その人が休んだり退職したりした時のリスクがかなり大きくなります。こうした業務は、ルールを整理し、デジタルツールに落とし込むことで、誰でも一定の品質で対応できる”仕組み化”につなげやすい領域です。三つの軸で業務を評価していくと、「ここから変えるとインパクトが大きそうだ」という箇所が自然と見えてきます。
小売DXの具体アイデア
ここまでの考え方を踏まえて、DX 小売の具体的なイメージをいくつか紹介します。自社に近いものがあれば、「うちならこう変えられるかも」と想像しながら読んでみてください。
例えば在庫管理では、「棚卸し表を紙からアプリに変える」だけでも、かなり世界が変わります。商品バーコードを読み取って数量を入力すると、その場で在庫数が更新され、差異も自動で計算されるような仕組みを作れば、「数え間違い」「転記ミス」「集計にかかる残業時間」を一気に減らせます。発注では、売上データと在庫データをひも付け、「このペースなら何日後に欠品しそうか」といった視点を加えることで、発注担当者の勘と経験を、データで後押しするスタイルに変えていけます。
売上集計に関しては、各店舗がそれぞれExcelでまとめて本部に送るのではなく、共通のフォームやアプリに日々入力してもらい、本部では自動集計されたグラフを見るだけ、という形も現実的です。これなら、「数字が届かない」「フォーマットがバラバラで集計し直し」といった悩みを減らせます。スタッフ連絡では、シフト希望・シフト表・お知らせ・マニュアルなどを、クラウド上の一つの仕組みにまとめることで、LINEグループや口頭連絡だけに頼らない、抜け漏れの少ない情報共有ができるようになります。
これらはすべて、ノーコードツールやkintoneを使えば、短期間でプロトタイプを作り、現場で試しながら育てていける内容です。伴走ナビでも、「発注・在庫」「売上見える化」「スタッフ管理」といった小売DXの定番テーマについて、最初の設計からkintoneアプリ化、運用の回し方までを一緒に考え、最終的には社内で改善を続けられる状態を目指して支援しています。
ツール選定の考え方:自社に合うDX 小売の進め方を見極める

DX 小売の話になると、必ずといっていいほど出てくるのが「どのツールを選べばいいのか分からない」という悩みです。POSレジ、在庫管理システム、ECモール、自社EC、ノーコード、kintone…名前だけでもたくさんあり、比較しているうちに疲れてしまいますよね。ここで大切なのは、「一番有名なツール」や「一番機能が多いツール」を選ぶことではなく、「自社の課題と相性が良いかどうか」で考えることです。
POSレジ・在庫システムの入れ替え判断
まず検討対象になりやすいのが、POSレジや在庫システムです。「古いからそろそろ入れ替えたい」「クラウド型に変えたい」という声は多いのですが、ここで一度立ち止まって考えたいのが、「本当に入れ替えないと解決しないのか、それとも既存の仕組みを活かしながらDX 小売を進められるのか」という視点です。
例えば、今使っているレジから売上データをCSVで出力できるのであれば、そのデータをkintoneや別の集計ツールに取り込むことで、「売上の見える化」や「発注ロジックへの活用」は十分に実現できます。「レジ自体はそのまま、分析や業務改善の部分だけを別のツールに担わせる」という考え方ですね。一方で、「売上データが全く出せない」「サポート終了が近い」「店舗が増えているのに管理が追いつかない」といった場合は、入れ替えを検討するタイミングかもしれません。
どちらの場合でも、いきなり全店舗を一気に変えるのではなく、一部店舗でスモールスタートして、現場の反応や運用のしやすさを確かめることが重要です。伴走ナビのような外部パートナーに相談する際も、「とにかく最新にしたい」ではなく、「今あるものを活かしつつ、足りない部分を埋めたい」という意図を伝えることで、ムダな投資を抑えた現実的なDX 小売の進め方を一緒に考えやすくなります。
ECと実店舗の連携ポイント
次に、ECとの連携はDX 小売で外せないテーマです。楽天やAmazonなどのECモール、自社ECサイト、実店舗。この三つをどう組み合わせるかは、商材や規模によって正解が異なりますが、共通して大事なのは、「在庫」「価格」「顧客情報」をできるだけ分断しないことです。
例えば、実店舗とECで在庫管理が別々だと、「ECでは売り切れ表示なのに、店舗には在庫が山ほどある」「ECで売れたことに気付かず、店舗で売ってしまって在庫が足りなくなる」といったトラブルが起こりやすくなります。これを防ぐには、在庫データをできるだけ一元管理し、どのチャネルで売れた分も同じ在庫を減らすようなルールを整えることが重要です。完全なリアルタイム連携が難しくても、「一日に何回更新するか」「どのタイミングで在庫を締めるか」を決めておくだけでも、かなり混乱を減らせます。
また、ポイントや会員情報も重要なポイントです。実店舗とECで別々の会員番号・ポイント制度になっていると、お客さまもスタッフも混乱してしまいます。理想は共通IDに統一することですが、それが難しい場合でも、「少なくとも、後から購買履歴をひも付けられる形にしておく」「店舗とECのどちらで買っても、同じようなサービスが受けられるようにする」など、お客さま目線での分かりやすさを意識して設計していくことが大切です。
ノーコード×kintoneという選択肢
最後に、小売DXの重要な選択肢として、ノーコードツールやkintoneのような「現場でアプリを育てていけるプラットフォーム」があります。ノーコードとは、プログラミングの専門知識がなくても、画面操作を中心にアプリや業務システムを作れる仕組みのことです。特にkintoneは、「商品台帳」「在庫台帳」「顧客管理」「問い合わせ管理」「日報」などを一つの土台の上で扱えるため、小売の現場に散らばった情報を集約するのに向いていると言われています。
小売では、「実際に運用してみたら想定より入力が大変だった」「売り方を変えたので項目を足したい」といったことが頻繁に起こります。そのたびにシステム会社に改修を依頼していると、コストも時間もかかり、現場のスピード感と合わなくなってしまいます。ノーコード×kintoneであれば、項目の追加や表示順の変更、簡単な集計・グラフの設定などを、社内の担当者が自分で行えるようになります。「現場で試しながらすぐ直せる」柔軟さは、小売DXと非常に相性が良いポイントです。
伴走ナビでは、単にkintoneの設定代行をするのではなく、「どの業務をアプリにすると効果が大きいか」「どこまでをシステム化し、どこからを人の判断に任せるか」といった設計の部分から一緒に検討します。そのうえで、担当者の方が自分でアプリを触れるようにレクチャーし、最終的には社内でDX 小売の改善サイクルを回せる”内製化”の状態を目指して伴走しています。
失敗しないDX 小売の進め方

ここまでで、「なぜDX 小売が必要なのか」「どこから手を付けるか」「どんなツールがあるか」という全体像は見えてきたと思います。次に気になるのは、「実際にプロジェクトとしてどう進めればいいのか」「よくある失敗パターンは何か」という点です。DX 小売で失敗してしまう多くのケースは、実は技術やツールの問題ではなく、「進め方」と「体制づくり」の問題であることがほとんどです。
社内体制と役割分担の決め方
DX 小売のプロジェクトで非常に多いのが、「DX担当に任命された人が、日常業務と並行して全部抱え込んでしまい、疲れ切って終わる」というパターンです。これを避けるためには、最初の段階で「誰が、どの役割を担うか」をシンプルで良いので決めておくことが大切です。
例えば、最低限こんな役割に分けて考えると分かりやすくなります。
- 現場代表:実際に店舗で使う立場として、要望や現場の声を集める役
- 企画・推進役:全体のゴールやスケジュールを整理し、意思決定をサポートする役
- システム担当:ツールの設定やアプリ作成、運用ルールの整理を行う役
- 経営・本部:投資判断や優先順位の最終決定、全社へのメッセージを出す役
一人の人が複数の役割を兼ねても構いませんが、「全部を一人でやる」のは避ける方が無難です。また、「このプロジェクトは何のためにやるのか」「まずどの店舗・どの業務から始めるのか」といった、ゴールとスコープを最初に10〜20行でいいので文章にして共有することも効果的です。これがあるだけで、「いつの間にか話が大きくなって収拾がつかない」といった事態を防ぎやすくなります。
伴走ナビのような外部パートナーを入れる場合も、「外注先」ではなく「チームの一員」として役割を決めるイメージを持つと、コミュニケーションがスムーズになりやすく、社内メンバーの負担を軽くしながら、ノウハウをしっかり移していく体制を作りやすくなります。
三カ月で小さく試す進行ステップ
DX 小売をうまく進めている会社に共通するのは、「まず三カ月程度の小さなプロジェクトから始める」ことです。いきなり全店舗・全業務を対象にするのではなく、「この店舗のこの業務を、まず三カ月で改善してみる」というテーマを一つだけ決めるところからスタートすると、成果も出やすく、社内の理解も得やすくなります。
三カ月のイメージとしては、次のような流れが多いです。
- 一カ月目:現場ヒアリング、業務の棚卸し、課題の整理、ゴール設定
- 二カ月目:ツールやアプリの試作、テスト運用、細かい改善
- 三カ月目:本番運用、効果の振り返り、次に広げるかどうかの判断
この期間中に大事なのは、「完璧なシステムを作ること」ではなく、「現場が実際に使ってくれているか」「作業時間やミスがどれくらい減っているか」といった、”使われ方”と”効果”に目を向けることです。そのためにも、最初から「何をもって成功とするか」を簡単に決めておくと良いでしょう。例えば、「レジ締めにかかる時間を30分から15分に減らす」「棚卸しの残業をゼロにする」といった具体的な目標です。
この三カ月の取り組みがうまくいけば、同じやり方を横展開していくことで、DX 小売の輪を自然に広げていけますし、「最初のテーマはうまくいかなかったけれど、ここを変えれば次はいける」といった学びも得られます。いずれにしても、短いサイクルで試して学ぶ姿勢が、DX 小売を継続させる一番のポイントです。
振り返りと改善サイクルの回し方
DX 小売の取り組みが「入れて終わり」「作って終わり」になってしまう大きな原因は、振り返りと改善のサイクルが決まっていないことです。せっかくアプリや新しい仕組みを導入しても、使われ方を追いかけなかったり、現場の声を聞く場がなかったりすると、徐々に使われなくなり、「あれは結局うまくいかなかったね」という印象だけが残ってしまいます。
これを防ぐためには、月に一度で良いので、「数字」と「現場の声」をセットで振り返る場を用意することが有効です。例えば次のようなポイントを簡単に共有するだけでも、改善のヒントが見えてきます。
- 新しい仕組みを導入してから、作業時間や残業時間はどう変わったか
- ミスの件数やクレームの件数に変化はあるか
- 現場のスタッフはどこが便利になったと感じていて、どこに不満があるか
- 想定外の使われ方や、うれしい副次効果はなかったか
この振り返りをもとに、「入力項目を一つ減らそう」「マニュアルをもう少し分かりやすくしよう」など、小さな改善を積み重ねていくことで、DX 小売の仕組みは”現場に馴染んだ本物”に育っていきます。伴走ナビでも、こうした定例の振り返りに同席し、kintoneの画面や運用ルールをその場で調整しながら、「現場にフィットするDX」を一緒に作っていくスタイルを取っています。
小売DXの成功事例イメージ

最後に、「DX 小売を進めたら実際どう変わるのか」のイメージを持っていただくために、よくある小売現場の課題をもとにした成功イメージを紹介します。ここでお伝えするのはあくまでイメージですが、自社の状況に当てはめながら読んでもらうことで、「うちも似たことができるかも」と感じてもらえるはずです。
発注・在庫管理DXの事例
ある食品スーパーでは、発注と在庫管理が店長の経験と勘に大きく依存していました。発注用紙は紙で、夜な夜な売場を回りながら数量を書き込み、翌朝FAXで本部に送るスタイル。繁忙期には、欠品や売れ残りが多発し、「なんとなくモヤモヤするけれど、どこを直せばいいのか分からない」という状態が続いていました。
そこでDX 小売の一歩として、kintoneを使った「発注・在庫管理アプリ」を導入しました。商品マスタと発注画面をkintone上に用意し、タブレットから数量を入力すると、その場で在庫と売上の状況が見えるようにしました。さらに、「前週同曜日の売上」「前年同月の売上」などの簡単な指標も画面上で確認できるようにし、発注担当者が数字を参考にしながら数量を決められるようにしたのです。
その結果、発注作業にかかる時間は三割ほど短縮され、欠品や売れ残りの件数も目に見えて減少しました。何より大きかったのは、「新人でも一定レベルの発注ができるようになった」ことです。店長は最初だけ横に付き添い、発注の考え方を説明すれば、あとは画面を見ながら新人が判断できるようになりました。これにより、発注業務の属人化が解消され、店長の負担も大きく軽くなったのです。
売上・粗利の見える化事例
別のチェーンでは、各店舗が毎日Excelで売上を集計し、本部にメールで送る運用をしていました。本部側はそれをさらにExcelでまとめ直し、週次・月次のレポートを作るのが大きな負担に。数字が見えるのは早くて翌週で、「気付いた時にはチャンスを逃していた」ということもよくありました。
そこで、kintoneと既存POSのデータ連携を行い、店舗別の売上・粗利・客数・客単価が自動で集計されるダッシュボードを作成しました。店舗側は特別な作業をする必要はなく、本部と店舗が同じ画面を見ながら、「今週はこのカテゴリが伸びている」「この店舗だけ粗利率が下がっている」といった話ができるようになりました。
この仕組みによって、「なんとなく売れていない気がする」という感覚ではなく、数字をベースにした会話ができるようになったことが大きな変化でした。ある店舗では、粗利率の低い特売品を出しすぎていたことに数字で気付き、特売の頻度や組み合わせを見直した結果、全体の粗利率が改善したというケースもありました。このように、DX 小売による「見える化」は、単なるレポート作りの効率化ではなく、現場の打ち手の質を上げる土台にもなります。
スタッフ管理DXの事例
多くの小売現場で地味に効いてくるのが、シフト調整とスタッフ連絡の負担です。紙のシフト表に手書きで希望を書き、店長がそれを見ながらエクセルでシフトを作り、完成したものをバックヤードに貼り出す。休みの変更はLINEや口頭で飛び交い、「誰がいつ言ってきたのか分からない」というトラブルが起きる…。そんな状態に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
ここで、kintoneとクラウドの勤怠サービスを組み合わせ、「シフト希望」「確定シフト」「勤怠打刻」「店からのお知らせ」を一つの仕組みにまとめたイメージを考えてみます。スタッフはスマホからシフト希望を入力し、店長は画面上でバランスを見ながらシフトを組む。変更があれば、アプリ上で申請・承認が行われ、誰でも履歴を追える。重要なお知らせも同じ仕組みで配信され、既読状況が分かる。そんな運用ができるようになると、「連絡した・していない」「聞いた・聞いていない」といったストレスがぐっと減ります。
実際にこのような仕組みを導入した店舗では、店長のシフト作成にかかる時間が半分以下になり、スタッフからも「休みの相談がしやすくなった」「情報が一箇所にまとまっていて安心」という声が上がりました。結果として、定着率の改善や雰囲気の良さにもつながり、採用コストの削減という副次的な効果も生まれています。こうした「働きやすさ」の改善も、立派なDX 小売の成果の一つです。
まとめ|明日から動くための三つのステップ
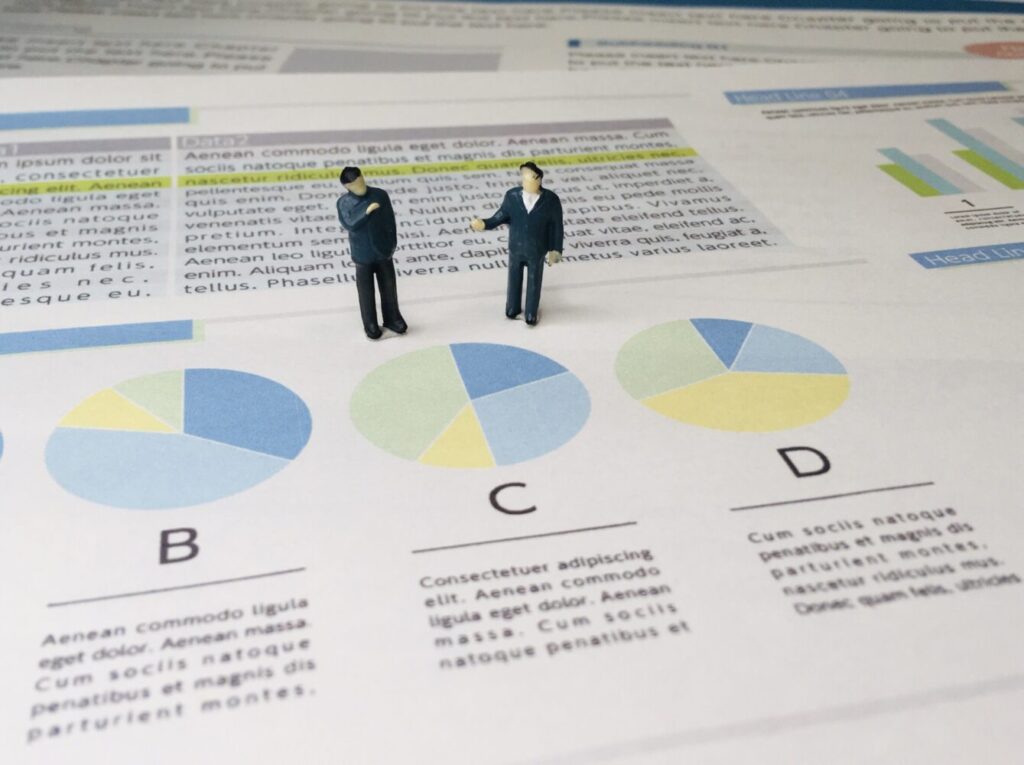
ここまで、DX 小売の基本から始め方、ツール選定の考え方、進め方、イメージ事例までを一気通貫で見てきました。「思っていたより、身近なところから始めて良いんだ」と感じてもらえていればうれしいです。最後に、明日から実際に動き出すためのステップを整理しつつ、伴走ナビとしてお手伝いできることも少しだけご紹介します。
DX 小売成功のチェックリスト
まずは、本記事でお伝えしてきたポイントをざっくりチェックリストにして振り返ってみましょう。自社の状況と照らし合わせながら、「できていること」「これからやりたいこと」を整理するのに使っていただければと思います。
- DX 小売を「最新技術の導入」ではなく、「現場の困りごとをデジタルで解決する取り組み」と捉え直せているか
- 紙・Excel・口頭で回している業務を一度棚卸しし、「時間がかかる」「ミスが多い」「担当者が限られる」業務を洗い出しているか
- 「発注・在庫」「売上見える化」「スタッフ管理」など、自社で特にインパクトが大きそうなテーマに目星をつけられているか
- ツール選定を、「一番有名なもの」ではなく「自社の課題と相性が良いかどうか」を基準に考えられているか
- DX担当者ひとりに任せるのではなく、現場代表・企画推進・システム担当・本部の役割をゆるくでも決められているか
- まず三カ月程度の小さなプロジェクトから始めるイメージを持てているか
- 導入して終わりではなく、「数字」と「現場の声」をセットで振り返る場をつくる意識があるか
全部を一度にクリアする必要はありませんが、このチェックリストのうち二〜三個でも「やってみよう」と思える項目があれば、DX 小売の準備は十分に整い始めていると言えます。
明日からできる最初の一歩
「結局、明日から何をすればいいの?」という疑問に対して、一番おすすめしたいのはシンプルにこれです。「紙・Excel・口頭」で回している業務を、付箋やメモでざっくり書き出してみること。これなら、ツールの契約もいりませんし、今日・明日にでも始められます。
具体的には、次のようなやり方が分かりやすいです。
- 店長・スタッフ・本部のメンバーで30〜60分ほど集まり、「紙やExcelで面倒だと思っている作業」を出し合う
- 各業務について、「誰が」「どれくらいの頻度で」「どのくらい時間がかかっているか」をメモする
- その中から、「時間がかかる」「ミスが多い」「担当者が限られる」に当てはまりそうなものに印をつける
ここまでできたら、それはもう立派なDX 小売プロジェクトの第一歩です。そのうえで、「この中から一つだけ、三カ月で改善してみるとしたらどれか」を決めて、具体的な進め方やツールの選択を考えていくと、机上の空論ではない”現場起点のDX”になっていきます。
外部パートナーをうまく使うコツ
最後に、伴走ナビのような外部パートナーとの付き合い方についても触れておきます。DX 小売は、社内だけで全て完結させるのが難しいケースも多く、外部の知見や実績を借りることは決して悪いことではありません。ただし、その際に意識していただきたいのが、「丸投げするパートナー」ではなく「内製化を前提に一緒に走ってくれるパートナー」を選ぶことです。
具体的には、次のような観点で見てみると良いでしょう。
- 業務整理や課題の見える化の段階から、一緒にディスカッションしてくれるか
- kintoneなどのツールを設定して終わりではなく、現場への定着や運用改善まで関わってくれるか
- 社内メンバーが自分でアプリや仕組みを育てていけるように、ノウハウや考え方を言語化してくれるか
伴走ナビでは、こうした考え方に基づき、DX 小売の「相談相手」としての無料相談や、具体的な事例や進め方が分かる資料請求をご用意しています。「自社でどこから手を付けたらいいか整理したい」「kintoneが小売のうちにも合うか話を聞いてみたい」といった段階でも、もちろん構いません。
この記事を読み終えた今が、DX 小売の一歩目を考えるタイミングです。まずは社内で今日話せそうなことを一つ決めてみる。そして、必要であれば、伴走ナビの無料相談や資料請求も気軽に活用しながら、無理のないペースでDX 小売を進めていきましょう。