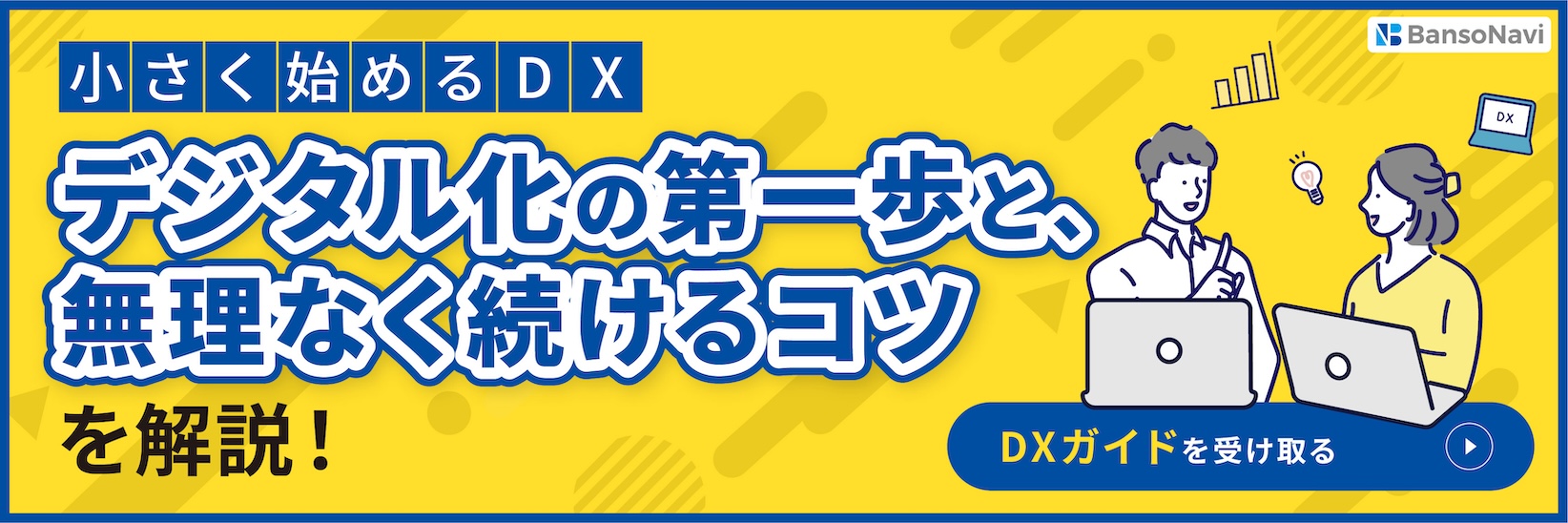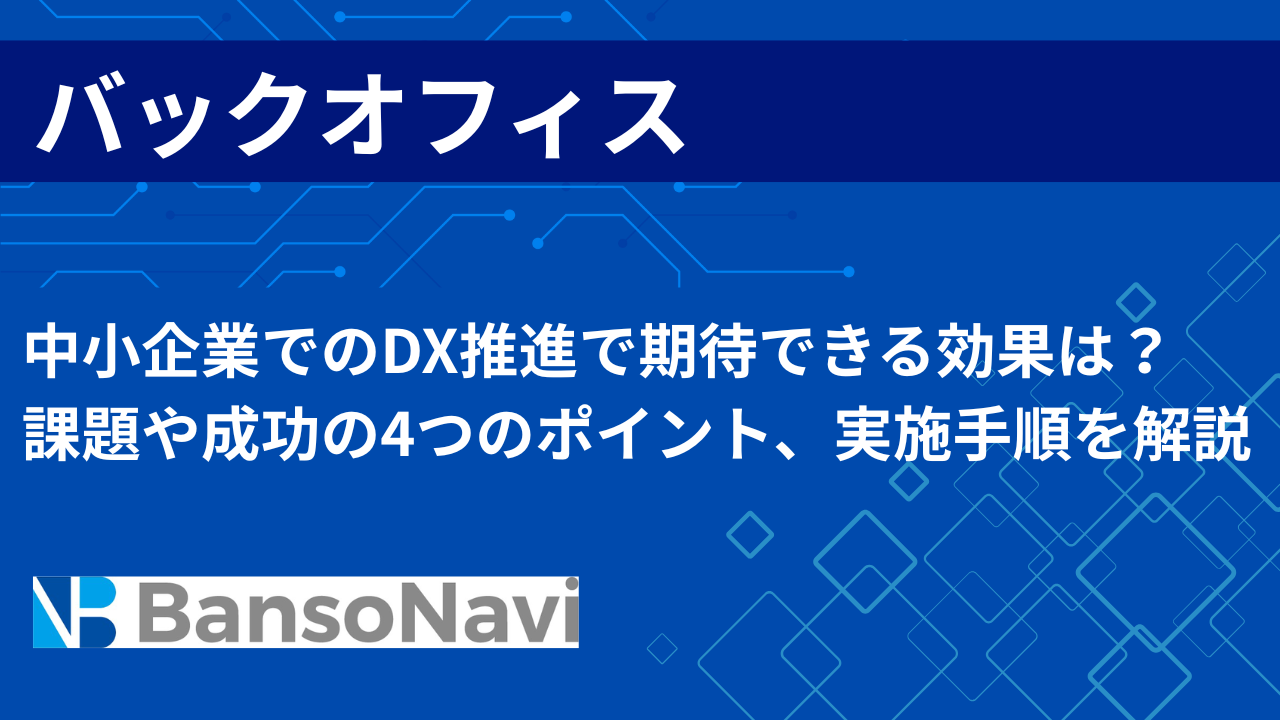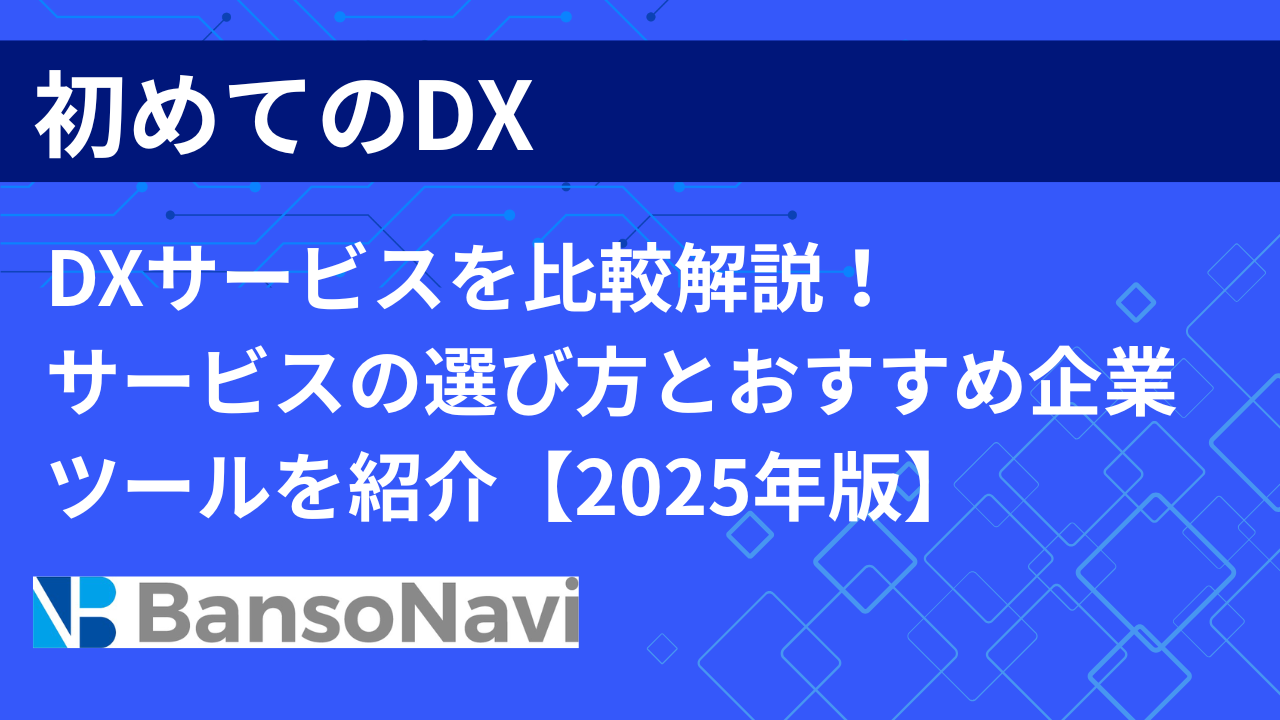社内DXの進め方とは?5ステップの手順と注意点を徹底解説!
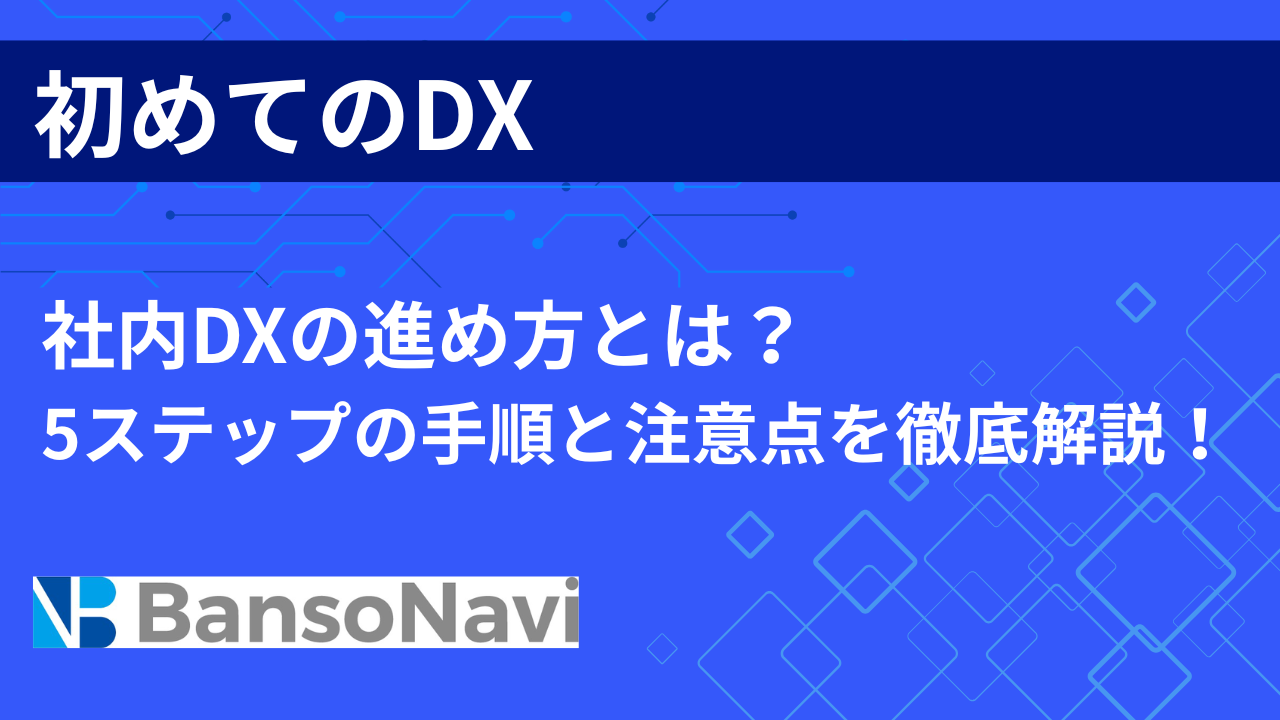
社内DXを検討している中で、以下のお悩みはありませんか?
「社内でDXを推進したいが、何から始めればいいかわからない」
「社内でDXを進める上での注意点を知りたい」
社内DXは単にITツールを導入するだけではなく、ビジネスモデルを変革し、企業の競争力を高める重要な取り組みです。
本記事では社内DXが必要とされる理由や具体的な進め方を詳しく解説します。陥りがちな注意点も紹介するので、最後までご覧ください。
なお、DXコンサルティングを活用したいなら「伴走ナビ」にご相談ください。
目次
社内DXが必要とされる3つの理由

社内DXが必要とされる3つの理由は以下のとおりです。
- BCP(事業継続計画)対策
- 業務効率化と生産性向上
- 「2025年の崖」問題への対応
いずれも企業の将来を左右する可能性を秘めています。各理由を詳しくみていきましょう。
BCP(事業継続計画)対策
BCP対策とは、自然災害や感染症のまん延など予期せぬ事態が発生した際に、事業を継続させるための計画を指します。DXの推進は、BCP対策で重要な役割を果たします。
たとえば、クラウドサービスを導入しておけば、災害時でもオフィス以外の場所から業務を続けられ、事業が停止するリスクを減らせるでしょう。
また、リモートワーク環境を整えておくと、交通機関の乱れなどにも柔軟に対応可能です。
重要なデータをクラウド上にバックアップしておけば、物理的な被害から情報資産を守り、迅速な事業の復旧を実現できます。
業務効率化と生産性向上
社内DXは業務効率化と生産性の向上に直接つながります。従来手作業で行っていた定型業務を自動化すれば、従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できるはずです。
また、デジタルツールを用いて情報共有をスムーズにすれば、意思決定のスピードが上がり、市場の変化に素早く対応可能です。
さらに、ペーパーレス化を進めると、書類の管理や検索にかかる時間を削減し、業務プロセス全体をスリム化できます。
データの一元管理によって、重複作業や転記ミスを防ぎ、業務の品質と生産性を同時に高められます。
「2025年の崖」問題への対応
「2025年の崖」は、日本企業が直面する大きなリスクであり、経済産業省が警鐘を鳴らしています。
多くの企業で使われている古い基幹システムのサポートが終了し、システムの運用を担ってきた人材が定年を迎えることで、システム障害のリスクが高まると予測されています。
社内DXを推進し、基幹システムを新しいものへ刷新刷れば、「2025年の崖」問題のリスクを回避し、将来的なIT投資の最適化を実現できるでしょう。
参考:レガシーシステム脱却に向けた「レガシーシステムモダン化委員会総括レポート」を取りまとめました|経済産業省
社内DXとIT化の違い

社内DXとIT化は混同されがちですが、両者の目的と範囲には明確な違いが存在します。
IT化が既存の業務プロセスをデジタルツールで効率化する「手段」であるのに対し、DXは業務やビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造する「目的」を指します。
たとえば、紙の請求書を電子帳票システムに置き換えるのはIT化です。 一方、システムで収集したデータを分析し、新しいサービスの開発につなげることがDXにあたります。
IT化は社内の特定業務の改善に焦点を当てますが、DXは顧客体験の向上や市場での競争力強化など、より広い視野での全社的な取り組みです。
つまり、IT化は、DXを実現するための重要な手段の一つとなります。
社内DXの進め方【5STEP】

社内DXの進め方は以下のとおりです。
- 目的設定と経営のコミットメント
- DX推進体制の構築と人材確保
- 現状把握(As-is)と課題の優先度付け
- あるべき姿(To-Be)とマイルストーン設定
- ツール選定とPDCAサイクルの構築
社内DXを成功させるためには、計画的に手順を踏むことが重要です。具体的な進め方を5つのステップに分けて解説します。
1.目的設定と経営のコミットメント
社内DXを始める場合、まず経営層が明確なビジョンを示す必要があります。
「生産性を向上させる」「新しい働き方を実現する」など、社内DXで何を目指すのか、目的をはっきりと定めなくてはいけません。
目的が曖昧なままツール導入だけを進めてしまうと、現場の従業員の反発を招き、思うような成果が得られない結果になりがちです。
経営トップが社内DXの必要性を全社員に伝え、推進していく強い意志(コミットメント)を示すと、組織全体の意識改革と協力体制を築けます。
2.DX推進体制の構築と人材確保
社内DXは、一部の部署だけで進められるものではありません。
社長をトップとし、各部署の責任者を含むプロジェクトチームを立ち上げ、全社的な推進体制の整備が必要不可欠です。
推進チームには迅速な意思決定を可能にするため、適切な権限を与える必要があります。また、社内DXを進めていくデジタルスキルを持った人材の確保も重要な課題です。
既存社員への教育と外部からの専門人材の登用を組み合わせ、人材基盤を整えましょう。
3.現状把握(As-is)と課題の優先度付け

次に、自社の現状を正確に把握します。業務プロセスを一つひとつ可視化し、無駄が多い部分や不要なタスクを洗い出しましょう。
データ収集や分析を通じて、感覚ではなく客観的な事実に基づいて課題を把握するのが大切です。
複数の課題が見つかった場合は、何から手をつけるべきか、費用対効果や実現のしやすさなどを考慮して優先順位をつけてください。
実際に業務を行っている現場従業員に丁寧にヒアリングし、実態と理想のギャップを正確に把握することを心がけましょう。
4.あるべき姿(To-Be)とマイルストーン設定
現状分析が終わったら、DX推進後の理想的な業務プロセスや組織の姿(To-Beモデル)を具体的に描きます。
目標を明確にすると、関係者全員が同じ方向を向いて進めるはずです。
ただし、大きな目標だけでは日々の活動がむずかしくなるため、短期・中期・長期のマイルストーンを設定し、実現可能な計画を立てるのが大切です。
また、「売上を何%向上させる」と具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、進捗を客観的に測定できる仕組みも整えましょう。
5.ツール選定とPDCAサイクルの構築
最後に、設定した目標を達成するための具体的なツールを選定します。 ただし、ツール導入そのものを目的にしないよう注意しましょう。
まずは、小規模な範囲で導入し、効果を検証しながら段階的に適用範囲を広げていくのが賢明です。
ツール導入後も定期的に効果を測定し、改善点を見つけて修正していくPDCAサイクルを回し続けて、社内DXの取り組みを最適化していきましょう。
社内DXを進める際の3つの注意点

社内DXを進める際の3つの注意点は、以下のとおりです。
- トップダウンのDX推進体制を作らない
- デジタル人材の確保・育成を怠らない
- 目的が曖昧なままツールを導入しない
社内DXの推進には、いくつかの注意点が存在します。上記のポイントを押さえておかなければ、プロジェクトが停滞したり、失敗に終わったりする可能性があります。
トップダウンのDX推進体制を作らない
DXの推進には、経営層の強力なリーダーシップが必要不可欠です。
経営層を巻き込まずに現場だけで進めようとすると、社内の抵抗勢力からの反発にあい、プロジェクトが停滞してしまう可能性が高まります。
経営トップが本気で社内DXに取り組む姿勢を示し、全社的な指示として各部署に協力を求めることで、公式な推進力を得られます。
なお、経営戦略と現場のニーズの両方を満たすためには、トップダウンとボトムアップを組み合わせた推進体制が理想的です。
デジタル人材の確保・育成を怠らない
DXを推進するには、デジタル技術やデータ活用に関するスキルを持つ人材が欠かせません。
スキルを持った人材が不足していると、せっかく立てた計画も絵に描いた餅となり、投資が無駄になってしまうリスクがあります。
そのため、社内で研修プログラムやワークショップを実施し、従業員全体のデジタルリテラシーを高めるとともに、次世代のDXを担う人材を計画的に育成するのが重要です。
社内だけでの育成がむずかしい場合は、外部の専門家や経験者を活用し、不足するスキルやノウハウを補う戦略も有効です。
目的が曖昧なままツールを導入しない
「何か新しいツールを導入すればDXになる」と考えるのは失敗のもとです。
ツールの導入自体が目的化してしまうと、業務のデジタル化で終わってしまい、本来目指すべき課題解決や競争力の強化にはつながりません。
まずは「何を解決したいのか」を明確にし、課題に合ったツールを慎重に選定しましょう。
導入前には現場の意見を十分に聞き、実際の業務フローに合ったツールを選んでください。また、ツール導入後の運用体制までしっかりと設計すれば、社内DXを成功に導けるはずです。
社内DXの成功事例

社内DXに取り組み成果を上げている企業の事例を3つ紹介します。
- 日産自動車株式会社|ニッサン インテリジェント ファクトリー
- パナソニック ホールディングス株式会社|Panasonic Transformation
- マテリアル・カッパー・プロダクツ株式会社|RPAによる業務自動化
各事例から自社のDX推進のヒントを得られるでしょう。
日産自動車株式会社|ニッサン インテリジェント ファクトリー

日産自動車は従来の集約型生産からの脱却を目指し、ロボットとデジタル技術を駆使した次世代工場「ニッサン インテリジェント ファクトリー」を実現しました。
従来、熟練の職人が担ってきた匠の技術をロボットに継承させ、MR(複合現実)技術を活用して作業員の習熟を早めることで、人手不足や高齢化の課題に対応しています。
2014年から製造現場のDXに着手し、試行錯誤を重ねながら、栃木工場での新型EV「アリア」の生産から全社展開を進めています。
参考:ニッサン インテリジェント ファクトリー|日産自動車株式会社
パナソニック ホールディングス株式会社|Panasonic Transformation
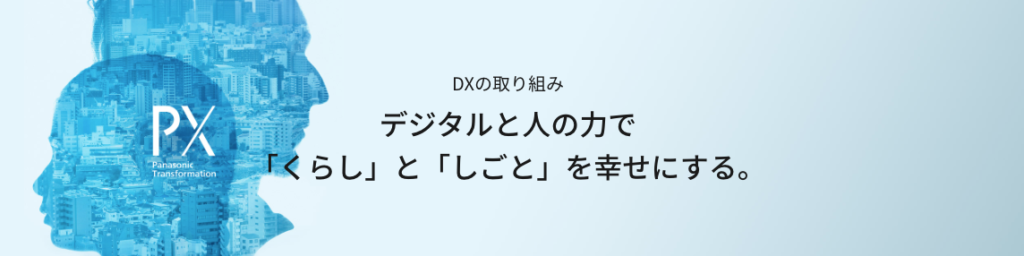
パナソニック ホールディングスは、「PX」と名付けた全社的なDX改革に取り組んでいます。
PXは、情報システム、オペレーティングモデル、企業カルチャーの3つを同時に変革することを目指しているのが特徴です。
経営幹部全員が署名した7つの原則を策定し、単なるIT導入に偏らない、業務プロセスや組織風土の改革を会社全体でコミットしています。
PXでは、生成AIの活用やデータ基盤の整備などを短期集中型で進め、2021年から4年間で着実な成果を創出しています。
参考:デジタルと人の力で「くらし」と「しごと」を幸せにする。|パナソニックホールディングス株式会社
マテリアル・カッパー・プロダクツ株式会社|RPAによる業務自動化

新潟県上越市の銅合金メーカーであるマテリアル・カッパー・プロダクツは、慢性的な人材不足を解消するためにRPAやAI-OCR、ペーパーレス化を積極的に推進しています。
生産現場で培った業務標準化の手法を間接業務に応用し、受発注業務など20の業務を自動化するロボットをわずか2ヵ月で開発しました。
また、2022年には、上越地域初のDX認定事業者となり、地域のDX推進のロールモデルとして、後方支援や知見の共有を無償で行っています。
社内DXの進め方でお悩みであれば「伴走ナビ」にご相談ください
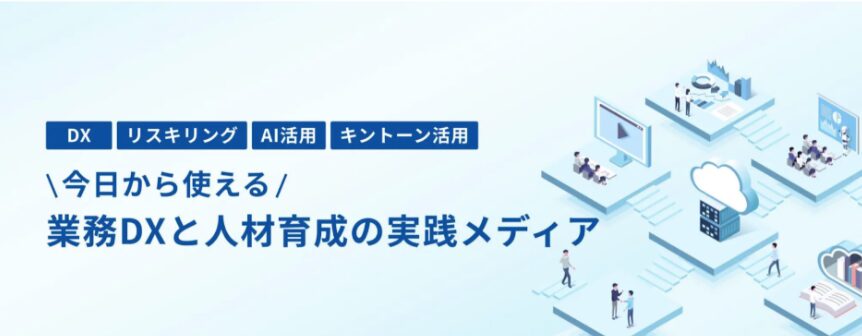
社内DXは、単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革し、企業の競争力を高める取り組みです。
成功させるには、明確な目的設定と経営層のコミットメント、全社的な推進体制の構築が必要不可欠です。
ただし、トップダウンの体制構築やデジタル人材の育成、目的に合ったツール選定など、注意すべきポイントを押さえることも重要です。
社内DXは一朝一夕で実現できるものではありませんが、PDCAサイクルを回しながら着実に進めると、業務効率化や生産性向上につながります。
自社だけでのDX推進に不安がある場合は、専門家の支援を活用することも検討しましょう。
DXコンサルティングを活用したいなら「伴走ナビ」にご相談ください。