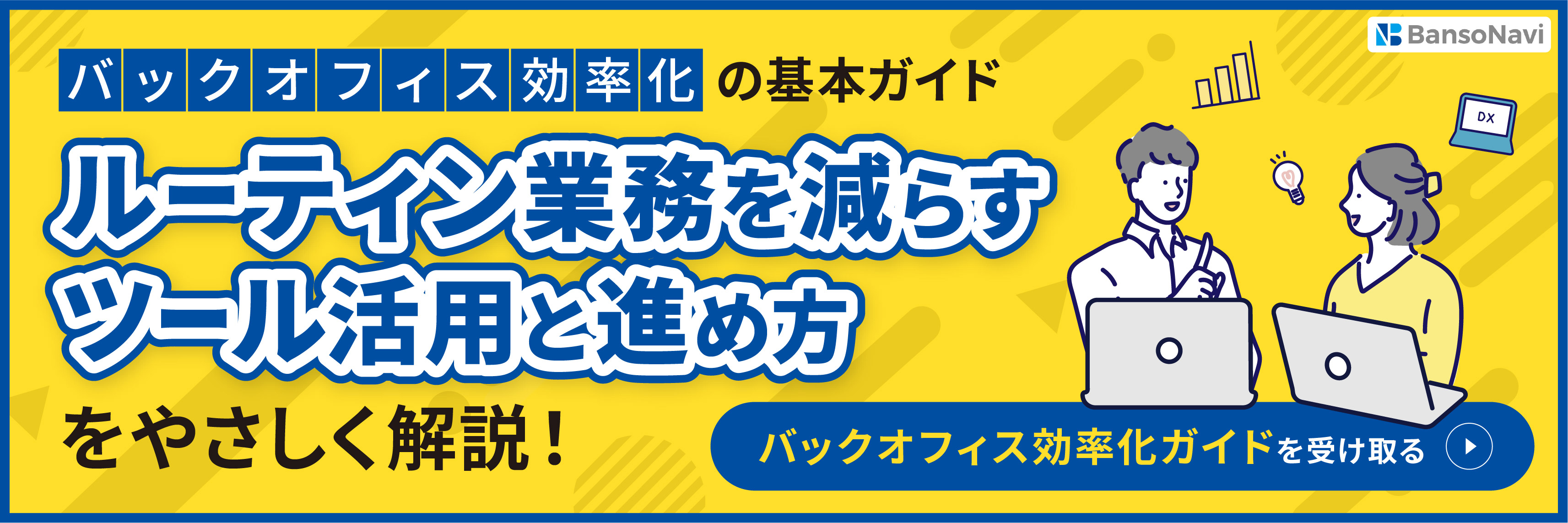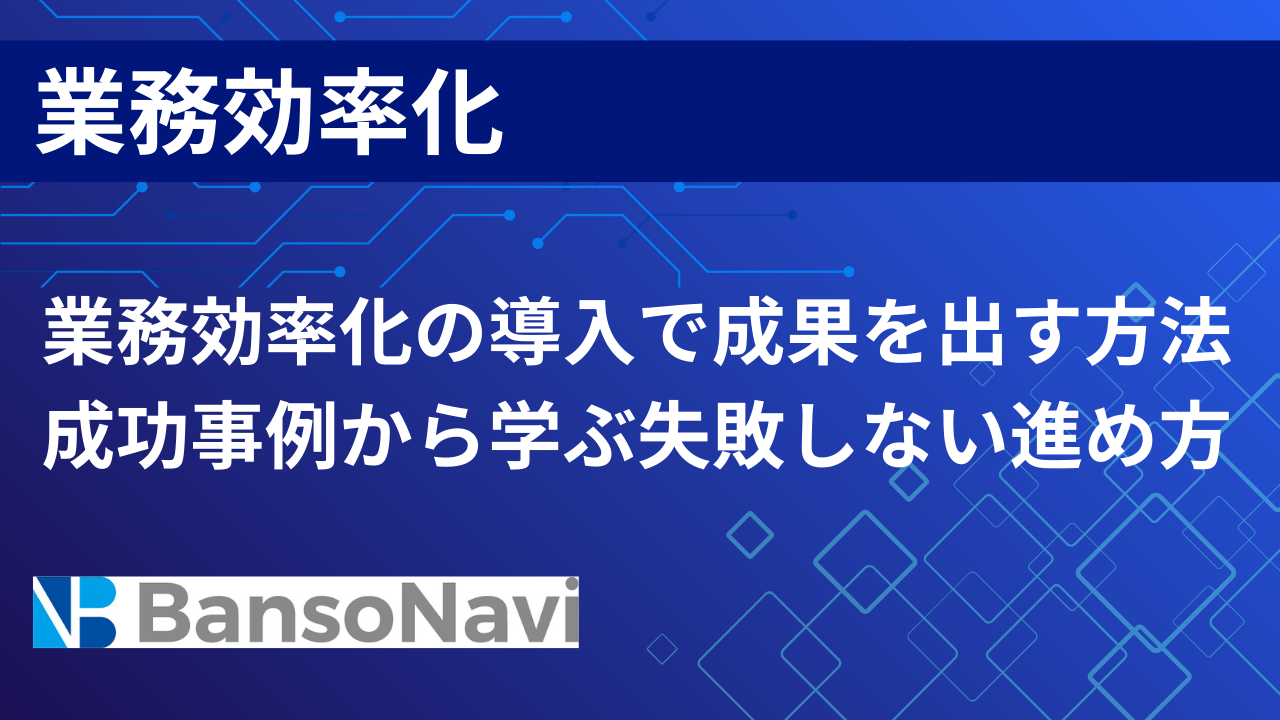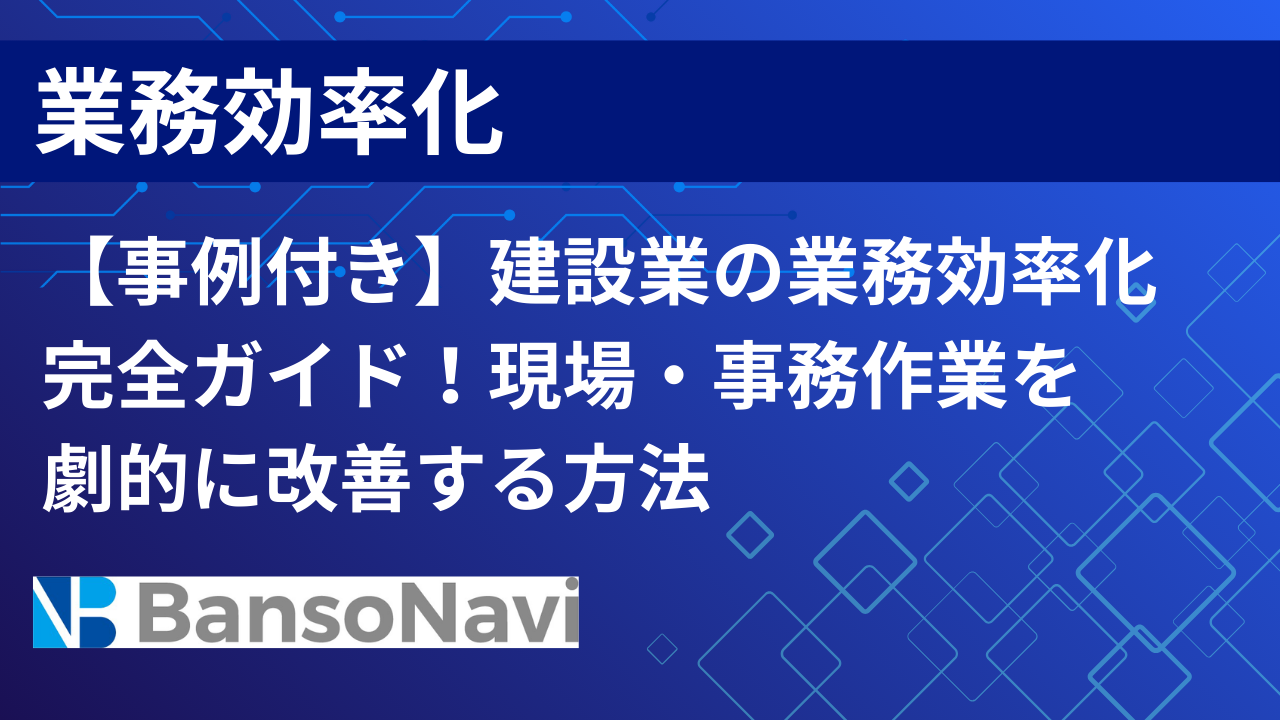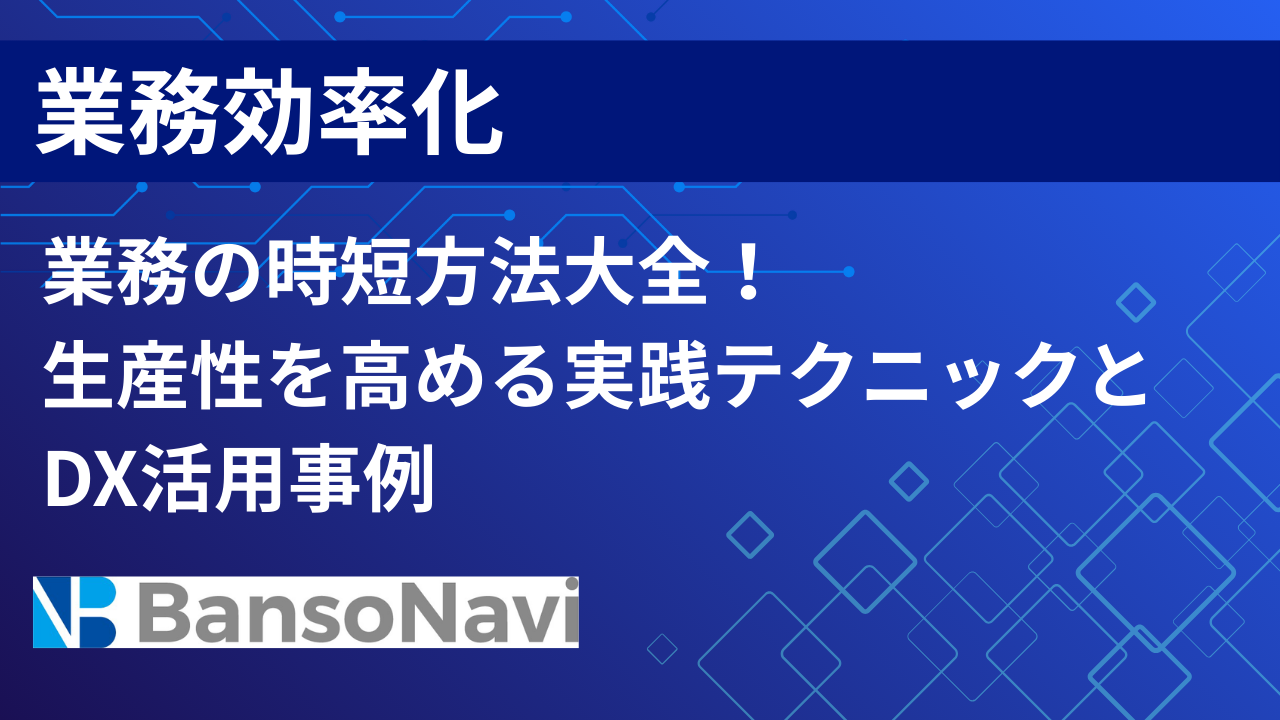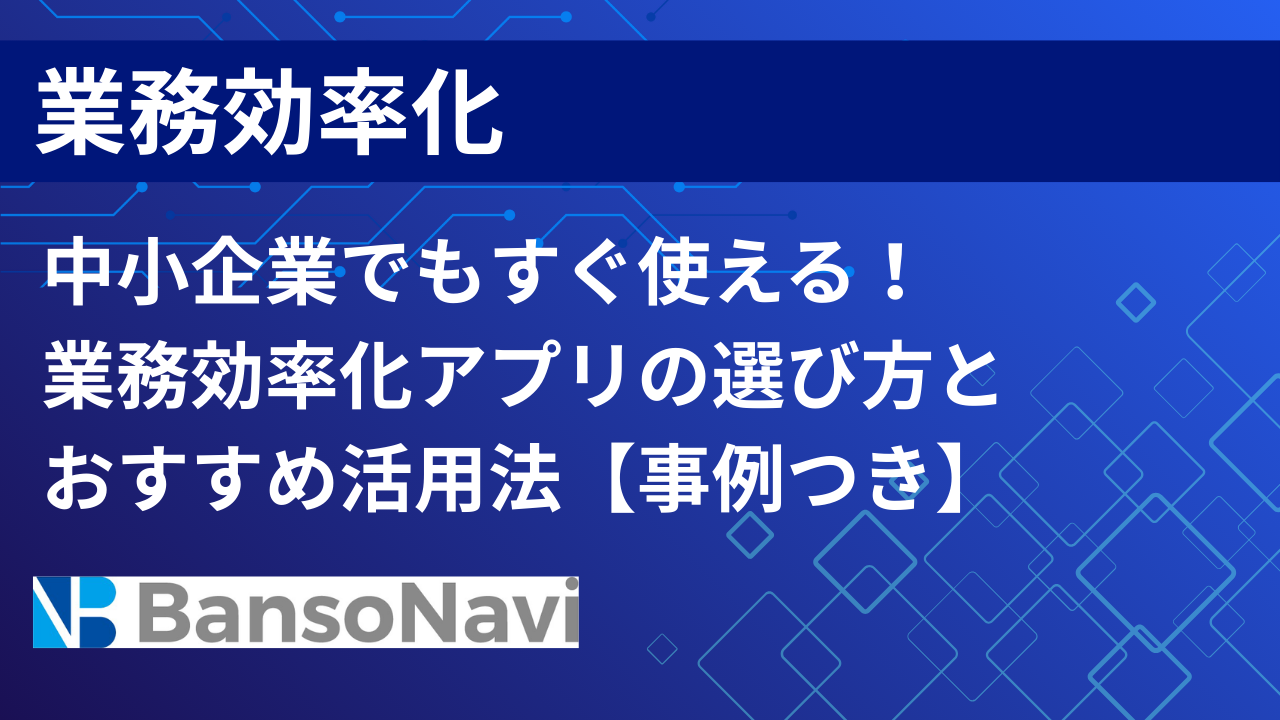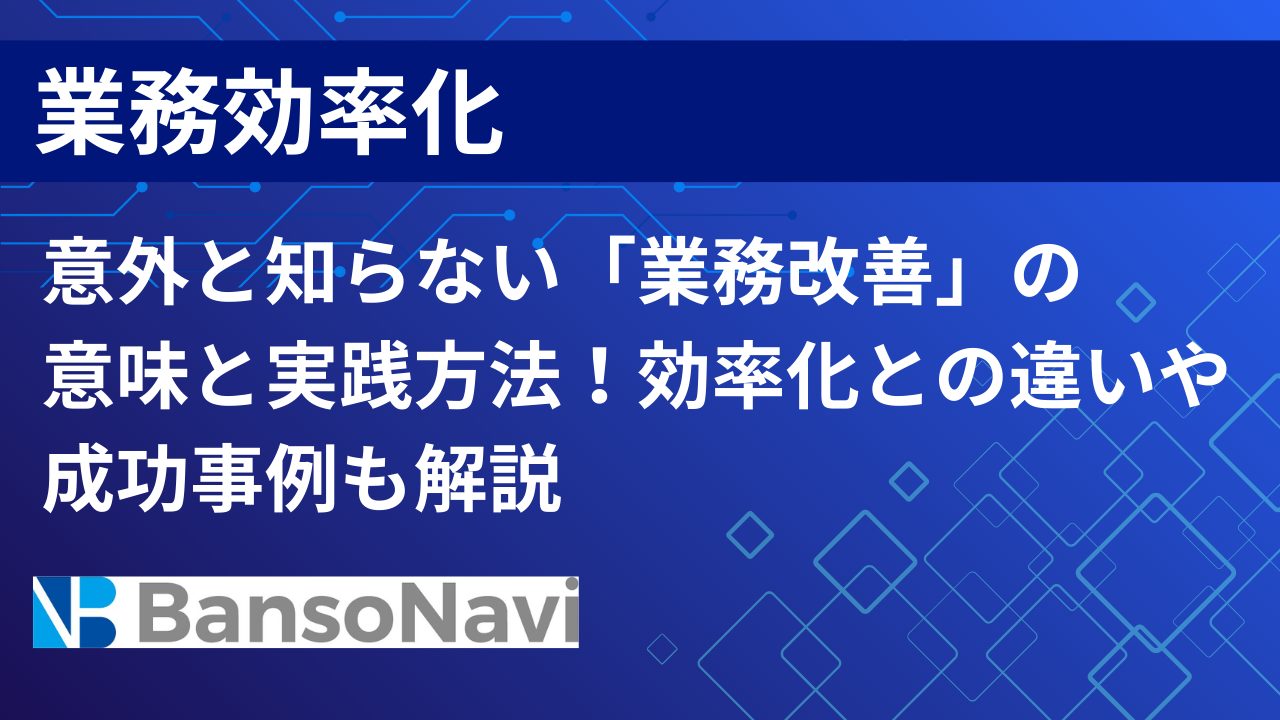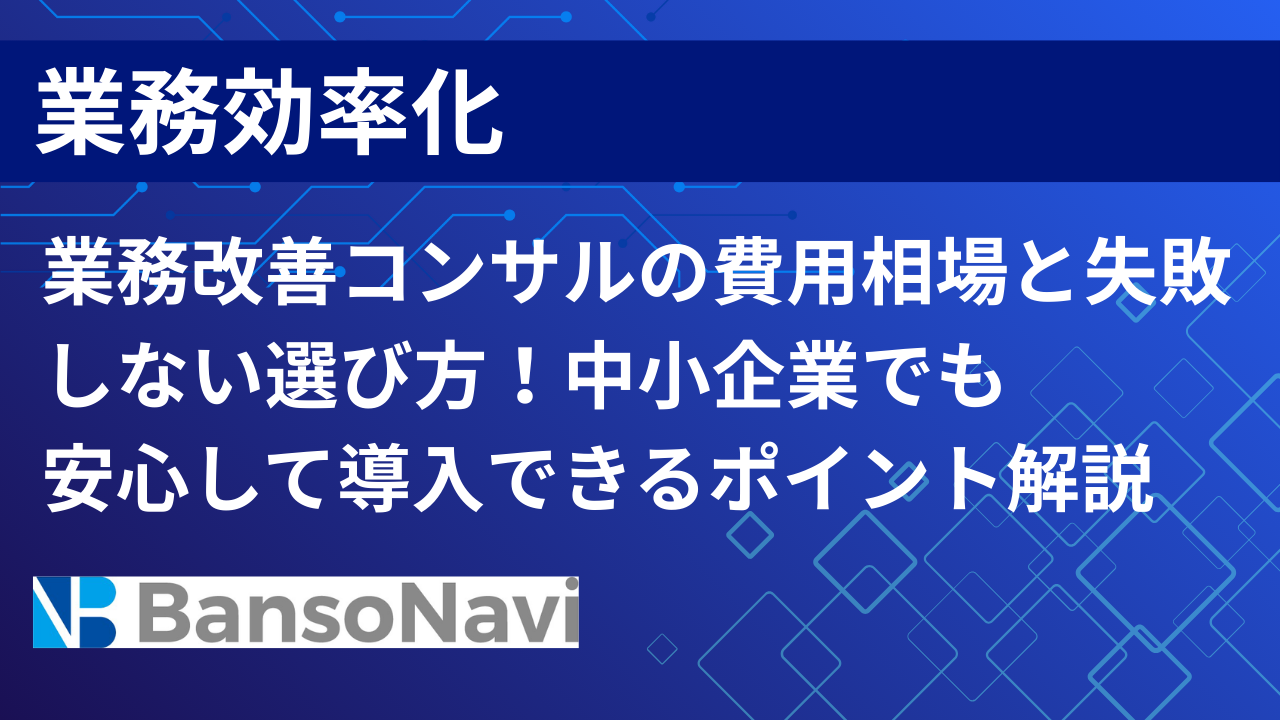業務効率化とは?メリットやデメリット・進め方7STEPとおすすめツールを徹底解説
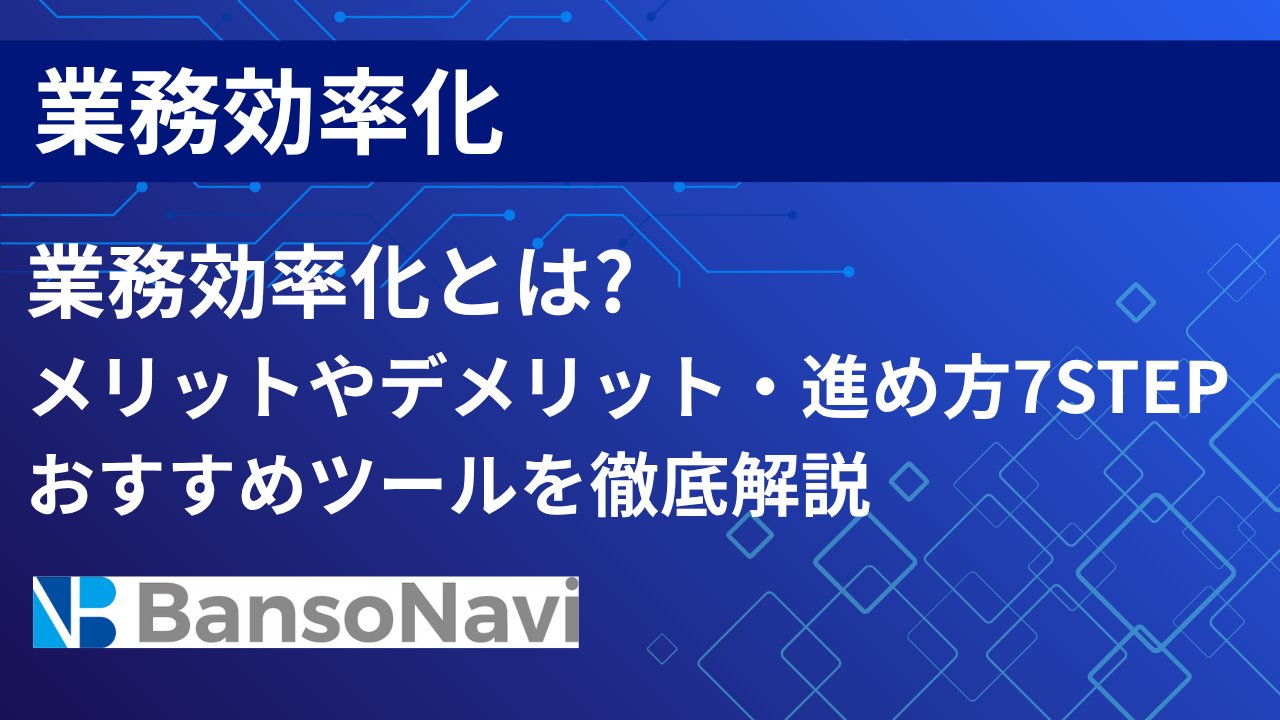
「業務のムダを減らして生産性を上げたい」
「ツール導入や自動化を検討しているが、どこから始めればいいかわからない」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
業務効率化は、単なる時間短縮ではありません。業務プロセスに潜むムリ・ムダ・ムラを解消し、企業の生産性を根本から高める取り組みです。この記事では、業務効率化の基本からメリット・デメリット、具体的な進め方、役立つツールまで網羅的に解説します。
自社に合った業務効率化の施策を見つけるなら「伴走ナビ」にご相談ください。
目次
業務効率化とは?

業務効率化とは、業務プロセスに存在する「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、余計な作業や時間をへらして生産性を高める取り組みです。主な目的は、業務時間を短くし、限られたリソースで最大の成果を上げることです。
たとえば、RPA(事務作業のような定型業務を自動化できるロボット技術)やAIといったITツールを導入し業務を自動化したり、業務フローの見直しや作業の標準化を行ったりして実現をめざします。
個人単位では、タスクの優先順位をつけたり、書類のテンプレートを用意したりといった工夫も有効です。組織全体で取り組む場合は、業務内容を可視化し、課題を見つけ出し、改善策の実施と効果検証を継続的に実行していく必要があります。
業務効率化が求められている背景

現代の企業は、複数の社会的要因により業務効率化への対応を迫られています。特に以下の3つの要因が大きく影響しています。
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 働き方改革の推進
- DX(デジタルトランスフォーメーション)やリモートワークの普及
労働人口の減少により、限られた人員で従来以上の成果を生み出すことが求められる一方、働き方改革では長時間労働を削減しながらも生産性を維持・向上させる必要があります。また、DXやリモートワークの加速により、業務プロセスのデジタル化は選択肢ではなく必須条件となりました。
しかし、多くの企業では依然として紙書類やExcelでの管理、特定の担当者に依存する属人化業務が残っており、旧来型の業務フローのままでは変化に対応することが困難です。こうした状況を背景に、業務プロセスの見直しと効率化が喫緊の課題となっています。
業務効率化を行う4つのメリット

業務効率化は、企業に多くの良い影響をもたらします。具体的には、主に下記のようなメリットがあります。
- 生産性の向上
- コスト削減効果
- 従業員モチベーションの向上
- 顧客満足度と競争力の強化
これらのメリットは、企業の成長に直接つながる重要な要素です。それぞれを詳しくみていきましょう。
生産性の向上
業務効率化は、企業全体の生産性を大きく引き上げます。業務プロセスから重複した作業や不必要な工程をなくすため、従業員は本来やるべき付加価値の高い仕事に集中できます。
ITツールや自動化システムを導入すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力などの時間がかかる作業を減らし、処理速度を向上させることも可能です。
さらに、業務の流れを可視化して標準化すると、担当者による作業のばらつきがなくなり、組織全体の生産性が底上げされます。
コスト削減効果
コストの削減も大きなメリットです。作業を自動化して業務時間を短くできるため、残業代をはじめとする人件費を圧縮可能です。
また、会議の時間や資料作成といった間接的な業務にかかる時間をへらすことで、見えにくいコストの削減にもつながります。
特定の従業員しかできない業務、いわゆる属人化が解消されると、業務の引き継ぎや新人教育にかかる手間も軽くなり、採用や育成にかかる費用も抑えられます。
従業員モチベーションの向上
従業員のモチベーション向上にも良い影響があります。単純作業や複雑な手続きから解放されるため、従業員はより創造性が求められる仕事や、やりがいを感じやすい業務に時間を使えます。
長時間労働が是正されれば、プライベートの時間を確保しやすくなり、働きやすい環境整備も可能です。自分の働きが成果として目に見えるようになると、自身の貢献を実感でき、仕事への満足感も高まるでしょう。
顧客満足度と競争力の強化
業務効率化は、顧客満足度の向上と企業競争力の強化にもつながります。たとえば、申請や回答にかかる時間が短くなれば、顧客への対応スピードが上がり、顧客対応力の向上が可能です。
社内で情報がスムーズに共有される仕組みを整えれば、担当者が違っても均一で質の高いサービスを提供でき、顧客からの信頼も安定します。組織全体の対応が俊敏になるため、市場の変化にも柔軟に対応でき、他社に対する優位性も強化されるでしょう。
業務効率化を行う4つのデメリット

業務効率化は多くのメリットがある一方で、進め方を間違えるとデメリットが生じる場合があります。具体的には、主に下記のような点が挙げられます。
- 従業員の収入減少リスク
- 導入コストと運用負荷
- 現場の抵抗・心理的負担
- 優秀な人材の流出リスク
これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じながら進めることが大切です。
従業員の収入減少リスク
業務効率化によって労働時間が短くなると、時給制で働く従業員や残業代に頼っている従業員の給与が減ってしまう可能性があります。
特に、固定の支出が多い家庭を持つ従業員にとって、収入の減少は生活に直結する大きな問題であり、仕事へのモチベーションが下がる原因になりかねません。効率化によって生まれた利益が従業員の給与に還元されない場合、不公平感が生まれる場合があります。
導入コストと運用負荷
新しいITツールや業務システムの導入には、初期投資や月々のライセンス費用がかかります。特に、予算が限られている中小企業にとっては、導入の判断が難しい場合もあるでしょう。
また、新しいシステムに従業員が慣れるまでは、一時的に生産性が落ちることも覚悟しなくてはいけません。導入後も、定期的なメンテナンスやアップデート、社内からの問い合わせに対応するサポート体制の整備といった運用負荷が発生します。
現場の抵抗・心理的負担
業務フローの変更は、現場の従業員から抵抗にあう場合があります。現状の業務を変更することで一時的に従業員の工数も増加するため、「今のままで問題ない」と反発につながることも珍しくありません。
新しいシステムの操作を覚えたり、手順が変わったりすることに、プレッシャーや不安を感じる従業員もいます。また、「自分の仕事がなくなってしまうのではないか」という不安から、業務効率化の取り組み自体に否定的な感情を抱くケースも少なくありません。
優秀な人材の流出リスク
業務の標準化や平準化を推し進めすぎると、優秀な人材が離れてしまう危険性があります。決められた業務をこなすだけでは、創造性の高い仕事で能力を発揮したい人材にとっては、業務の幅が狭くなり、不満を抱える原因になります。
効率を優先するあまり、従業員同士のコミュニケーションが減るなどして、組織の文化が希薄になることにも注意が必要です。定型業務の最適化ばかりを重視するようになると、企業の将来を考える戦略的な業務への関心が薄れてしまうかもしれません。
業務効率化の進め方【7STEP】

業務効率化を成功させるためには、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。
- 現状の業務を可視化する
- 課題とムダを洗い出す
- 改善の優先順位を決める
- 改善策を立てる
- ツールや仕組みの導入を検討する
- 効果検証を行う
- PDCAサイクルを回して継続的に改善する
ここでは、具体的な進め方を7つのステップに分けて解説します。
1.現状の業務を可視化する
まず、すべての業務フローを洗い出し、「誰が・どのタイミングで・何の業務を・どのくらいの時間で」行っているかを整理しましょう。
業務内容を客観的に可視化することで、これまで気づかなかった業務の重複や、特定の担当者に依存している作業、非効率な手順などが明らかになります。全体像を把握できれば、どこから手をつけるべきか、改善の対象を特定しやすくなるでしょう。
業務の可視化方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
関連記事:業務フローを見える化するおすすめツールと選び方|効率化・ミス削減を実現する方法
2.課題とムダを洗い出す
業務の可視化ができたら、次にその情報をもとに削減可能な業務を探します。特に、次のような業務は、効率化できる可能性が高い部分です。
- 単純なデータ入力や書類の転記作業
- 発生する頻度が高い業務
- 特定の担当者しかやり方がわからず属人化しているタスク
現場の担当者にヒアリングを実施したり、チェックリストを使ったりして、実情に合った課題を洗い出すことが大切です。
課題とムダを洗い流す具体的な方法について知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
関連記事:無駄な業務を減らす方法|中小企業でもすぐ実践できる改善策と事例を徹底解説
3.改善の優先順位を決める

影響の範囲や改善による効果の大きさを考えて、取り組むべき優先順位をつけましょう。
洗い出した課題のすべてを一度に改善しようとするのは現実的ではありません。ビジネスの世界には、「成果の8割は、2割の業務から生まれる」というパレートの法則があります。この考え方にならい、最も成果につながりそうな課題から着手するのがおすすめです。
大きな改革よりも、まずは小さな改善を積み重ねて成功体験を得ることで、その後の活動も進めやすくなります。
4.改善策を立てる
優先順位が決まったら、具体的な改善策を考えましょう。このとき、「改善の4原則」と呼ばれるフレームワークが役に立ちます。
具体的には、次の4つの視点です。
- Eliminate(排除):その業務をやめられないか
- Combine(結合):一緒にできないか
- Rearrange(交換・再配置):順序を変えられないか
- Simplify(簡素化):もっと単純にできないか
まずは「やめられる業務はないか」を検討し、その後にツールの導入などを考えると、より本質的な改善につながります。
5.ツールや仕組みの導入を検討する
改善策を支える手段として、ITツールや新しい仕組みの導入を検討しましょう。
たとえば、RPA(事務作業のような定型業務を自動化できるロボット技術)やAIを導入して定型業務を自動化したり、CRM(顧客関係管理)や業務アプリで情報を一元管理したりする方法があります。また、申請や承認を効率化するグループウェアやワークフローシステムの導入も有効です。
さらに、社内のリソースを重要な業務に集中させるため、一部の業務を外部に委託するアウトソーシングも選択肢の一つとして考えられます。
6.効果検証を行う

改善策を実行した後は、必ず効果を検証しましょう。このとき、定量的な視点と定性的な視点の両方から測定することが重要です。
定量的な指標の例としては、作業時間の削減率やコスト削減額、残業時間の変化などが挙げられます。一方、定性的な指標には、従業員の満足度やチーム内の連携、仕事へのモチベーションの変化などがあります。
短期的な成果だけでなく、職場環境や離職率といった長期的な変化も観察し、多角的に評価しましょう。
7.PDCAサイクルを回して継続的に改善する
業務効率化は、一度実施したら終わりではなく、継続的に改善を続けることが大切です。そのために、「PDCAサイクル」を回す仕組みを取り入れましょう。
PDCAとは、次の頭文字をとったもので、このサイクルを繰り返すことで、改善の質を継続的に高めていけます。
- Plan(計画)
- Do(実行)
- Check(検証)
- Action(改善)
定期的に現場の従業員から意見を聞き、社会の変化に合わせてツールや手法を見直していく姿勢が重要です。
業務効率化に役立つツール・仕組み5選

業務効率化を進める上で、ツールの活用は欠かせません。ここでは、業務効率化に役立つ代表的なツールや仕組みを5つ紹介します。
- タスク管理・進捗管理ツール
- 情報共有・コミュニケーションツール
- 自動化・RPAツール
- CRM・顧客管理・業務アプリ
- アウトソーシングの活用
自社の課題に合わせて、これらのツールや仕組みの導入を検討してみてください。
業務効率化ツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:業務効率化ツール徹底比較!選び方・おすすめ機能・導入事例まで解説
タスク管理・進捗管理ツール
タスク管理・進捗管理ツールによって、チームの「いま、誰が、何をやっているのか」をリアルタイムで見える化が可能です。個々のタスクやプロジェクトの進行状況がひと目でわかるため、作業の抜け漏れや遅れを防ぐのに役立ちます。
担当者や期限を明確に共有することで、チーム全体の目標達成に向けた意識も統一可能です。これまで会議や報告書作成に使っていた時間を削減できる点もメリットです。業務の属人化を防ぎ、誰でも同じ基準でタスクを把握できるようになります。
タスクの管理方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:タスク管理を効率化する方法とは?誰でも実践できるコツとツール活用事例を徹底解説
情報共有・コミュニケーションツール
情報共有やコミュニケーションを円滑にするツールで、社内や社外との情報共有をクラウド化すれば、関係者はいつでも最新の資料を確認可能です。
ビジネスチャットやビデオ会議ツールを活用すると、従来のメールや対面での会議のやり取りを大幅に削減できます。複数人が同時にファイルを編集できる機能を使えば、在宅勤務や遠隔地の拠点間でもリアルタイムでの共同作業がスムーズに進みます。
自動化・RPAツール

自動化・RPAツールを導入すると、これまで人が行っていたデータ入力や伝票処理、メールの振り分けといった作業をソフトウェアのロボットが代行します。
作業時間が短くなるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減できるのが大きな利点です。自動化によって生まれた時間を、従業員はより付加価値の高い業務に使えるようになり、生産性が向上します。
なお、業務の自動化について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:ルーチン業務の自動化完全ガイド|種類・ツール・事例・導入手順まで徹底解説
CRM・顧客管理・業務アプリ
CRM(顧客関係管理)や業務アプリは、顧客情報や案件の進捗などを一元管理するツールです。これまで別々のファイルで管理していた情報を一つにまとめることで、情報の重複や入力ミスを防ぎます。
営業担当者やサポート担当など、関係者全員が常に最新の顧客情報にアクセスできるため、部門間の連携がスムーズになり、結果として顧客満足度の向上につながります。紙の申請書や報告書をオンライン化するワークフロー機能を備えたサービスもおすすめです。
アウトソーシングの活用
アウトソーシングは、自社の業務の一部を外部の専門業者に委託する仕組みです。経理や総務、受付といったノンコア業務を外部に任せることで、社内の従業員を企業の核となるコア業務に集中させられます。
専門知識やノウハウを持つ外部の力を活用するため、業務の品質とスピードの向上が期待できます。繁忙期だけ依頼するなど、人員やコストの変動に柔軟に対応できるため、固定費の削減にも有効です。
アウトソーシングの活用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:【保存版】業務改善コンサルの費用相場と失敗しない選び方|中小企業でも安心して導入できるポイント解説
業務効率化を成功させるための3つのポイント

業務効率化は、ただツールを導入するだけでは成功しません。ここでは、取り組みを成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
- 業務効率化に向けたロードマップを描く
- 現場の声に耳を傾ける
- 数値化により定量的な改善を行う
これらのポイントを意識して、全社一丸となって取り組むことが大切です。
ムダな業務を効率化する方法をより詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
関連記事:業務効率化の導入で成果を出す方法|成功事例から学ぶ失敗しない進め方
業務効率化に向けたロードマップを描く
まず、計画的なロードマップを作成することが重要です。現状の業務フローを分析して、どの工程がボトルネックになっているかを明確にします。
改善すべき領域を特定したら、なぜ効率化するのか(コスト削減、時間短縮など)という目的をはっきりさせた上で、具体的な目標を設定しましょう。すべてを一度に変えるのではなく、優先順位をつけて段階的に実施できるよう、現実的なスケジュールを立てます。
ただし、改善後の効果を検証し、継続的に見直しができる仕組みを組み込むことも忘れてはいけません。
現場の声に耳を傾ける
業務効率化を進める上で、実際にその業務を担当している現場の従業員を巻き込むことが不可欠です。
現場が抱えている課題や意見を吸い上げることで、机上の空論ではない、実用的で定着しやすい改善策につながります。また、改革の目的やメリットを丁寧に共有しながら進めることで、変化に対する抵抗感や不安を和らげられます。
まずは小さな成功体験を積み重ね、社内の理解を得ることが、大きな推進力になるでしょう。
数値化により定量的な改善を行う
改善の効果は、具体的な数値で可視化することが大切です。
「作業時間を〇%削減できた」「コストを〇円削減できた」「ミス発生率が〇%低下した」のように、定量的なデータで示すことで、誰にでも成果が明確にわかります。客観的なデータに基づいて判断するため、再現性の高い改善が可能になります。
また、成果がはっきりと見えることは、従業員のモチベーション向上にもつながるでしょう。もちろん、従業員満足度のような定性的な指標と合わせて総合的に評価することが理想です。
業務効率化を検討中なら「伴走ナビ」にご相談ください
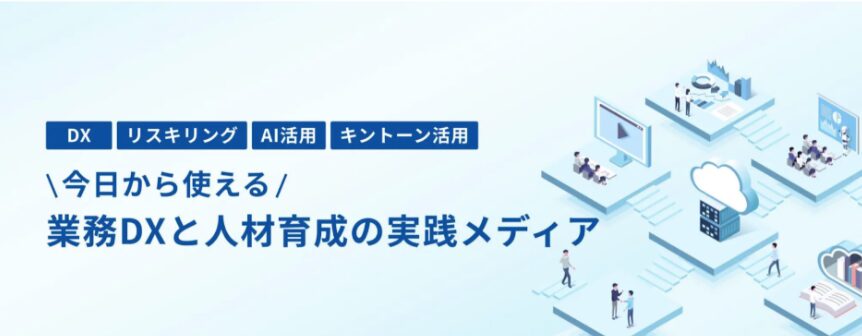
業務効率化は、単に作業を早く終えるための取り組みではなく、企業全体の生産性を高め、従業員がより価値の高い仕事に集中できる環境を整えるための経営戦略です。
効果的な業務効率化を進めるためには、次のステップを繰り返し、PDCAサイクルを継続的に回すことが重要です。
- 現状の業務を可視化して課題を明確にする
- 現場の声を反映しながら改善を進める
- 数値化によって成果を定量的に把握する
一方で、ツール導入や業務フローの見直しには専門的な知見が求められます。
「自社に最適な効率化施策を見つけたい」「社内に合う改善ロードマップを描きたい」とお考えの方は、ぜひ「伴走ナビ」にご相談ください。
業務効率化の専門家が、課題整理からツール選定・導入支援まで、貴社に寄り添いながらサポートします。