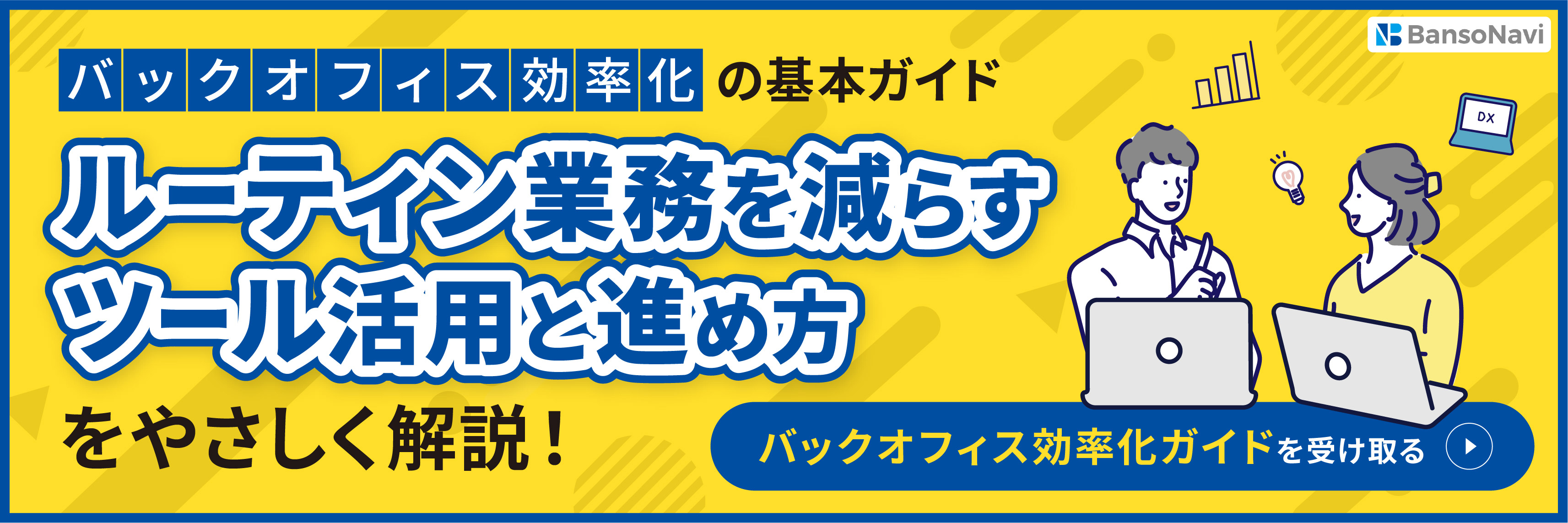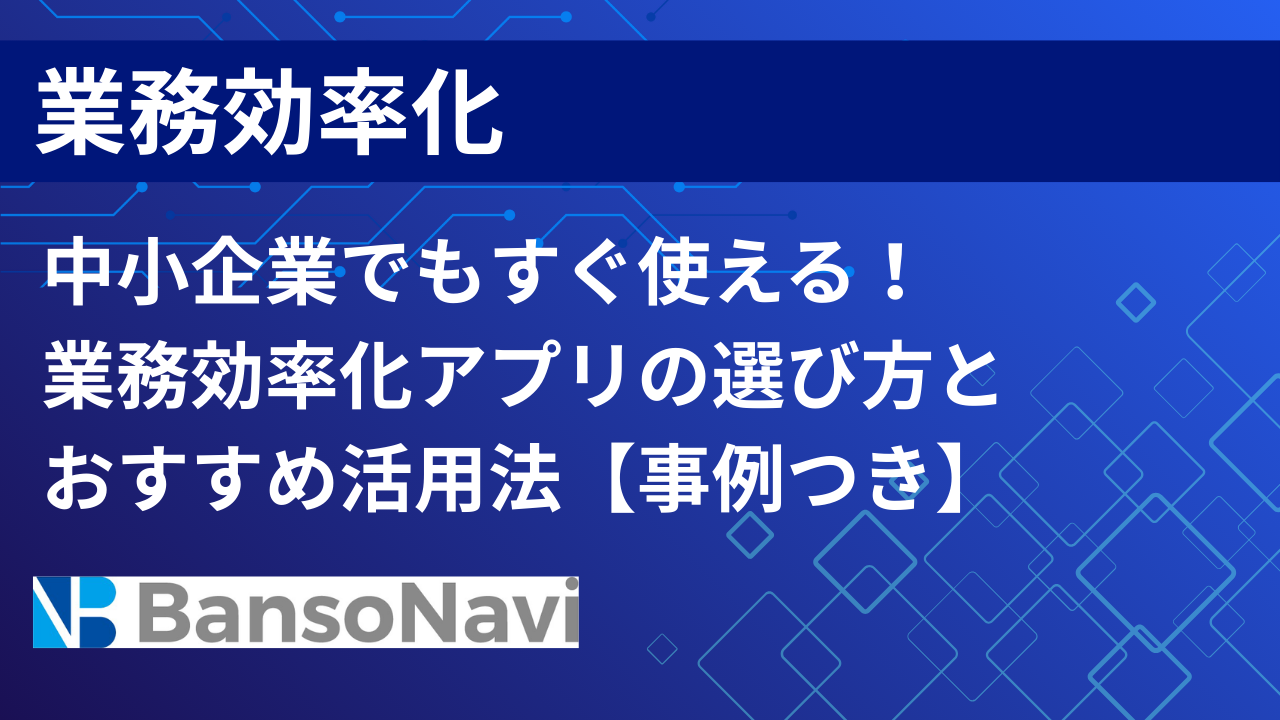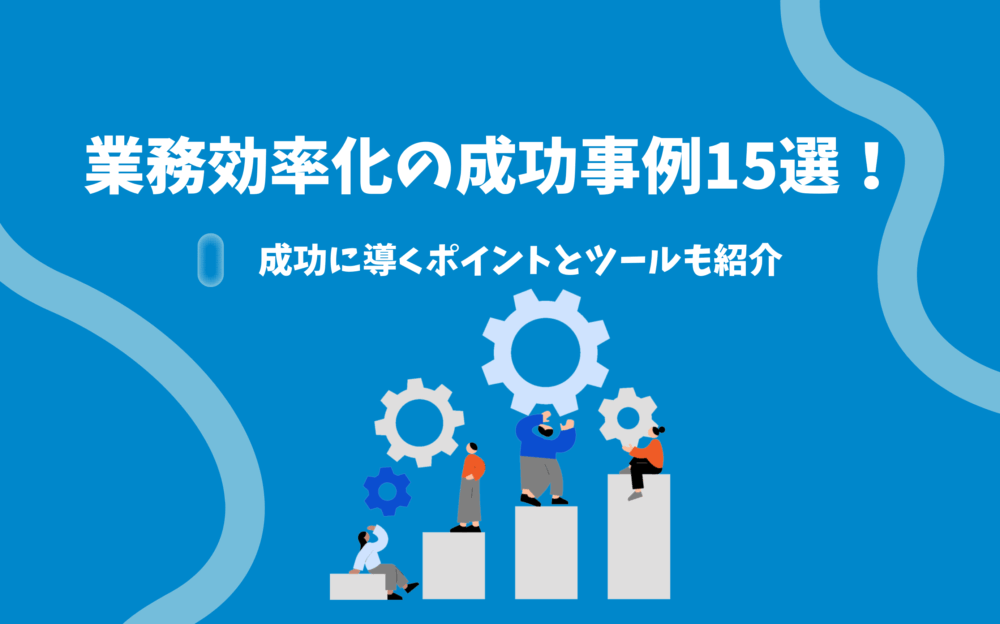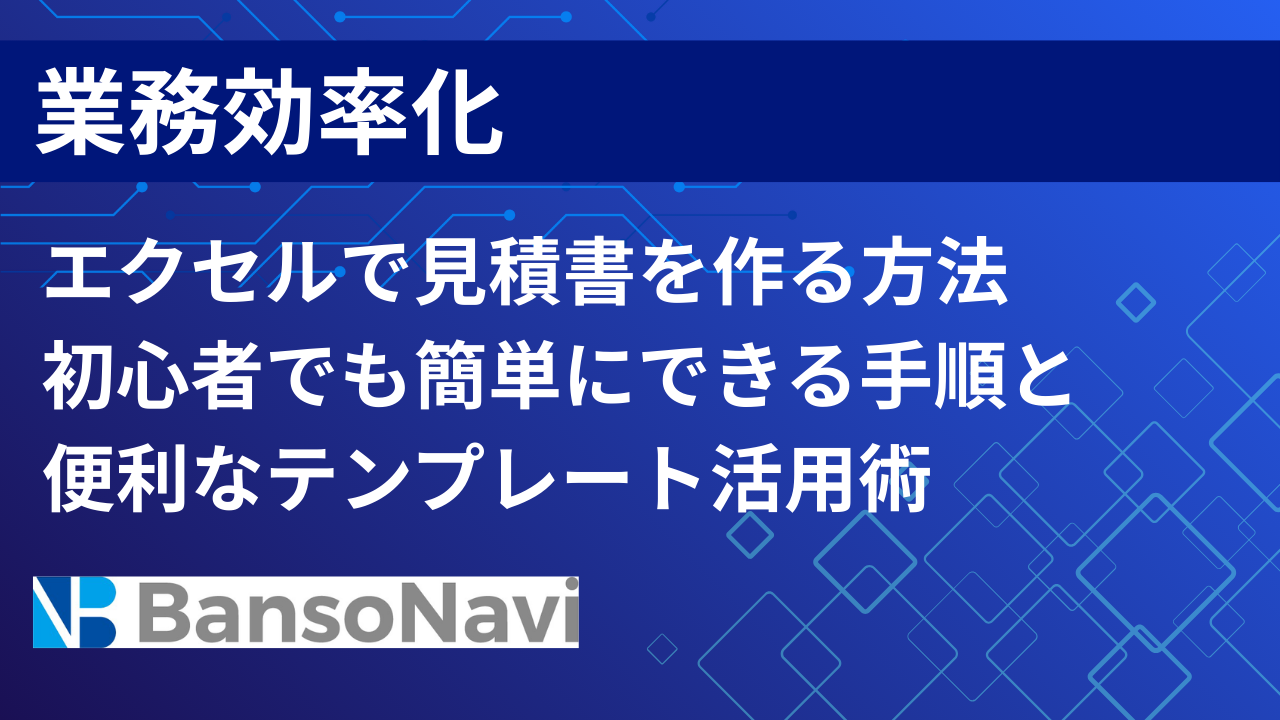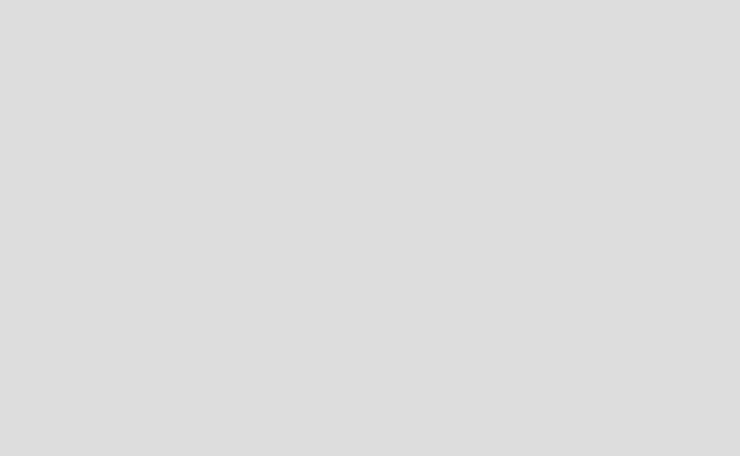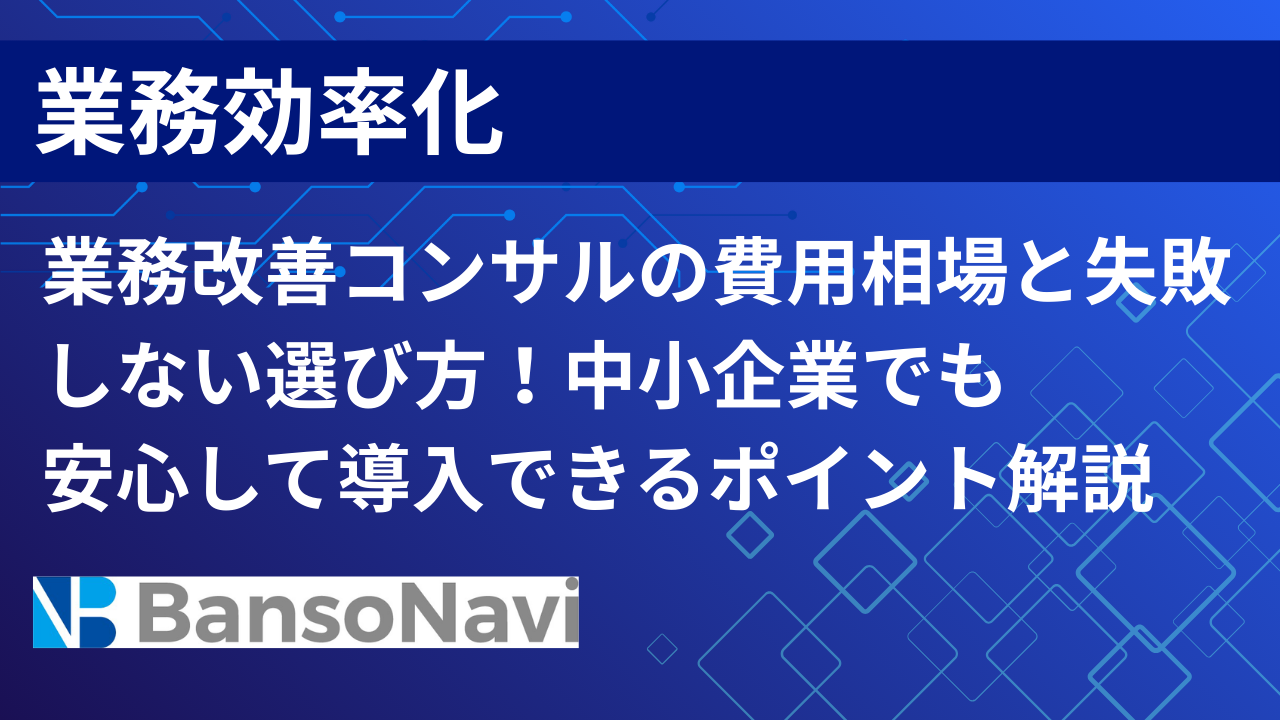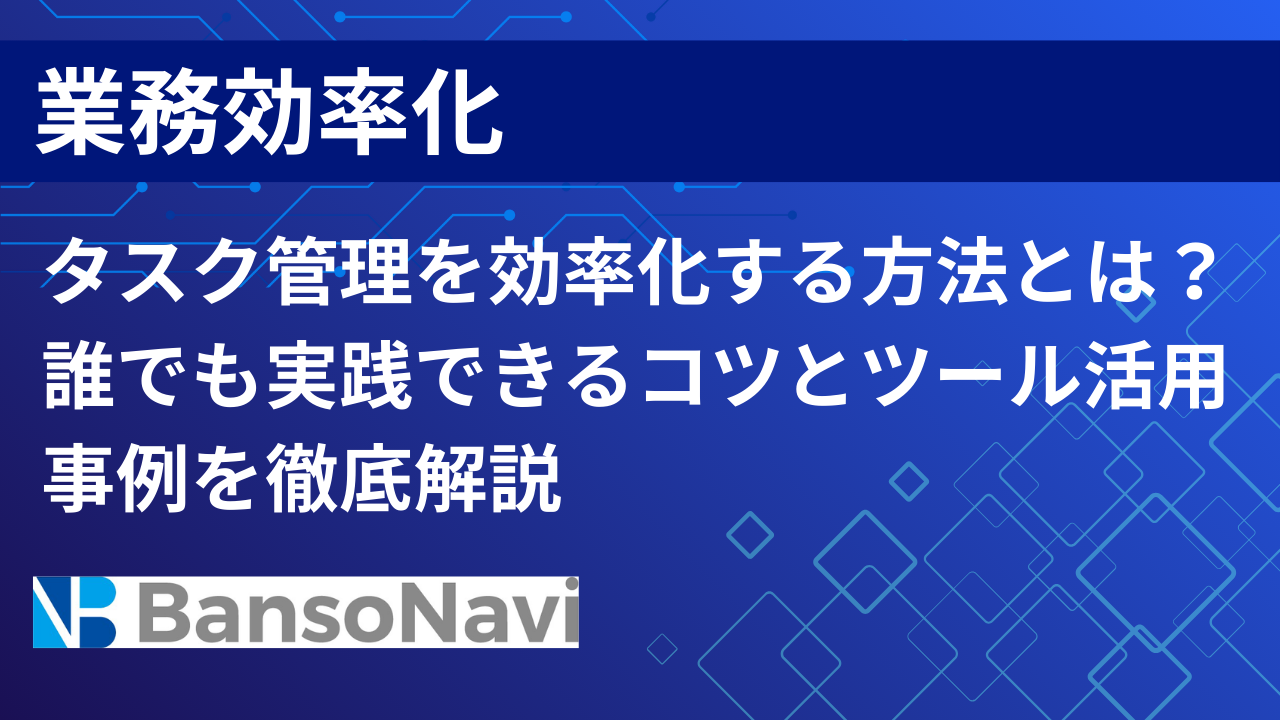営業を効率化するための方法とは|手順とツールも解説

「営業の成果が伸び悩んでいる」
「人手不足でも売上を維持する方法を知りたい」
営業活動が効率化できない悩みを抱えていませんか?
営業活動は、属人化や事務作業の多さによって非効率になりがちです。働き方改革や競争激化のなか、限られたリソースで成果を出すには営業の効率化が欠かせません。
本記事では、営業を効率化する背景や目的、具体的な施策や手順を分かりやすく解説します。さらに、業務支援に役立つおすすめツールも紹介します。
営業体制の見直しを図りたいマネージャーや現場リーダーの方は、ぜひ最後までご覧ください。
■この記事でわかること
- 営業を効率化すべき理由と背景
- 営業効率化の手順と改善施策
- 導入すべきおすすめツール
■こんな人におすすめの記事です
- 営業チームの生産性を高めたい方
- 現場の属人化を解消したいマネージャー
- 営業の仕組み化に悩んでいる企業担当者
目次
営業の効率化とは?
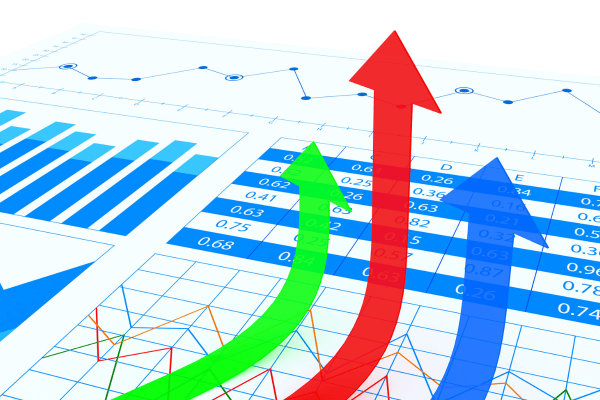
営業の効率化とは、営業プロセス全体を見直し、最小限のリソースで最大の成果を上げる仕組みを構築することです。属人化の解消や情報共有、ツールの導入などを通じて、無駄を省きながら業務の質を高めていきます。
たとえば、訪問記録や日報作成をシステムで自動化すれば、担当者は提案活動に集中しやすくなります。また、案件管理や見込み顧客の情報をチームで共有できると、連携もスムーズになるでしょう。
効率化は単なる業務の短縮ではなく、売上や顧客満足度向上にも直結する重要な施策です。変化の激しいビジネス環境を勝ち抜くためには、営業体制の見直しが欠かせません。
営業の効率化が必要な3つの背景
近年、営業の現場ではさまざまな要因が重なり「従来どおりのやり方」では成果を上げにくくなっています。ここでは、なぜ今「営業の効率化」が重要なのか、以下3つの視点から解説します。
- 営業人員の確保がますます難しくなっている現状
- 業務の見直しと柔軟な働き方が求められている流れ
- スピードと成果が問われる時代の課題
それぞれ見ていきましょう。
労働人口が不足している
日本では少子高齢化が進行し、生産年齢人口が年々減少しています。総務省の統計によれば、2030年には労働力人口が約6400万人まで落ち込むと予測されています。これは多くの企業にとって深刻な人手不足を意味するといえるでしょう。
営業部門も例外ではなく、新人採用や人材育成にかかるコストや時間が重くのしかかるようになってきました。限られた人材で業績を維持・拡大するには、従来の働き方では立ち行かなくなる可能性が高いです。
だからこそ、営業活動のムダを減らし、少数精鋭でも成果を上げられる体制の構築が急務といえます。
働き方改革が進んでいる
労働環境の改善を目的とした「働き方改革関連法」により、企業は長時間労働の是正や柔軟な勤務制度の導入を求められるようになりました。営業職も、移動時間の短縮や残業削減が重要なテーマです。
また、テレワークやフレックスタイム制の導入により、個々の働き方に合わせた業務設計も求められています。属人的なやり方に依存していては、効率的に業務を回すのは困難でしょう。
そのため、ITツールの活用や業務プロセスの見直しにより、場所や時間にとらわれずに成果を出す営業スタイルが必要とされています。
企業の競争力を高める必要がある
顧客ニーズの多様化や市場環境の変化が加速する中で、企業にとって「営業力の強さ」は競争力の重要な指標の1つです。スピード感のある提案や、タイムリーなフォローができる企業ほど、顧客からの信頼を得やすくなっています。
一方で、アナログな営業手法を続けている企業は、商談機会の損失や対応遅れによって、競合に後れを取るリスクが高まっています。とくに、デジタル化が進むBtoB分野では、営業活動のスピードと精度が差を生む要因といえるでしょう。
営業フローを整え、常に変化に対応できる体制を築くことが、今後の企業成長に直結するポイントです。
営業の効率化が進まない理由
営業の効率化が求められているにもかかわらず、実際には思うように進んでいない企業も多く見られます。
ここでは、営業活動がスムーズに進まない代表的な課題を3つ解説します。
- 業務が個人に依存しやすく、属人的になっている
- チーム内で営業方針や優先順位が共有されていない
- 本来注力すべき活動以外に手間がかかっている
それぞれ自社の課題と照らし合わせてみてください。
担当や案件が属人化している
特定の担当者だけが顧客情報や提案内容を把握している状態が珍しくありません。属人化が進むと、業務の進捗が可視化されず、ほかのメンバーが状況を把握できないまま取り残されることになります。
とくにベテラン社員に情報やノウハウが偏っている場合、業務の継続性が脅かされるリスクが高まります。急な人員の入れ替えや担当変更が発生した際、顧客対応に支障が出るケースも少なくないでしょう。
また、属人化された体制ではチーム全体の連携も難しく、営業成果が個人頼みになる傾向があります。組織としての営業力が安定せず、継続的な成長が阻害されてしまう点が大きな課題です。
注力すべき内容が共有されていない
本来優先すべき顧客や案件が社内でうまく共有されていないことがあります。その結果、各担当者が独自の判断で対応を進めてしまい、営業方針に一貫性がなくなることが少なくありません。
たとえば、見込み度の高い案件が把握されないまま放置されたり、別の担当と同じ顧客に重複対応してしまったりなどの問題が生じます。このような情報の断絶は、対応漏れや遅れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す要因となるでしょう。
また、営業リーダーがチーム全体の状況を把握できていない場合、適切な指示や判断が困難です。営業戦略と現場が噛み合わない状態が続くことも、1つの原因です。
事務作業にリソースが取られる
営業担当者は顧客対応や提案活動だけでなく、多くの事務作業にも時間を割いています。たとえば、日報の作成、名刺の整理、訪問履歴の入力、見積書の作成などが代表例です。
営業成果に直結しないにもかかわらず、これらの業務の対応に追われて、本来の活動時間が圧迫されがちです。とくに手作業による管理や重複入力が必要な環境では、作業負荷が一層高まります。
このような状況では、商談準備や提案の精度を高める時間を十分に確保できず、結果的に売上機会の損失につながるおそれがあるでしょう。
営業効率化の4つの目的

単に作業時間を短縮するだけが、営業効率化の目的ではありません。組織としての営業力を底上げし、企業全体の成果に貢献することがもっとも大切です。
ここでは、営業効率化のおもな目的を4つ解説します。
- 商談機会を逃さず、売上を最大化する
- 担当者の負担を軽減し、提案業務に注力させる
- 顧客対応のスピードと精度を向上し、満足度を高める
- 間接業務や人件費の削減により、コストを最適化する
それぞれ見ていきましょう。
売上向上につながる
営業を効率化する最大の目的は、売上の増加です。営業プロセスのムダを減らし、顧客対応や提案に集中できる時間を増やすことで、1人あたりの生産性が向上します。
また、情報共有や案件管理の質が高まれば、商談の抜け漏れや対応の遅れが減少し、受注機会を逃しにくくなります。このような積み重ねによって、営業活動が全体的に活性化され、成約数や単価アップにつながる可能性が高まるでしょう。
人員を増やさずに売上を伸ばすためには、限られた時間とリソースを最大限に活用する体制作りが欠かせません。
営業負荷を軽減し、顧客への提案に集中する
煩雑な事務作業や移動の多さにより、提案の検討や商談準備の時間が圧迫されるケースは少なくありません。そのため、担当者の過度な負担を軽くし、提案業務に集中する環境を整えることも目的の1つです。
営業担当者が価値提供に集中できない状態は、顧客満足度や成果にも直結する重大な問題です。だからこそ、業務の負担を減らし、創造的・戦略的な業務に時間を割けるようにすることが求められます。
担当者が自信を持って提案に臨める環境をつくることが、企業の営業力強化にもつながっていくのです。
顧客満足度を上げる
営業効率化の先にある重要な目的が、顧客満足度の向上です。迅速で的確な対応は、顧客の信頼を得るうえで欠かせない要素です。しかし、業務が煩雑なままではそれが実現しにくくなります。
情報の整理や対応フローが整っていれば、顧客の課題や要望をスムーズに把握でき、満足度の高い対応が可能です。結果として、継続的な取引やリピート受注、さらには紹介などの好循環が生まれるきっかけにもなります。
顧客満足度向上は短期的な目標ではなく、長期的な信頼関係と収益の安定を築くために継続すべき目標です。
コストを削減する
営業活動には目に見える費用だけでなく、時間や手間などの目に見えにくいコストも多く存在します。間接的なコストを抑え、経営資源の無駄を減らすことも大切です。
たとえば、商談準備や移動、報告作業に多くの時間が割かれていれば、それだけで人件費がかさみます。また、業務が属人化していれば、引き継ぎや教育にかかる負荷も増えるでしょう。
しかし、営業プロセスが最適化されれば、同じ成果をより少ない工数で達成できます。
営業を効率化する8つの方法
営業活動を効率化するには、単に業務量を減らすのではなく、やり方そのものを根本から見直すことが必要です。
ここでは、営業活動のムダを省き、成果を最大化するために実践できる具体的な8つの方法を紹介します。
- 営業担当の行動や思考に変化を促す
- システムやツールで業務の仕組みを見直す
- 経験や知識をチーム全体に展開する仕組みを作る
- 間接業務を減らし、本来の営業活動に注力する
- 提案書や資料の改善で商談の質を高める
- Webから見込み客を獲得する
- 見込み顧客を育成し、商談化率を向上させる
- 外部リソースを活用し、効率的に営業を支援する
それぞれ参考にしてください。
担当者の意識を変える
営業効率化を進めるうえで、まず重要なのは「意識改革」です。ツールや仕組みを整えても、現場の理解と行動が伴わなければ効果は限定的でしょう。
とくに、業務のデジタル化が進む今、営業担当者にも一定のITリテラシーが求められます。システムの活用を前提とした営業スタイルを定着させるためには、意識と知識の両面からの底上げが欠かせません。
また、社内でリテラシーに差がある場合は、全体のレベルを揃える工夫が必要です。たとえば、DX推進に関する基礎知識を習得する「リスキリング講座」を活用すれば、全体の意識を変えやすくなります。
そのためには、外部リソースの講習を利用するのもよいでしょう。リスキリング講習に興味のある方は、ぜひこちらよりお問い合わせください。
関連情報は伴走ナビ「リスキリングに関する記事一覧」も参考になります。
ツールやシステムを導入する
営業効率を高めるためには、アナログな作業を見直し、業務を可視化・自動化できるツールの導入が有効です。とくに、案件管理や顧客対応、日報提出などが属人的に行われている場合は、仕組み化の効果が出やすいでしょう。
SFA(営業支援ツール)やCRM(顧客管理システム)を活用すれば、進捗状況や対応履歴の共有がスムーズになり、チームでの連携も強化されます。また、データ分析によって営業活動の改善点を把握しやすくなるのも大きなメリットです。
中でもおすすめなのが、柔軟なカスタマイズが可能な「kintone(キントーン)」です。営業日報や案件管理、商談履歴の一元化など、現場に合わせて自由に業務アプリを構築できます。
営業活動の属人化を防ぎ、情報の整理と共有を一手に引き受けてくれるkintoneは、効率化の取り組みとして相性のよいツールといえるでしょう。
営業に関するノウハウを担当者間で共有する
営業現場では、経験豊富な担当者が蓄積してきたノウハウが可視化されず、属人的に留まっているケースが多く見られます。この状態では、ほかのメンバーが同じ課題に何度も直面し、非効率な対応を繰り返すことになりかねません。
成功事例や失敗の背景、効果的な提案資料やトーク例などは、全員で活用すべき貴重な知見です。共有の仕組みがあれば、未経験者や中途入社メンバーも短期間で現場に順応できるでしょう。
ノウハウを蓄積・共有する文化が根付けば、チーム全体の営業力が安定し、個人差による成果のばらつきも抑えやすくなります。
事務作業を短縮する
営業職は外回りや提案活動が中心と思われがちですが、実際には日報の入力や見積書作成、会議資料の準備など、事務作業に多くの時間を費やしています。これらの業務が積み重なると、顧客対応に割くべきリソースが圧迫されてしまうのが実情です。
とくに、紙ベースや手作業が残っている環境では、入力ミスや二重登録などのトラブルも発生しやすくなります。そのため、確認や修正作業が増え、さらに時間を奪う悪循環に陥ることもあるでしょう。
事務作業の量が多すぎると、本来の役割である「売上をつくる活動」に集中できなくなります。営業効率を高めるためには、このような間接業務の負荷を減らす意識が必要不可欠です。
営業資料や提案資料を改善する
営業現場では、資料の質が商談の成否を左右することも少なくありません。内容が分かりにくかったり、情報が古かったりすると、せっかくの提案も魅力が伝わらず、受注のチャンスを逃してしまいます。
とくに、資料作成の属人化が常態化していると、担当者ごとに表現や構成がバラバラになり、組織としての一貫性が損なわれるおそれもあります。また、都度ゼロから作るようなフローでは、時間も無駄にかかってしまうでしょう。
営業効率を高めるためには、伝わる資料・すぐ使える資料をチームで共有し、改善し続ける文化を根づかせることが大切です。資料のブラッシュアップは、提案力の底上げと業務時間の短縮、両方につながります。
Webサイトからリードを獲得できるようにする
従来の飛び込み営業や電話営業に代わり、Webを活用したリード獲得が重要性を増しています。情報収集の多くがオンラインで行われる今、顧客の関心を引く入り口を用意しておくことが重要です。
たとえば、資料請求フォームやお問い合わせページ、ホワイトペーパーの無料配布などを通じて、見込み顧客と接点を持つ仕組みを作ります。これにより、営業がゼロから関係を築く負担が軽減されます。このようなインバウンド型のリード獲得は、成約率が高く効率的な営業活動につながるでしょう。
また、Webでの集客体制が整っていないと、せっかくの関心層を逃すことにもなりかねません。効率化を進めるなら、オンラインでのリード獲得は今や欠かせない営業活動の1つです。
インサイドセールスを導入し、リードナーチャリングする
リードナーチャリングとは、獲得した見込み顧客を育成し、最適なタイミングで営業につなげる活動です。この役割を担うのが、非対面で営業活動を行う「インサイドセールス」です。
商談化の可能性がまだ低い見込み顧客に対して、段階的に関係性を築きながら、メールや電話、セミナーなどを通じて情報を提供します。そして、顧客の購買意欲が高まるまでアプローチし続け、顧客の熱を育てていきます。この役割とフィールドセールスを分業することで、営業の時間と労力の最適化が可能です。
営業の成果を短期的に求めるばかりでは、見込み顧客を失うリスクも高まります。中長期で接点を維持する体制を整えることで、安定的な商談創出が実現できるでしょう。
アウトソーシングを活用する
近年では、営業アシスタントやテレアポ代行、データ入力などの一部業務を外部に委託するケースが増加傾向です。特定業務のアウトソーシングにより、限られた人材を戦略的な営業活動に集中させられます。
外注にはコストがかかるイメージもありますが、リソース配分の見直しにより、結果的に全体の効率が上がり、費用対効果が改善されます。営業力を最大化する手段として、柔軟な外部活用は有効な選択肢といえるでしょう。
営業を効率化する手順

営業の効率化を成功させるためには、やみくもに施策を実行するのではなく、明確な手順を踏んで進めることが重要です。
ここでは、営業効率化を段階的に実現するための具体的な8つの手順を紹介します。
- 現場の問題点を見える化する
- どの課題に優先的に着手するかを決める
- 実行する内容とスケジュールを計画する
- 改善施策の実施内容を最終決定する
- 限定的な範囲で試験導入する
- 運用現場からの意見を取り入れる
- 全社展開に向けて本格運用に移行する
- 効果を定量的に評価・分析する
それぞれ順に見ていきましょう。
1.課題を洗い出す
営業の非効率を解消するには、まずどこに問題があるのかを明らかにすることが必要です。属人化、情報共有不足、報告業務の煩雑さなど、現場レベルの声を丁寧に拾い上げてください。
ヒアリングやアンケート、業務フローの見直しなどを通じて、現状の営業活動で発生しているボトルネックを整理します。感覚や印象に頼るのではなく、数値や事実に基づいた分析により、改善すべき課題も明確になるでしょう。
2.改善すべき課題の優先順位を決める
複数の課題が見えてきたら、それぞれの重要度と緊急性を踏まえて優先順位をつけてください。すべてを一度に改善しようとすると、かえって混乱や反発を招くおそれがあるためです。
たとえば、売上へのインパクトが大きい問題や、工数削減の効果が高い領域などを優先的に対応することで、初期の成果が得られやすくなります。その結果、現場のモチベーションも高まり、施策の定着が進みやすくなるでしょう。
判断の際には、経営層の意見だけでなく、現場感覚の考慮が大切です。
3.施策を検討し、スケジュールを決める
改善すべき領域が定まったら、具体的にどのようなアクションを取るかを検討します。ツール導入や人員配置の見直し、業務フローの変更など課題に応じた対応策を立案してください。
同時に、施策の実行タイミングや段階的な展開方法も決めておくとよいでしょう。無理のないスケジュール計画により、現場への負担を最小限に抑えながら進められます。
関係部署との連携や事前の社内説明なども計画に含めておくと、実施段階でのトラブルを防ぎやすくなります。
4.施策を確定する
検討した複数の施策案の中から、実際に取り組む内容を最終的に決定します。この段階では、コスト・効果・運用体制などを多角的に比較しながら判断することが求められます。
また、必要に応じて経営陣の承認や関係部門との合意形成を進め、組織としての意思決定を明確にしておくことが大切です。施策の目的や期待される成果、担当者の役割なども事前に整理しておくとよいでしょう。
あいまいなまま実行に移すと、途中で軌道修正が難しくなるため、実行前に方針を固めておくことが重要です。
5.テスト運用する
いきなり全社的に施策を展開するのではなく、まずは一部のチームや部署でテスト的に運用を始めます。小規模で導入することで、課題や想定外のトラブルを早期に発見しやすくなるためです。
たとえば、ある営業拠点や特定の商材に限定して新しいツールや業務フローを試してみると、実践的な改善点が見えてくるでしょう。初期段階で得たフィードバックは、本番導入時の成功率を高めるうえで貴重です。
また、検証期間中は導入効果を数値で記録し、次の手順への判断材料として残してください。
6.営業担当からフィードバックを得る
施策を運用する中で、実際に使う営業担当者の意見を積極的に収集することが大切です。現場に即した視点がなければ、理想と現実にギャップが生まれてしまうからです。
たとえば、「作業が増えた」「使いにくい」「目的が伝わっていない」などの声は、改善のヒントになります。アンケートや定例ミーティングを活用し、率直な意見を聞ける機会を設けましょう。
これらのフィードバックの反映により、担当者の納得感も高まり、現場への定着がスムーズに進みます。
7.本番運用する
全社的に仕組みを導入するタイミングでは、周知・教育・フォロー体制の整備が欠かせません。とくに初期段階は、運用が軌道に乗るまでに戸惑いや混乱が起きやすくなるため、サポート体制を手厚くしておくことが重要です。
導入の目的や活用のメリットを改めて周知し、現場の理解を促しましょう。スタート段階での丁寧な対応が、長期的な定着と継続的な活用につながります。
8.効果測定を行う
施策を導入したあとは、必ずその効果を定量的に評価するフェーズが必要です。実施前と比較して、業務時間の削減や成約率の変化、営業担当の満足度などをチェックしてください。
効果測定を怠ると、改善のインパクトが曖昧になり、次の施策につながる材料も得られません。ツールの利用状況や目標達成度など、具体的な指標を設定し、振り返りを行いましょう。
結果によっては運用方法を微調整し、別の改善策を検討する必要があるかもしれません。測定と改善の繰り返しにより、営業効率化を持続させられます。
営業を効率化するためにおすすめのツール・システム

営業活動の効率化には、業務を支援してくれるツールやシステムの導入が欠かせません。
ここでは、営業現場で活用されている代表的なツールと、それぞれの特徴を紹介します。
- 営業プロセス全体を管理するSFAツール
- 見込み客へのアプローチを自動化する仕組み
- 顧客データを一元化して分析・活用できる管理システム
- 移動を減らし商談効率を高めるオンライン会議ツール
- 商談設定や会議調整をスムーズに行えるスケジュール連携ツール
- 提案資料や契約書などを安全に共有するストレージサービス
- 名刺情報をデジタルで活用・管理するアプリケーション
それぞれ導入の参考にしてください。
SFA(セールス・フォース・オートメーション)
SFAは、営業活動の進捗や顧客対応履歴、成約見込みなどを可視化し、チーム全体で情報を共有・管理するための仕組みです。個人の経験や記憶に頼ることなく、営業プロセスが標準化されるため、属人化の解消にもつながります。
訪問件数や提案内容、商談結果などをリアルタイムで記録すれば、上司も適切なタイミングでフォローや指導が可能です。また、受注確度や活動量をデータで把握することで、営業戦略の見直しや施策改善に活用できます。
中でも、柔軟なカスタマイズ性と使いやすさを兼ね備えた「kintone(キントーン)」は、SFAツールとして高い評価を受けています。現場のニーズに合わせて入力項目やレイアウトを自由に設計できるため、営業担当者の運用ストレスが軽減される点も魅力です。
Excelや紙での管理に限界を感じている企業には、kintoneによる営業支援の導入がおすすめです。
CRM(顧客管理)
CRMは、顧客との関係を維持・強化し、継続的なビジネスを生み出すための重要なツールです。問い合わせ履歴、過去の商談内容、購入履歴などの一元管理により、ニーズに合った対応がしやすくなります。
顧客情報がバラバラに管理されている状態では、対応漏れや認識のズレが起こりやすく、営業機会を逃してしまうこともあります。部門間で情報を共有できるCRMを導入することで、チーム連携の質も大きく向上するでしょう。
中でもおすすめなのが、柔軟な業務アプリを自社で簡単に作れる「kintone(キントーン)」です。顧客情報の登録項目や管理画面のレイアウトを、業種や営業スタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能なため、定着率が高く、現場でも使いやすいと評価されています。
Excel管理から脱却したい企業にとって、kintoneは実用性と拡張性を兼ね備えた理想的なCRMツールといえるでしょう。
MA(マーケティング・オートメーション)
見込み顧客の育成(リードナーチャリング)やセグメント別のアプローチを自動化するのがMAツールの役割です。Webサイトの閲覧履歴や問い合わせ履歴をもとに、見込み度に応じた情報提供が実現します。
たとえば、資料請求後に自動でフォローメールを送る、特定条件に合致した顧客にだけキャンペーン情報を送信するなど、手動では難しい対応が可能です。これにより、商談化率の向上や営業部門へのスムーズなパスにつながるでしょう。
MAは営業だけでなく、マーケティングとの連携にも役立つツールです。営業活動を効率化しつつ、見込み顧客の質を高めたい企業におすすめです。
Web会議システム
移動時間を削減し、商談の機会損失を防ぐ手段として、Web会議システムの活用は不可欠です。対面での営業にこだわらず、遠隔地の顧客ともタイムリーに商談できます。
ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsなど、企業がすでに導入しているツールも多く、操作性や安定性の向上によりビジネス用途での活用が一般化しています。1日に複数の商談をこなすなど、時間の使い方に大きな変化をもたらすでしょう。
加えて、画面共有や録画機能によって、提案内容の理解度も高めやすくなります。
スケジュール管理・日程調整ツール
営業担当者は、日々多くの顧客や社内関係者とアポイントを調整しています。この作業にかかる時間と労力を削減できるのが、スケジュール調整ツールです。
たとえば、Calendlyや調整さんなどを使えば、空いている日時を提示するだけで相手に日程を選んでもらえるため、メールのやりとりが不要です。候補日が一目でわかる仕様により、ダブルブッキングの防止にも役立ちます。
また、チーム単位での予定共有や、社内外のスケジュール連携も簡単です。アポイント取得の効率を高めることで、より多くの時間を提案活動に充てられるでしょう。
オンラインストレージ
提案資料や契約書など、営業で取り扱うデータは年々増加しています。これらを効率的かつ安全に管理・共有するために、オンラインストレージの導入は効果的です。
Google DriveやDropbox、Boxなどのサービスを使えば、社内外のメンバーとのファイル共有が容易になります。外出先からでも資料にアクセスできるため、急な顧客対応にも柔軟に対応可能です。
バージョン管理やアクセス権限の設定など、情報漏洩リスクへの対策も充実しており、セキュリティ面でも安心です。
名刺管理
名刺交換で得た顧客情報を有効に活用できている企業は多くありません。紙の名刺は紛失リスクも高く、検索性や共有性の面でも課題が残ります。
名刺管理アプリを使えば、名刺情報を即座にデジタル化し、担当者間での共有や顧客管理が実現します。たとえば、SansanやEightなどのサービスは、営業支援システムやCRMとの連携も可能です。
これにより、名刺情報が単なる記録ではなく、顧客アプローチやフォローアップの起点となることもあるでしょう。
まとめ:営業の効率化は、kintoneで実現しよう
本記事では、営業効率化が必要とされる背景と課題、目的を整理し、具体的な改善手法や導入手順を解説しました。また、営業DXを支えるSFAやCRMなどの有効なツールも紹介しました。
中でも、自由度の高い業務アプリを現場主導で構築できる「kintone(キントーン)」は、営業活動の可視化と情報共有に効果的です。属人化の防止や業務の一元管理を実現し、チーム全体の生産性向上にも大きく貢献します。
営業改革を進めたい企業にとって、kintoneは柔軟性と操作性を兼ね備えた最適な選択肢です。ぜひ、営業の現場課題を可視化し、継続的な改善を実現するツールとして導入を検討してください。
なお、kintoneの導入を検討されている方は、ぜひペパコミの伴走サービスをご覧ください。