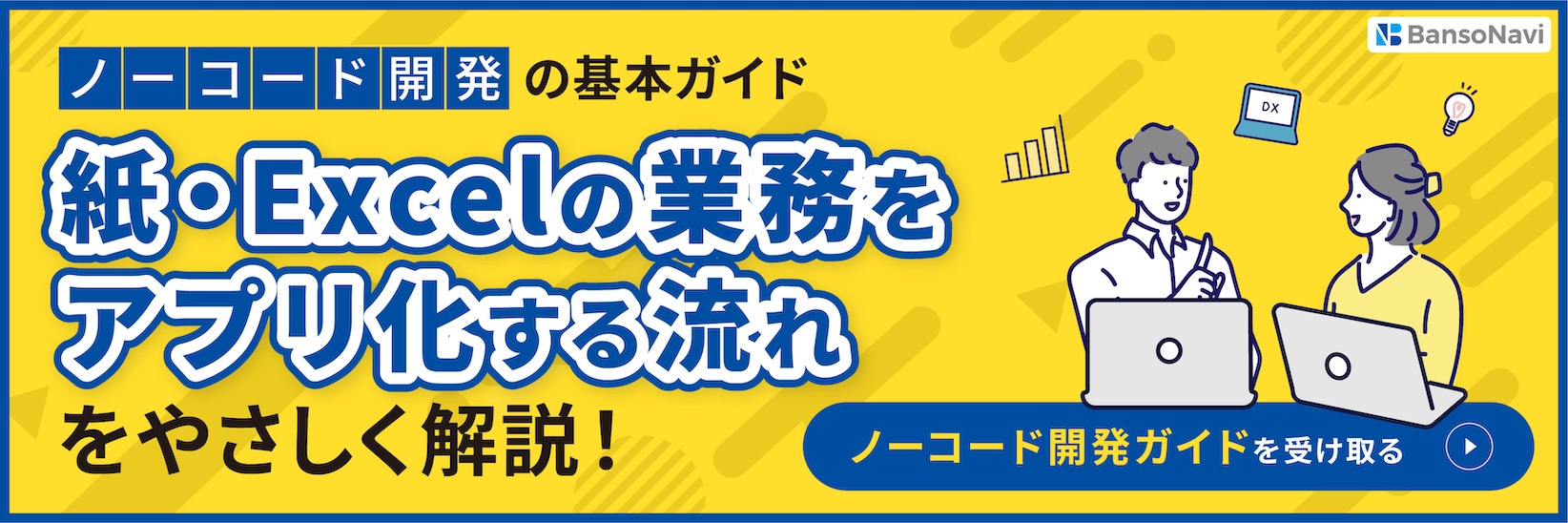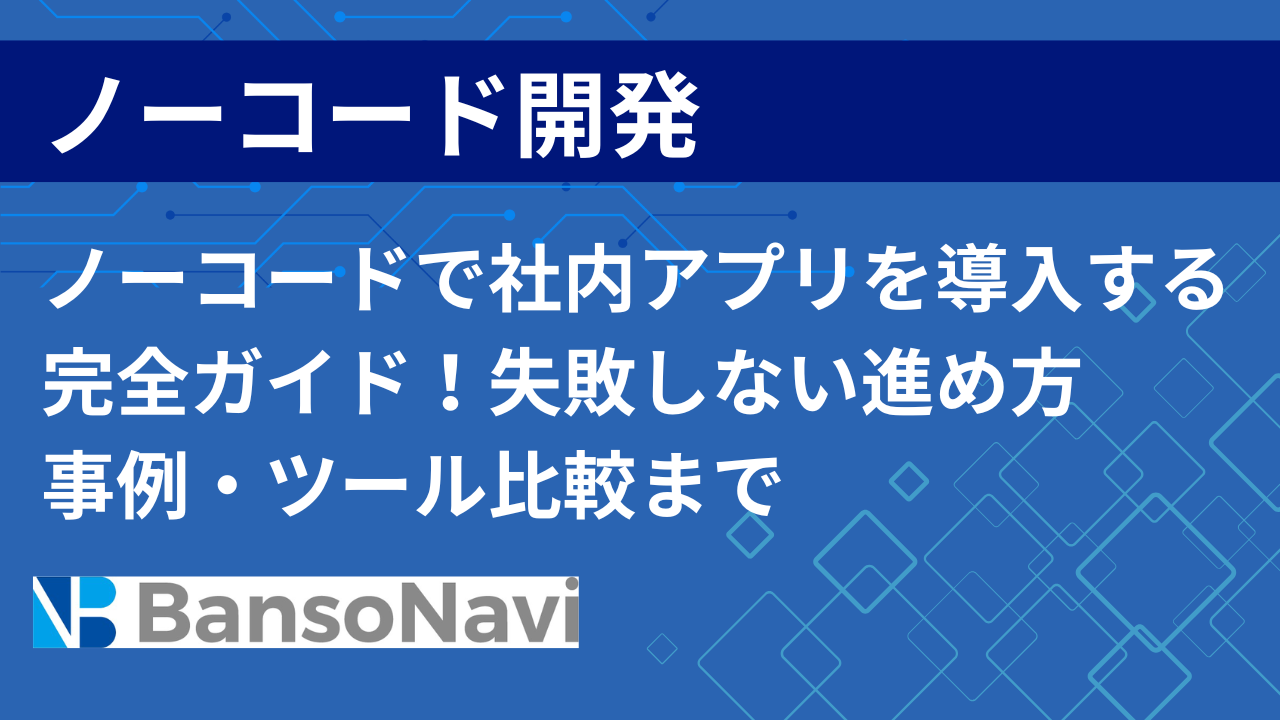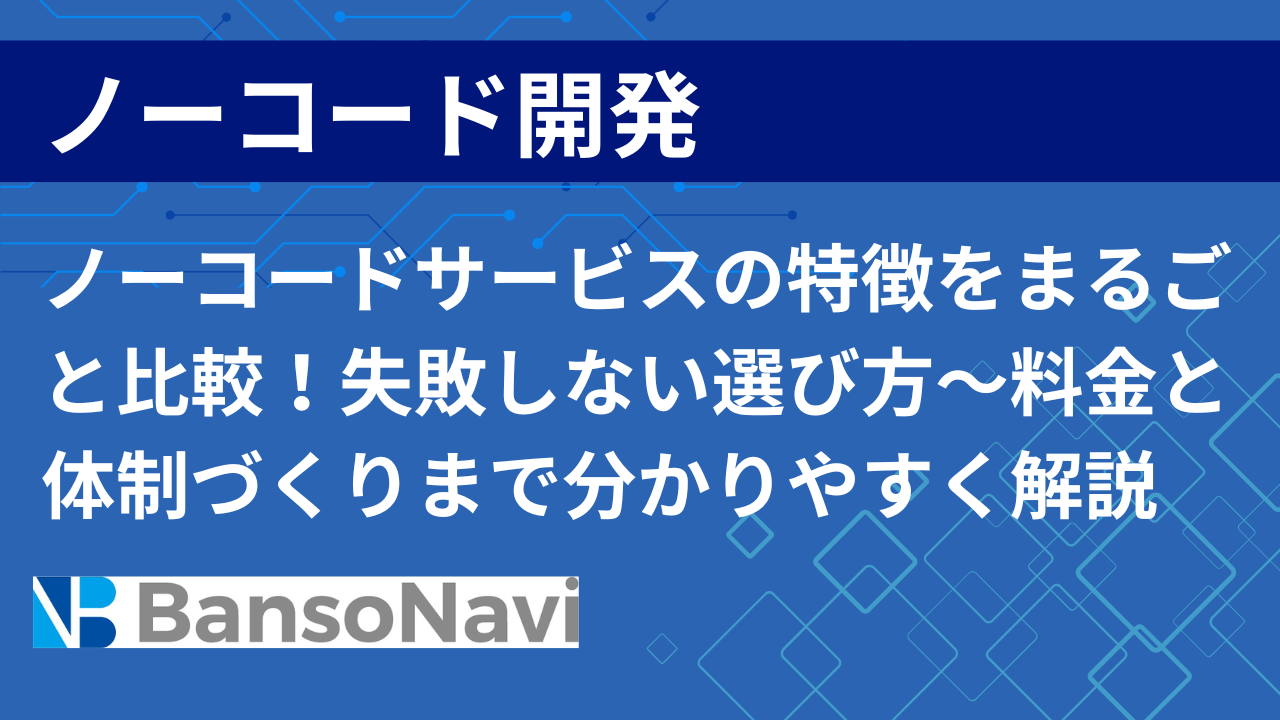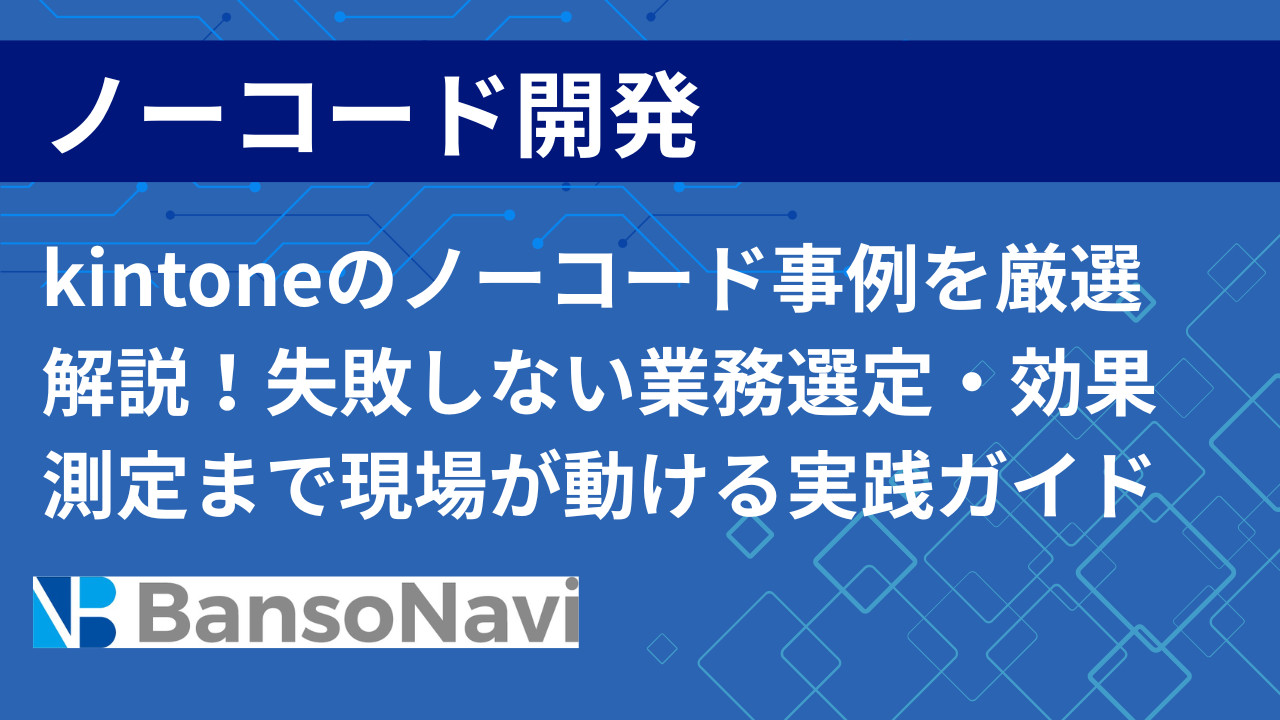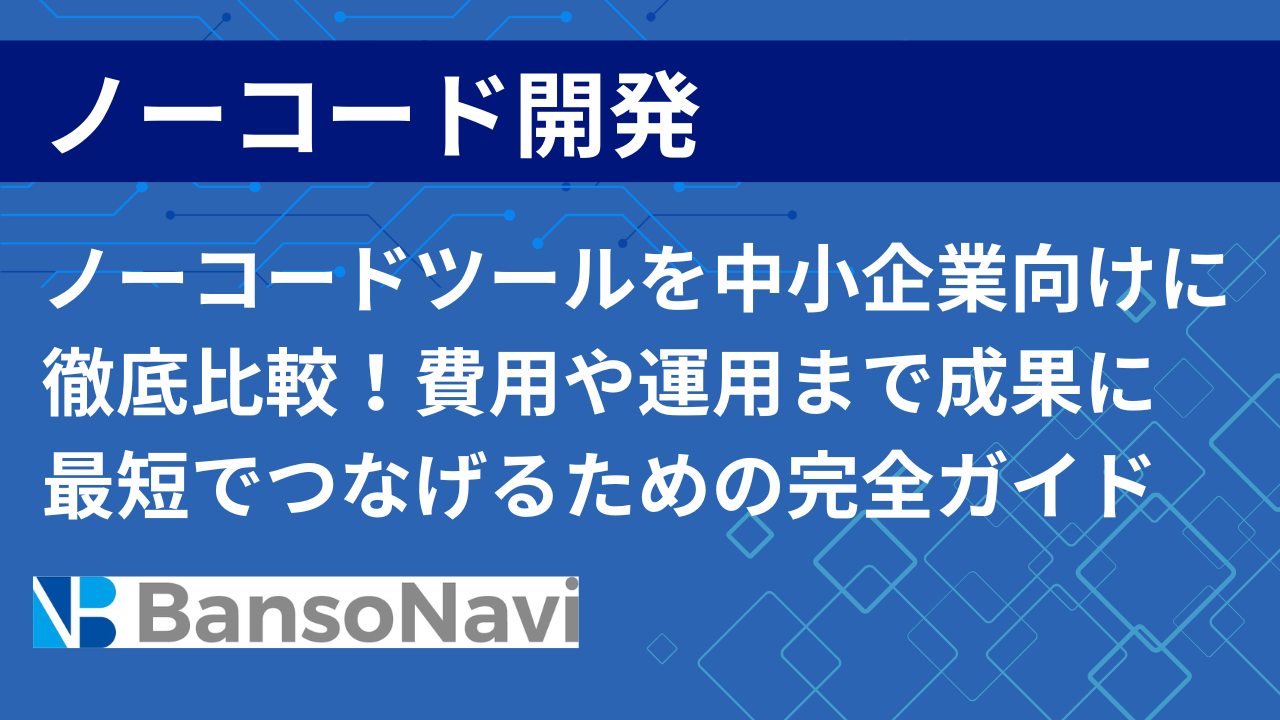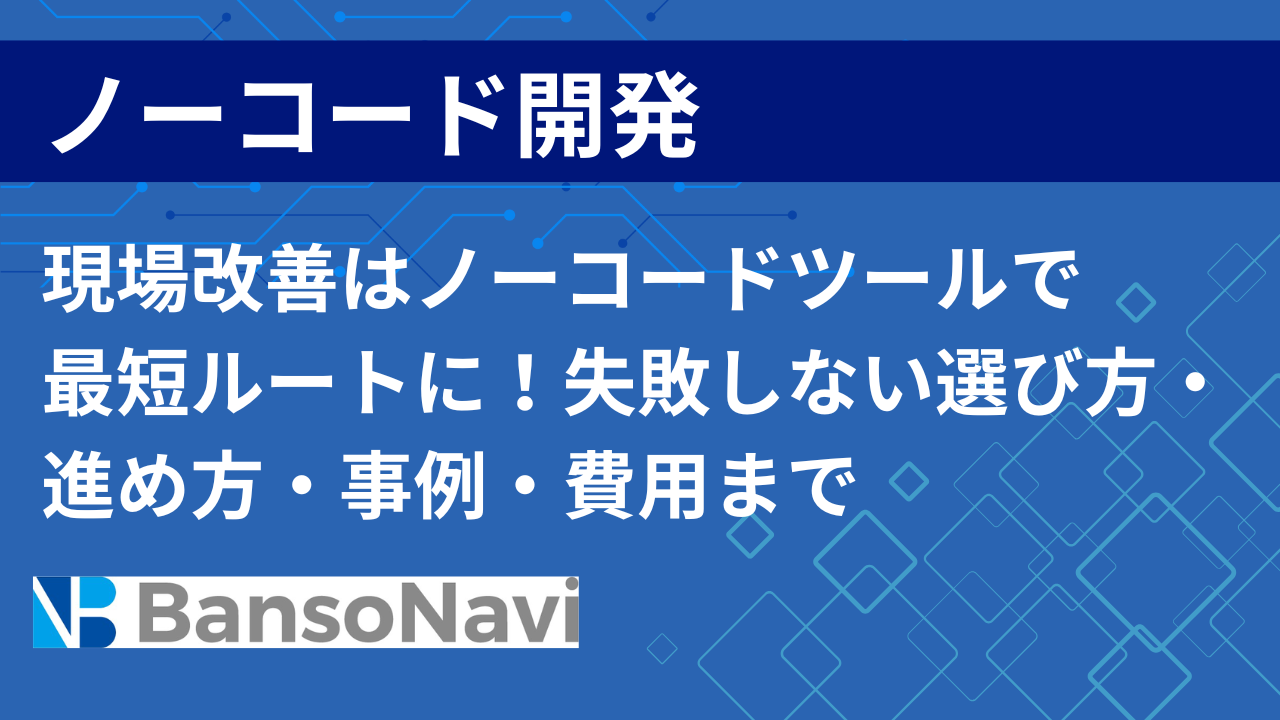ノーコードとローコードの違いとは?メリットやデメリット・開発事例を2つ紹介
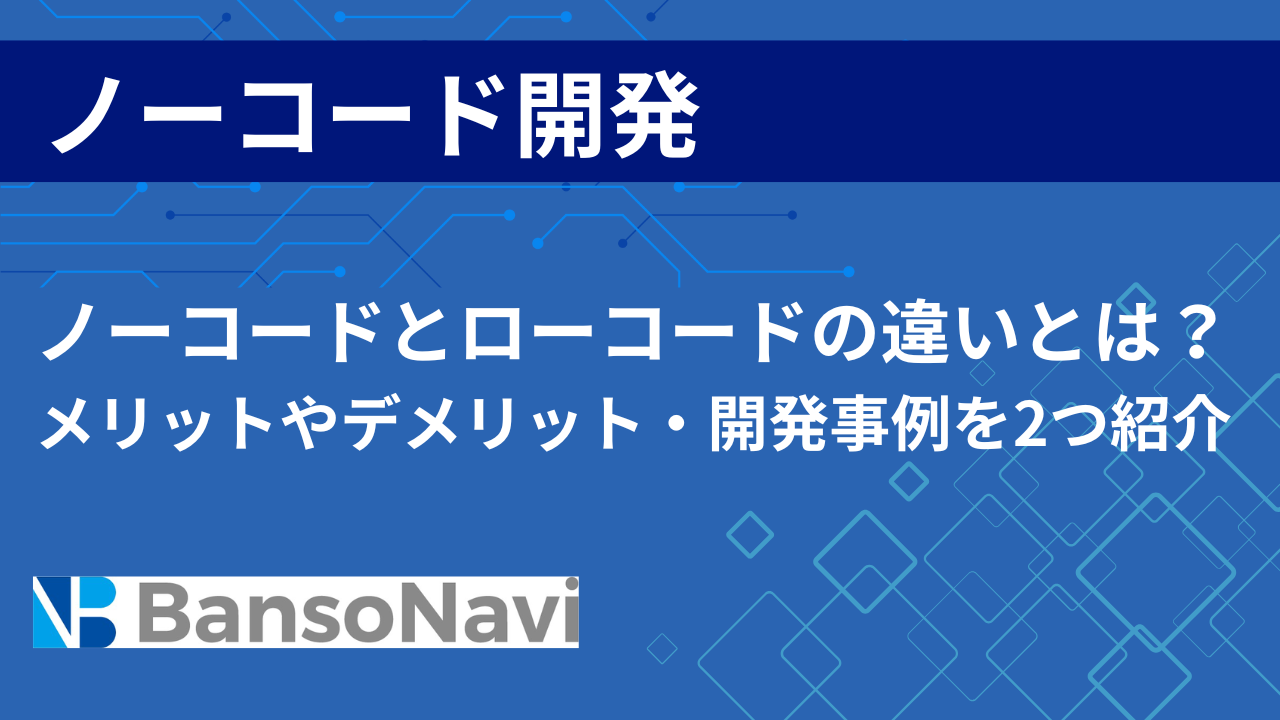
「自社サイトや社内業務を改善するため、エンジニアの工数をかけずにシステム導入したい」 「ノーコードツールとローコードツールがあると聞いたが、違いが分からない」
このような悩みを持つ人はいませんか。 業務改善のために新しいシステムを導入しようとしても、専門的な知識を持つエンジニアがいないと難しい場合があります。
この記事では、ノーコードとローコードの違い、それぞれのメリット・デメリットを解説します。 さらに、ノーコードとローコードツールの選び方や開発事例もあわせて紹介します。
なお、ノーコードツールやローコードツールの導入コンサルティングを活用したい方は、「伴走ナビ」にご相談ください。業務効率化のプロが徹底的に伴走支援し、貴社の業務を5倍楽にします。
目次
ノーコードとローコードの違いとは?

ノーコードとローコードの大きな違いは、ソースコードを記述するかしないかです。 ソースコードとは、プログラミング言語で書かれた、コンピューターへの指示内容を指します。
それぞれの特徴を下の表にまとめました。
| 特徴 | ノーコード | ローコード |
| ソースコード | 不要 | 最低限必要 |
| 開発手法 | パーツをドラッグ&ドロップ | テンプレートと最低限の記述 |
| 開発期間 | 短い | ノーコードよりは長い |
| 自由度 | 低い(定型的な開発向き) | 高い(ある程度自由に開発可能) |
| 必要な知識 | 不要 | プログラミングの基礎知識 |
ノーコードは、ソースコードをまったく使わずにシステムやアプリを開発できます。 コーディングと呼ばれるソースコードを書く作業も不要なため、開発完了までの期間が短い点が特徴です。
一方でローコードは、最低限のソースコードを使って開発を進められます。 そのため、ノーコードと比べると開発期間は長くなりますが、ある程度自由に機能を設計できます。
ノーコードを活用する3つのメリット

ノーコードを活用するメリットは、主に3つあります。
- 専門知識がなくても使える
- 短期間で実装できる
- システム開発のコストを抑えられる
大きな魅力は、エンジニアがいない企業でもシステム開発が可能な点です。それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
専門知識がなくても使える
ノーコードツールは、プログラミングなどの専門知識がなくてもシステム開発ができます。 そのため、エンジニアがいない企業でも導入しやすいのが特徴です。
開発の際は、あらかじめ用意されているパーツやテンプレートを使い、マウス操作にてドラッグ&ドロップし直感的に組み立てられます。
IT人材が減少している現代において、専門知識がなくてもシステムを開発できるノーコードの需要は高まっています。
短期間で実装できる
ノーコードツールは、システムが完成した後のメンテナンスや多少の改修であれば、エンジニア以外の人が対応できる場合も多いです。
プログラミングを一から書く必要がないため、システムを簡単に実装可能です。結果として、社内のDX化、つまりデジタル技術による業務変革も進めやすくなります。 すぐに業務改善を始めたい部署や、すばやく新しいサービスを試したい場合に役立ちます。
システム開発のコストを抑えられる
システム開発には、プログラミング言語やコーディング技術の習得が必要ですが、ノーコードは学習する必要がありません。
また、開発を担当するエンジニアなどIT関係の人件費も抑えることが可能です。 システム開発を外注する場合も、社内で対応する場合も、必要な作業時間を減らせます。
開発コストを削減できた分は、新しい製品の開発や、既存顧客の満足度を強化する施策に回せられます。
ノーコードで開発する2つのデメリット

ノーコード開発には、注意すべきデメリットが2つあります。
- カスタマイズ性が低い
- ツールが使えなくなるリスクが高い
誰でも簡単に開発できる反面、提供される機能の範囲内でしか対応できない制限があります。
カスタマイズ性が低い
ノーコードは簡単で誰でも開発しやすい反面、定型的な機能しか実装できません。
用意された部品を組み合わせる仕組みのため、複雑なサーバーの処理や、独自の機能を付け加えたい場合、ノーコードツールだけでは対応しづらいです。
もし、自社の業務に合わせた特殊な機能や、他社と差別化するような自由度の高い開発を求める場合は、ローコードの利用も検討したほうが良いでしょう。 ノーコードを導入する際は、開発したいシステムが定型的な範囲で収まるかどうかを確認してください。
ツールが使えなくなるリスクが高い
ノーコード開発は、利用するツールに大きく依存します。
もし、開発の土台となるサービスの利用料が値上げしたり、サービス自体が終了したりした場合、開発したシステムが利用できなくなるかもしれません。
別のツールへ移行する場合も、レイアウトが崩れて使えなくなるリスクも考えられます。
またノーコードツールを提供しているのは海外企業が多い傾向にあります。 そのため、導入前には、日本語のサポート対応を行っているかどうかの確認も必要です。
ローコードを活用する4つのメリット

次に、ローコードを活用する主なメリットは以下の4点です。
- プログラミング初心者でも操作しやすい
- バグが発生しにくい
- 生産性が向上しやすい
- セキュリティ対策がしやすい
ローコードは、ノーコードの「簡単さ」と、従来の開発手法の「自由度」を両立しやすい点が特徴です。
プログラミング初心者でも操作しやすい
ローコードは、プログラミング初心者でも操作しやすい点がメリットです。
すでにある程度用意されているパーツを組み合わせた状態で、大部分を開発できます。 足りない部分だけを最低限のコーディングで対応します。
プログラミング作業もほとんど必要ないため、数分から数時間程度でシステムを公開することも可能です。
また、システムの利用者側も開発に携われるため、通常の開発で必要な「要件定義」のプロセスを省略できる場合があります。 要件定義とは、開発するシステムに必要な機能や性能を決める作業です。
バグが発生しにくい
ローコード開発は、バグが起きにくい点も強みです。バグとは、プログラムの誤りや不具合を指します。
開発におけるプログラミングの要素が少ないため、バグが起きにくく、修正にかかる時間も短縮できます。理由は、すべてのコードを手作業で記述する場合と比べて、タイプミスなどの可能性が低いためです。
バグ修正にかかる時間を減らせた分、システムをリリースした後のユーザーの反応に合わせた改修などに時間を使えるようになります。
生産性が向上しやすい
ローコード開発は、社内の生産性を向上させやすいです。
開発の土台となる環境は、開発者がすでにテストを行っているため、バグなどのミスがほとんどありません。
スムーズに開発ができるため、1から構築するよりも短時間でシステムを公開できます。
開発が迅速に進む結果、社内の生産性が向上し、業務改善にもつなげられます。 市場の変化にすばやく対応したい場合に適した開発手法です。
セキュリティ対策がしやすい
ローコード開発は、セキュリティ対策がしやすい点もメリットです。
Webアプリケーションなど、インターネット経由で使うシステムを開発する場合、常にインターネットに接続しています。そのため不正なアクセスへの対策や、アクセス権限の付与など、さまざまなセキュリティ対策が求められます。
ローコードの場合は、使用するプラットフォーム側ですでにセキュリティ対策をしていることがほとんどです。 そのため、自社でゼロから対策するよりもリスクを軽減できます。
ただし、自社でプログラミングした箇所については、しっかりとした対策が必要です。
ローコードで開発する3つのデメリット

ローコード開発のデメリットは、以下の3つです。
- プログラミングの基礎知識が欠かせない
- オリジナル機能は実施できない
- 開発ができなくなるリスクが高い
ノーコードよりは自由度が高いものの、従来の開発手法と比べると制限もあります。
プログラミングの基礎知識が欠かせない
ローコードは、最低限のプログラミングで開発できる点が魅力です。しかし、裏を返せばプログラミングで機能を追加する部分は、専門知識が欠かせません。
特に、システム運用を開始した後のデータ活用では注意が必要です。アプリケーションを作る時に、正しくデータベース設計を行っておく必要があります。
データベース設計とは、集めた情報をどのように整理・保存するかを決める作業です。専門知識なしで構築を進めると、ローコード開発の良さを活かせなかったり、開発が失敗したりする可能性があります。
オリジナル機能は実施できない
ローコード開発は、基本的にプラットフォームで用意されたテンプレートを組み合わせて行います。 そのため、カスタマイズの自由度は、ゼロから開発する手法と比べると低くなります。
自社のアプリを拡張したくなっても、プラットフォームの制限で対応できない可能性があります。
ノーコードよりは自由度が高いですが、非常に複雑なシステムの構築や、完全に独自の機能を求める開発には向いていません。 自社が求める機能が、ローコードの範囲内で実現できるかを確認してください。
開発ができなくなるリスクが高い
ローコード開発は、ノーコードと同様にツールが使えなくなるリスクがあります。
利用しているプラットフォームがサービスを終了した場合、開発が続けられなくなります。 システムもプラットフォームに依存しているため、別の環境へ移行する際にエラーが起こる可能性も高いです。
ローコード開発を始める場合は、利用するプラットフォームが自社の目的や業務に合っているかを、事前にしっかり確認してください。 サービス提供元の信頼性や、長期的な運用が可能かどうかも判断材料になります。
ノーコードの開発事例

ある企業では、ノーコードツールの「kintone」を導入して営業活動の改善に成功しました。
導入前は、社内と社外の情報が分断されていました。 そのため、営業担当が顧客情報や在庫の確認をする場合は、一度帰社するか、社内に電話で確認する必要があります。
ノーコードツールを導入したところ、販売管理システムの構築が可能になりました。 外出先からでも情報にアクセスできるようになり、営業活動がスムーズになっています。
ほかにも、手書きの日報をやめたことで業務のムダがなくなり、データを活用しやすくなった事例もあります。以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ローコードの開発事例

ローコードツールの導入で、複雑だった基幹システムを刷新した事例があります。
ある企業では、旧基幹システムが複雑で非効率な状態でした。 そこで、ビジネスのニーズに合ったシステム構築を実現するため、ローコード開発を実施しています。
結果として、取引データなどが組み込まれた一気通貫のシステム、つまり途切れず連携するシステムが実現しました。
経営状況をまとめた資料の迅速な作成が可能になり、経営判断のスピードアップにつながっています。 また、業務フローが統一されることで、無駄のない業務運営が可能になりました。
参考:導入事例 ローコード開発ツールの強みを活かし 段階的導入により旧システムから脱却
ノーコードとローコードツールの選び方

業務に最適なツールを選ぶ際は以下3つのポイントを意識すると、導入後の効果を最大化できます。
- 既存システムとの連携性
- セキュリティ対策
- 予算と必要機能
まず、すでに社内で使っているアプリや、連携したい外部サービスとの相性が良いツールを選びましょう。相性が良いと、自社のアプリやWebサイトの充実度が大きく向上します。
次に、情報セキュリティが万全なツールを選ぶことで、情報漏洩などのリスクを最小限に抑えられます。最後に、自社の予算に合うツールか、使いたい機能が十分に備わっているかをしっかり確認してください。
上記のポイントを踏まえてツールを選定することで、導入後のトラブルを避け、スムーズに業務改善を進められます。
実務で使えるローコードツール・ノーコードツール3選

ここでは、実務で使える代表的なローコードツール・ノーコードツールを3つ紹介します。
- kintone | 社内データやフォルダを一括管理できる
- Power Apps | マイクロソフトの業務アプリ開発ができる
- Click | 業務を自動化できる
それぞれのツールの特徴を解説します。自社に合うツール選びの参考にしてください。
kintone | 社内データやフォルダを一括管理できる

kintone(キントーン)は、ノーコード・ローコードで業務アプリを自作できるクラウド基盤です。
専門知識が不要で、IT部門以外でもローコードの手法で開発が可能です。
社内のフォルダに散らばっているデータや書類、メールを一括で管理できます。 バラバラだった情報を一つにまとめることで、業務を進めやすくなります。
業務の変化に対してすばやく対応ができ、改善もすぐに反映できるノーコード型のシステム管理体制が整っています。
Microsoft Power Apps | マイクロソフトの業務アプリ開発ができる

Microsoft Power Apps(マイクロソフト パワーアップス)は、ノーコード・ローコードで社内業務アプリを早く開発できるプラットフォームです。
1番の強みは、既存のデータを活用しやすい点です。Excel・SharePoint・Teamsなど、ほかのMicrosoft 365製品と円滑に連携できます。
フォーム作成や承認フロー、分析ダッシュボードなどを、画面上のボタンやアイコンをマウスで操作して作成できます。 非エンジニアでも業務改善が実現可能です。
また、AI Builder機能を使えば、請求書処理やデータ入力などの定型業務も自動化できます。
Click | 業務を自動化できる

Click(クリック)は、ノーコードで業務の流れを自動化できるプラットフォームです。
現場の担当者が自分でアプリを作れるほど操作が簡単です。 作業報告書や議事録の自動生成にも対応しています。
kintoneやGoogleスプレッドシートなど、ほかのシステムとのデータ連携も容易にできます。 これまで紙やExcelで管理していた業務からの脱却が可能です。
さらにAPI連携やチャット通知、承認フローなど、業務に必要な機能をノーコードで一覧管理できます。
ノーコード・ローコードを活用した業務改善は伴走ナビへご相談ください
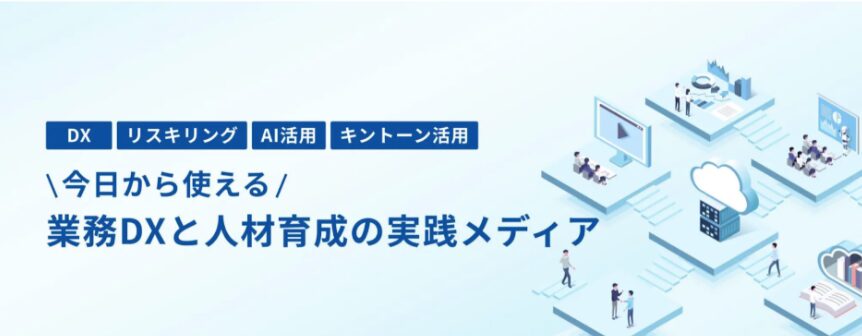
ノーコードは知識がなくても開発できるため、エンジニアを雇用するコスト削減が可能です。ただし自由度が低いため、オリジナルの仕様を実現しづらいデメリットがあります。
ローコードは自由度が高い反面、最低限の知識が必要です。自社の目的や担当者のスキルに合わせて、適した手法を選んでください。
なお、ノーコードツールやローコードツールの導入コンサルティングを活用したい方は、「伴走ナビ」にご相談ください。業務効率化のプロが徹底的に伴走支援し、貴社の業務を5倍楽にします。