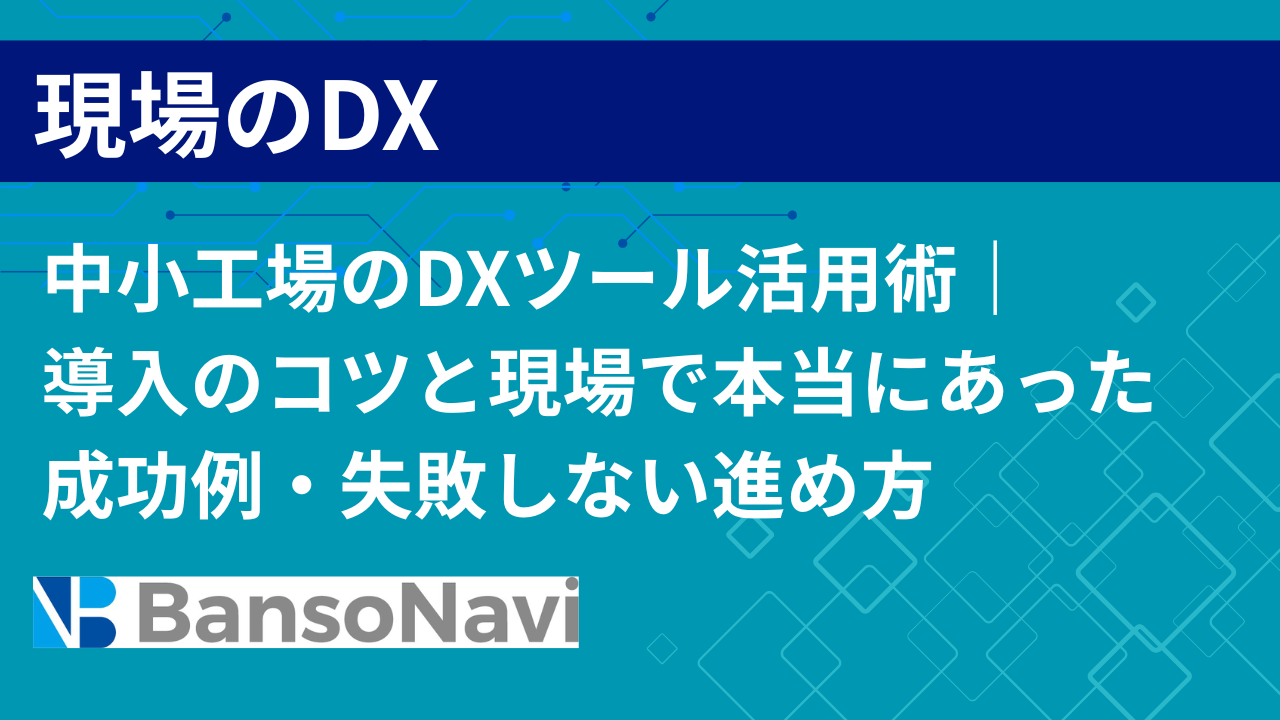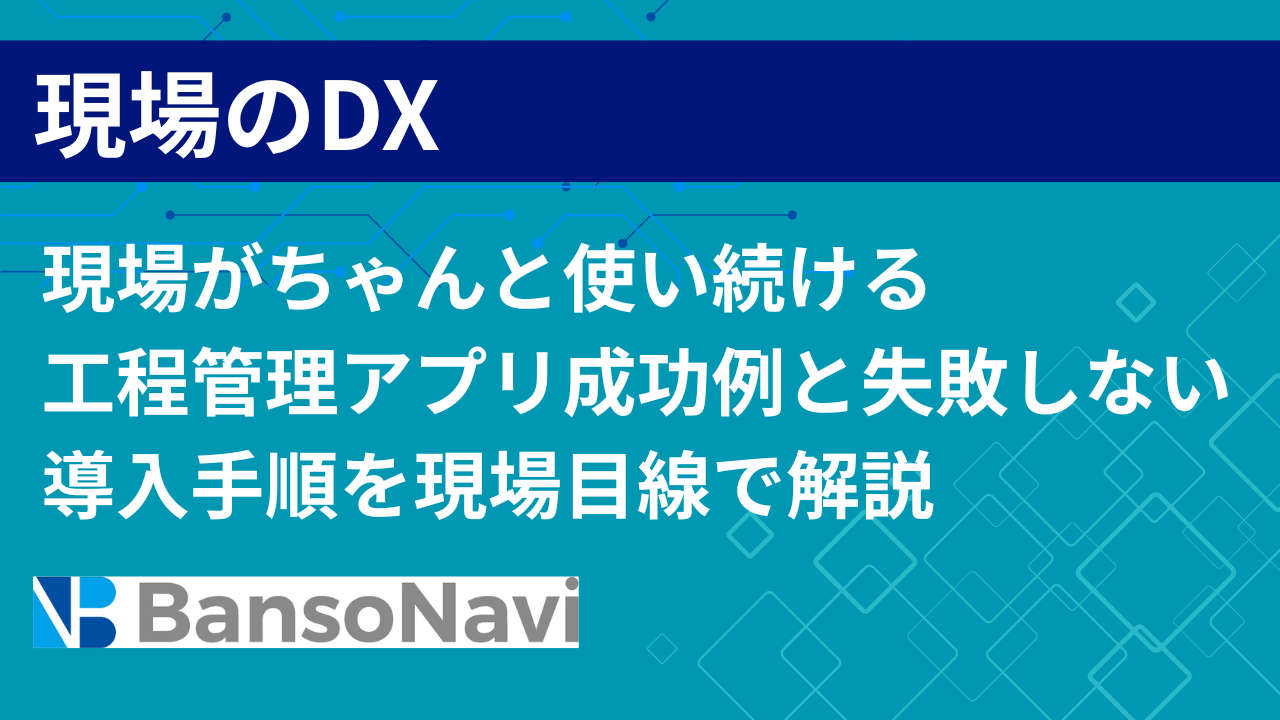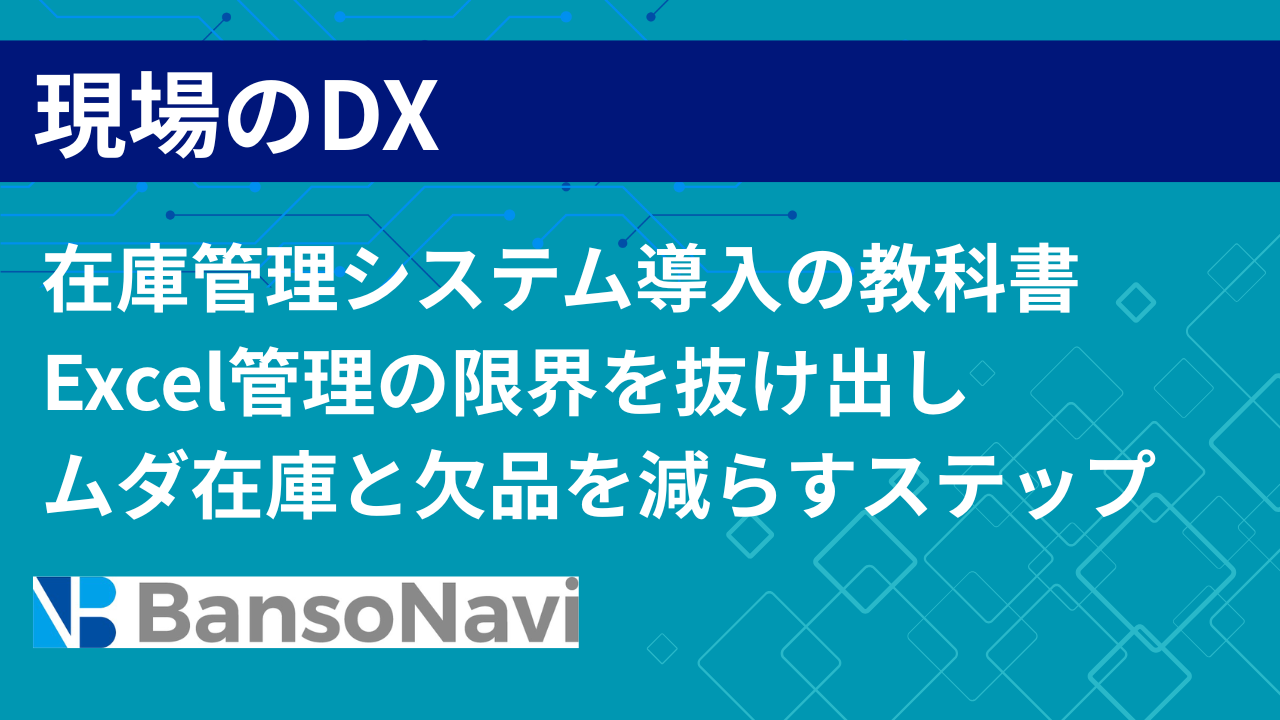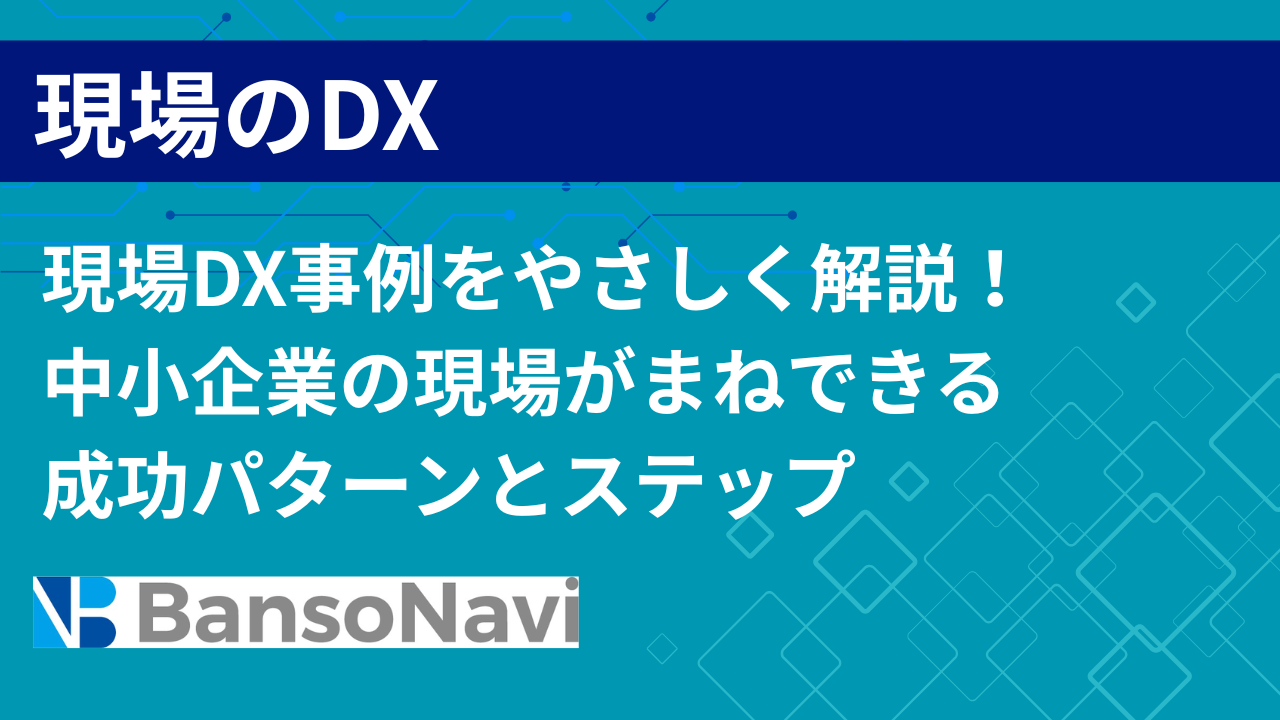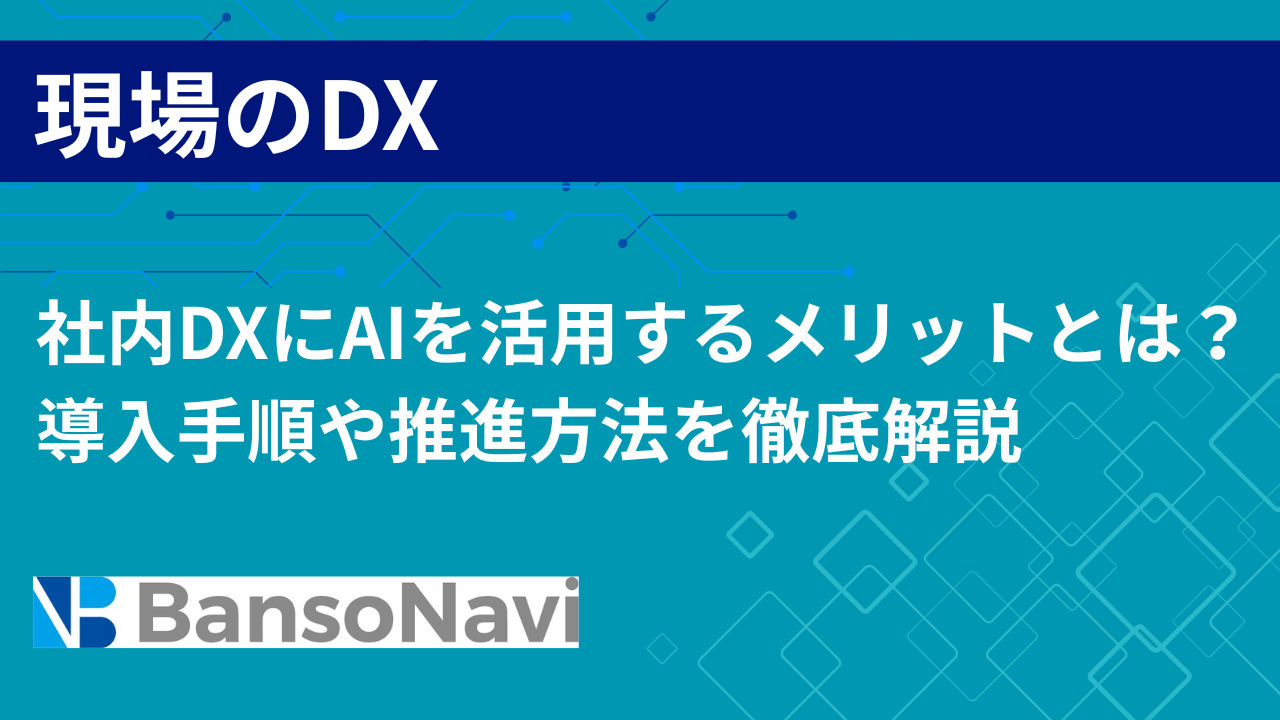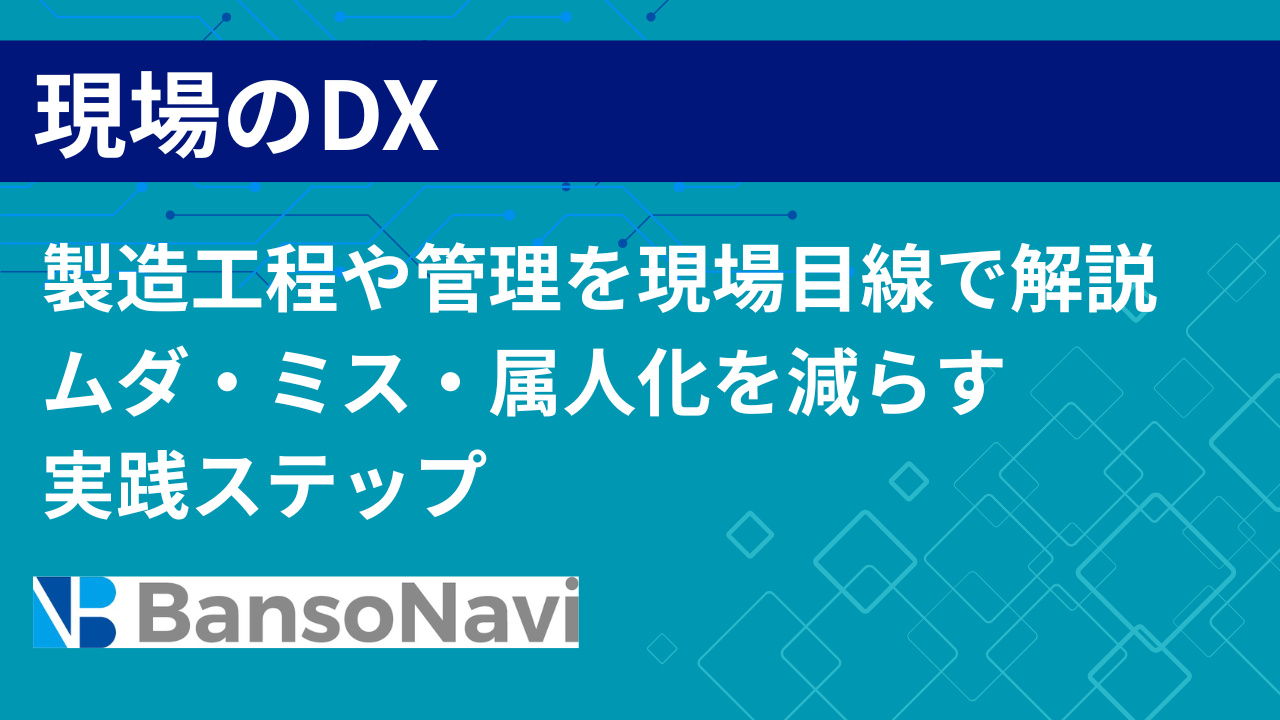LINE頼みの現場連絡を整える:混乱しない情報共有と連絡体制の作り方
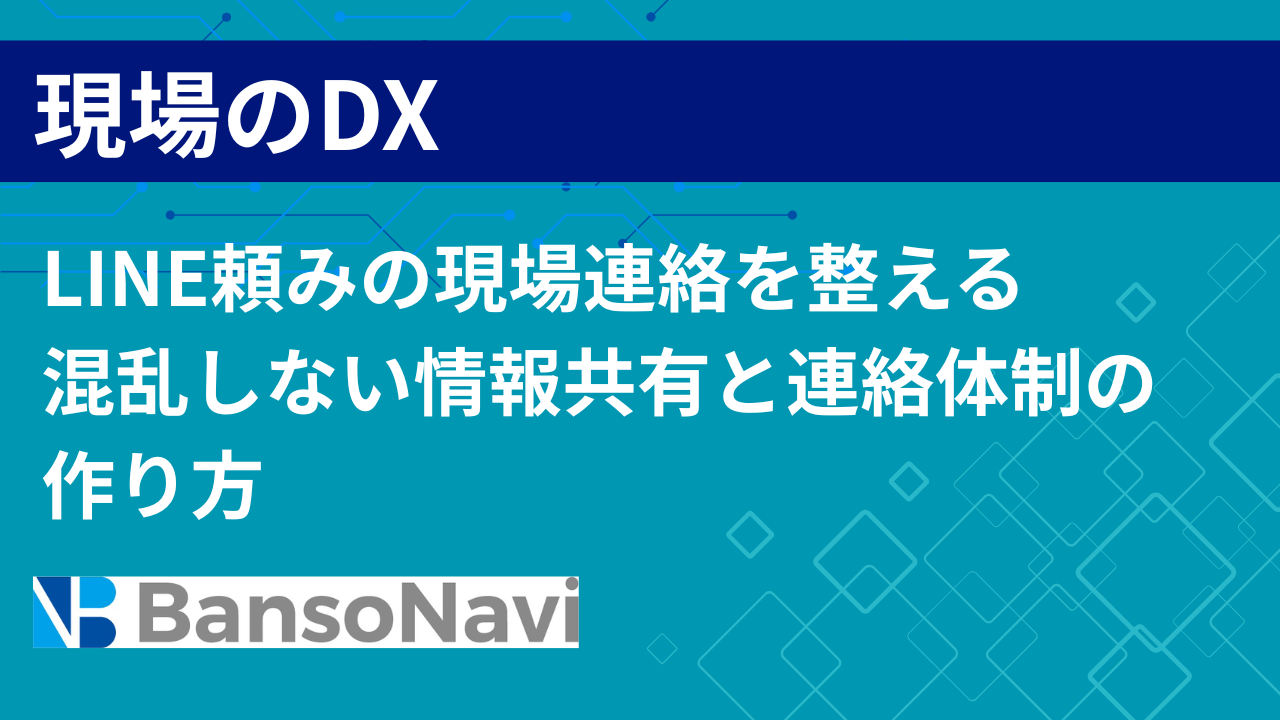
現場の連絡をほぼLINEだけで回していると、最初は「ラクで早い」ように見えても、だんだんと
「どのグループで何が決まったか分からない」
「誰が対応するのかあいまい」
「夜中まで通知が鳴りっぱなし」
といったモヤモヤが積み重なってきます。
とはいえ、「明日からLINEは禁止です」といきなり宣言してもうまくいきません。現場の人にとっては、すでに生活インフラのようなツールですし、いきなり別のツールに切り替えようとしても、結局またLINEに逆戻りしてしまうケースが本当に多いです。
この記事では、現場の連絡をLINE中心でやっていて混乱している会社・チームに向けて、
- どこで混乱が起きやすいのか
- 何をやめて、何を残すとよいのか
- LINEのままでもできる運用改善
- 専用ツールやkintoneに切り替える時の考え方
- 伴走ナビが実際にサポートしてきた進め方
を、できるだけかみ砕いて紹介します。
「いきなり完璧なシステム」を目指す必要はありません。まずはLINEの使い方を整理しつつ、少しずつ別の仕組みに逃がしていくことで、抜け漏れの不安を小さくしながら、現場の負担も増やさない連絡体制を一緒に考えていきましょう。
目次
LINE中心の連絡で起きる混乱
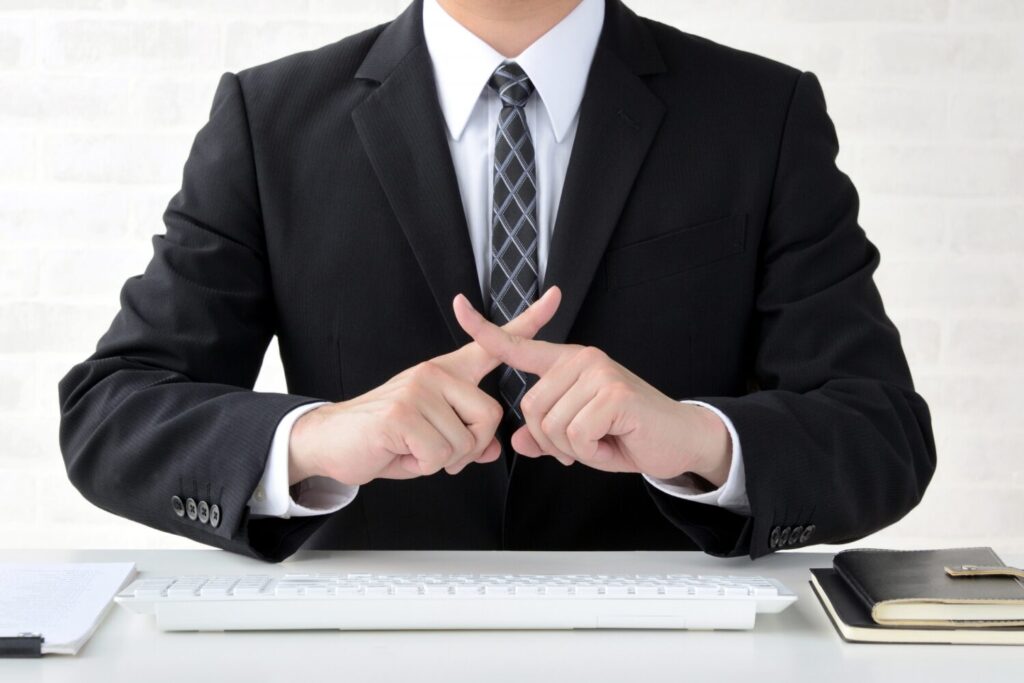
現場の連絡をほとんど全部チャットアプリに流していると、一見スピード感は出ますが、その裏側でひそかに大きなストレスとリスクがたまっていきます。「うちの会社だけかな」と思いがちですが、実はどこでも同じようなパターンにハマっています。まずは、よくある混乱の形を知るところから始めましょう。
グループ乱立で情報迷子
最初は「現場メンバー全員のグループ」と「管理職だけのグループ」くらいだったのが、時間がたつにつれて、現場ごとのグループ、案件ごとのグループ、夜勤メンバーだけのグループ、業者さんとのグループ…と、気づけばグループだらけになっていないでしょうか。
誰かが「とりあえず新しいグループを作りました」と始めるたびに、連絡の入り口が増えていきます。その結果、「あの話ってどのグループで出たんだっけ?」と探し回る時間が増え、肝心の仕事に集中できなくなってしまいます。
また、グループごとにメンバーやルールがバラバラなため、あるグループではスタンプで返事しているのに、別のグループではリアクションすらない、という状態もよく起こります。こうなると、「この連絡はどこに流すのが正解か」「誰に届いている前提で話していいのか」が分からなくなり、何度も同じ説明をすることになります。
グループが増えるほど、情報の「置き場所」があいまいになり、結果的に誰も全体像を把握していない状態が出来上がってしまうのです。
既読=理解・合意と勘違い
チャットアプリには「既読」が付きますが、これはあくまで「開いたかもしれない」というだけで、「内容を理解して、納得している」という意味ではありません。にもかかわらず、忙しい現場ほど「既読が付いているから伝わったはず」と思い込み、「この前言いましたよね?」という会話になりがちです。
相手からすると、移動中にチラッと見ただけで、そのまま別の案件に気を取られていた、ということも多くあります。
さらに、「誰が責任を持って対応するのか」がメッセージから読み取れない場合、全員が自分ごととして受け取らず、誰も動かないまま時間だけが過ぎる、ということもあります。
後から問題になった時に、「ちゃんと共有しました」「いや、そんなつもりで受け取っていない」というすれ違いが発生し、関係性までギスギスしてしまうことも少なくありません。本来は口頭や書面でしっかり確認すべき重要なことまで、ついチャット一発で済ませてしまうと、既読の数だけ見て安心してしまい、実際の理解や合意が置き去りになる危険があります。
写真やファイルが流れて情報の墓場に
現場では、写真や動画で状況を共有することが増えています。破損箇所の写真、設置状況の動画、見積もりに使う図面や資料など、チャットで送ると相手にすぐ届くのでとても便利です。しかし、数日たってから「以前送ったあの写真をもう一度見たい」と思っても、タイムラインを延々とさかのぼらないと見つからない、という経験をしたことはないでしょうか。
特に複数人が頻繁にやりとりしているグループでは、数時間の間に数十件のメッセージが流れ、重要なファイルが簡単に埋もれてしまいます。
また、現場で撮った写真をその場で送って終了、という運用だと、社内のどこにも正式には保存されていない状態になります。担当者のスマホが変わったり、グループから退職者が抜けたりすると、過去の情報にアクセスできなくなってしまうこともあります。
本来は社内の共有フォルダやシステムに整理しておくべき資料が、チャットの中でぐるぐると回っているだけの状態になると、「一度共有したはずなのに、また誰かが取り直して送る」というムダな作業が生まれてしまいます。
禁止より先に目的整理と線引きをする
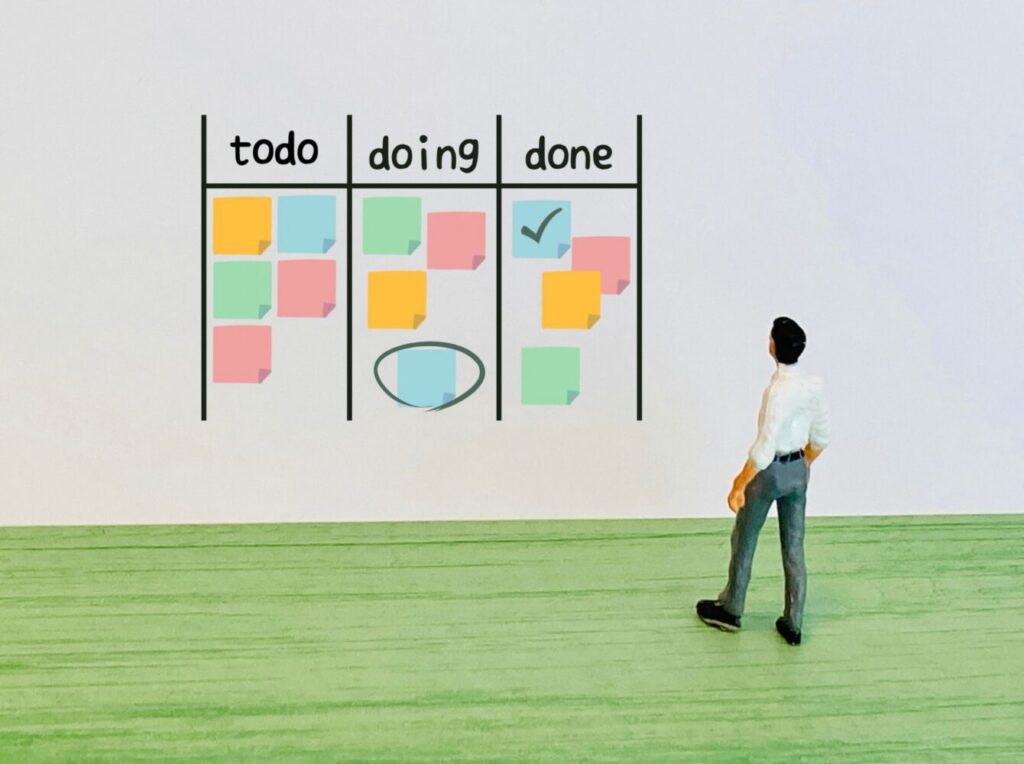
混乱している原因が見えてくると、「やっぱりLINEはやめるべきだ」と極端に振り切りたくなります。しかし、現場メンバーにとっては使い慣れた道具を急に取り上げられる感覚になるため、現実的ではありません。
まずやるべきは、「そもそも現場の連絡にはどんな目的があるのか」を整理し、その中で「この種類の情報はチャットに流さない」と線を引くことです。使い方を見直すだけでも、混乱はかなり減らせます。
現場の連絡を4つの目的に分ける
まず、「現場の連絡」と一口に言っても、中身はバラバラです。緊急のトラブル報告もあれば、日々の作業報告、シフト調整、雑談まで全部同じ場所に流れてくるから混乱します。そこで、連絡の目的をざっくり次のような4つに分けてみましょう。
1. 緊急の連絡(事故・トラブル・急な欠勤など)
2. 定期的な報告(作業日報、進捗報告、申し送りなど)
3. 依頼・指示・確認(やってほしいこと、決めてほしいこと)
4. 相談・雑談(ちょっとした質問やコミュニケーション)
このように分けてみると、「本来は記録として残したいもの」と「その場でやりとりできれば十分なもの」が見えてきます。例えば、日報や申し送り、正式な指示内容は、後で見返す前提の情報なので、チャットよりも別の仕組みで管理した方が安全です。
一方、雑談や軽めの相談は、スピード重視でチャットを使う方がストレスがありません。いきなり難しい表を作る必要はなく、まずは紙に書き出してみるだけでも十分です。
目的ごとに整理した上で、「どの目的の連絡は、どこでやるのがよさそうか」を話し合うことで、なんとなくチャットに全部流していた状態から一歩抜け出すことができます。
チャットに流さない情報を決める
次に、「これはチャットで送らない」と決める情報をはっきりさせておくことが大切です。例えば、顧客の個人情報が多く含まれる内容、正式な契約や料金の決定、社外に出ては困る機密情報などは、誤送信やスマホ紛失のリスクを考えると、チャットに載せるべきではありません。
また、複数の部署にまたがる重要な決定事項も、チャットだけで済ませると、後から「誰がその話を聞いていたのか」があいまいになり、トラブルの元になります。
さらに、「いつまでに、誰が、何をするのか」が明確でない依頼文をチャットに投げると、相手は解釈に迷い、結果として動かないことが多くなります。このような内容は、簡単なフォーマットに沿って別の場所に残し、チャットでは「フォーマットを登録したので確認してください」と案内するだけにした方が、認識のズレを減らせます。
あれもこれも禁止にするのではなく、「少なくともこの種類の情報だけは別のところに残そう」と決めることで、チャットの中身が軽くなり、読み流しても大丈夫な情報が増えるという効果もあります。
ルールは現場と作りシンプルに始める
ルールを決める時にありがちなのが、管理側だけで細かい運用ルールを考えてしまい、現場メンバーにとっては複雑で覚えきれないものになってしまうパターンです。そうなると、「最初の一週間だけ頑張って、気づけば元通り」という結果になりがちです。
ルールづくりのコツは、現場メンバーを巻き込んで、「今どこで困っているのか」「これなら続けられそう、これは無理」という生の声を聞きながら決めることです。
例えば、最初の一歩としては「正式な依頼と決定事項は、このフォーマットにだけ残す」「緊急連絡はこのグループだけに流す」といった、数個のルールから始めるのが現実的です。その上で、1〜2週間使ってみてうまくいかない部分を小さく修正していきます。
完璧なルールを一発で作ることよりも、「試して直すサイクル」をみんなで回すことの方が大切です。こうすることで、ルールが現場に押し付けられるのではなく、自分たちで作った約束事として受け入れられるようになり、定着しやすくなります。
チャットを残して混乱を減らす工夫

目的と線引きがある程度見えてきたら、次は今使っているチャットの運用を整えていきます。ツールそのものを変えなくても、グループの分け方やメンションの使い方、テンプレートの工夫だけで、かなり混乱を減らすことができます。ここでは、明日からでも試せる小さな改善策を紹介します。
グループ整理と目的別の部屋分け
まず取り組みやすいのが、グループの整理です。今あるグループを一覧にして、「このグループって何のためにあるんだっけ?」を一つひとつ確認していきます。その上で、「緊急連絡用」「日々の情報共有」「案件ごとの詳細やりとり」など、目的ごとにグループを整理していきましょう。
不要になっているグループはアーカイブするか、一定期間を決めて使わない方針にしてしまうのも手です。
また、グループごとに管理役を一人決めておき、「この部屋ではこういう話題だけにしましょう」というルールを簡単に書いておくと、空気が引き締まります。例えば、緊急連絡用のグループでは、雑談は一切禁止にして、「日時・現場・状況・初期対応」を短くそろえて書く、と決めておくなどです。
逆に、雑談やちょっとした相談は別のグループで受け止めるようにすると、緊急の情報が埋もれにくくなります。これだけでも、「なんとなく何でも流していた状態」から、「この話はここに書く」という意識が生まれます。
担当を明確にするメンションとリアクション
次に意識したいのが、「誰が動くのか」をはっきりさせる書き方です。全員が入っているグループに「誰か〇〇対応お願いします」と投げると、多くの場合は誰も動きません。「自分じゃない誰かがやるだろう」という心理が働くからです。
そこで、少なくとも一人、できれば第一担当とバックアップ担当の二人に対して名前を添えてメンションし、「〇〇さん、まず確認をお願いします。△△さん、もし難しければフォローお願いします」と書くようにします。
また、対応状況を見えるようにするリアクションのルールを決めておくのも有効です。例えば、「目を通しただけなら了解スタンプ」「対応中なら特定のスタンプ」「完了したら別のスタンプ」という具合に、最低限のルールを決めておくと、誰がどこまで進めているのかが一目で分かります。
こうした仕組みによって、「既読は付いているのに誰も動かない」という、よくあるイライラを減らすことができます。
テンプレと二重記録で重要情報を守る
どれだけ運用を工夫しても、チャットはあくまで会話の場であり、正式な記録としては心もとないところがあります。そこで、「この手の情報だけは、必ず別の場所にも残す」という線を引き、そのためのテンプレートを用意するとよいでしょう。
例えば、日々の作業報告やクレーム対応の記録、設備トラブルの履歴などは、簡単なフォームやシートに項目を決めて記録するようにします。
運用としては、担当者がまずフォームに必要事項を入力し、その内容の要約をチャットに貼り付けて共有する、という流れが現実的です。こうしておけば、チャットで全員に状況を伝えつつ、詳細は別の場所にきちんと残すことができます。
「どこまでやるか」を決めるのが難しい場合は、まずは一つの業務に絞り、「この件だけ二重記録にする」と決めて試してみるのがおすすめです。小さく始めて慣れてくると、「全部チャットに流して終わり」から「残すべき情報はきちんと残す」運用に、無理なく移行していけます。
専用ツールやkintoneへの切り替え方
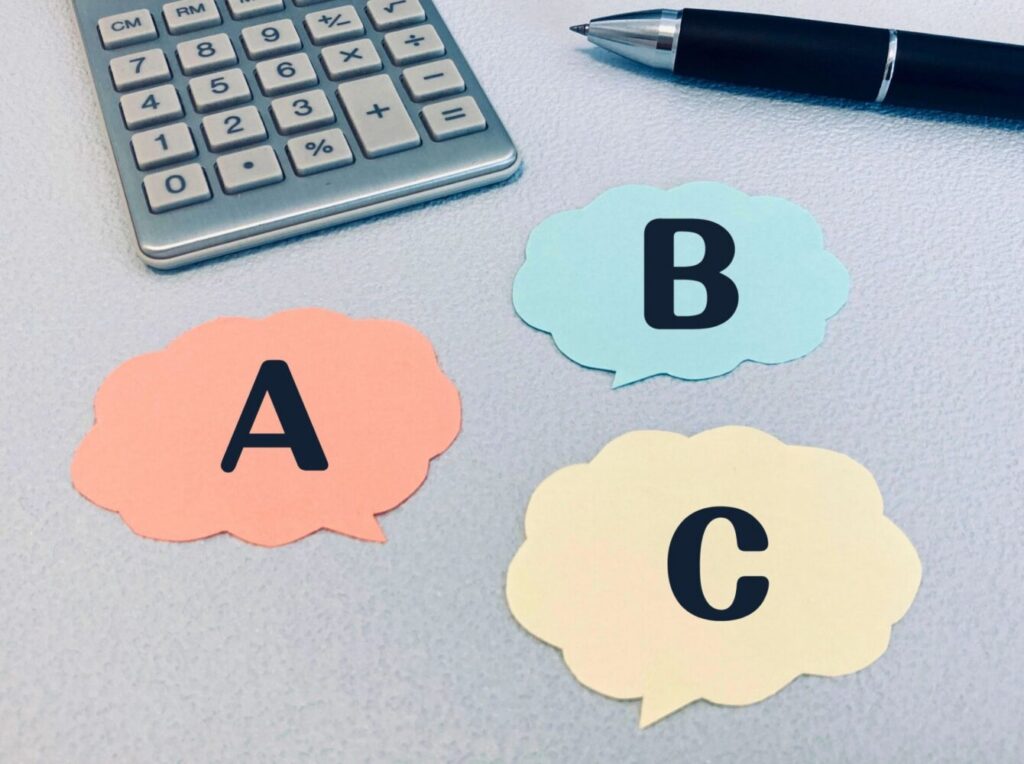
チャットの運用を工夫しても、「そもそも履歴や集計をきちんと残したい」「紙やExcelも混在していて限界」と感じている会社も多いはずです。その場合は、いよいよ専用ツールの出番です。ただし、「有名だから」「価格が安いから」という理由だけで選ぶと、現場に合わずに定着しないこともあります。
この章では、切り替えを検討する時の考え方と、代表的な選択肢の違いを整理します。
チャットツール乗り換え時の注意点
まず検討されやすいのが、LINE以外のビジネスチャットに乗り換えるパターンです。SlackやChatwork、Teamsなどは、業務向けの機能がそろっており、社外との切り分けやセキュリティも考慮されています。
既読の代わりにリアクション機能を使えたり、チャンネルごとにテーマを分けられたりするため、今よりは格段に運用しやすくなります。また、社外との連絡は従来のアプリ、社内のやりとりだけをビジネスチャットにまとめるといった使い方も可能です。
ただし、これらはあくまで「コミュニケーションのためのツール」です。日報・点検記録・クレーム対応履歴など、後から検索して一覧で見たい情報を管理するには向いていません。メッセージの検索機能はありますが、一覧表のように条件を絞ったり、グラフにしたりするのは苦手です。
現場の課題が「今の連絡が見づらい」だけならチャットツールの乗り換えで解決することもありますが、「記録を整理して、集計や分析にも使いたい」というところまで望むのであれば、チャットと別に「情報をためる場所」が必要になってきます。
申し送りや日報はデータベース型が向く
日報や申し送り、作業指示、設備点検などの業務は、「いつ・どこで・誰が・何をしたか」という情報を、長期的に蓄積していくことが重要です。こうした情報管理には、データベース型のツールが向いています。
項目を決めて入力すれば、自動で一覧になり、条件で絞り込んだり、グラフ化したりできるため、「どの現場でトラブルが多いか」「どの時間帯に残業が集中しているか」といった傾向が見えるようになります。
紙やExcelでも近いことはできますが、入力漏れや誤入力が起きやすく、集計のたびに手作業が発生します。一方、データベース型のツールであれば、入力画面と一覧画面が一体になっているため、現場の人も結果を確認しながら使うことができます。
また、スマホからの入力もしやすく、写真の添付なども標準機能で対応できることが多いです。「現場の情報はチャットで共有しつつ、正式な記録はデータベースに残す」という組み合わせは、スピードと正確さの両方を取りに行く現実的な形と言えます。
kintoneで現場連絡を見える化する
データベース型の代表的なサービスの一つがkintoneです。kintoneでは、日報アプリ、クレーム対応アプリ、シフト調整アプリなど、業務ごとにアプリを作り、項目を自由にカスタマイズできます。
各レコード(1件1件のデータ)にはコメント機能があり、そこで担当者同士がやりとりできるため、「チャット」と「記録」が同じ画面で完結します。例えば、設備トラブルがあった時には、トラブルの記録を残すと同時に、そのレコードのコメント欄で原因調査や対応方針を話し合う、といった運用が可能です。
また、一覧画面を絞り込みや並び替えで自由に切り替えられるため、「今日対応が必要な案件」「対応中のトラブルだけ」「クレーム対応が完了したもの」など、知りたい切り口で簡単にリストアップできます。
これにより、チャットだけでは把握しづらかった「全体の状況」が一目で分かるダッシュボードを作ることもできます。使い方次第では、現場の情報がkintoneに集まり、チャットは通知と簡単な相談に絞るという形にしていくこともできます。
伴走ナビの現場連絡改善と内製化支援

ここまで読んで、「うちも何とかしたいけれど、自社だけで設計やツール選定を進めるのは不安」と感じた方も多いと思います。伴走ナビでは、現場のチャット運用に限界を感じている中小企業と一緒に、kintoneなどを使った仕組みづくりを数多く支援してきました。この章では、実際の進め方のイメージをお伝えします。
現状のやりとりを見える化するところから
最初のステップは、とてもシンプルです。今、現場でどのようなやりとりが行われているかを、ありのまま見せていただくところから始めます。具体的には、よく使われているチャットグループのスクリーンショットや、紙の日報、現場で使っているExcelのファイルなどを共有していただきます。
それを一緒に眺めながら、「どのやりとりが重要か」「どこで同じ情報が何度も出てくるか」「抜け漏れが起きると危ないところはどこか」を整理していきます。
この作業を通じて、優先順位がはっきりしてきます。「まずはクレームとトラブル対応の記録から整えよう」「シフト調整が一番混乱しているので、ここから変えよう」といった具合です。いきなり全ての業務に手を付けるのではなく、リスクが高い、もしくは現場のストレスが大きい部分から着手することで、効果を実感しやすくなります。
伴走ナビでは、こうした棚卸しの段階から並走することで、「何から手を付ければいいか分からない」という状態を一緒に解きほぐすことを大切にしています。
小さなアプリを一緒に作り現場で直す
優先度の高いテーマが決まったら、kintone上にシンプルなアプリを作ります。例えば、「トラブル・クレーム記録アプリ」「日報アプリ」「シフト希望入力アプリ」など、現場でよく使う業務に絞ってスタートすることが多いです。
この時点では、完璧な設計を目指すのではなく、「最低限、今より困りごとが減る形」を意識します。項目名や入力方法も、現場の言葉に合わせて調整していきます。
実際に数週間使ってもらいながら、使いにくいところや入力されない項目を洗い出し、その場で画面を直していきます。ここで重要なのは、担当の方にも一緒に画面の修正方法を覚えてもらうことです。
外部に丸投げして作ってもらうのではなく、「どういう考え方で設計し、どうやって直すのか」を共有することで、社内にノウハウが残るDXの内製化につながります。伴走ナビは、このプロセスを「一緒に手を動かす」スタイルで支援しています。
社内で回せる体制づくりと継続サポート
アプリがある程度形になり、現場で問題なく使われるようになったら、次は社内で回せる体制づくりです。例えば、各部署から一人ずつ「業務アプリ担当」を決め、その人たちが集まる場を定期的に設けます。
そこで、「最近こういう要望が出ている」「ここを少し直したらもっと使いやすくなりそう」といった話を出し合い、kintone上のアプリを少しずつ育てていきます。
伴走ナビは、このフェーズでも必要に応じて相談に乗りながら、アプリの改修や新しい業務のアプリ化をサポートします。ただし、あくまで主役は社内の担当者です。外部のベンダーに全部任せてしまうのではなく、自分たちで連絡と情報管理の仕組みをコントロールできる状態を目指します。
これにより、現場の状況が変わっても、それに合わせて仕組みを柔軟に変えていけるようになり、一度作った仕組みがすぐに陳腐化するリスクを減らすことができます。
まとめ:チャットの利便性と仕組み化を両立する
最後に、この記事のポイントを整理します。現場の連絡をチャットだけに依存していると、グループが増え、既読の意味があいまいになり、写真や資料が流れていく「情報の墓場」のような状態になりがちです。
そこでまず大事なのは、
1. 現場の連絡を目的ごとに分ける
2. チャットに流さない情報を決める
3. 少数のルールから現場と一緒に整える
という、運用の見直しから始めることです。
次のステップとして、グループの整理やメンションのルール、テンプレートと二重記録といった工夫を入れることで、今のツールのままでも混乱はかなり減らせます。その上で、「日報や申し送りのように記録を残したい業務」は、kintoneのようなデータベース型のツールに少しずつ移していくと、全体の見通しが格段によくなります。
チャットはあくまで通知と軽い相談の場と位置づけ、重要な情報は仕組みに逃がすのが、現実的で続けやすい形です。
連絡のやり方を変えることは、現場の働き方そのものを見直すことにもつながります。「自社だけでどこから手を付ければよいか分からない」という場合は、まずは身近なメンバーとこの記事を共有し、「自分たちが一番困っているのはどこか」を話すところから始めてみてください。
その上で、より具体的な進め方を知りたい、kintoneの活用イメージを相談したいという時は、伴走ナビの無料相談をご利用いただけます。また、事例や進め方をじっくり検討したい場合には、資料請求で詳しい情報を確認してから社内で検討することも可能です。
チャットの便利さを活かしながら、抜け漏れや混乱を減らす仕組みづくりは、一気に完璧を目指す必要はありません。今日できる小さな一歩から、一緒に現場の連絡を「ちゃんと伝わる形」に整えていきましょう。