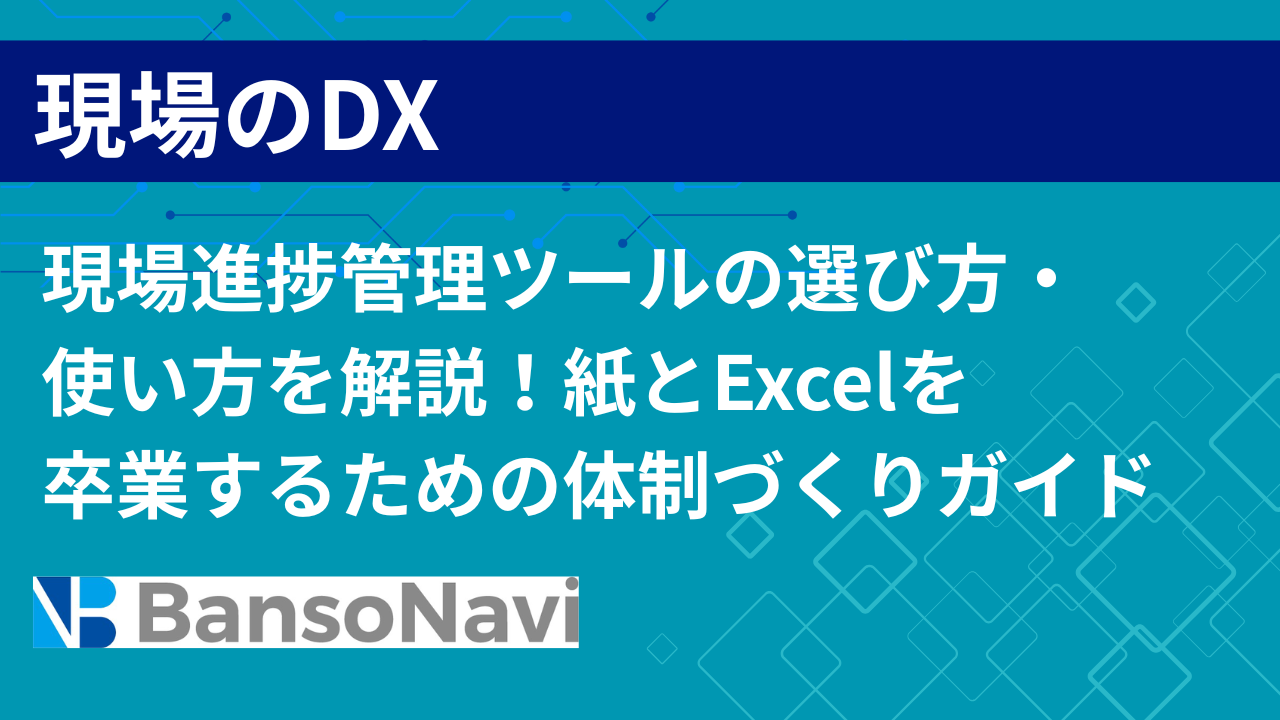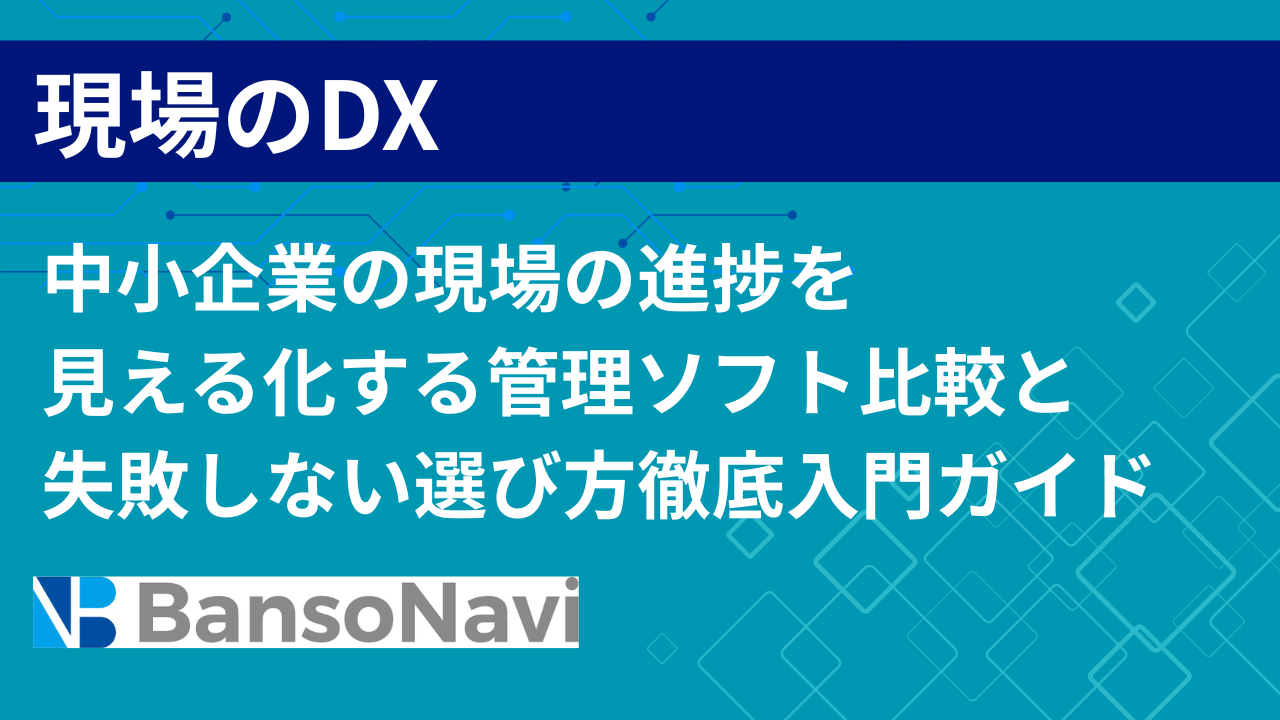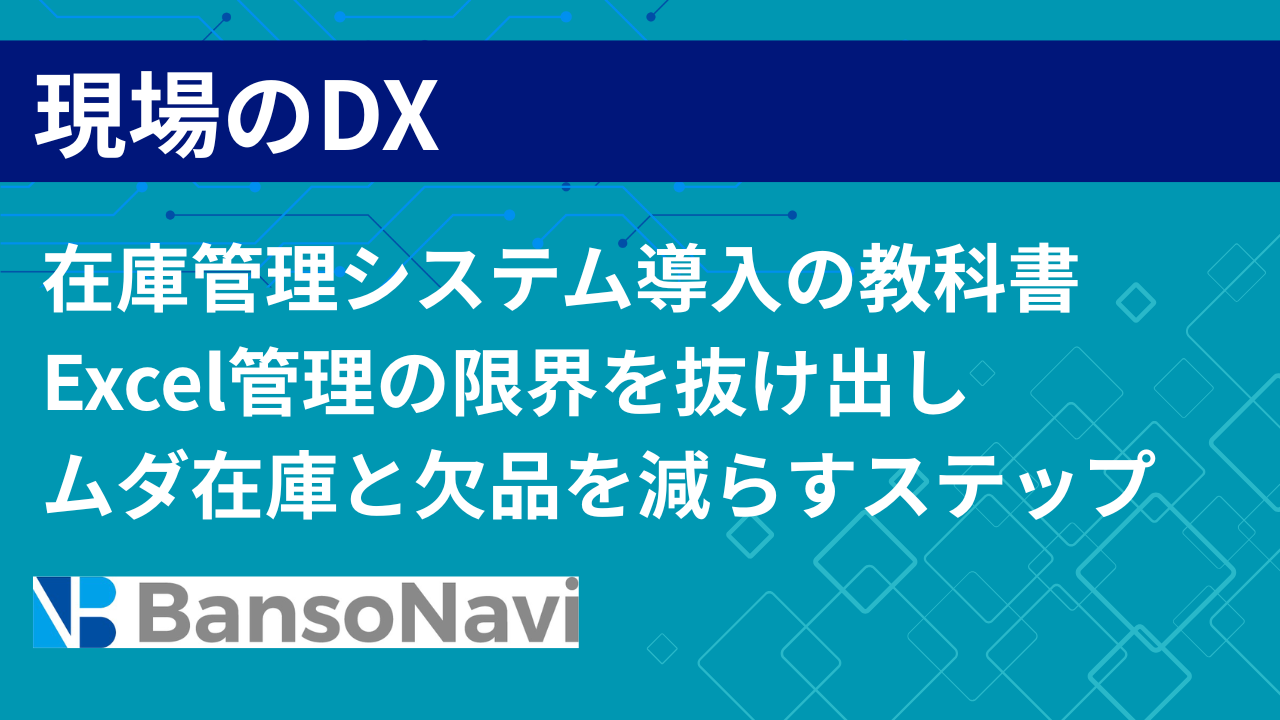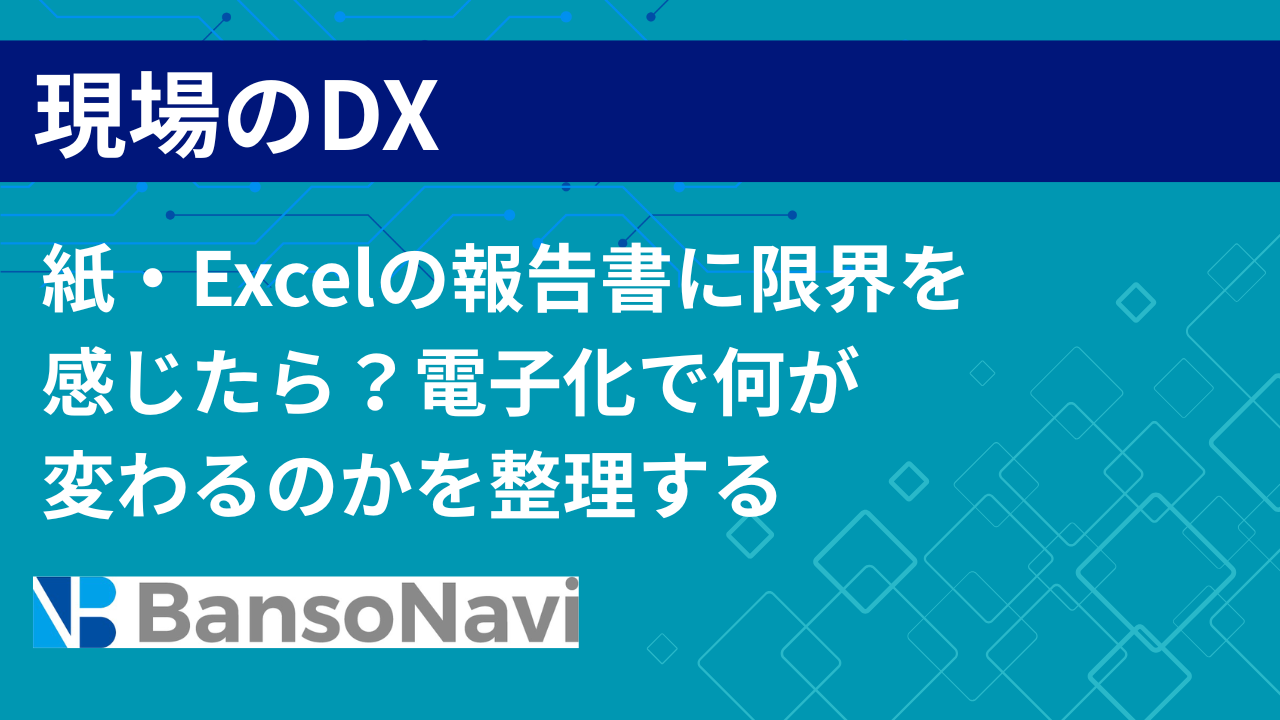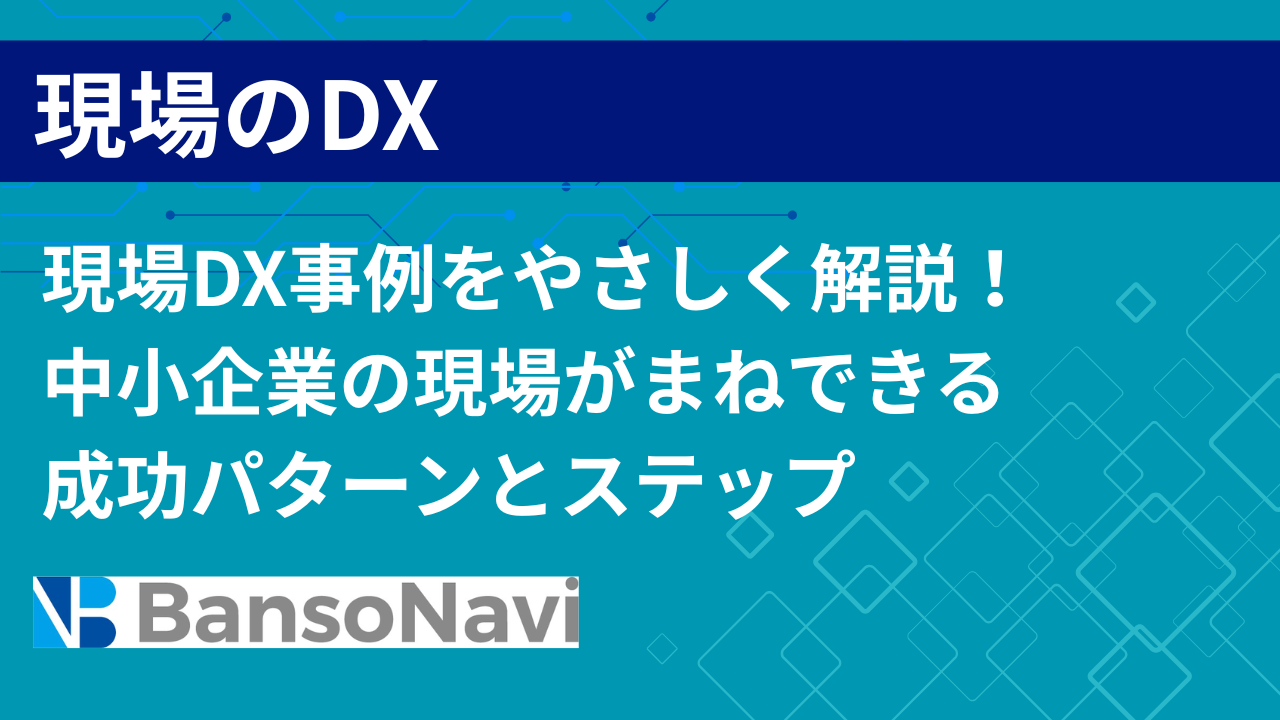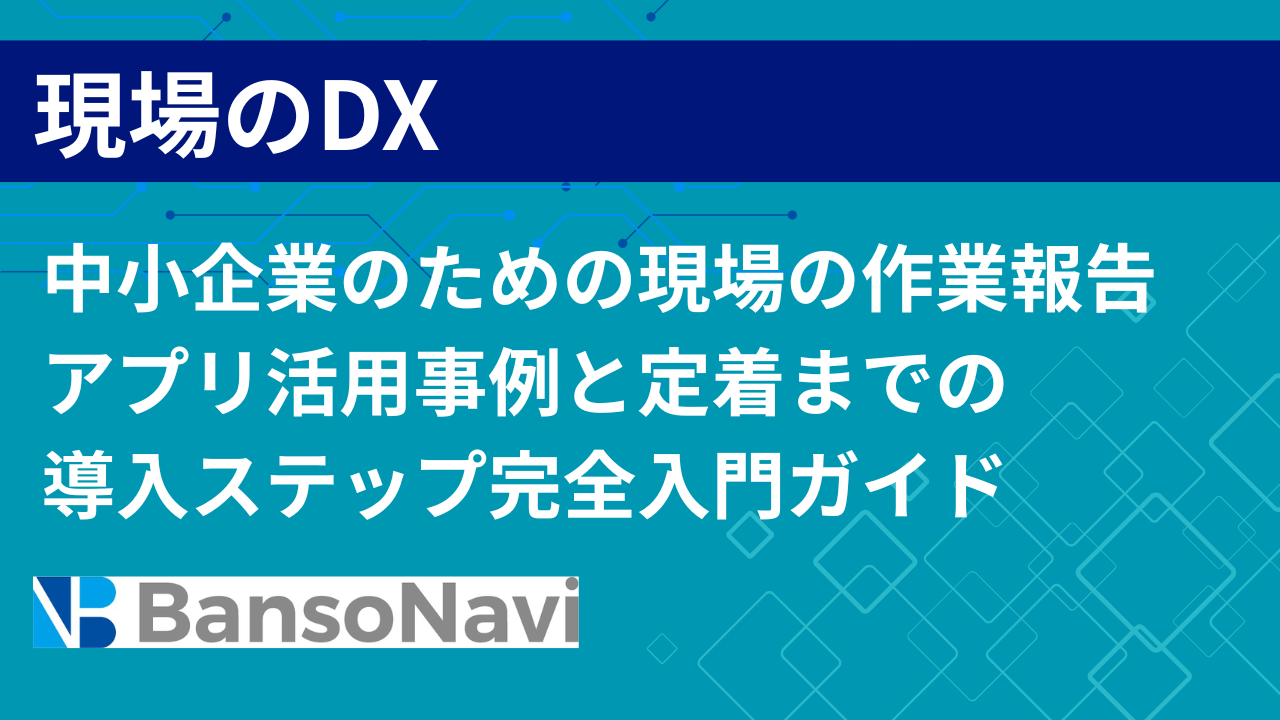シフト表のデジタル管理完全ガイド:紙とExcelから卒業して現場のモヤモヤを減らす実践ステップ
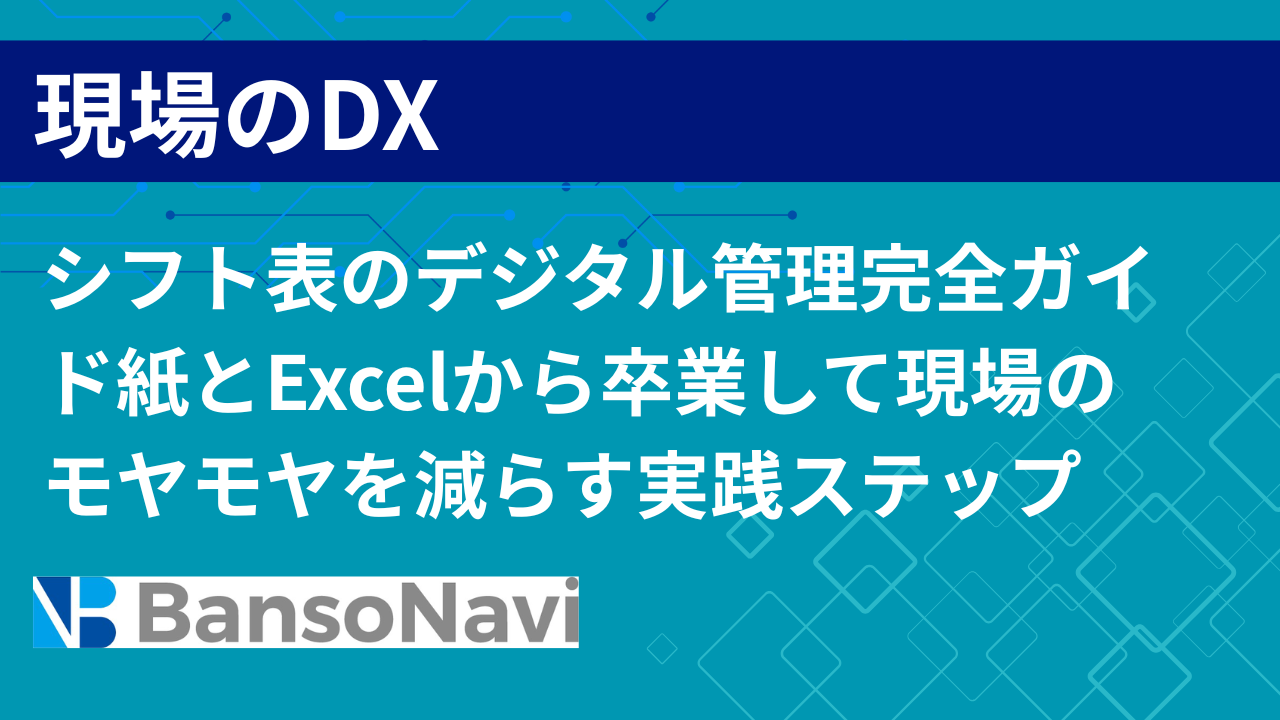
「シフト表が最新なのか分からない」「誰がどの店舗に入っているか一目で見えない」「急な欠勤のたびに電話とLINEで大騒ぎ」。そんなモヤモヤを抱えながら、紙やExcelで何とかシフトを回している会社は少なくありません。
一方で、いざシフト表のデジタル管理を検討しようとしても、どんなツールがあるのか、自社の規模やITリテラシーで本当に使いこなせるのか、費用や導入の手間はどれくらいなのか、失敗しない進め方や、現場に定着させるコツは何か、といったポイントが分からず、検討が止まってしまうケースも多いです。
この記事では、シフト表のデジタル管理について知りたい疑問を、できるだけやさしく、でも実務レベルでしっかり解説します。情報収集段階の方も、具体的にツール比較をしている方も、導入直前で「本当に大丈夫かな」と不安な方も、読み終わる頃には「ここから始めればいいんだな」と一歩踏み出せる状態を目指します。
途中では、伴走ナビが得意とする「kintoneを使ったシフト表のデジタル管理」「DX内製化の支援」にも触れますが、特定ツールのゴリ押しではなく、まずは現場目線の考え方を大事にして進めていきます。
目次
シフト表をデジタル管理する理由

紙のシフト表やExcelでも、正直「今までも何とかなってきた」かもしれません。ただ、人数が増えたり店舗が増えたり、労務管理が厳しくなったりする中で、その「何とか」がどんどん綱渡りになっていくのも事実です。このセクションでは、紙・Excelのシフト管理で起きがちな問題を整理しながら、シフト表をデジタル管理に切り替えると何がラクになるのかを、難しい言葉抜きで確認していきます。
紙・Excelシフト表で起きがちなミス
紙のシフト表やExcelは、最初のうちは一番手軽で始めやすい方法です。ただし、人数やパターンが増えてくると、途端に管理が苦しくなってきます。例えば、印刷したシフト表を掲示板に貼っている場合、「最新版がどれか分からない」「書き込みの修正が重なって読めない」といった問題がよく起きます。Excelの場合は、ファイルが複数コピーされてしまい「どのファイルが正なのか」分からなくなることも珍しくありません。
また、シフト希望の回収も大きな負担になります。紙の申請書を集めて手入力したり、LINEやメールでバラバラに届いた希望を見ながらExcelに打ち込んだりと、「作業そのものは単純なのに時間だけはかかる」状態になりがちです。この単純作業が増えるほど、入力ミスやダブルブッキング、休憩時間の入れ忘れ、労働時間のカウント漏れなど、ヒューマンエラーのリスクも高まります。
さらに、急な欠勤や代打の調整が発生すると、紙やExcelでは一気に混乱しやすくなります。誰がどの時間帯に空いているのか、他店舗の応援が可能か、シフト変更後の総労働時間がどう変わるか、といった情報が一目で見えないため、そのたびに「電話・チャット・Excel」を行き来して調べる必要が出てきます。その結果、本来やりたい売り場づくりやスタッフ育成の時間が、シフト調整に削られてしまうのです。
シフト表をデジタル管理すると何がラクか
シフト表をデジタル管理に切り替える最大のメリットは、「最新のシフト情報が、関係者全員に同じ形で届く」という点です。クラウド上でシフトを管理すれば、店長が変更を保存した瞬間に、スタッフや本部にも最新状態が共有されます。掲示板に貼り替える必要もなく、「古い紙を見て出勤してしまう」といったトラブルも防げます。
また、スタッフがスマホやパソコンから直接シフト希望を入力できるようにすると、店長の手入力作業を大幅に減らせます。中には、希望シフトの締め切りを過ぎたら自動でアラートを出したり、未提出者だけにリマインドを送ったりできる仕組みもあります。こうした仕組みがあると、店長は「催促係」から解放され、シフトのバランスを考えることに集中しやすくなります。
さらに、デジタル管理では、労働時間や残業時間を自動で集計できるケースも多く、エクセルで関数を組むよりも楽になります。週や月の労働時間の上限を超えそうなスタッフがいれば、事前に気づいて調整できるため、法令違反や働き過ぎのリスクも減らせます。結果として、「気づいたら労働時間がオーバーしていた」「残業代の計算で手戻りが発生した」といったヒヤリハットを減らすことができます。
「とりあえず無料アプリ」で失敗しがちなパターン
一方で、「シフト表のデジタル管理が良いのは分かったから、とりあえず無料アプリを入れてみた」という始め方で、かえって失敗してしまうケースも少なくありません。代表的なのは、「最初は店長だけが頑張って使っているが、スタッフが付いてこない」というパターンです。スタッフのスマホにアプリを入れてもらえず、結局紙の掲示板との二重運用になってしまい、店長の負担だけが増える状態になってしまいます。
また、無料プランでは利用人数や機能に制限があり、「店舗が増えたら急に有料にしないといけない」「欲しい機能だけが有料プランに入っていて、想定より高くつく」といったこともよくあります。最初に「どこまでをデジタル化したいのか」「今後店舗やスタッフが増える可能性はあるのか」といった点を整理せずに選んでしまうと、数カ月後にツール選びをやり直さざるを得なくなるのです。
さらに、既存の勤怠システムや給与計算との連携を考えず、「シフトだけ単体で便利そうだから」という理由で選んでしまうと、結局どこかで手入力が残り、思ったほど効率化されないケースもあります。シフト表のデジタル管理を成功させるには、「ただアプリを入れる」だけではなく、「自社の運用に合うか」「将来の拡張にも耐えられるか」を、最初の段階で考えておくことが大事です。
シフト表のデジタル管理で実現したいことを整理する

次に大切なのは、「ツール選びの前に目的をはっきりさせる」ことです。どんなに高機能なシステムでも、現場の困りごととズレていたら使われません。このセクションでは、店長・スタッフ・本部といった立場ごとに課題を洗い出し、シフト表のデジタル管理で何を解決したいのかを整理する方法を解説します。
現場の困りごとを言語化する
シフト表のデジタル管理を検討するとき、多くの会社がいきなり「どのツールが良いか」という話から始めてしまいます。しかし、最初にやるべきは「誰が、どんな場面で困っているのか」を整理することです。
例えば店長は、「シフト希望の取りまとめに時間がかかる」「急な欠勤の調整で休日でも連絡が止まらない」といった負担を感じているかもしれません。一方でスタッフは、「自分のシフトが直前まで確定しない」「希望を出しても反映されたか分からない」といった不安を抱えていることが多いです。
本部側の視点では、「店舗ごとの人件費をタイムリーに把握できない」「残業時間や法令順守の状況を一元管理できない」といった課題もよく挙がります。こうした立場ごとの課題を、簡単なヒアリングシートや打ち合わせを通じて集めていきます。最初から完璧に整理しようとする必要はありませんが、「誰のためのシフト表デジタル化なのか」「どの課題を優先して解決したいのか」が見えてくるだけでも、ツール選定の軸がぐっと明確になります。
これらの課題をホワイトボードやオンラインメモに書き出し、「頻度が高いもの」「インパクトが大きいもの」「法令や会社方針に関わるもの」といった観点で優先順位を付けていきます。そうすると、「まずは希望シフトの回収と集計をラクにするところから」「複数店舗のシフト状況を本部で見える化するところから」といった、現実的な第一歩が見えやすくなります。
シフト表のデジタル管理でおさえたい機能
次に、「どこまでできると便利か」をざっくり整理しておきましょう。シフト表のデジタル管理ツールには様々な機能がありますが、最低限おさえておきたい観点としては、例えば次のようなものがあります。
- スタッフの希望シフトをオンラインで申請できる
- 店長がドラッグ&ドロップなどでシフトを組みやすい
- 作成したシフトをスタッフにすぐ共有できる(スマホアプリやWebページなど)
- シフト変更があったときに自動で通知できる
- 週・月単位の労働時間や人件費を集計しやすい
これらを全部、完璧に満たしていなくても構いませんが、「今の紙やExcelで一番しんどいところはどこか」「そこをどの機能でラクにしたいのか」を意識しておくことが大切です。特に、スタッフ側からの見やすさ・操作のしやすさは、定着に直結します。画面の文字が小さすぎたり、ログインがやたらと面倒だったりすると、それだけで利用率が下がってしまいます。
また、勤怠打刻や給与計算と連携したい場合は、「シフト情報を他システムに渡せるかどうか」も事前に確認しておく必要があります。CSVでの出力・取り込みができるだけでも、手入力の手間を大きく減らせます。将来的にどこまで連携していきたいかをイメージしながら、「今必要な機能」と「今後あると嬉しい機能」を分けて整理しておくと、ツール比較の際に迷いにくくなります。
情報収集で確認したいチェックポイント
目的と必要な機能がざっくり見えたら、いよいよ情報収集です。このときに大切なのが、「料金表だけで判断しない」ことです。もちろん費用は大事ですが、安く見えてもサポートが弱かったり、設定が難しかったりすると、結局現場に浸透せず、投資対効果が下がってしまいます。特にITに詳しくない現場では、「設定やトラブル対応を誰がやるのか」を具体的にイメージしておくことが重要です。
情報収集の際には、次のようなポイントをチェックしておきましょう。
- 料金体系(ユーザー単位か、店舗単位か、機能ごとなのか)
- 初期設定やデータ移行のサポートがあるか
- マニュアルやヘルプが分かりやすいか、日本語で充実しているか
- 無料トライアル期間や、少人数でお試し利用できるプランがあるか
- 自社が使っている他システムとの連携実績があるか
また、「自社と似た規模・業種の導入事例」があるかどうかも、かなり重要な判断材料になります。同じ小売業でも、単独店舗と複数店舗チェーンではシフト管理の難易度が違いますし、介護や医療のように資格やスキルによって配置基準が厳しい業界では、必要な機能も変わってきます。「うちに近い会社がどのように使っているのか」を確認することで、よりイメージを具体的にしやすくなります。
シフト表デジタル管理ツールの種類と選び方

ここからは、「どんな選択肢があるのか」を整理していきます。一口にシフト表のデジタル管理と言っても、シフト専用のクラウドサービスもあれば、Excelやスプレッドシートの拡張利用、kintoneのような業務アプリプラットフォームを使う方法もあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、「自社の規模・予算・ITリテラシーに合うものはどれか」という視点で見ていくことが大切です。
シフト表専用クラウドの特徴と向く会社・業種
シフト表のデジタル管理の代表的な選択肢が、「シフト専用クラウドサービス」です。これは、飲食・小売・介護など、シフト勤務が多い業界に特化して設計されたツールで、「希望シフトの回収」「自動シフト作成」「LINE連携」「勤怠システムとの連携」など、現場で欲しい機能がそろっていることが多いのが特徴です。画面もシフト管理に特化しているため、直感的に操作しやすいというメリットがあります。
一方で、専用クラウドサービスは「用意された機能の範囲で使う」前提になるため、自社独自のルールや運用を細かく反映しづらい場合があります。例えば、「この店舗だけ特殊な勤務区分がある」「この部署だけシフト決定プロセスが違う」といったケースでは、運用をツールに合わせるか、別の方法で補う必要が出てくることがあります。また、業務がシフト管理だけで完結していれば問題ありませんが、他の業務(店舗日報や在庫管理など)との連携は、別途検討が必要です。
シフト専用クラウドサービスは、次のような会社・現場に特に向いています。
- シフト勤務スタッフの人数が多く、店長がシフト作成に追われている
- 業種として、飲食・小売・介護・医療・コールセンターなど、シフト管理が業務の中心になっている
- 既に勤怠システムや給与計算システムがあり、それと連携できるシフト管理だけを導入したい
「まずはシフト管理だけを早くラクにしたい」「ある程度、業界標準のやり方に合わせても構わない」という場合には、専用クラウドサービスは有力な選択肢になります。
Excel・スプレッドシートで始めるデジタル管理のポイント
ExcelやGoogleスプレッドシートでシフト表を管理する方法は、「一番身近でコストも安い」選択肢です。既にExcelでシフト表を作っている場合は、そのファイルをOneDriveやGoogleドライブに置き、共有設定を整えるだけでも、最初の一歩としては立派なデジタル管理と言えます。クラウドストレージを使えば、「最新版がどれか分からない」という問題も減らせますし、基本的な関数を使えば労働時間の集計もある程度自動化できます。
ただし、Excel・スプレッドシートには限界もあります。まず、入力ルールや権限設定をしっかり決めておかないと、思わぬところを上書きされたり、数式を消されてしまったりするリスクがあります。また、スタッフが自分で希望シフトを入力する運用にするとき、編集可能な範囲を細かく制御するのは意外と難しく、「他の人のセルを触ってしまった」「行を削除してしまった」といったトラブルが起きることもあります。
さらに、Excel・スプレッドシートは「シフト表専用の画面」ではないため、スマホからの見やすさや操作性で専用サービスに劣ることが多いです。ピンチアウトして拡大しないと文字が読めない、スクロールがしづらいなど、日常的に使うにはややストレスになる場面もあります。「まずはコストをかけずにシフトをデジタル管理する」には良い選択肢ですが、店舗数やスタッフ数が増えてきた段階で、「そろそろ専用ツールか業務アプリに移行したい」という状況になることが多いのも事実です。
kintoneなど業務アプリで内製するシフト表管理
もう一つの選択肢が、kintoneのような業務アプリプラットフォームを使って、「自社専用のシフト表管理アプリ」を作る方法です。これは、最初からシフト専用に作られたサービスではなく、「業務アプリを組み立てるための土台」を使って、シフト管理の仕組みを組み上げるイメージです。ノーコード・ローコードで画面や項目を自由に設計できるため、会社ごとのルールや運用を細かく反映しやすいのが大きなメリットです。
例えば、「資格保持者が必ず何人以上いるようにアラートを出したい」「この時間帯だけ時給を自動で変えたい」「店舗日報や勤怠情報と一緒にダッシュボードにまとめたい」といった要望も、kintoneのアプリ同士を連携させることで実現しやすくなります。また、シフト表のデジタル管理だけにとどまらず、在庫管理、問い合わせ管理、稟議申請など、他の業務アプリも同じ基盤の上で増やしていけるため、「DX内製化の足場」としても役立ちます。
一方で、業務アプリプラットフォームを使う場合は、ある程度の設計・開発スキルが必要になります。とはいえ、ゼロからシステムを作るほどの専門知識は要らず、「エクセルで関数や簡単なマクロを組めるレベル」の人が社内にいれば、外部のパートナーと一緒に内製化していくことも十分可能です。伴走ナビでは、まさにこの「kintoneを使ったシフト管理アプリの設計・内製化支援」を数多く行っており、現場の声を聞きながら、運用に乗るところまで伴走する形を取っています。
現場に定着するシフト表デジタル管理ステップ

どんなに良いツールを選んでも、「現場に定着しない」「最初だけ使って終わり」では意味がありません。このセクションでは、シフト表のデジタル管理を実際に導入し、紙やExcelからスムーズに移行していくためのステップを解説します。ポイントは、いきなり全部を変えようとせず、小さく始めて徐々に範囲を広げていくことです。
紙とデジタルを並走させるスモールスタートのコツ
シフト表のデジタル管理への移行で失敗しがちなのが、「来月から紙は禁止。全部新システムでお願いします」という大胆な切り替え方です。現場からすると、慣れていないツールだけに頼ることになるため不安が大きく、「結局紙も併用しよう」という動きが出てしまい、二重管理で混乱することになりがちです。そこでおすすめなのが、「一定期間は紙とデジタルを並走させる」というアプローチです。
例えば、最初の1〜2カ月は、「シフト希望の提出だけデジタル化し、最終の確定シフトは紙で掲示する」という形から始める方法があります。スタッフはスマホから希望を入力することに慣れ、店長は希望の集計がラクになりますが、最終的な確認は従来通り紙で行えるため、不安を抑えやすいのがポイントです。その期間に、操作方法でつまずきやすいポイントや、ルールの抜け漏れを洗い出しておくと、本格移行の際のトラブルを減らせます。
また、「最初は一つの店舗だけで試す」「ITに強いメンバーが多い部署から始める」といった段階的な導入も有効です。パイロット導入を通じて、社内向けの簡単なマニュアルやよくある質問集を作っておくと、他店舗へ展開するときの説明コストを大きく下げられます。小さく始めて成功体験を作り、その事例をもとに社内説明をしていくことで、「よく分からないけどとりあえず反対しておこう」という心理的な抵抗も和らげやすくなります。
権限・入力ルール・通知設定を整え「誰でも使える」状態にする
シフト表のデジタル管理がうまくいくかどうかは、「ツールそのものの良し悪し」よりも、「ルールの設計」と「役割分担」がしっかりしているかに大きく左右されます。紙やExcelの運用では、何となくの空気感で回っていた部分もありますが、デジタルではそれをきちんと言語化する必要があります。ここを面倒がってしまうと、「人によって使い方がバラバラ」「いつの間にか誰も入力しなくなる」といった状態になりやすいので注意が必要です。
まず押さえておきたいのが、権限の設計です。例えば、次のような役割をざっくり決めておくイメージです。
- 全体設定を触れる管理者(本部や店長クラス)
- シフトを作成・調整できる人(店長・副店長・リーダーなど)
- 自分の希望や調整内容だけ入力できる人(一般スタッフ)
「誰がどこまで触れるのか」があいまいだと、「知らないうちに重要な項目が変えられていた」「権限が足りずに調整が止まる」といったトラブルにつながります。可能であれば、最初の段階で画面を一緒に見ながら、「ここは店長だけが変えられるようにしよう」「ここはスタッフも入力していい領域にしよう」と具体的に決めていきましょう。
次に大事なのが入力ルールです。
- 名前はフルネームか、苗字のみか
- 休暇区分や勤務パターンの表記をどう統一するか
- 締め切り時刻や、希望が通らなかったときの扱いをどうするか
こういった細かいルールを先に決めておくことで、「人によって書き方が違う」「誰かのクセに引っ張られる」といったムラを減らせます。ルールは難しくしすぎず、短いドキュメントや紙一枚にまとめておき、スタッフがいつでも見返せるようにしておくと安心です。
最後に、通知設定も重要なポイントです。希望シフトの締め切り、シフト確定のお知らせ、変更があったときの通知など、「どのタイミングで、誰に、どのチャネルで通知するか」をあらかじめ決めておきます。通知が多すぎると「また来たか」と無視されやすくなり、少なすぎると「気づかなかった」という言い訳の温床になってしまいます。最初は少なめに設定し、実際の運用を見ながら必要な通知を足していくくらいのスタンスがちょうど良いことも多いです。
形骸化させない振り返り方法と改善サイクル
シフト表のデジタル管理は、導入した瞬間がゴールではなく、そこからがスタートです。最初の数カ月は特に、「運用してみて初めて見えてくる課題」が次々と出てきます。例えば、「希望の締め切りが早すぎて現場の予定が読めない」「通知のタイミングが遅くて調整がバタバタする」「本部が知りたい数字がレポートに含まれていない」など、実際に回してみないと分からないポイントがたくさん出てきます。
ここで大事なのは、不満やトラブルが出たときに「ツールが悪い」で終わらせないことです。もちろん、どうしてもツール側の限界という場合もありますが、多くの場合は「ルールや画面の設計を少し変えれば解決できる」ことが多いです。そこで、導入後しばらくは、月に一度くらいのペースで簡単な振り返りの場を持つことをおすすめします。店長やリーダー、場合によっては代表的なスタッフにも参加してもらい、次のような観点で意見をもらっていきます。
- 使ってみて「楽になったこと」「まだ困っていること」は何か
- 紙やExcelのときと比べて、「時間が減った作業」「逆に増えてしまった作業」は何か
- 入力ミスや認識違いが起きやすいのはどの場面か
これらを整理したうえで、「やめること」「変えること」「新しく決めること」に分けて小さく改善していきます。一度に多くのルールを変えようとすると現場がついてこないので、改善内容は毎月一つか二つに絞り、「どこがどう変わるか」を分かりやすく共有することがポイントです。
また、シフト表のデジタル管理の効果を感じやすくするために、あらかじめ簡単な指標を決めておくのも有効です。例えば、「シフト作成にかかる時間(店長の作業時間)」「希望シフトの提出率」「直前のシフト変更件数」などを、導入前後でざっくり比較してみるだけでも、変化が見えやすくなります。目に見える成果が数字で分かると、現場のモチベーションも上がり、改善サイクルが回りやすくなります。
伴走ナビが支援できること

ここまで読んで、「自社なりのやり方を反映しシフト表のデジタル管理をしたいが、どこから手をつければいいか分からない」「ツール選びだけで疲れてしまって、設計や運用のイメージが湧かない」という方も多いと思います。伴走ナビでは、そうした企業の方と一緒に、kintoneをベースにしたシフト管理アプリを設計し、内製化の体制づくりまで支援してきました。
kintoneベースのシフト表デジタル管理アプリのイメージ
kintoneを使うと、自社のルールに合わせたシフト表のデジタル管理アプリを、ノーコード・ローコードで組み立てることができます。例えば、次のような画面・機能構成が考えられます。
- スタッフごとの希望シフト入力フォーム(スマホから入力可能)
- 店長用のシフト作成画面(ドラッグ&ドロップや絞り込みで調整しやすいビュー)
- 店舗別・部署別のシフト一覧と、労働時間集計のダッシュボード
- 残業時間や連続勤務など、ルールを超えそうな場合のアラート表示
これらを、既存の勤怠管理や日報、売上データなどと同じkintone環境の中で連携させることで、「シフト」「実績」「数字」をひと目で追いかけられるようになります。例えば、「人件費率が高くなっている店舗は、シフトの組み方にどんな傾向があるか」といった分析も、少し設定を加えるだけで見えてくるようになります。
また、シフト表のデジタル管理からスタートしつつ、後から「有給申請アプリ」「店舗問い合わせ管理アプリ」などを同じ基盤の上に追加していくこともできます。一度kintoneで基盤を整えておくと、シフト以外の業務改善にも横展開しやすいのが大きなポイントです。
伴走型サポートとDX内製化の進め方
伴走ナビが大事にしているのは、「作って納品して終わり」ではなく、社内で回せるようになるまで一緒に走ることです。最初は、要件整理やアプリ設計、初期構築といった部分をこちらでリードしながら、徐々に社内のご担当者が自分で修正・追加できるようになることを目指します。
例えば、シフト表をデジタル管理するプロジェクトでは、次のような進め方を取ることが多いです。
1.現場ヒアリングと課題整理:店長・スタッフ・本部からそれぞれ困りごとを洗い出す
2.アプリ設計と試作:最初のシフト管理アプリを作り、テスト運用でフィードバックを得る
3.ルール整備とマニュアル作成:権限や運用ルールをまとめ、社内で共有できる形にする
4.社内トレーニング:ご担当者向けに、kintoneの基本操作やアプリ改修方法をレクチャーする
こうしたプロセスを通じて、社内に「少し手を加えれば自分たちで変えていける」という感覚を持ってもらうことを重視しています。結果として、シフト表デジタル管理の改善サイクルを自分たちで回せるようになり、他の業務アプリの内製化にもつなげやすくなります。
社内説明・稟議に使える資料と相談窓口
シフト表のデジタル管理するための導入検討では、「現場としては必要だと感じているが、経営層や本部を説得するのが大変」という声もよく聞きます。特に、システムの費用や運用負荷について、納得感のある説明が求められるケースが多いです。伴走ナビでは、そうした社内説明・稟議の場面で使えるように、次のような内容をまとめるお手伝いも行っています。
- 現状の課題と影響(時間ロス・ミス・機会損失)の整理
- シフト表のデジタル管理によって期待できる効果の整理
- kintone活用による中長期的なDX内製化のメリット
「自社の状況だとどこから話を組み立てればいいか」「どのくらいの費用感で考えるべきか」といった点も含めて、まずは伴走ナビの無料相談をご活用いただけます。また、「社内で検討するための材料が欲しい」「他社の導入例や、kintoneを使ったシフト管理のイメージをもう少し詳しく知りたい」という場合は、より詳しい情報をまとめた資料請求もご利用いただけます。
まとめ|シフト表のデジタル管理で現場のモヤモヤを減らす次の一手
ここまで、シフト表をデジタル管理する必要性から、ツールの種類、現場で定着させるコツ、そして伴走ナビが支援できることまで整理してきました。情報量は多かったかもしれませんが、根っこにあるポイントはシンプルです。「自社の現場がどこで困っていて、何を楽にしたいのかをはっきりさせる」「それに合ったやり方で、小さく始めて少しずつ広げる」という二つに尽きます。
最後に、この記事を読み終えたあとに「明日からできるアクション」を三つだけ挙げておきます。
1.現場の店長やスタッフと一緒に、「シフト作成・調整で一番しんどいところはどこか」を紙一枚に書き出してみる
2.紙やExcelの運用のうち、「まずはここだけデジタルにしたい」という範囲を決めてみる(例:希望シフトの回収だけ)
3.シフト表をデジタル管理するツール候補や、kintoneを使ったシフト管理の事例を、社内で共有するために簡単にまとめてみる
そして、「自分たちだけで検討を進めるのは少し不安だな」「うちの規模や業種だとどう考えるべきか、第三者の目線も欲しいな」と感じたら、ぜひ一度、伴走ナビの無料相談にお声がけください。現場のヒアリングから要件整理、ツール選定の検討材料の整理まで、一緒に伴走しながら考えていきます。
もう少し落ち着いて社内で検討したい方は、kintoneを活用したシフト表のデジタル管理や、DX内製化の進め方をまとめた資料請求をご利用いただければ、社内共有や稟議にも使いやすい形で情報を整理していただけるはずです。
シフト表のデジタル管理は、「難しいITプロジェクト」ではなく、現場のモヤモヤを一つずつ減らしていくための取り組みです。この記事が、紙とExcelから一歩踏み出すきっかけになれば嬉しいです。