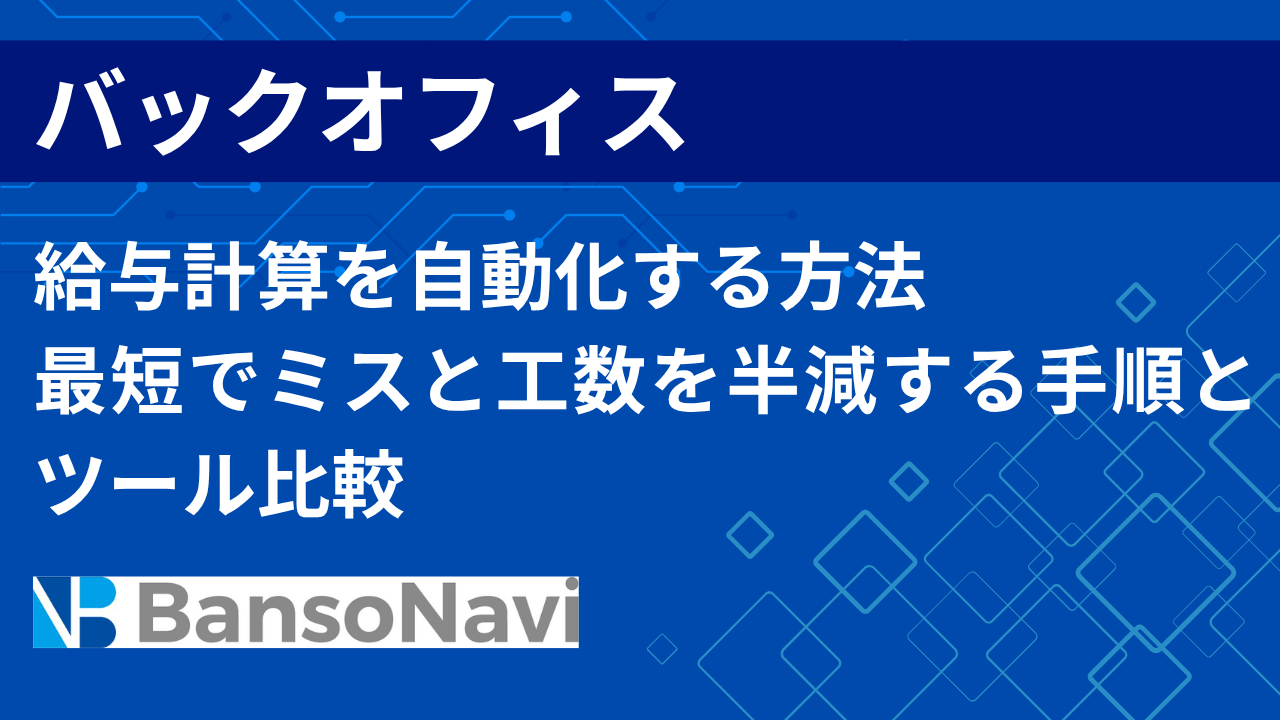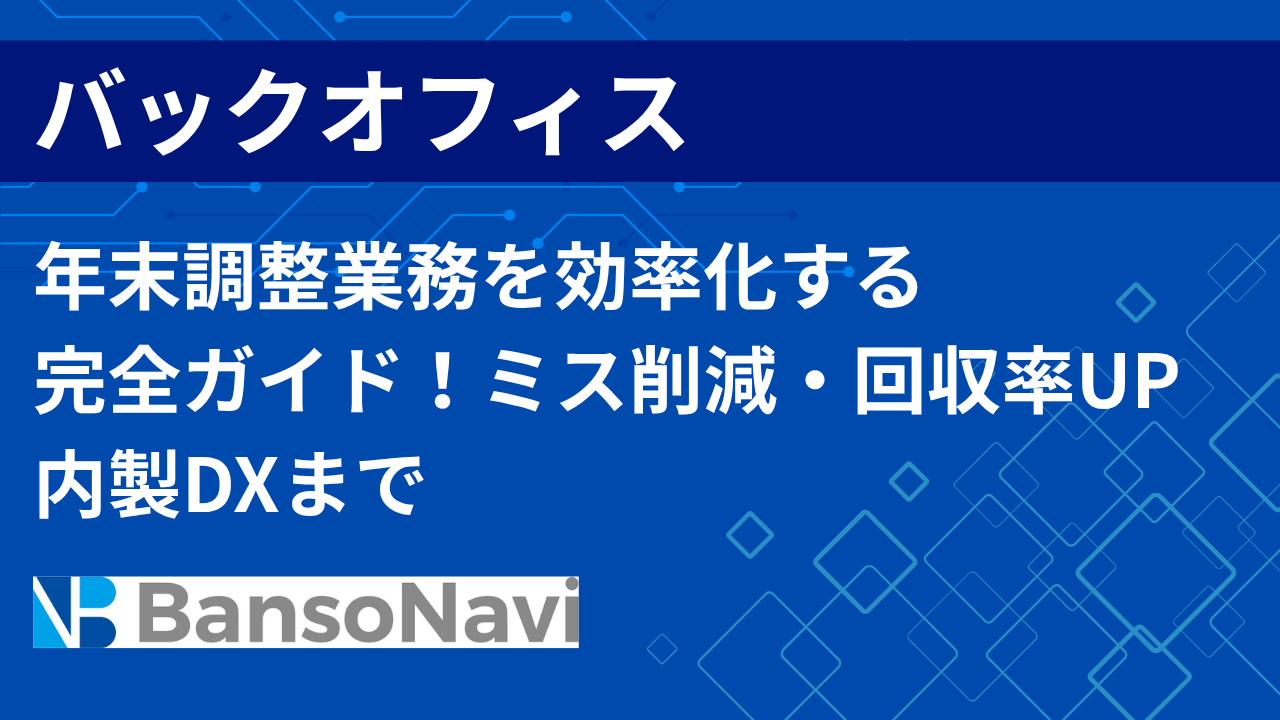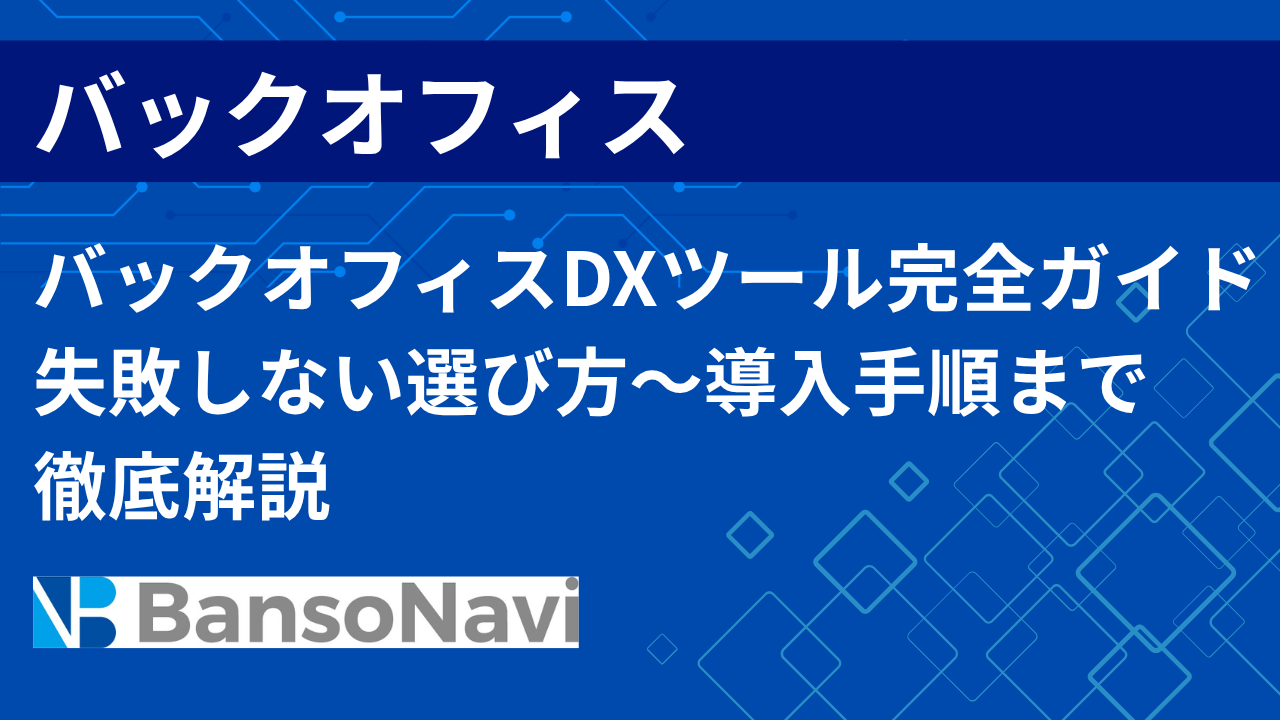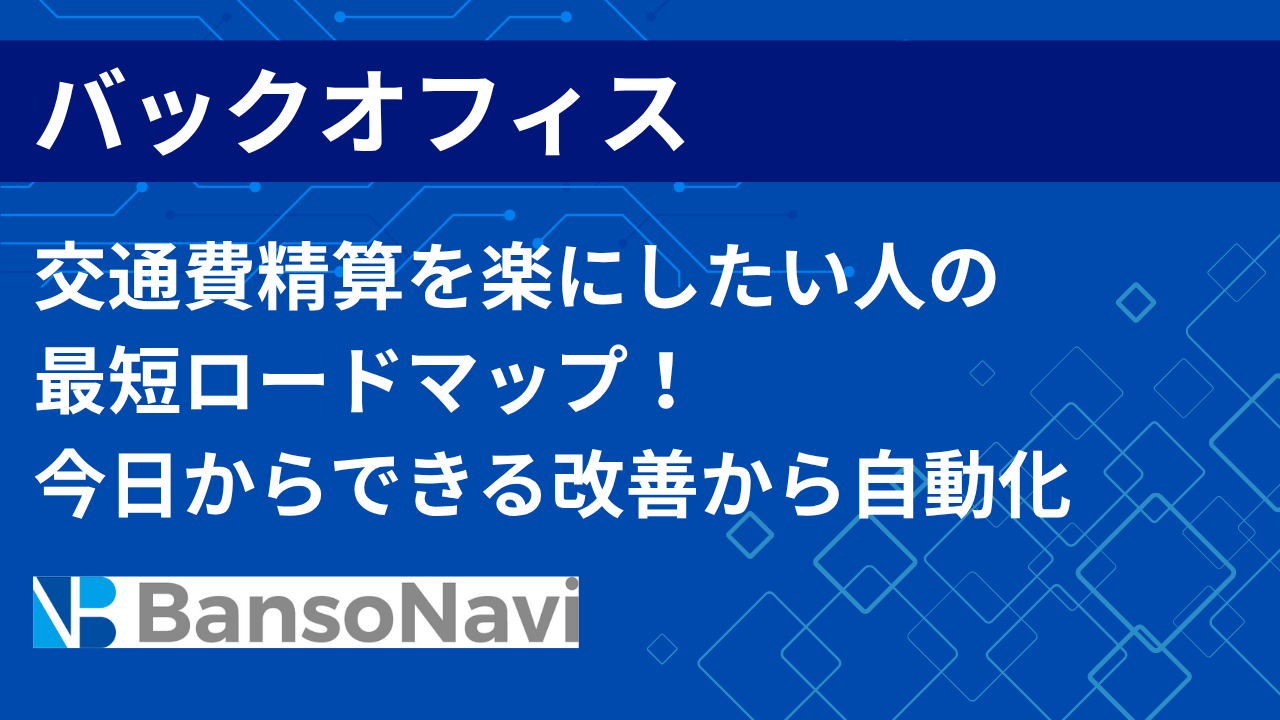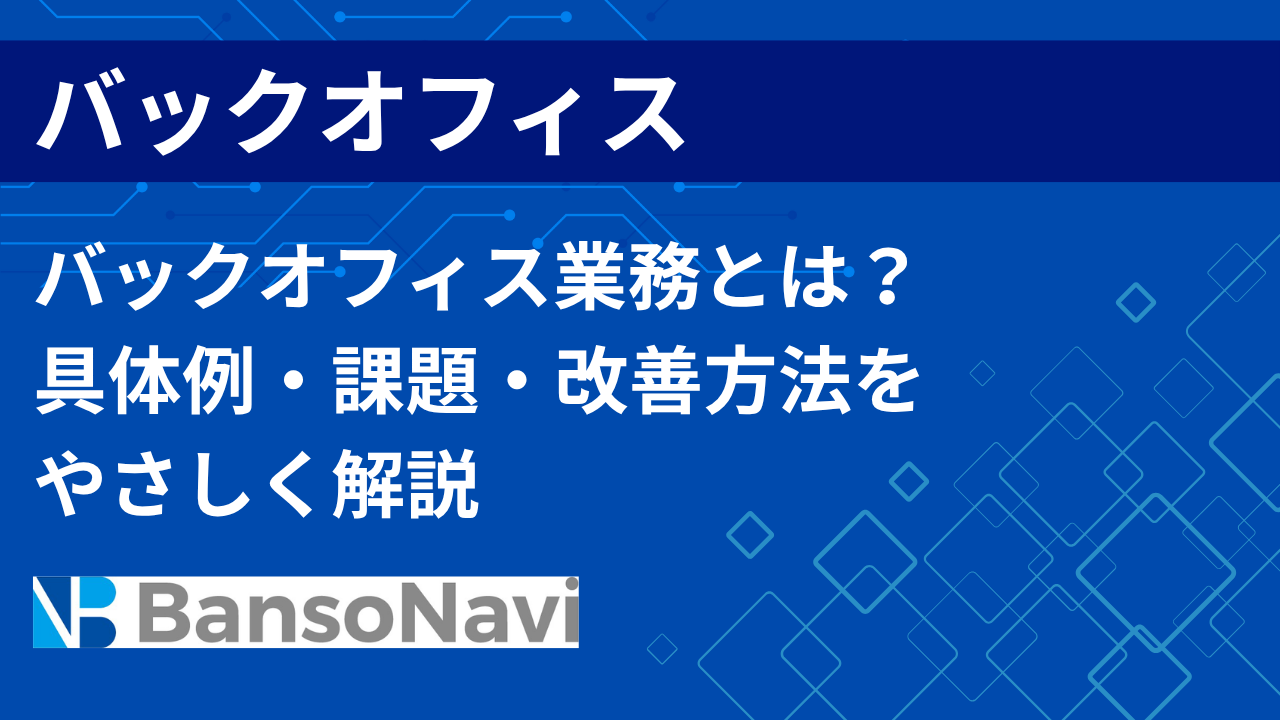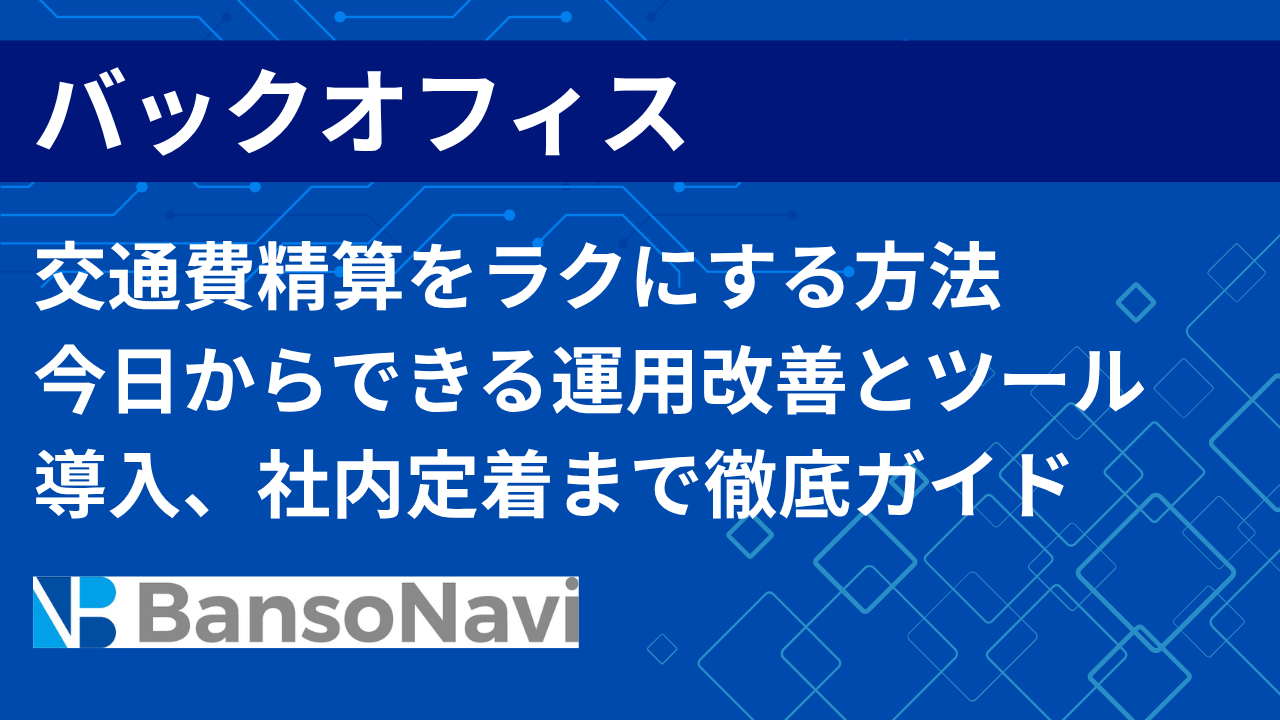バックオフィスを効率化する方法とは|メリットや成功事例も解説

「バックオフィス業務が非効率で、日々の対応に追われている」
「テレワークやDXを進めたいけれど、何から手をつけるべきかわからない」
このようなお悩みはありませんか?
この記事では、バックオフィス業務の抱えがちな課題を整理し、効率化する方法やメリットを解説します。また、実際に業務改善に成功した企業の事例や、ツール導入を含めた具体的な改善手順も説明します。
バックオフィス業務の人手不足や属人化を解消したい方にとって、役立つ情報が満載です。経営層から実務担当者まで、業務改善のヒントとして参考にしてください。
■この記事でわかること
・バックオフィスが抱える代表的な課題とその原因
・業務効率化によって得られる具体的なメリット
・成功企業に学ぶ、効率化の実践方法と導入手順
■こんな人におすすめの記事です
・バックオフィスの業務効率を改善したい中小企業の経営者や管理職
・DXやRPAに興味はあるが、導入にハードルを感じている方
・バックオフィス改革の具体例や手順を知りたい企業担当者
目次
バックオフィスの業務とは?

売上を直接生まないものの、社内体制を整え、従業員が円滑に働ける環境を作る役割がバックオフィスです。
ここでは、以下3点に分けて、バックオフィスの役割と他部門との違いを整理します。
- 担当業務ごとに異なる4つの主要部門
- 補助的な作業が中心の事務職との違い
- 顧客と接するフロント部門との役割分担
裏方だからこそ見落とされがちですが、企業全体のパフォーマンスに直結する重要な業務です。
バックオフィスとされる4つの職種
バックオフィスには、以下4つの職種が含まれます。
| 職種 | おもな役割 |
| 人事 | 採用・教育・労務管理を通じて人材を支える |
| 総務 | 備品や施設管理などの社内環境を整備する |
| 経理 | 入出金管理や決算対応で資金を正確に処理する |
| 法務 | 契約書の精査や法的リスクへ対応する |
これらの部門は、顧客対応の最前線には立ちませんが、企業活動を内側から支える不可欠な存在です。業務は専門性が高く、部署ごとに異なるスキルが求められます。
バックオフィスと事務職との違い
「バックオフィス=事務職」と思われがちですが、実際には役割の深さが異なります。
事務職は、電話対応や書類整理、データ入力などの定型業務が中心です。
対して、バックオフィス職は、運用フローの設計や業務改善など、仕組みづくりに関わる業務が含まれます。
以下に、おもな違いを記載しました。
- 事務職:日々の処理をミスなくこなす
- バックオフィス職:全体最適を見据えて業務体制を構築する
いずれも必要な業務ですが、期待値やキャリア形成が異なります。
フロントオフィスとの違い
フロントオフィスは営業・接客・サポートなど、顧客と直接接する部門を指します。バックオフィスとは役割が対照的で、社内対応や管理業務が中心です。
たとえば、営業部が契約を獲得した際、そのあとの請求処理や契約内容の確認を担うのがバックオフィスです。
以下に、おもな違いを整理しました。
| 区分 | フロントオフィス | バックオフィス |
| 対象 | 顧客・取引先 | 社内・社員 |
| おもな業務 | 営業・販売・接客 | 経理・人事・総務・法務 |
| 成果の見え方 | 売上・顧客満足として表面化 | 業務効率や制度整備として内部反映 |
どちらか一方だけでは企業は回りません。両役割により、組織全体の連携がスムーズになります。
バックオフィスの抱える4つの課題
バックオフィスは裏方業務なため、改善を後回しにしがちです。しかし、さまざまな課題が積み重なれば、組織全体の生産性に影響を及ぼします。
ここでは、バックオフィスが直面するおもな課題を4つ整理しました。
- 1人に業務が集中し、負担が偏ってしまう
- ノウハウが共有されず、仕組みが属人化する
- アナログ管理が残り、デジタル移行が進まない
- 柔軟な働き方が困難でテレワークが浸透しにくい
これらの課題を放置すれば、業務効率だけでなく人材定着にも影響するため、注意が必要です。
業務負担が大きくなりがち
バックオフィスでは、定型的な処理業務に加え、イレギュラーな対応が多く発生します。人事・経理・総務などの業務は年間行事も多く、繁忙期には通常の数倍の作業量になることも少なくありません。
とくに中小企業では、1人で複数の業務を兼務しているケースも多く、負担が一部の担当者に偏る傾向があります。
以下はよくある実情です。
- 休暇中に代替要員がいない
- マニュアルがなく、ほかの担当者で代替できない
- 締切に追われ、チェック体制が不十分になる
このような負荷が、ヒューマンエラーや離職の要因につながります。
属人化によりDX推進しづらい
担当者しか業務内容を把握していない「属人化」は、バックオフィスでよく見られる問題の1つです。ファイルの保管場所が個人依存だったり、手順が口頭のみで伝えられていたりすると引き継ぎが困難になります。
属人化が進行すると、以下のようなリスクが発生します。
- 担当者の退職や異動で業務が停止する
- 業務全体が見えづらく、改善ポイントが不明瞭になる
- ツール導入時に現場からの抵抗が起きやすくなる
DXを進めるには、「誰でもできる」業務体制に整えることが先決です。まずは、マニュアル整備や業務の見える化に取り組みましょう。
紙の管理から脱却できない
バックオフィスでは、契約書・稟議書・勤怠届など紙で運用されている業務が多く存在します。紙ベースの管理は印刷・押印・郵送といった工程が必要なため、処理に時間とコストがかかります。
また、以下のような課題も見逃せません。
- 書類が探しづらく、情報共有に時間がかかる
- 紛失や劣化による情報トラブルのリスクがある
- テレワークや外出先での対応が困難になる
近年はクラウド契約や電子帳簿保存法対応のツールも充実しており、ペーパーレス化は現実的な選択肢になりつつあります。
テレワークの導入がしづらい
柔軟な働き方を推進したくても、「社内サーバーにしかアクセスできない」「紙の承認が必要」などの理由で在宅勤務が難しいケースが多く見られます。
おもなハードルは以下のとおりです。
- セキュリティ上の懸念で外部アクセスが制限されている
- 承認フローが紙や対面中心で、遠隔対応が難しい
- 社員のITスキルにばらつきがあり、導入が進まない
これらの課題は、クラウド型ワークフローの導入や、ITリテラシー研修により改善が期待できます。制度やツールだけでなく、社内の文化的な側面の見直しも必要です。
バックオフィスを効率化する5つのメリット

バックオフィスの業務改革は、作業スピードを上げるだけでなく、企業全体によい影響を与えます。
ここでは、代表的な5つのメリットを紹介します。
- 支出の無駄を抑え、予算配分の見直しが可能になる
- 人的ミスが減り、処理の精度が安定する
- 担当者の能力を最大限に活かす体制を整えられる
- 働きやすさが向上し、社員のモチベーションを維持できる
- 内部管理が強化され、組織の健全性が高まる
それぞれ見ていきましょう。
コストを削減できる
ツールの導入や業務フローの見直しにより、バックオフィスではさまざまな経費の削減が見込めます。
たとえば、紙の使用量の減少により印刷代・郵送費を抑えられます。また、作業時間が短縮されれば人件費の負担も軽減されるでしょう。
とくに中小企業では、1つの施策が大きな成果につながるケースも少なくありません。結果として、コスト構造全体の見直しや投資先の再検討につながる可能性もあります。
ヒューマンエラーを防げる
人の手で行う作業は、どれだけ注意しても確認漏れや記入ミスなどの問題が発生します。しかし、定型業務をデジタルツールに置き換えれば、このようなミスは大幅に減少します。
たとえば、ワークフローシステムを導入すれば、承認漏れや二重入力のような人為的ミスを防止可能です。エラーの少ない体制の構築により、業務が安定するでしょう。
生産性が上がる
効率化は、単に早く終わらせることを目的とするものではありません。時間的な余裕が生まれることで、担当者は企画や改善などの創造的な業務に集中しやすくなります。これにより、チームや組織全体のアウトプットの質が底上げされるのです。
定型処理から解放されることで、自発的な提案や業務改善も活発になります。このような流れが定着すれば、社内全体の生産性も自然と引き上げられるでしょう。
従業員の満足度が上がり離職率が下がる
業務負荷が軽減されると、従業員は精神的・肉体的に余裕をもって働けます。働き方の柔軟性が広がることで、自分のライフスタイルに合ったペースで仕事に取り組めるのも大きな変化です。
このような職場環境は、長く働きたいと感じられる要素の1つとなり、離職率の低下にもつながります。
人材の流出を防ぎ、定着率を高めることは、企業の持続的に成長するために不可欠な取り組みです。
ガバナンスが強化される
業務の見える化が進むと、誰が・いつ・どのような処理を行ったのかが明確になります。これにより、業務の透明性が高まり、万が一トラブルが起きた際も迅速に対応できます。
また、社内のルールや権限管理が整備されれば、不正や情報漏洩といったリスクの抑止力にもつながるでしょう。
バックオフィスの効率化は、単なる作業改善にとどまらず、企業全体のコンプライアンスの体制強化も果たします。
バックオフィスを効率化する8つの方法

バックオフィス業務の改善には、単に人手を増やすのではなく、テクノロジーや外部リソースの活用が欠かせません。業務を棚卸しし、ムリ・ムダを省くことが生産性向上のために重要です。
ここでは、とくに効果の高い8つの施策を紹介します。
- 専用システムで業務処理を最適化する
- 単純作業を自動化する
- 問い合わせ対応を効率化する
- 書類を電子化して運用の手間を軽減する
- ITスキル向上を促し、社内浸透を後押しする
- 特定業務を外注してリソースを確保する
- 業務プロセスを見える化する
- テレワークの導入・拡大に向けて基盤を整備する
それぞれ参考にしてください。
ITツールを導入する
バックオフィスのITツールとは、勤怠管理・経費精算・進捗管理などの業務を効率的に処理できるクラウドサービスやアプリケーションを指します。
紙やExcelによる管理と比べて、情報の入力・共有・集計がスピーディに行えるため、業務全体をスムーズに運用可能です。データのリアルタイム共有や検索性の向上、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。
なかでもおすすめなのが、サイボウズが提供する業務改善プラットフォーム「kintone(キントーン)」です。kintoneはノーコードで業務アプリを自由に作成できる点が大きな魅力で、業務内容や運用体制に応じたカスタマイズにも対応しています。
たとえば、プロジェクトや申請状況、問い合わせ対応などの複数業務の一元管理により、バックオフィスの見える化・標準化に役立ちます。導入後は部門間の連携がスムーズになり、情報共有の質も格段に上がるでしょう。
なお、kintoneについてより詳しく知りたい方は、こちらの公式サイトをご覧ください。
参考:サイボウズ株式会社「導入社数30,000社突破!キントーンとは」
RPAを活用する
RPA(Robotic Process Automation)とは、定型的なパソコン業務を自動で処理するソフトウェアです。人が行っている繰り返し作業をロボットに置き換えることで、処理スピードの向上とミスの削減が実現します。
バックオフィスでは以下の業務で導入が進んでいます。
- 請求書の発行
- 取引データの転記
- 勤怠情報の集計
- 各種申請の処理
導入後は作業時間が大幅に短縮され、担当者は分析や企画などの本来注力すべき業務に集中できるでしょう。RPAは、一度設定すれば24時間稼働させられるのも大きな強みです。人手に頼らず業務を継続する体制構築に役立ちます。
チャットボットを導入する
チャットボットは、あらかじめ登録した情報に基づいて自動で質問に答えるプログラムです。業務時間や担当者の有無にかかわらず、問い合わせ対応が可能です。
バックオフィスでは、よくある社内質問への即時対応や、申請手続きの案内、社内ルールの確認などに活用されています。操作も直感的で、専門知識がなくても使いこなせるケースが多く、担当者の対応工数が大きく削減されます。
最近ではAI型チャットボットも増えており、使うほどに回答精度が向上するのも魅力です。情報提供の手間を減らし、社内対応のスピードと質を両立する手段として注目されています。
紙から脱却(ペーパーレス化)する
ペーパーレス化とは、これまで紙で行っていた業務を電子化し、データで管理・運用する取り組みです。書類の印刷やファイリングが不要で、業務をスピーディに進められます。
バックオフィスでは、契約書や申請書の電子化、電子押印の活用、クラウドストレージでの書類共有などが代表的な活用例です。紙のやり取りが減ることで、オフィスの省スペース化や業務の場所を選ばない柔軟な働き方にもつながります。
運用ルールやセキュリティ体制の構築により、業務効率と情報管理を両立できるでしょう。
全社的にITリテラシー向上を推進する
業務効率化の基盤となるのが、社員一人ひとりのITリテラシーです。ツールを導入しても、現場で使いこなせなければ効果は限定的になります。そのため、操作スキルだけでなく、業務にどのように活用できるかという視点を含めた教育が求められます。具体的には、社内マニュアルの整備や階層別の研修、社内勉強会の開催などが有効です。
また、成功事例を全社で共有することで、ツール活用に対する心理的ハードルを下げられます。ITに対する前向きな姿勢が広がれば、現場からの改善提案も生まれやすくなり、組織全体のデジタル活用力が高まっていくでしょう。
なお、社内DX推進におすすめなのが、外部リソースによるリスキリング講習です。リスキリング講習に興味のある方は、ぜひこちらよりお問い合わせください。
アウトソーシングを利用する
アウトソーシングは、自社で行っていた業務の一部を専門業者に委託する仕組みです。業務の質を保ちつつ、社内リソースをコア業務に集中させることが可能です。
バックオフィスでは、専門性が高く手間のかかる業務を委託するケースが多く見られます。たとえば以下があげられます。
- 給与計算
- 社会保険の手続き
- 年末調整
- 法務対応
社内に専門知識がない分野でも、安心して業務を任せられる点がメリットです。委託先との連携や情報共有の体制を整えておけば、安定した品質で効率的に運用できます。コストだけでなく、時間と人的資源の再配分という観点からも有効な手段といえるでしょう。
ワークフローを見える化する
業務の流れを可視化することで、誰が・いつ・何をしているのかが明確になります。これにより、進捗管理がしやすくなり、業務の重複や抜け漏れを防止可能です。
申請・承認フローや各種手続きの進行状況の見える化により、確認作業のスピードが向上します。その結果、関係者全体の認識もそろいやすくなるでしょう。
ワークフロー管理ツールを導入すれば、業務の流れをリアルタイムで把握でき、情報共有の効率も高まります。業務の属人化を防ぎ、組織としての対応力を強化するためにも、見える化は重要な施策の1つです。
テレワークを促進する
テレワークの実現により、働く場所に縛られない柔軟な業務体制の構築が可能です。クラウド型の勤怠管理やワークフローシステム、ファイル共有ツールなどを導入すると、オフィス外でも一連のバックオフィス業務を問題なく遂行できます。
たとえば、申請・承認・報告などの業務は、すべてオンライン上で完結させられるため、意思決定のスピードが上がります。
また、Web会議やビジネスチャットをあわせて活用することで、部門間の連携もスムーズになるでしょう。テレワーク環境の整備は、生産性や従業員満足度向上に関わる重要な取り組みです。
バックオフィスの効率化を進める手順
業務を効率化するには、ツールを導入するだけでなく、明確な手順を踏んで進めることが重要です。
ここでは、効率化を進める際に押さえておきたい基本的な手順を紹介します。
- 担当業務や業務量を棚卸しし、全体像を明らかにする
- 無駄や手間が発生している箇所を見つける
- 実行可能な改善策を比較し、最適な方法を選び出す
- 小規模に試しながら、実運用に向けて調整する
- 全社的に理解と協力を得るための周知活動を行う
- 環境を整えたうえで、本格的な運用をスタートさせる
それぞれ順に見ていきましょう。
1.現状の業務を整理し、分析する
業務の効率化は、まず「今なにをしているか」を正確に把握することから始まります。Excelや業務フローチャートなどを活用し、業務ごとの所要時間や関係者、使用ツールをリストアップしましょう。
たとえば、請求処理に毎週3時間かかっていて次の業務に進めないことが判明すれば、改善の余地が明確になります。重要なのは、思い込みではなく事実ベースで業務を可視化することです。
可能であれば、実務担当者へのヒアリングも併用し、現場の実態を正確に反映させてください。
2.ボトルネックを見つけ、解決策を検討する
整理した業務フローをもとに、時間や手間が集中している部分を見つけ出します。たとえば、紙による承認業務で書類の回覧が滞っているなら、それがボトルネックです。
このような箇所に対して、ツール導入・フロー簡素化・担当者変更など複数の対策を考えましょう。社内だけで解決策が見つからない場合は、外部の成功事例やツールの無料トライアルを活用すると視野が広がります。小さな違和感にも注目することが、改善のヒントにつながります。
3.解決策を選定する
検討した案の中から、自社の業務規模・予算・リソースに合う方法を見極めます。たとえば、請求処理を見直す場合、「A社製ツールで管理画面を構築する」「現在使っているクラウド会計ソフトと連携する」などの選択肢が考えられます。
この段階で大切なのは理想像だけでなく、自社で運用可能かどうかという現実的な視点です。とくにITに不慣れな部署が関わる場合は、スモールスタートできる柔軟性があるかを重視しましょう。
さらに、ツールの導入を検討する際に、複数社の比較も欠かせません。以下に、最適な選定のための比較ポイントをまとめました。
| 比較項目 | 詳細 |
| 機能の柔軟性 | 自社の業務にフィットする機能が備わっているか |
| 連携性 | 他システムとデータ連携が可能か、既存環境との親和性はどうか |
| 操作のしやすさ | 現場担当者が直感的に使えるUIか |
| コスト | 初期費用とランニングコストのバランスはよいか |
| サポート体制 | 導入後の問い合わせ対応やマニュアル提供が充実しているか |
このような視点で冷静に比較すれば、導入後のミスマッチも防ぎやすくなります。
4.テスト運用し、フィードバックを得る
いきなり全社導入せず、まずは一部のチームや部署に小規模で試験導入します。たとえば、申請業務の電子化を試すなら、総務部門から先行実施するかたちです。
導入中は利用者の声を積極的に収集し、「使いにくい」「手順が分かりにくい」などのフィードバックをもとに調整を重ねましょう。特定の機能だけを段階的に追加する方式も有効です。現場との対話を重ねながら改善することで、導入の成功率が高まります。
5.社内周知を行う
新しい仕組みを定着させるには、運用開始前の社内説明が欠かせません。ただ通知を出すだけではなく、「なぜ変えるのか」「導入でどう変わるのか」を具体的に伝えると、協力を得やすくなります。
たとえば、稟議書の電子化では「申請から承認までが1日短縮される」「紙の書類を回す手間がなくなる」などのメリットを提示すると効果的です。
説明会や操作マニュアルの配布、質問受付の窓口設置など、丁寧な対応が社内で理解を得るポイントです。
6.本番運用を開始する
準備が整ったら、いよいよ全社的な本番運用に移ります。初期段階は混乱を避けるため、導入初月に集中フォロー体制を設けると安心です。
たとえば、チャットやメールで問い合わせに即時対応できるサポート窓口を設けると、現場の不安も軽減されます。
運用後も定期的に改善点を洗い出し、小さな調整を重ねる姿勢が成功につながります。導入はゴールではなく、継続的な業務改善のスタートと捉えましょう。
バックオフィスの効率化に成功した事例6選

実際に業務改善を進めた企業の事例を見ることで、効率化の具体的なイメージがつかめます。業種や組織規模が異なっても、共通する工夫や成果が参考になる場面は多いはずです。自社の状況と照らし合わせながら、活用できそうなヒントを探してみてください。
ここでは、以下6つの成功事例を紹介します。
- 建設業がExcel依存から脱却し、文書管理を効率化
- 大手商社がRPAを用いて案件処理を自動化
- 労務業務を一元管理し、ミスと作業量を削減
- アプリ導入により経費精算のスピードを大幅に向上
- 自社ツールとRPAの併用で採用関連業務を省力化
- 勤怠管理を見える化し、働き方改革を実現
それぞれ見ていきましょう。
建設業が脱Excelに成功!ペーパーレス化実現|エコサイクル株式会社
全国に営業所を展開するエコサイクル株式会社は、AccessやExcelへの依存による非効率な情報管理に課題を抱えていました。営業所間の情報共有はメールや電話が中心で、データの分散や入力ミスも頻発していた状況です。
これらを解消するために、kintoneを導入し、情報の一元管理と業務のペーパーレス化を推進。現場のDX化も進み、業務全体の効率と透明性が大きく向上しました。
| 実施した内容 |
|---|
| ・営業・現場情報・名刺管理をkintoneに統合し、分散管理を解消 |
| ・請求業務にクラウドサービスを連携し、紙からの脱却を実現 |
| ・導入時から現場の意見を重視し、操作性に配慮したアプリ設計を実施 |
| 成果 |
|---|
| ・社内の情報共有がスムーズになり、業務の属人化を防止 |
| ・二重入力やデータミスが減少し、業務の正確性が向上 |
| ・請求書や資料のやりとりが効率化し、ペーパーレスを実現 |
なお、同社の事例についてより詳細に知りたい方は、こちらのページも参考にしてください。
参考:【導入事例】kintoneで建設業のDXを実現!Excelからの脱却【エコサイクル株式会社様】
RPA連携で案件管理を効率化|住友商事株式会社
同社の輸送機・建機事業部門では、新規ビジネス創出に向けた時間の確保を目的に、既存業務の効率化が急務となっていました。グローバル案件の進捗管理やデータ共有の煩雑さを解消するため、kintoneを導入。
また、RPAと連携することで、業務の標準化と自動化を推進し、情報管理の質とスピードが大幅に向上しました。
| 実施した内容 |
|---|
| ・担当者主導でkintoneを試験導入し、グローバル情報の一元管理を実現 |
| ・RPA対象業務の進捗や効果を可視化するアプリをkintone上に構築 |
| ・プラグイン活用やセキュリティ設定により、社内展開とクラウド導入を促進 |
| 成果 |
|---|
| ・案件の進捗やロボット効果をダッシュボードで共有し、判断が迅速化 |
| ・各担当者の管理表が一本化され、RPA導入時の工数を削減 |
| ・情報共有の習慣が根付き、会議準備や日常業務の手間が軽減 |
なお、同社の事例の詳細は、こちらのページからもご確認いただけます。
出典:サイボウズ株式会社
労務業務の一元管理に成功|株式会社フクシア
児童発達支援施設を運営する同社は、従業員数の増加に伴い、スプレッドシートによる労務管理に限界を感じていました。
情報の正確性や共有のしやすさを向上させるため、チャット型勤怠とクラウド労務システムを導入。業務を一本化し、打刻の習慣化や経営判断の迅速化を実現しました。
| 実施した内容 |
|---|
| ・勤怠・給与・従業員情報の一元管理が可能なクラウド労務システムを導入 |
| ・チャットアプリと連携し、従業員が簡単に打刻できる仕組みを構築 |
| ・労務ツールの操作性に配慮し、ITに不慣れな職員にも対応できる環境を整備 |
| 成果 |
|---|
| ・勤怠データや給与明細の即時確認により、士業との連携が円滑化 |
| ・LINE連携で打刻ミスが減少し、従業員の問い合わせ対応が軽減 |
| ・勤怠情報の可視化により、将来を見据えた経営戦略を立案 |
出典:フリー株式会社
アプリ導入で、経費精算業務を1/3に短縮|サンラリー株式会社
多角的な事業を展開する同社では、紙による経費精算業務に膨大な時間がかかっていました。とくに申請・承認・確認の各工程が複雑で、月900時間もの負担となっていたため、スマホ対応の経費精算アプリを導入。
スマホ操作による即時対応と自動連携により、全社の作業工数が大幅に削減され、業務の見える化を実現しました。
| 実施した内容 |
|---|
| ・経費申請・承認が可能なスマホアプリを全社に導入 |
| ・日当条件など複雑な経費規定に対応できるシステムを設定 |
| ・専任サポートを受けながら、社内研修を実施 |
| 成果 |
|---|
| ・経費精算業務の作業時間を従来の1/3まで短縮 |
| ・スマホ操作により、出張中や隙間時間で処理可能に |
| ・手入力や確認作業の負担が減少し、ヒューマンエラーも大幅に軽減 |
出典:株式会社マネーフォワード
自社ツールとRPAで新卒採用業務の工数削減|株式会社クレオ
毎年1,000名以上の学生データを扱う同社では、複数の求人媒体からの情報管理に手間がかかり、データの重複やヒューマンエラーが課題となっていました。
そこで、自社の業務管理ツールとRPAを連携し、採用プロセスの可視化と自動化を同時に推進。工数を大幅に削減し、より戦略的な採用活動が実現しました。
| 実施した内容 |
|---|
| ・学生情報や選考状況の一元管理を目的に業務管理システムを導入 |
| ・採用業務マニュアルを整備し、自動化対象業務を明確化 |
| ・RPAツールを活用し、情報抽出・登録・資料作成を自動化 |
| 成果 |
|---|
| ・新卒採用にかかるデータ処理や確認作業の大部分を削減 |
| ・採用広報や社員教育など、人にしかできない業務に集中 |
| ・ミスの防止や精神的負担の軽減により、組織全体の業務効率が向上 |
出典: オープン株式会社
ツール導入により、勤務状況の見える化を実現|株式会社内池建設
同社では、現場の勤怠が可視化されず、長時間労働が常態化していたことが課題でした。そこで、経費精算や勤怠管理、営業支援などの複数のクラウドシステムを導入。
業務フローを見直しながらITツールを段階的に連携させ、働き方改革とスマート経営の実現につなげました。拠点展開や採用活動にも好影響を及ぼしています。
| 実施した内容 |
|---|
| ・会計ソフトとの連携を前提とした各種クラウドツールの導入 |
| ・勤怠・経費・営業支援システムを段階的に整備し、運用を標準化 |
| ・拠点展開を見据えた業務棚卸しとフローのスリム化を実施 |
| 成果 |
|---|
| ・勤務状況の可視化により、残業時間が大幅に減少 |
| ・拠点拡大時の管理負担やコストを最小限に抑えることに成功 |
| ・採用活動において「働きやすさ」を裏付ける数字を活用 |
まとめ:バックオフィスの効率化にはツール導入が必須!kintoneを検討しましょう
この記事では、バックオフィス業務を効率化するための基本的なアプリの種類や代表的なツールを解説しました。業務の見える化やテレワーク推進、情報の一元管理にはツールの活用が欠かせません。
また、実際の企業事例からツール導入がもたらす業務改善効果や、生産性向上のポイントも紹介しました。現場の運用やITリテラシーに応じた選定・導入により、業務効率化が実現します。
なかでもkintoneは、柔軟なカスタマイズ性と高い拡張性を備え、バックオフィス全体の最適化に役立ちます。自社に合った業務改革を進めるために、kintoneの導入がおすすめです。
なお、kintone導入に不安のある方は、ペパコミの伴走支援サービスをご検討ください。ペパコミは、導入支援実績が300件以上ある信頼できるkintoneパートナーです。御社のバックオフィス効率化のお手伝いをさせていただきます。