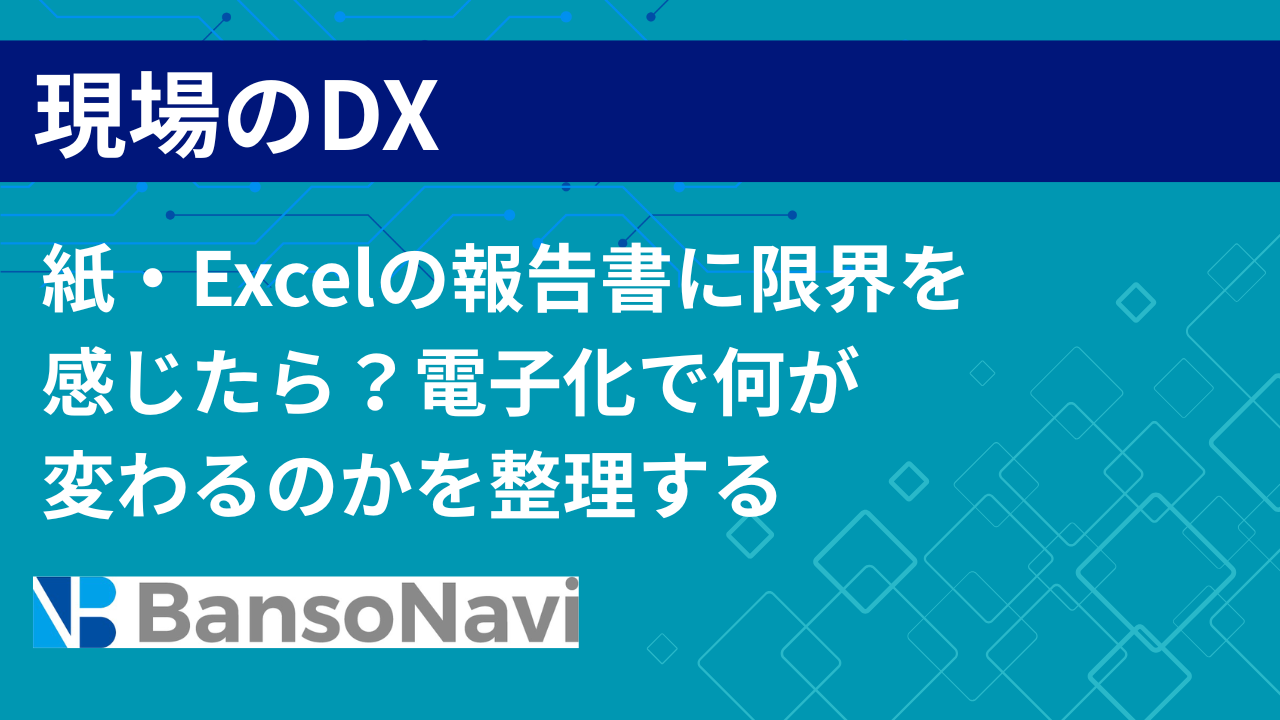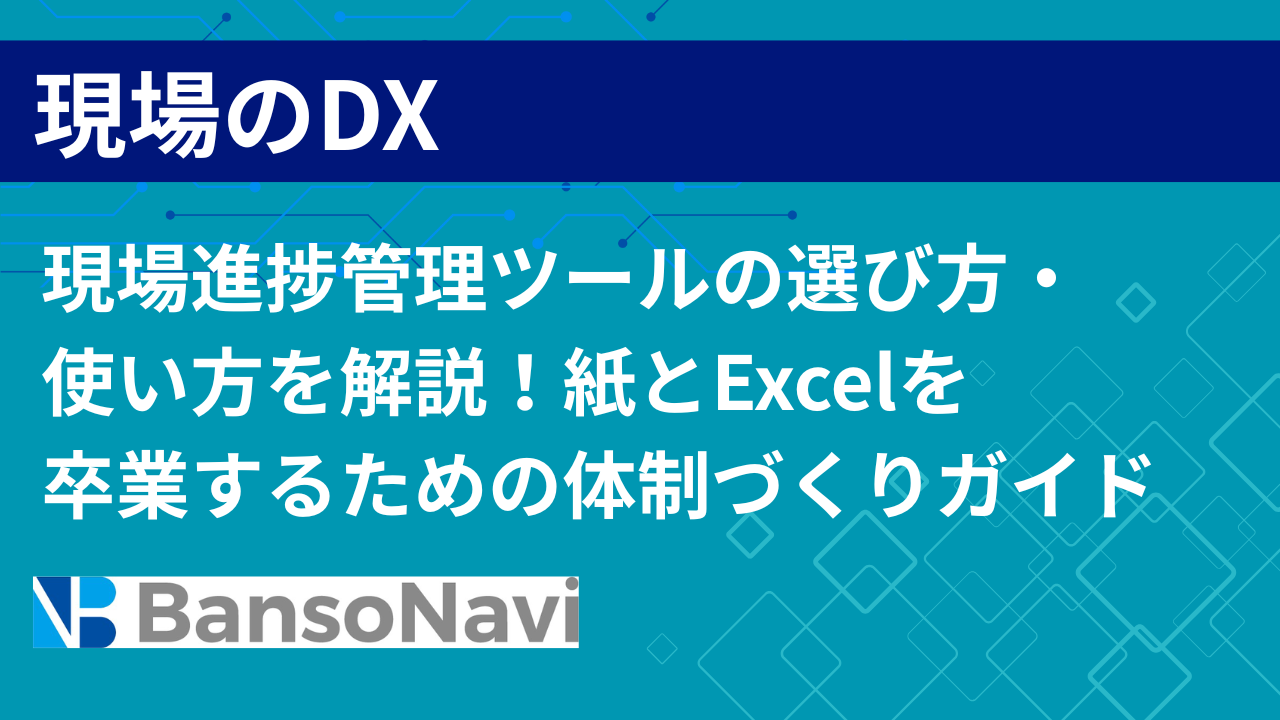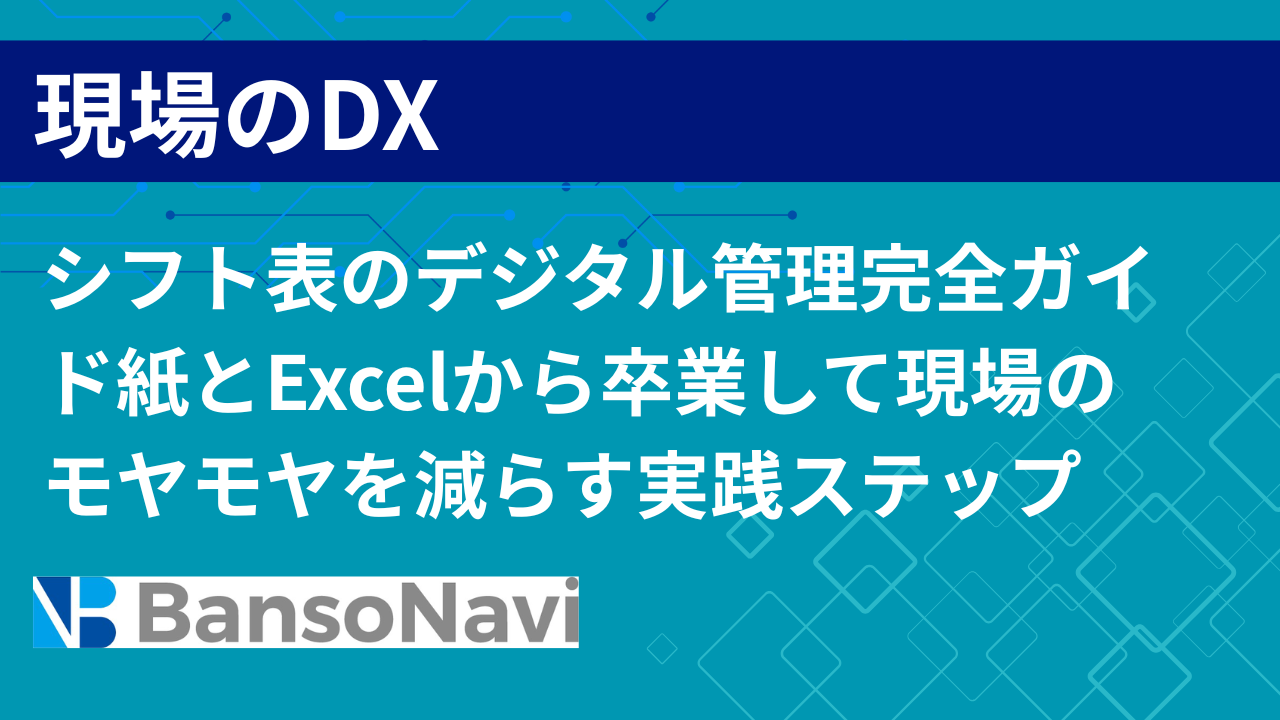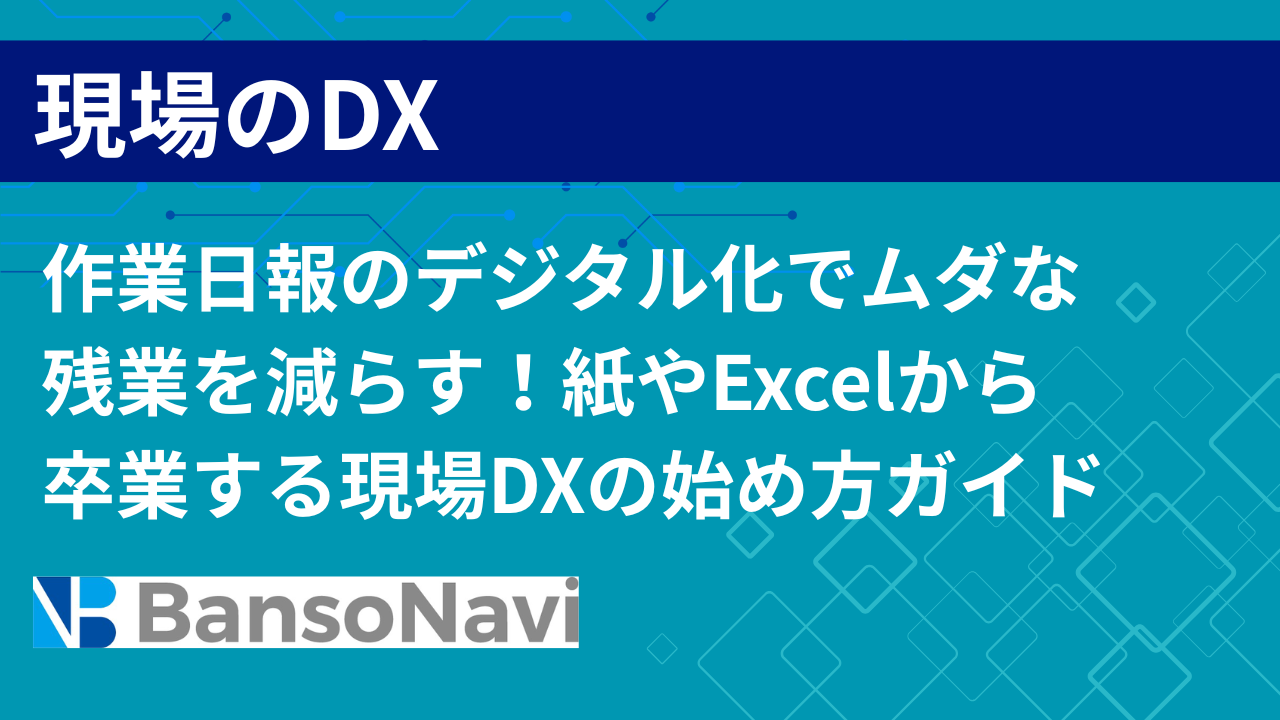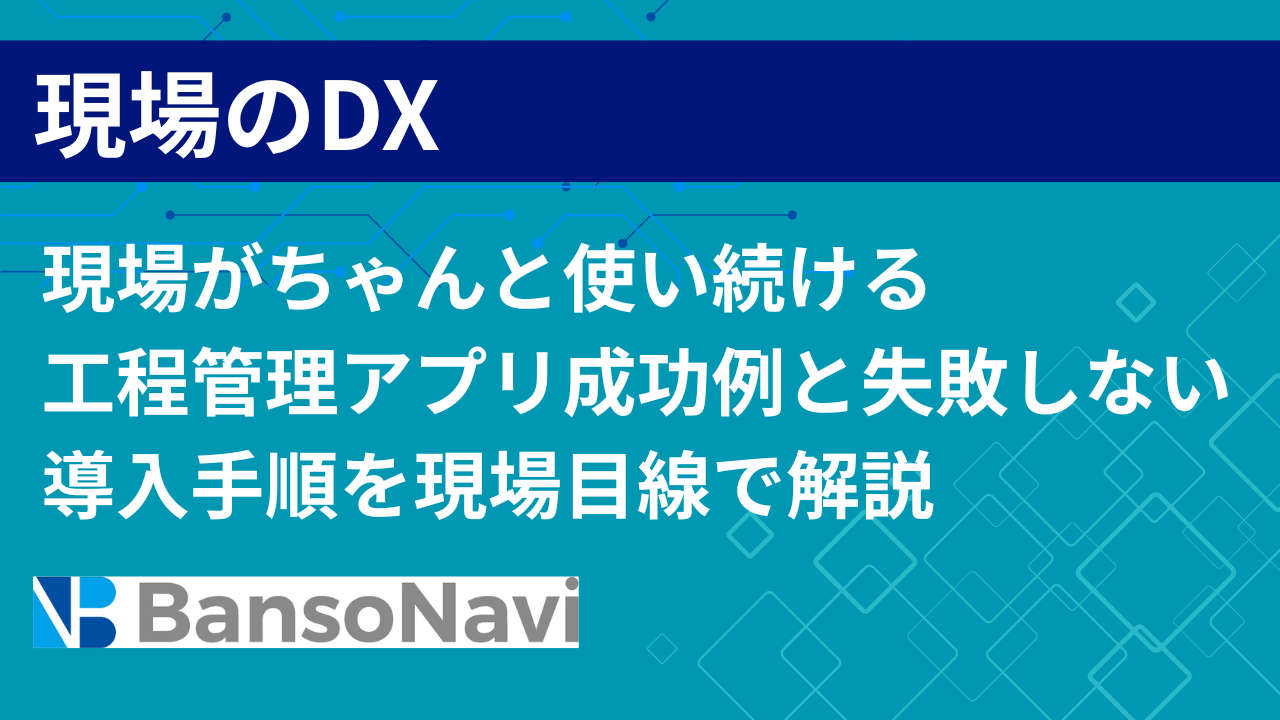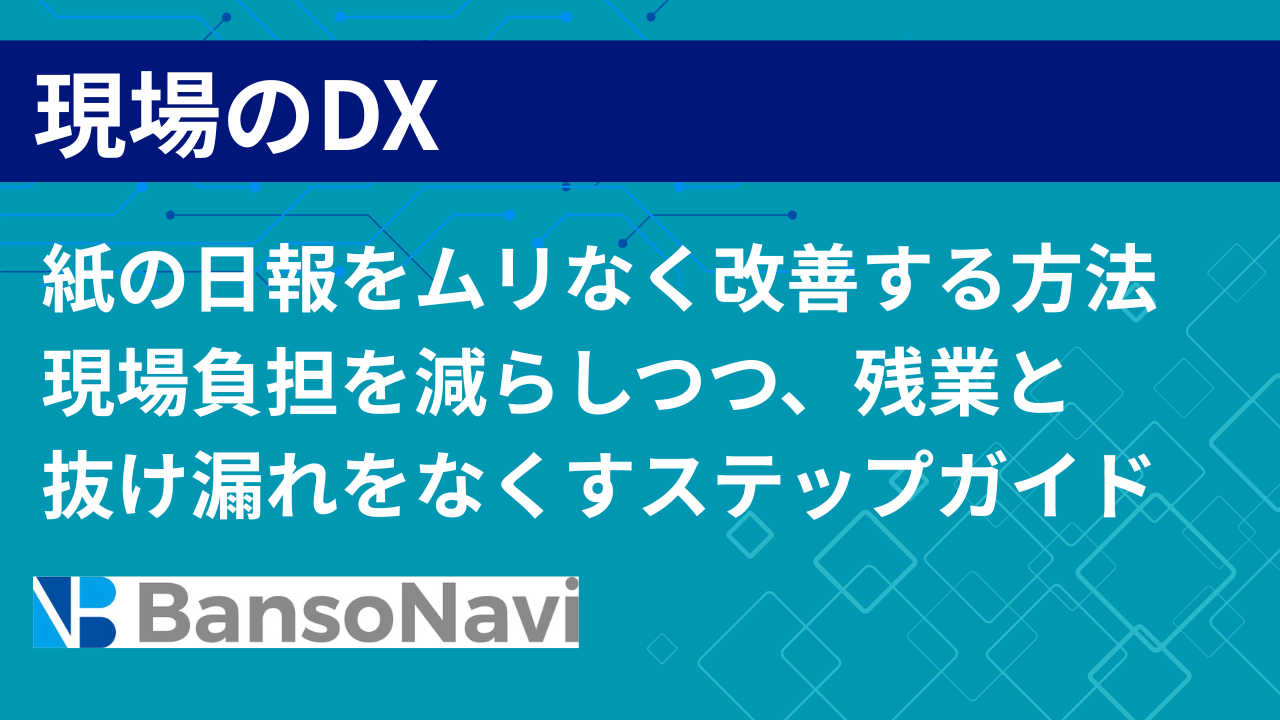現場DXとは?意味・具体例・進め方をやさしく解説する入門ガイド
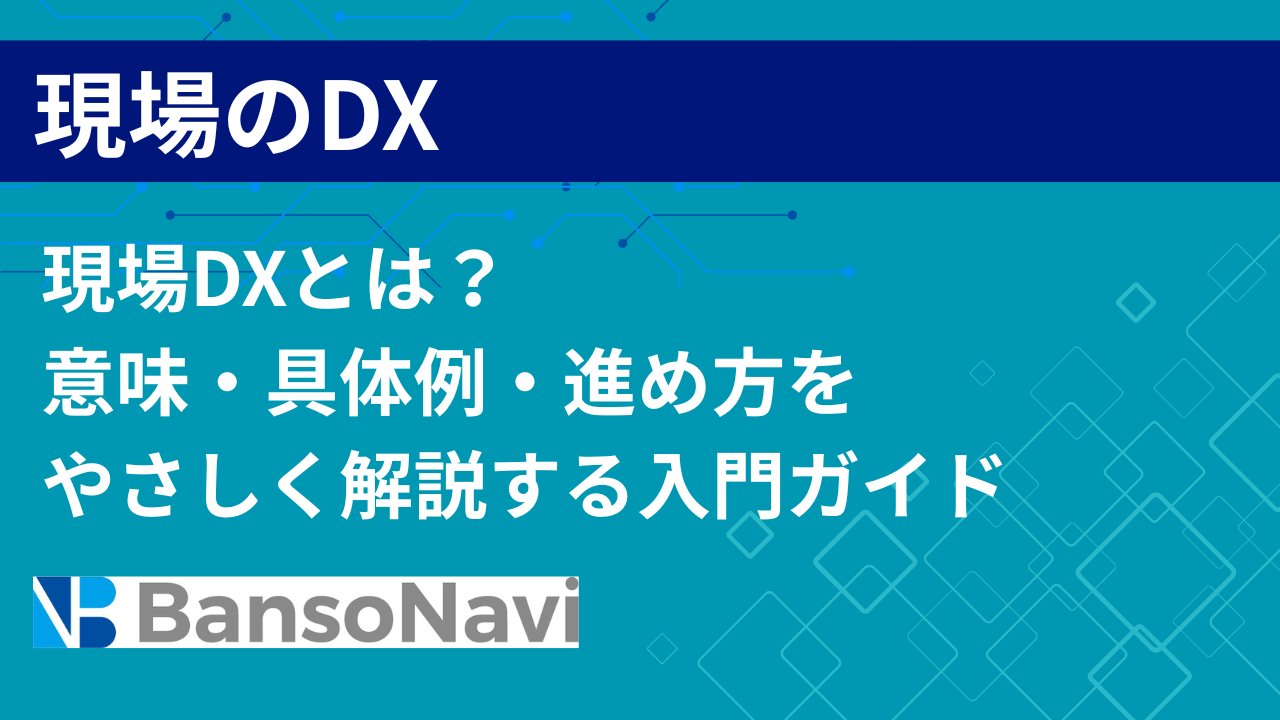
現場で「紙とExcelと電話でなんとか回しているけれど、正直しんどい」「DXと言われても、自社の現場にどう関係するのか分からない」という声はよく聞かれます。一方で、世の中では「現場DX」「デジタル化」「スマート工場」などの言葉が飛び交い、何となく置いていかれている気がしてモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな方に向けて、現場DXとは何かを専門用語をできるだけ避けて、現場目線でやさしく整理します。意味やメリットだけでなく、製造・建設・物流・サービスなどの具体例、進め方のステップ、ツール選びやDX内製化の考え方まで一通り分かるようにまとめました。
読み終わる頃には、「うちの現場でまずはここからDXに取り組んでみようか」「一度専門家に無料相談してみようか」と、次の一歩がイメージできる状態を目指します。肩の力を抜いて、身近な話として読み進めてみてください。
目次
現場DXとは?基本の意味

「現場DXとは何か」を一言で説明してほしいと言われると、急にハードルが上がったように感じるかもしれません。しかし、難しく考える必要はありません。現場DXは、最新のAIやロボットを入れる話だけではなく、まずは目の前の紙やExcel、電話や口頭でのやり取りを見直し、「現場の困りごとをデジタルの力で少しずつ良くしていく取り組み」と考えるとイメージしやすくなります。
ここでは、現場DXのシンプルな定義と、よく混同される「単なるデジタル化」との違いを整理していきます。
現場DXのシンプルな定義
まず押さえたいのは、現場DXとは「現場の困りごとを、デジタルの力を使って継続的に改善していくこと」だという点です。ここでいう現場とは、製造ラインや建設現場、店舗、倉庫、コールセンター、営業現場など、日々の業務が実際に行われている場所やチームを指します。
そして困りごととは、次のような日常的に感じているモヤモヤです。
・紙が多くて探せない
・Excelが複雑で触れる人が限られている
・誰が何をやっているのか見えない
現場DXと聞くと、「AIを入れないといけないのか」「ロボットや高価なシステムが必要なのか」と身構えてしまいがちですが、最初からそこまでやる必要はありません。例えば、紙の日報をスマートフォンから入力できるフォームに変え、リアルタイムで状況を確認できるようにするだけでも立派な現場DXの一歩です。
ポイントは、格好良いシステムを入れることではなく、「現場の人が楽になるか」「ミスが減るか」「仕事が見えるようになるか」という観点で取り組むことです。
また、現場DXは一度やって終わりではなく、少しずつ試しながら改善を重ねていく取り組みです。最初から完璧を目指すのではなく、小さく始めて、現場の声を聞きながら直していく前提で考えると、ぐっと取り組みやすくなります。難しい横文字よりも、「現場の困りごとメモを一つずつデジタルで解決していく活動」と捉えると、社内の説明もしやすくなるはずです。
DXと単なるデジタル化の違い
よくある混乱が、「デジタル化」と「DXは何が違うのか」「どこまでやれば現場DXと言えるのか」という点です。ざっくりと分けると、紙をそのままPDFにしたり、Excelで手作業入力しているだけの状態は「デジタル化」にとどまっているケースが多く、業務の流れや役割自体を見直しながら、仕事の進め方を変えていくのがDXというイメージです。
例えば、紙の報告書をスキャンして共有フォルダに保存するだけだと、「データはデジタルになったけれど、探しにくさや入力の二度手間はあまり変わらない」という状態になりがちです。
一方で、報告項目を見直して入力負担を減らし、スマートフォンから直接入力できるようにし、必要な人に自動通知が飛ぶように設定すれば、報告フローそのものが変わります。これは、単なるデジタル化を超えて、業務の進め方を見直しているので「DX」に近い取り組みと言えます。
現場DXでは、このような「やり方そのものを良くしていく視点」がとても重要です。例えば、次のような工夫は、すべて現場DXの一部です。
・手書きのチェックリストをそのままアプリ化するのではなく、項目を整理して入力を減らす
・Excelでバラバラに管理していた在庫や案件情報を、一つのアプリにまとめて二重入力をなくす
・電話や口頭で依頼していた作業を、申請フォームとステータス管理で見える化する
「ただデジタルに置き換えるだけで終わっていないか」「現場の負担やミスは本当に減っているか」という視点を持つことで、現場DXの質がぐっと変わってきます。
現場DXで解決できること

「確かに現場DXのイメージは分かったけれど、うちの現場で何が変わるのかピンとこない」という声もよくあります。そこで、この章では、さまざまな業種で共通して見られる現場の悩みを整理し、それに対して現場DXがどのように効いてくるのかを見ていきます。
人手不足や残業、ミスの多さ、情報共有の遅れなど、心当たりのあるテーマが一つでもあれば、そこが現場DXの出発点になり得ます。
現場でよくある困りごと
現場の悩みは業種ごとに違って見えますが、よくよく聞いていくと共通点も多くあります。例えば、次のような声は、多くの会社で共通するものです。
・報告書やチェックリストが紙で、とにかく探すのに時間がかかる
・同じような内容を、紙→Excel→社内システムと何回も転記している
・どの案件がどこまで進んでいるのか、担当者しか把握していない
こうした状況では、担当者が休んだだけで業務が止まったり、ミスが発生しても原因追及に時間がかかったりします。
また、人手不足や採用難が続く中で、「ベテランに頼り切り」「属人化している仕事」が増えているのも大きなリスクです。ベテランの頭の中にしかないノウハウや判断基準が引き継がれないまま、突然の退職や異動が起きると、現場の品質がガクッと下がることもあります。
若手や中途入社のメンバーが、「何を見てどう判断すればよいのか分からない」と戸惑い、戦力になるまでに時間がかかるケースも珍しくありません。
さらに、残業やムダな移動、探し物の多さも、現場の悩みとして頻繁に挙がります。紙の書類を探すために倉庫やキャビネットを行ったり来たりしたり、Excelファイルの最新版がどこにあるのか分からず、社内メールやチャットでやり取りが延々と続いたりする状況は、誰もが一度は経験しているのではないでしょうか。
こうした「じわじわ効いてくるムダ」を放置していると、気づかないうちに生産性やモチベーションを大きく下げてしまいます。
現場DXで期待できる効果
現場DXの目的は、最新技術を入れることではなく、今挙げたような現場の悩みを一つずつ解消していくことです。例えば、紙の報告書やExcelでバラバラに管理していた情報を、クラウド上のアプリにまとめるだけでも、「どこに何があるか分からない」というストレスは大きく減ります。
検索ですぐに必要な情報にたどり着けるようになれば、探し物にかけていた時間を他の仕事に回せるようになります。
また、現場DXによって、担当者しか分からなかった情報や判断基準を可視化できるようになります。チェック項目や判断の基準をアプリの中に落とし込み、誰でも同じ流れで仕事を進められるようにすれば、属人化のリスクを減らし、品質も安定しやすくなります。
若手や中途メンバーにとっても、「アプリの通りに進めれば大きく間違えない」という安心感が生まれ、育成スピードの向上につながります。
さらに、現場DXは残業削減や働き方改革にも直結しやすい取り組みです。移動せずに写真や報告を共有できるようにしたり、紙で回していた承認フローをオンライン化したりするだけでも、細かな時間のムダが積み重なりにくくなります。
結果として、「人を増やせていないのに、なぜか現場が回りやすくなった」という状態をつくることが可能です。こうした取り組みが進むと、働きやすさが向上し、採用や定着にも良い影響が出てきます。
業種別の現場DXイメージ
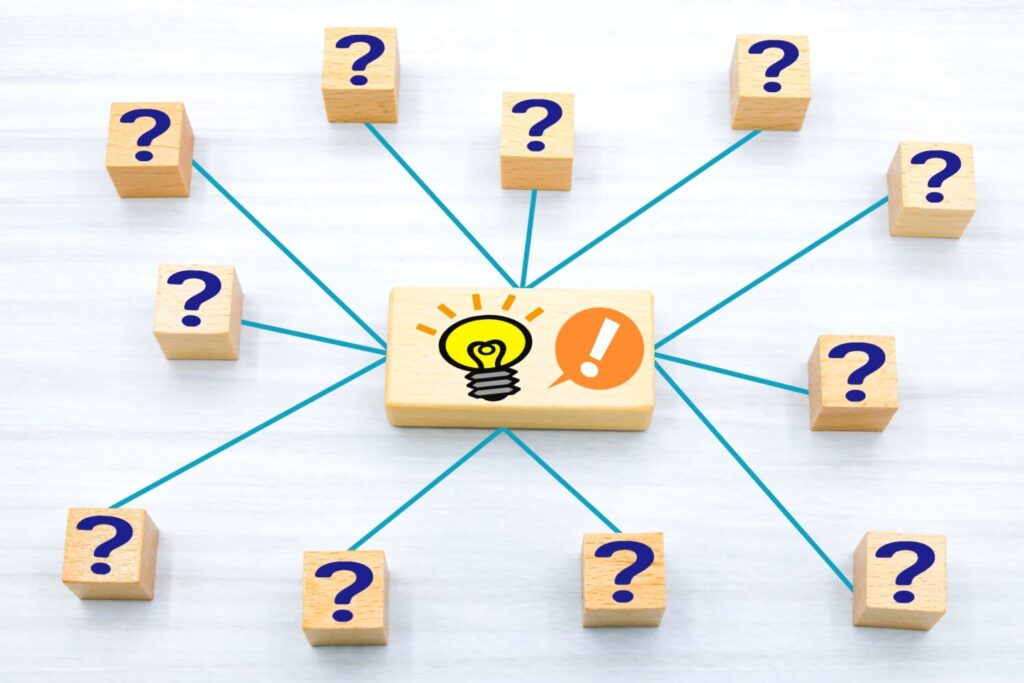
「うちは業種が特殊だから、よくある現場DXの例は参考にならない」と感じている方も少なくありません。ただ、実際に支援をしていると、業種が違っても「情報がバラバラ」「進捗が見えない」「口頭や紙でのやり取りが多い」といった課題には共通点が多くあります。
この章では、代表的な業種を例に挙げて、自社の現場に置き換えやすい形で現場DXのイメージを紹介します。
製造・建設の現場DX
製造現場では、日報や作業指示、品質チェック、設備の点検記録など、紙ベースの書類が多く存在します。ホワイトボードに「今日の段取り」や「進捗」が書かれ、現場に行かないと状況が分からないというケースもよくあります。
こうした現場で現場DXに取り組むと、例えば、日報や進捗報告をタブレットやスマートフォンから入力できるアプリに変え、リアルタイムでラインの状況を見える化するといった使い方が考えられます。
建設現場では、写真付きの報告や図面のやり取り、協力会社との連携がポイントになります。従来は、紙の図面に手書きでメモをしてFAXで送ったり、写真を個人のスマートフォンで撮ってLINEで共有したりしていたケースが多いですが、これでは情報が散らばり、後から振り返るのが大変です。
そこで、現場ごとに「写真・図面・メモ」を一元管理するクラウドアプリを用意し、関係者が同じ情報を見ながらやり取りできるようにすることで、手戻りや連絡ミスを大幅に減らせます。
伴走ナビでも、kintoneなどのノーコードツールを使って、こうした製造・建設の現場DXをお手伝いすることが多くあります。例えば、次のような取り組みです。
・紙の日報をkintoneアプリに置き換え、進捗や不良の情報をリアルタイムで可視化する
・建設現場ごとに案件アプリをつくり、写真や図面、打ち合わせメモを一か所で管理する
難しいシステムを一から作るのではなく、現場の仕事に合わせた小さなアプリを組み合わせていくことで、現場DXを進めていくことができます。
物流・サービスの現場DX
物流現場では、在庫や入出荷の管理、配車・ルート、荷主との連絡など、多くの情報が飛び交います。紙の伝票や電話、個人のメモに頼っていると、どこかで情報が抜け落ちたり、同じ内容を何度も確認したりするムダが発生しやすくなります。
現場DXでは、在庫や入出荷ステータスをスマートフォンやPCからリアルタイムに確認できるようにしたり、配車の情報を一元管理するアプリを用意したりすることで、「今どこまで進んでいるのか」「誰が何を担当しているのか」がひと目で分かる状態を目指します。
サービス業や店舗ビジネスでは、シフト管理や予約管理、お客様からの問い合わせ対応などがポイントになります。例えば、シフト表を紙やExcelで作ってLINEで送っていると、「最新版がどれか分からない」「急な欠勤が出るたびに電話とチャットで大騒ぎ」といった状況になりがちです。
ここでも、シフト管理アプリや問い合わせ管理アプリを用意し、スタッフやお客様の情報をまとめて見られるようにすると、調整や引き継ぎがスムーズになります。
このように、具体的な現場DXの形は業種によって少しずつ違いますが、次のような基本方針は共通しています。
・バラバラな情報を一か所にまとめる
・今どこまで進んでいるか見えるようにする
・紙や口頭のやり取りを減らす
伴走ナビでは、kintoneをはじめとしたノーコードツールを活用しながら、業種や会社の規模に合わせて現場DXの形を一緒に考えていく支援を行っています。自社の業種に近い事例を知りたい場合は、資料請求や無料相談をうまく活用してみてください。
現場DXの進め方

「現場DXにはメリットがありそうだ」と感じても、いざ社内で動き出そうとすると、「結局何から始めればいいのか」「誰が中心になって進めるのか」という壁にぶつかりやすいものです。
立派なDX戦略を作る前に、まずは現場の小さな一歩をどう踏み出すかが重要です。この章では、現場DXの進め方を、現場の担当者でもイメージしやすいようにシンプルなステップに分解して紹介します。
現場ヒアリングとテーマ選定
現場DXの第一歩は、立派な計画書作りではなく、「現場の困りごとを丁寧に聞くこと」です。いきなり経営層だけでテーマを決めてしまうと、現場の実態とズレてしまい、せっかくの取り組みが使われないシステムになってしまうリスクがあります。
そこで、まずは現場メンバーに、普段の仕事で感じているモヤモヤや、こうなったら楽だと思う点をざっくばらんに聞き出していきます。
このとき、「大きなテーマを一つだけ決める」のではなく、「小さくて具体的な困りごとをいくつかリストアップする」のがおすすめです。例えば、次のような具体的な話が出てくると、現場DXのテーマが見えやすくなります。
・紙の日報を回収して集計するのに毎日一時間以上かかる
・在庫数を確認するために倉庫を何往復もしている
・シフトの調整に毎回半日取られている
ここで大事なのは、現場の人が「これなら変わったらうれしい」と思えるテーマを選ぶことです。
リストアップした困りごとの中から、影響が大きく、かつ小さく始めやすいものを優先的に選びます。いきなり会社全体を変えるようなテーマを選ぶと、社内調整が大変になり、スタートまでに時間がかかってしまいます。
まずは一つの部署や一つの業務に絞って、「この範囲で現場DXの実験をしてみる」という感覚で始めると、成功しやすくなります。その成功例を社内で共有しながら、少しずつ範囲を広げていくのが現実的な進め方です。
小さく始めて育てるコツ
テーマが決まったら、次は具体的なツール選定やアプリ作成に進みますが、ここでも大事なのは「最初から完璧を目指さない」ことです。現場DXは、机上で完璧に設計しても、実際に使ってみると想定外のことが必ず起こります。
そのため、最初は必要最低限の機能だけを持った簡単なアプリを作り、短期間で現場に試してもらうのがポイントです。
実際に使ってもらったら、次のような観点でフィードバックを集めます。
・入力しづらいところはないか
・画面が見づらくないか
・誰に負担が集中していないか
このフィードバックをもとに、少しずつ改良を重ねていくことで、現場にフィットした形に育てていきます。現場DXは、一度作って終わりではなく、現場と一緒にアプリや仕組みを育てていく取り組みだと捉えると良いでしょう。
失敗しないためのコツとしては、次のようなポイントがあります。
1. テーマを欲張りすぎず、改善したい業務を絞ること
2. 現場のキーマン(リーダーやベテラン)を巻き込み、テスト利用に協力してもらうこと
3. 現場から出た意見をできるだけ早く改善につなげ、「言っても変わらない」という空気を作らないこと
こうした進め方を取ることで、現場DXは「誰かにやらされているプロジェクト」ではなく、「自分たちの仕事を良くする取り組み」として受け入れられやすくなります。
伴走ナビでは、この「小さく作って育てるプロセス」を一緒に回していく伴走型の支援を行っており、現場担当者だけで抱え込まない進め方を提案しています。
ツール選びとDX内製化

現場DXを進めるうえで、「どんなツールを選べばよいのか」「システム会社に全部お任せで良いのか」という悩みは付きものです。ここでは、ツール選びの基本的な考え方と、現場DXではなぜ内製化が重要になるのか、そしてkintoneのようなノーコードツールがどのように役立つのかを解説します。
現場DX向けツールの選び方
現場DXのツール選びでは、「有名な製品かどうか」よりも、「自社の現場にどれだけ合わせられるか」が重要です。パッケージ型のシステムは、最初から多くの機能を持っている反面、自社の現場にぴったり合わせるためのカスタマイズには時間と費用がかかることがあります。
一方で、ノーコードツールやローコードツールは、最初の見た目はシンプルですが、現場の業務に合わせて柔軟にアプリを作れるのが強みです。
特に現場の業務は、月ごと・季節ごとに少しずつ変化していきます。最初に作った仕組みが一年後もそのまま使えるかというと、そうとは限りません。変化する現場に合わせて、社内で自分たちで直せるツールを選ぶことが、現場DXを継続させるうえでのカギになります。
その意味で、メニューを組み立てる感覚で業務アプリを作れるノーコードツールは、現場DXとの相性が良いと言えます。
また、ツール選びの段階で、次のような観点も確認が必要です。
・現場が使う画面の分かりやすさ
・スマートフォンでも使いやすいか
・権限設定やセキュリティはどうなっているか
どれだけ機能が豊富でも、現場のメンバーが「難しそう」と感じてしまっては活用が進みません。伴走ナビでは、こうした視点からツールを比較し、現場目線で「この業務ならこのツールが合いそうです」といった整理を一緒に行うこともあります。
ノーコードとkintoneで進める内製化
ノーコードツールとは、プログラミングの専門知識がなくても、画面上の操作で業務アプリを作れるツールの総称です。その代表格の一つがkintoneであり、多くの企業が現場DXの土台として活用しています。
kintoneの強みは、顧客管理や案件管理、日報、申請フロー、在庫管理など、さまざまな業務アプリを一つのプラットフォーム上で作り、連携させられる点にあります。
現場DXでノーコードやkintoneを使う意味は、単に「安く作れるから」ではありません。大きなポイントは、現場に近いメンバーが自分たちでアプリを直したり、追加したりできるようになることで、DXを内製化できるというところにあります。
外部のシステム会社に毎回細かな修正を依頼していると、対応までの時間やコストがかかり、現場のスピード感と合わなくなってしまうことがあります。
とはいえ、「いきなり社内だけで全部やってください」と言われると不安になるのも当然です。そこで、伴走ナビでは、kintoneを中心とした現場DXについて、次のような伴走型の支援を行っています。
・最初の設計や初期アプリの作成は一緒に行う
・その過程で担当者の方にも少しずつ操作や考え方を覚えていただく
・分からないことがあれば質問しながら進められる
「完全に丸投げ」でも「完全に自力」でもない、中間の安心感のある進め方が可能になります。こうした伴走型の支援を受けながらDX内製化を進めることで、自社のペースで現場DXを育てていくことができます。
まとめ|現場DXの一歩を踏み出す
ここまで、現場DXとは何かという基本的な考え方から、具体例、進め方、ツール選び、内製化の考え方まで一通り整理してきました。最後に、明日から一歩踏み出すためのポイントと、伴走ナビの活用方法をまとめてお伝えします。
現場DXの要点と明日からの一歩
あらためて整理すると、現場DXとは「現場の困りごとを、デジタルの力を使って継続的に改善していく取り組み」です。最新の技術を導入すること自体が目的ではなく、紙やExcel、電話や口頭に頼っていた業務を見直し、現場の負担やミスを減らし、仕事を見えるようにしていくことが本質です。
単なるデジタル化との違いは、「やり方そのものを良くしていく視点があるかどうか」にあります。
明日からできる小さな一歩としては、例えば次のようなものがあります。
1. 現場メンバーに「今の仕事で一番困っていることは何か」を三つだけ聞いてみる
2. 困りごとの中から、「小さく始められそうなテーマ」を一つ選んでみる
3. そのテーマについて、「紙やExcelをやめるとしたら、どんな形が理想か」を簡単にメモしてみる
この三つができるだけでも、現場DXの出発点は整います。そこから先は、ノーコードツールやkintoneのようなプラットフォームを使って小さなアプリを作り、試しながら改善していく流れになりますが、最初の一歩は「現場の声を丁寧に聞くこと」です。
完璧な計画書を作る前に、身近なところから一つずつ動かしていくことが、結果的に早道になります。
無料相談・資料請求の活用
「話は分かったけれど、自社だけで進めるのはやはり不安」「どの業務から手を付けるべきか、第三者の意見も聞いてみたい」という方は、外部の専門家をうまく頼るのも一つの方法です。
伴走ナビでは、現場DXやkintone活用、DX内製化に関する無料相談を受け付けており、現場の状況やお悩みを伺ったうえで、次のような具体的な提案を行っています。
・まずはこの業務から始めてみてはどうか
・このような進め方ならリスクが少ない
また、「社内で説明する材料が欲しい」「経営層に現場DXの必要性を分かりやすく伝えたい」という場合には、事例や進め方をまとめた資料請求を活用していただくこともできます。実際に他社がどのような流れで現場DXを進めたのか、どのような課題にぶつかり、どのように乗り越えたのかを知ることで、自社でのイメージもぐっと具体的になります。
現場DXは、一気にゴールに到達するような短距離走ではなく、現場と一緒に少しずつ改善を積み重ねていく長距離走に近い取り組みです。だからこそ、最初の一歩で完璧を目指すのではなく、「まずは小さくやってみる」「困ったときは相談できる相手を持つ」というスタンスが大切になります。
もし今、「現場DXとは何か」を知りたい段階から一歩進んで、「自社ならどこから始めるべきか」を考え始めているのであれば、ぜひ伴走ナビの無料相談や資料請求をきっかけに、次のアクションへ進んでみてください。現場DXは、今日の小さな一歩から、確実に前に進めていくことができます。