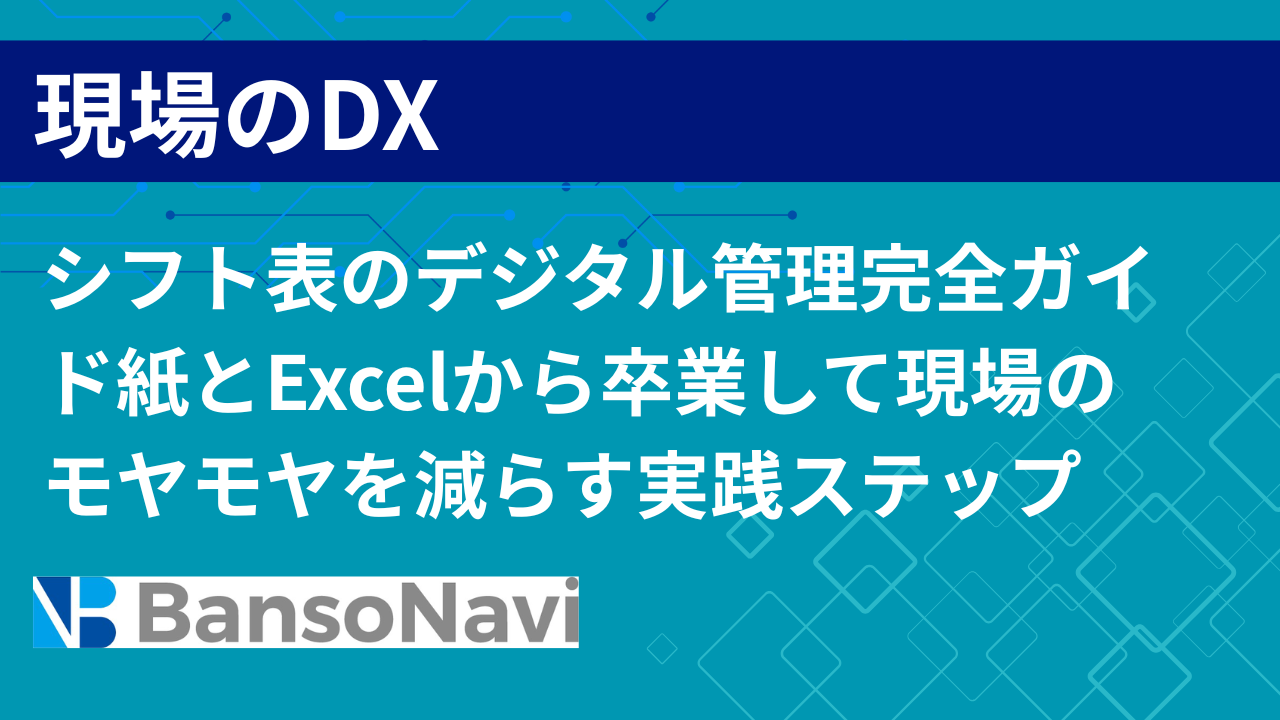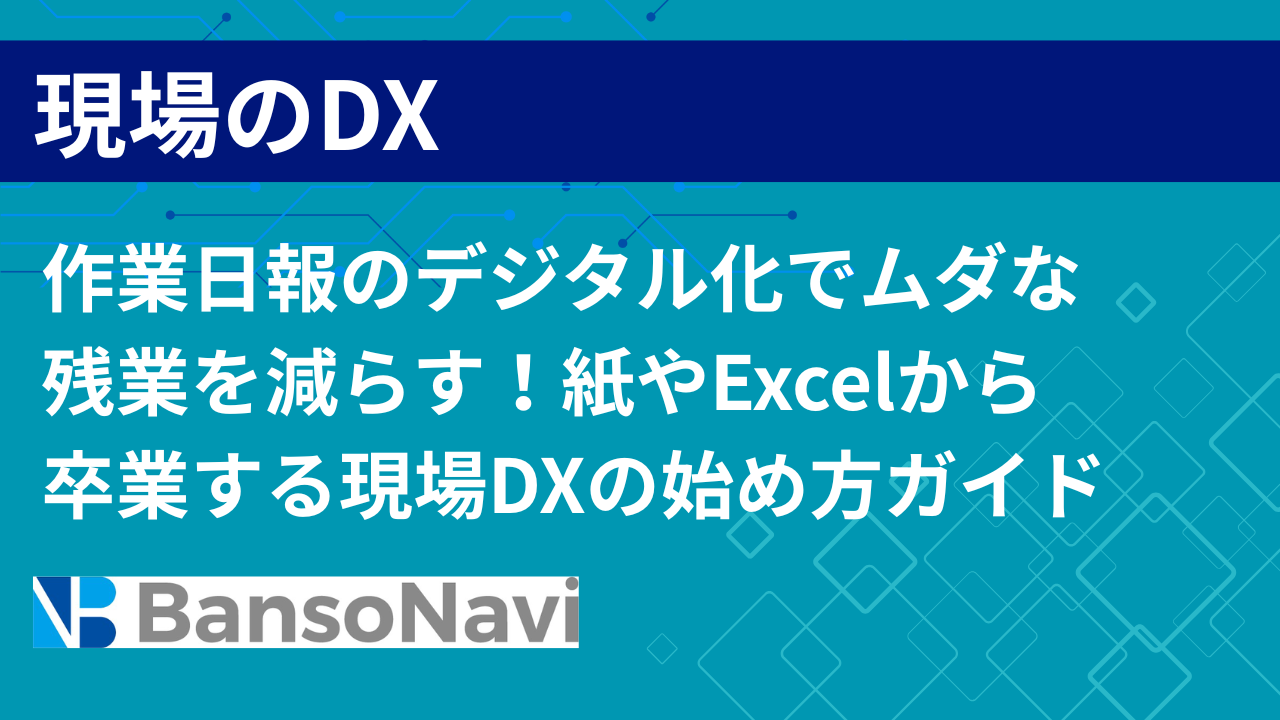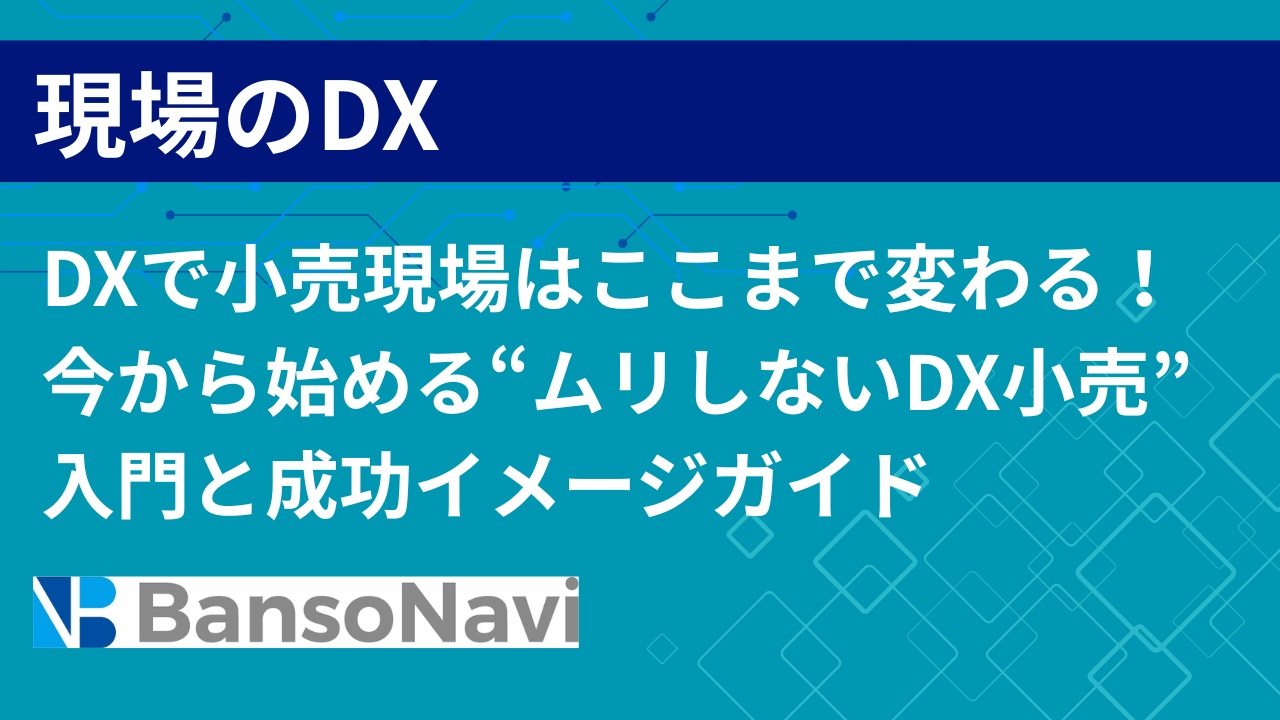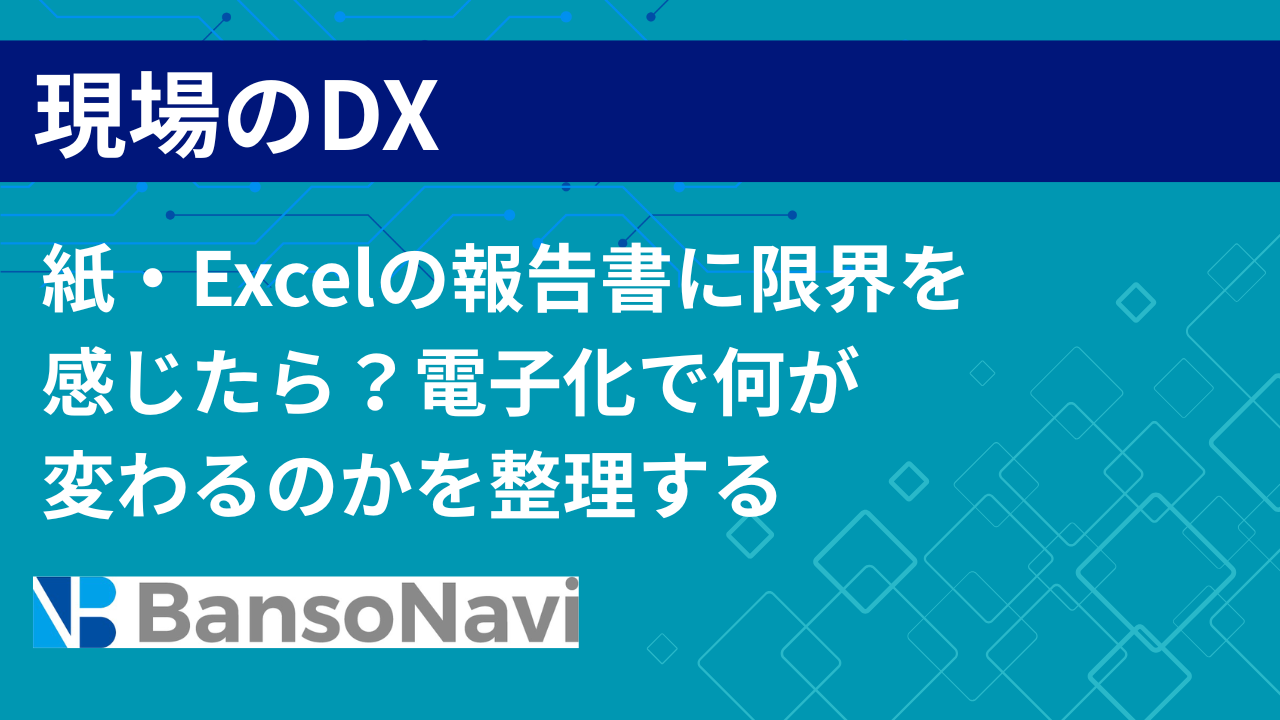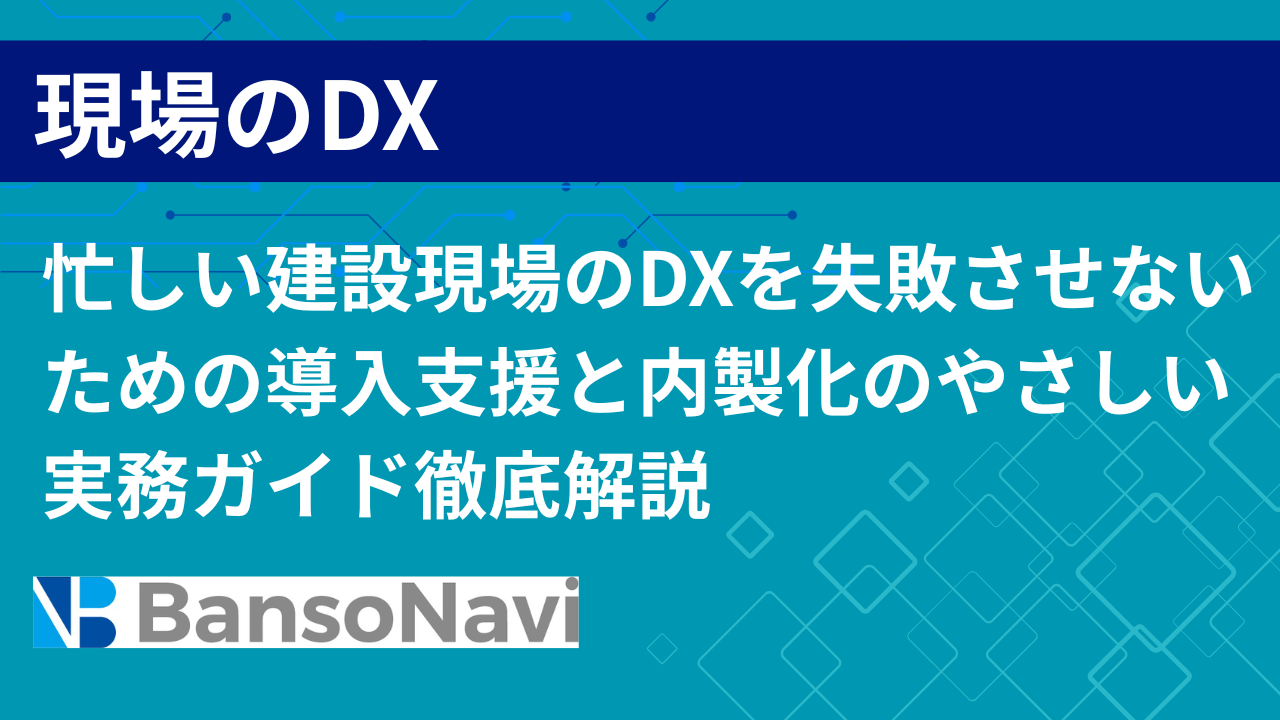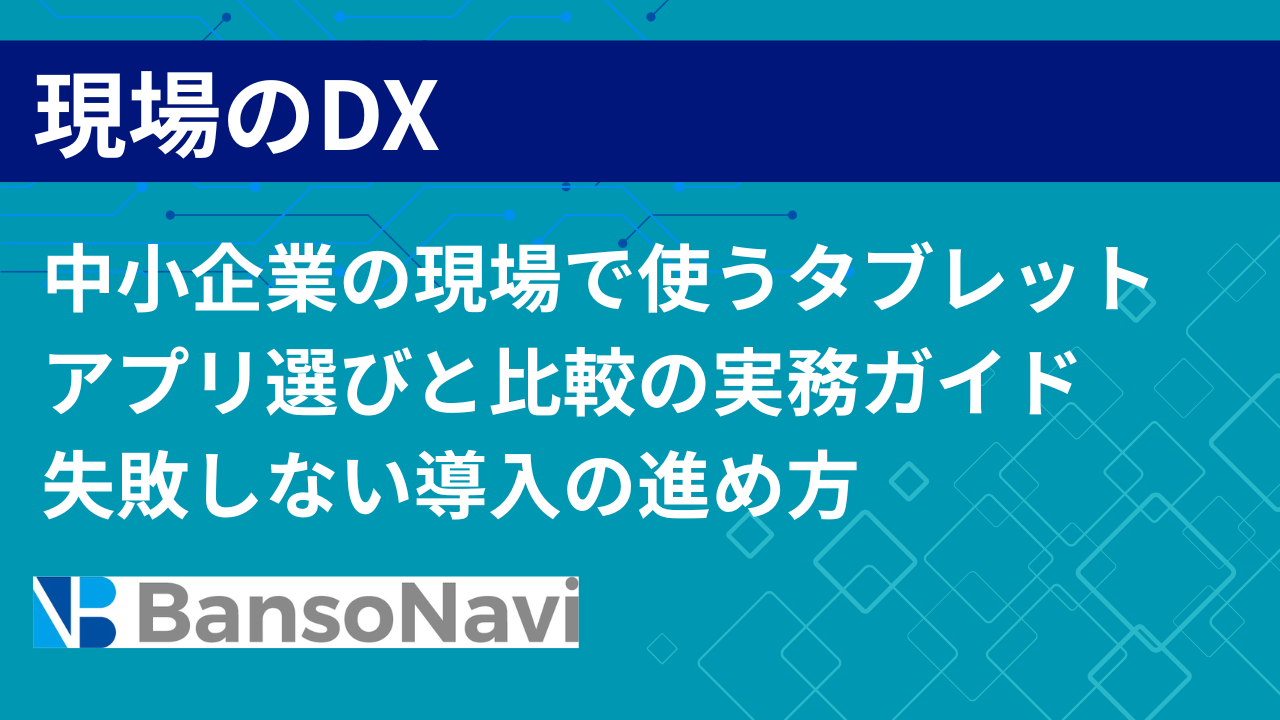中小企業の現場の進捗を見える化する管理ソフト比較と失敗しない選び方徹底入門ガイド
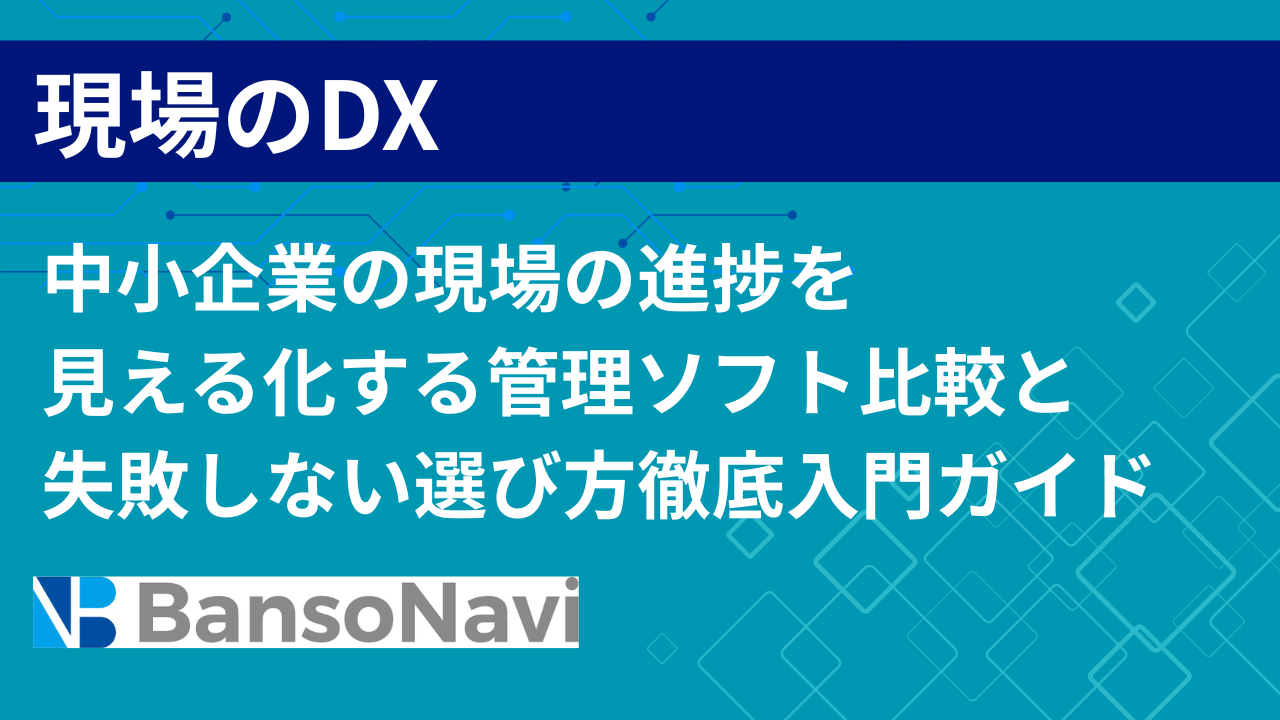
現場の進捗を紙やExcel、ホワイトボードやLINEで何とか回していると、「今日は回ったけれど、本当にこれでいいのかな」とモヤモヤする場面が増えてきます。案件や現場が増えるたびに連絡も集計も複雑になり、担当者の頭の中だけで管理している部分がどんどん増えていきます。
一方で、進捗を管理するソフトやアプリを調べてみても、横文字のサービス名が並び、機能も料金もバラバラで、「結局うちには何が合うのか」「どれを比べればいいのか」が分からないまま時間だけが過ぎてしまいがちです。
この記事では、現場のITリテラシーが高くない中小企業の方向けに、進捗を見える化するためのソフトの選び方を、できるだけやさしい言葉で整理します。「なぜ必要なのか」から始めて、「どんなタイプがあるのか」「何を基準に比較すればいいのか」「kintoneを使って自社に合う形に育てていく方法」まで、流れで理解できるようにまとめます。
読み終わる頃には、「完璧な一本を探す」のではなく、「自社の現場にちょうどいい進め方」をイメージできる状態を目指します。
目次
現場の進捗管理でよくある悩み
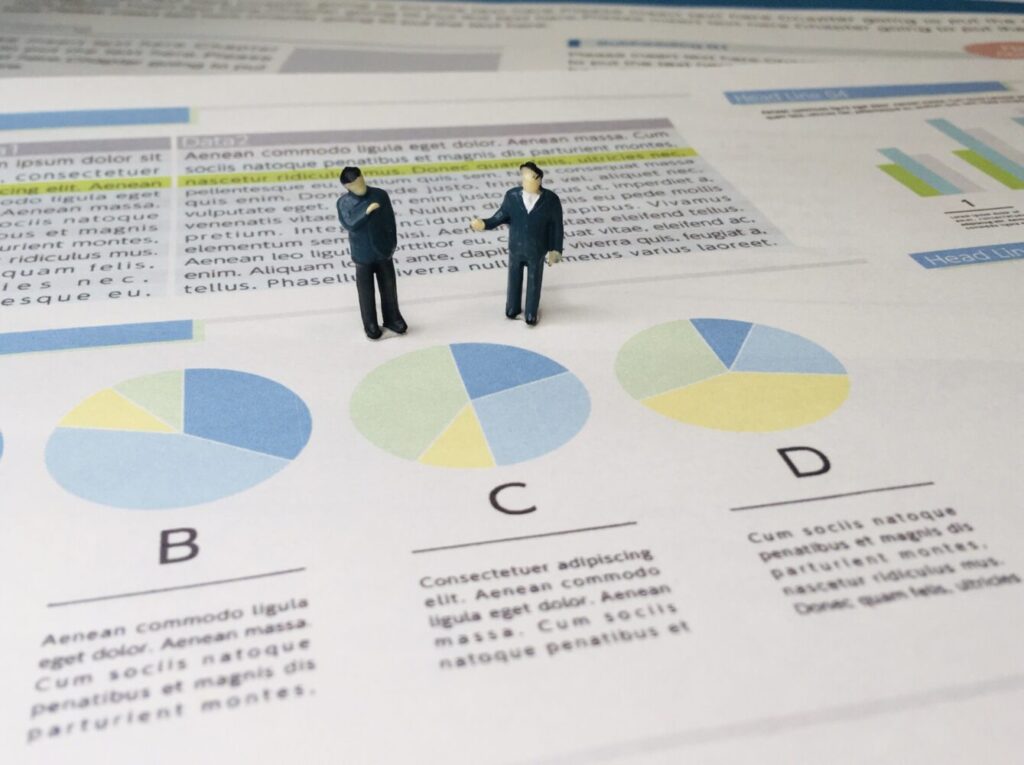
まずは、今のやり方でどんなモヤモヤが起きているのかを整理しておくと、後でソフトを比べる時に「何のために入れるのか」がぶれにくくなります。感覚的な不満を言葉にしておくことで、社内のメンバーとも話しやすくなり、「なんとなく便利そうだから」ではなく「ここを改善したいから」という軸で比較できるようになります。
紙・Excel・ホワイトボード・LINEで起きる典型トラブル
紙やExcel、ホワイトボード、LINEなどを組み合わせて進捗を追いかけている現場では、一見すると毎日回っているように見えても、よくよく振り返ると同じ種類のトラブルが繰り返し発生しています。
例えば、紙の日報や作業指示書が現場と事務所の間を行き来するうちに紛失してしまい、「どこまで終わっているのか」を確認するだけで半日かかる、といったケースは珍しくありません。
Excelで一覧表を作っている会社でも、ファイルが増え過ぎてどれが最新版か分からなくなったり、更新する人によって書き方がバラバラになったりします。その結果、「表の数字は完了になっているのに、現場に行くと全然終わっていない」「誰がどの情報を直したのか分からない」といった食い違いが起こりやすくなります。
特に、月末や納期直前など忙しいタイミングでは、こうした小さなズレが積み重なり、大きな抜け漏れにつながってしまいます。
ホワイトボードで進捗を管理している場合も、一箇所のボードの前に情報が集まり過ぎて、「ボードを見られる人」と「遠方の拠点や在宅で働いている人」との間で情報格差が生まれます。写真を撮ってLINEで共有していても、画像が流れていくだけで探しづらくなり、「確かに共有したはずだけど、どこにあるか分からない」という状態になりがちです。
また、LINEなどのチャットだけで進捗を追いかけていると、大事な決定事項が雑談や他の話題に埋もれてしまいます。メンバーが増えるほど通知も増え、誰がどこまで読んだのか分からないまま時間が過ぎていきます。
結果として、「聞いた・聞いていない」「言った・言っていない」といったすれ違いが増え、残業ややり直しに跳ね返ってしまいます。
ソフトを選ぶ前に自社の状況を言語化する
世の中のサービスをいきなり一覧で比較する前に、まずは自社の状況をざっくりと言葉にしておくことがとても大切です。ここを飛ばしてしまうと、「有名だから」「安かったから」といった理由だけで決めてしまい、後から「現場には難し過ぎた」「うちには機能が多過ぎた」と感じてしまうことになります。
少し時間を取って、現場メンバーと一緒に簡単な棚卸しをしてみましょう。
業種・人数・拠点数で管理範囲を決める
最初に考えたいのは、「何をどこまで見える化したいのか」という範囲です。例えば、製造業の場合は、受注から出荷までの一連の工程を追いかけたいのか、それとも一部の重要工程だけが分かればよいのかで、必要な項目や画面の作り方が変わってきます。
建設業であれば、現場ごとの進捗だけでなく、写真や報告書、原価情報までまとめて見たいのかどうかで、選ぶソフトのタイプが変わることも多いです。
人数や拠点数も重要な要素です。数人のチームで一つの現場だけを見ている場合と、数十人が複数の現場を並行して担当している場合では、必要になる機能の粒度が違います。前者であれば、シンプルなタスク管理に近い形でも十分回るかもしれませんが、後者では、「誰が・どの現場で・どの作業を・いつまでにやるのか」を一覧で見られる仕組みがないと、すぐに限界が来てしまいます。
さらに、「進捗の遅れにどう気づきたいか」も整理しておきたいポイントです。毎朝のミーティングで一覧を見ながら確認したいのか、遅れが出たときにだけ担当者へ通知が飛べばよいのか、管理職だけが全体を把握できればよいのか、あるいは現場メンバー全員が自分の担当状況をスマホで確認できる状態にしたいのか。
ここを決めておくと、後で画面レイアウトや通知の仕組みを考えるときに迷いにくくなります。
よく使われる進捗管理ソフトのタイプ

自社の状況をざっくりと言葉にできたら、次は世の中にどんなタイプのソフトがあるのかをざっくり把握しておきましょう。最初から細かな機能差を追いかける必要はありません。「だいたい三つくらいのタイプがあって、それぞれこんな現場に向いている」と理解しておくだけでも、候補を絞り込みやすくなります。
工程表型・タスク型・ノーコード型の比較
一つ目は、工程表やガントチャートと呼ばれる画面で、横に時間軸、縦に案件や工程が並ぶタイプです。製造や建設など、流れが比較的決まっている仕事で、いつどの工程に着手し、いつ終わるのかをバーの長さで表現したい場合によく使われます。
工程ごとの開始日と終了日、担当者、進捗率などを登録しておくことで、「今どこまで来ているか」「どこが遅れているか」を俯瞰しやすいのが特徴です。一方で、細かな仕様変更やイレギュラーが頻繁に起こる現場では、バーの修正が追い付かず、更新が止まってしまうこともあります。
二つ目は、タスクやカードを並べて管理するタイプです。かんばん方式とも呼ばれ、「未着手」「作業中」「完了」といった列にカードを移動させていくシンプルな画面が代表的です。
作業一つひとつの粒度で「誰が何をやるか」を分けて管理できるので、比較的小さなチームや、案件ごとにやることが変わりやすい現場で使いやすい傾向があります。ただし、タスクが多くなり過ぎると、全体像が見えにくくなり、「結局どの案件が遅れているのか」が分かりづらくなることもあります。
三つ目は、ノーコードと呼ばれる業務アプリのプラットフォームを使い、進捗管理の仕組みを自社用に組み立てるタイプです。kintoneのようなサービスが代表例で、案件管理や作業指示、日報、チェックリストなどを一つの土台の上で組み合わせていけるのが強みです。
最初はテンプレートやひな形をベースにスタートし、現場の声を聞きながら少しずつ項目や画面を変えていけるので、「やってみないと正解が分からない」現場との相性が良い形です。その一方で、ある程度社内に「設計する人」がいないと形にしづらく、最初の立ち上げには外部パートナーの力を借りた方がスムーズなケースも多くあります。
機能・費用・サポートの比較ポイント

タイプごとの違いが見えてきたら、いよいよ具体的なサービスを比較していきます。この時、「機能表を隅から隅まで読み込む」のではなく、「自社にとって外せないポイントはどこか」を決めてからチェックするのがおすすめです。
細かな画面の違いよりも、運用に乗せたときに困らないかどうかを中心に見ていきましょう。
チェックしておきたい三つの観点
まずは機能面です。すべての機能を使いこなす必要はなく、「最初の一年で本当に使う部分」がきちんと揃っているかを確認しましょう。例えば、案件ごとのステータス管理、担当者の割り当て、期日の設定、簡単なコメントや添付ファイルの共有など、日々の進捗を追いかけるうえで最低限必要な項目がストレスなく入力できるかどうかが大事になります。
画面が複雑過ぎて入力が面倒だと、どんなに高機能でも現場では続きません。
次に費用の見方です。月額料金や初期費用だけでなく、「社内でどれくらい時間を使うか」という隠れたコストも含めて考えると、判断がしやすくなります。例えば、導入後の三ヶ月間は、現場メンバーへの説明会やマニュアル作成、試運転のための打ち合わせなどに時間を割く必要があります。
ここを「投資」として見込んでおかないと、「忙しくて誰も触れないまま契約期間だけが過ぎていく」といったもったいない状況に陥ってしまいます。
最後に、サポートや他システムとの連携です。運用を始めてから出てくる細かな疑問に対して、日本語で相談できる窓口があるかどうか、メールだけでなくオンラインミーティングなどで画面を一緒に見ながら相談できるかどうかは、リテラシーが高くない現場ほど大きな安心材料になります。
また、既に使っている基幹システムや会計ソフト、チャットツールなどと連携できるかどうかも確認しておくと、二重入力を減らしやすくなります。いきなり難しい連携を組む必要はありませんが、「将来的にここまでできると楽になりそう」というイメージを持っておくと、選ぶときの参考になります。
代表的な現場タイプ別の選び方

ここまでの話を踏まえて、「うちの現場に近いのはどんなパターンか」をイメージしてみましょう。全ての会社がきれいにどれか一つの型に当てはまるわけではありませんが、似たような状況の事例を知っておくと、社内で話し合う際のたたき台にしやすくなります。
製造・建設・サービスのストーリー
製造業の例を考えてみます。例えば、小さな工場で少人数が多品種少量の製品を作っている場合、最初から全ての工程をシステムに登録するのはハードルが高いかもしれません。
この場合は、まず受注単位で「いつまでに出荷するか」「今どの工程にあるか」だけを見える化し、ボトルネックになりやすい工程だけを詳しく管理するところから始めると、現場の負担を抑えながら効果を実感しやすくなります。ある程度慣れてきたら、検査や出荷など周辺の工程に範囲を広げていくイメージです。
建設業では、一つの会社が複数の現場を同時に抱えているケースが多く、「どの現場で誰がいつ作業しているか」を把握することが大きなテーマになります。ここでは、工程表型のツールで全体のスケジュールを俯瞰しつつ、現場ごとの日報や写真、報告書を集められる仕組みを組み合わせると効果が出やすくなります。
現場監督がスマホから簡単に入力できる画面があるかどうか、写真やチェックリストをその場で登録できるかどうかが、定着の成否を分けるポイントです。
サービス業や店舗ビジネスでは、シフトや予約、当日の作業内容など、人の動きとお客様の予定が絡み合う形で進捗が決まっていきます。この場合、タスク型のツールで「今日やるべきこと」を見える化しつつ、店舗ごと・スタッフごとに負荷が偏っていないかを確認できる画面があると便利です。
また、来店数や売上などの数字と合わせて進捗を見られるようにしておくと、「どの施策が効果につながっているか」を振り返りやすくなります。最初は紙のチェックリストをそのまま画面に移し替えるイメージで始め、徐々に集計や分析に活用していくのが現実的です。
kintoneと伴走ナビで進捗管理を内製化する

ここまで読んで、「うちの現場はやってみないと正解が分からない」「業務の流れが頻繁に変わる」と感じた方には、ノーコード型のプラットフォームを使って、少しずつ自社に合う形に育てていく進め方も検討する価値があります。
特にkintoneは、案件管理や日報、チェックリストなどのアプリを組み合わせることで、一つの画面に近い感覚で現場の状況を見える化できるのが特徴です。
ひな形+伴走支援で現場に合わせて育てる
kintoneを使った進捗管理の良さは、「最初から完璧な設計をしなくてよい」という点にあります。まずは、よくある業務フローをもとにしたひな形アプリをベースに、案件一覧や作業指示、日報など最低限必要なアプリだけを用意します。
そのうえで、実際に現場メンバーに触ってもらい、「ここは入力が面倒」「この項目が足りない」といった声を拾いながら、少しずつ項目や画面を調整していきます。このサイクルを回しやすいことが、ノーコード型の大きな強みです。
ただし、社内だけでゼロから設計しようとすると、「どこから手をつければいいか分からない」「作ってみたものの、いまいち業務にフィットしない」という壁にぶつかりがちです。そこで、現場DXや内製化の支援をしているパートナーと一緒に進めると、最初の設計や運用ルール作りをショートカットしやすくなります。
伴走ナビでは、これまで多くの中小企業の現場でkintoneを活用してきた事例をもとに、「まずはこの範囲から」「この順番で広げていきましょう」といった具体的なプランを提案し、定例ミーティングなどで一緒に改善を続けていくスタイルを取っています。
このように、最初は外部の力を借りながらも、最終的には社内で運用や改修ができる状態を目指すと、「ツールを導入して終わり」ではなく、「自分たちで現場に合わせて育てていける仕組み」が手に入ります。結果として、業務の変化にも柔軟に対応できるようになり、新しいサービスや働き方にチャレンジしやすい土台が整っていきます。
まとめ|自社に合う進捗管理の形を選ぶ
進捗を見える化するソフトは、世の中に本当にたくさんありますが、大事なのは「どれが一番すごいか」ではなく、「自社の現場にとってちょうどいいかどうか」です。紙やExcel、ホワイトボードやLINEで感じているモヤモヤを具体的に言葉にし、自社の業種や人数、拠点数、仕事の流れを踏まえたうえで、無理なく続けられる形を選ぶことが何よりも重要です。
そのうえで、工程表型・タスク型・ノーコード型といった大まかなタイプの違いを知り、機能・費用・サポートといった観点から「外せない条件」を整理しておくと、情報に振り回されることなく比較検討を進められます。
特に、業務の変化が激しい現場や、やってみながら形を整えていきたい会社にとっては、kintoneのようなノーコード基盤を使って内製化していく進め方が、長い目で見て柔軟で費用対効果の高い選択肢になりやすいでしょう。
「とはいえ、自社だけでやるのは不安」「どこから手を付ければいいか分からない」と感じる場合は、外部のパートナーに相談してみるのも一つの手です。伴走ナビでは、事例豊富なコンサルタントが現場の状況を一緒に整理し、kintoneをはじめとするツールを使った進捗管理の仕組み作りやDX内製化を支援しています。
興味があれば、まずは画面越しにざっくばらんに話ができる無料相談や、具体的な事例や進め方をまとめた資料請求から、一歩を踏み出してみてください。