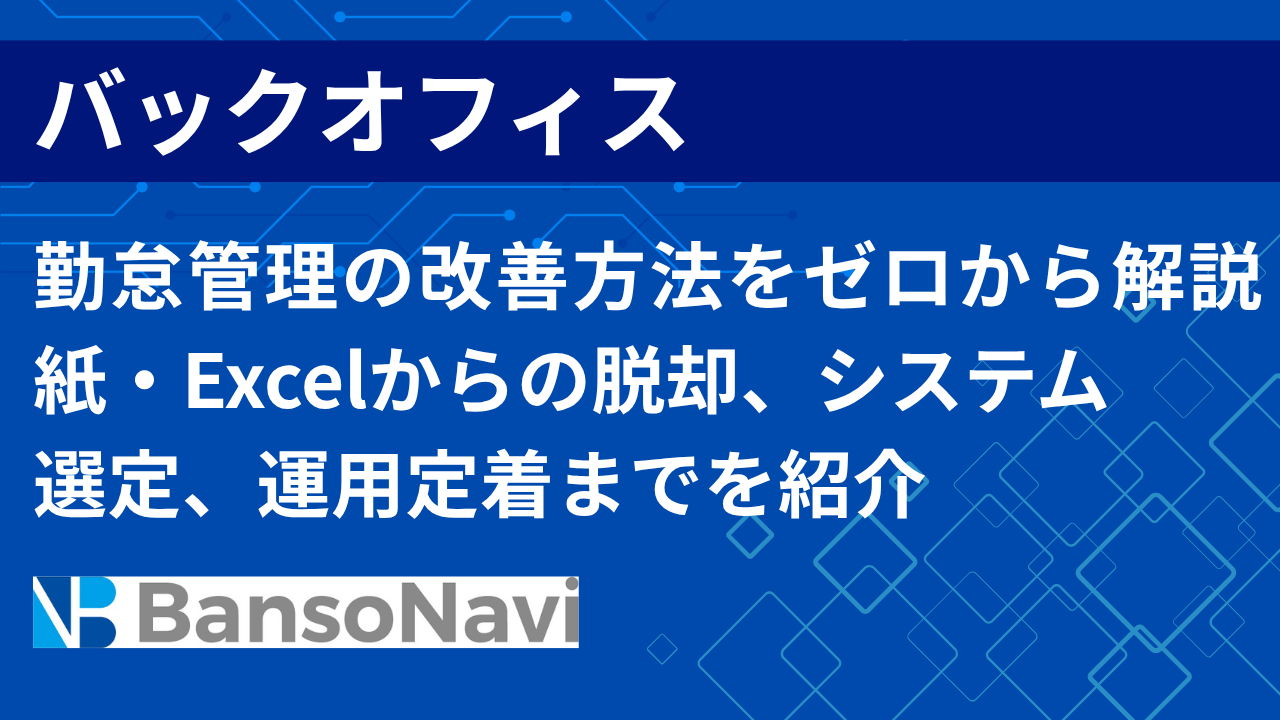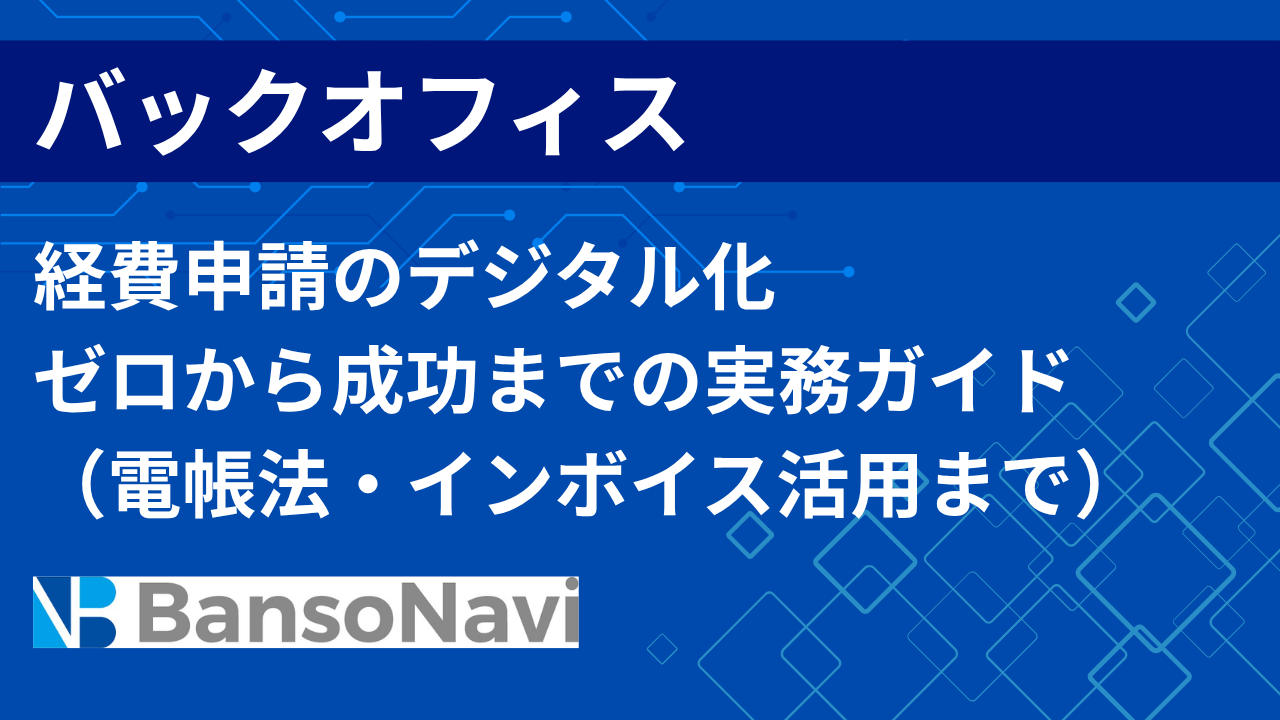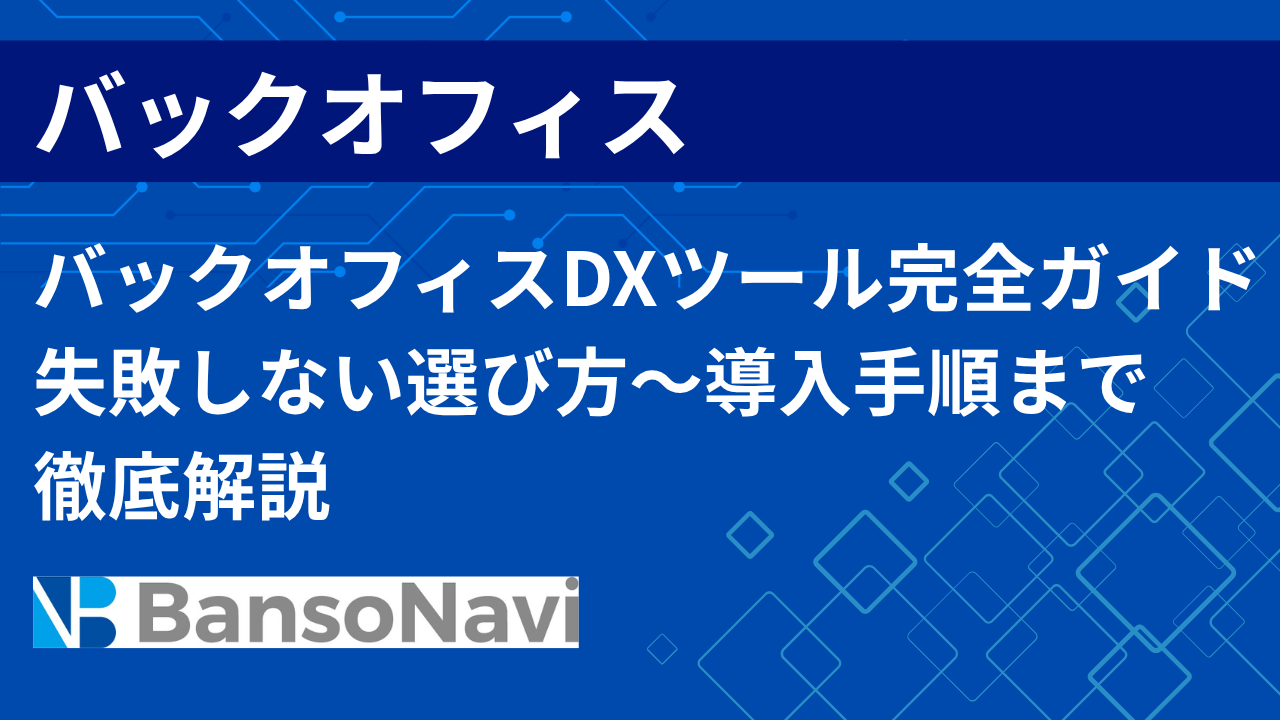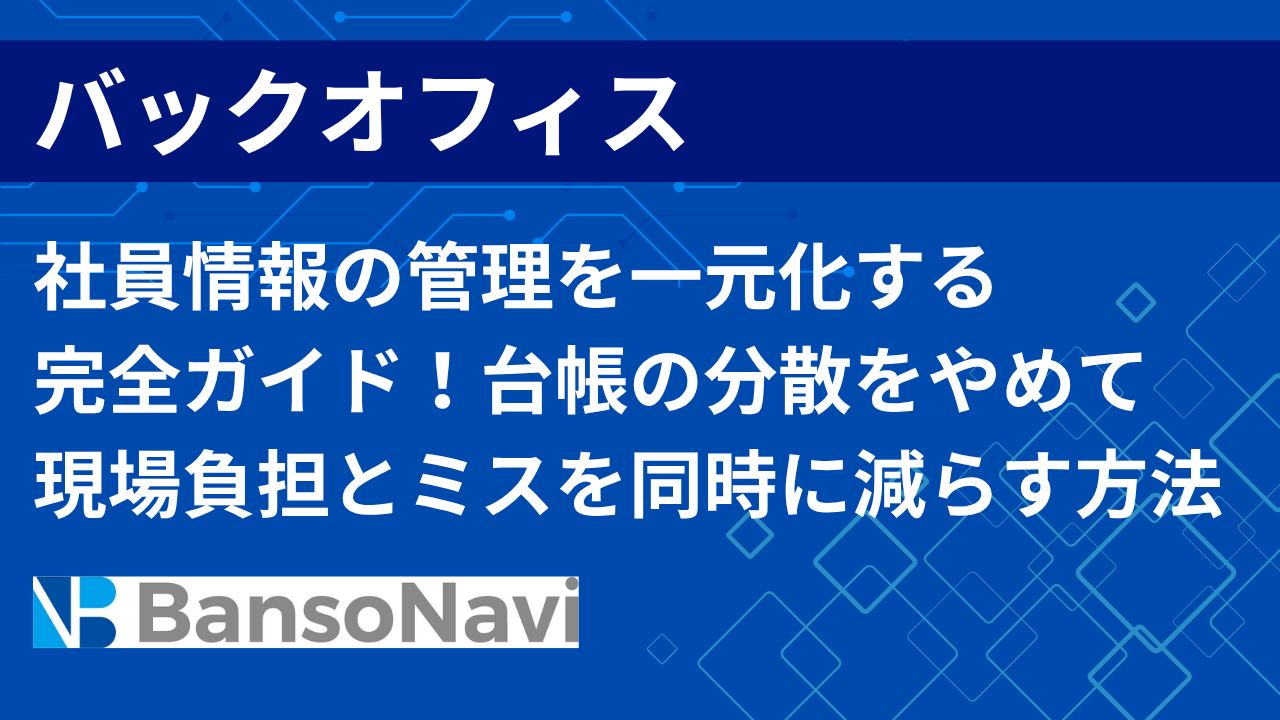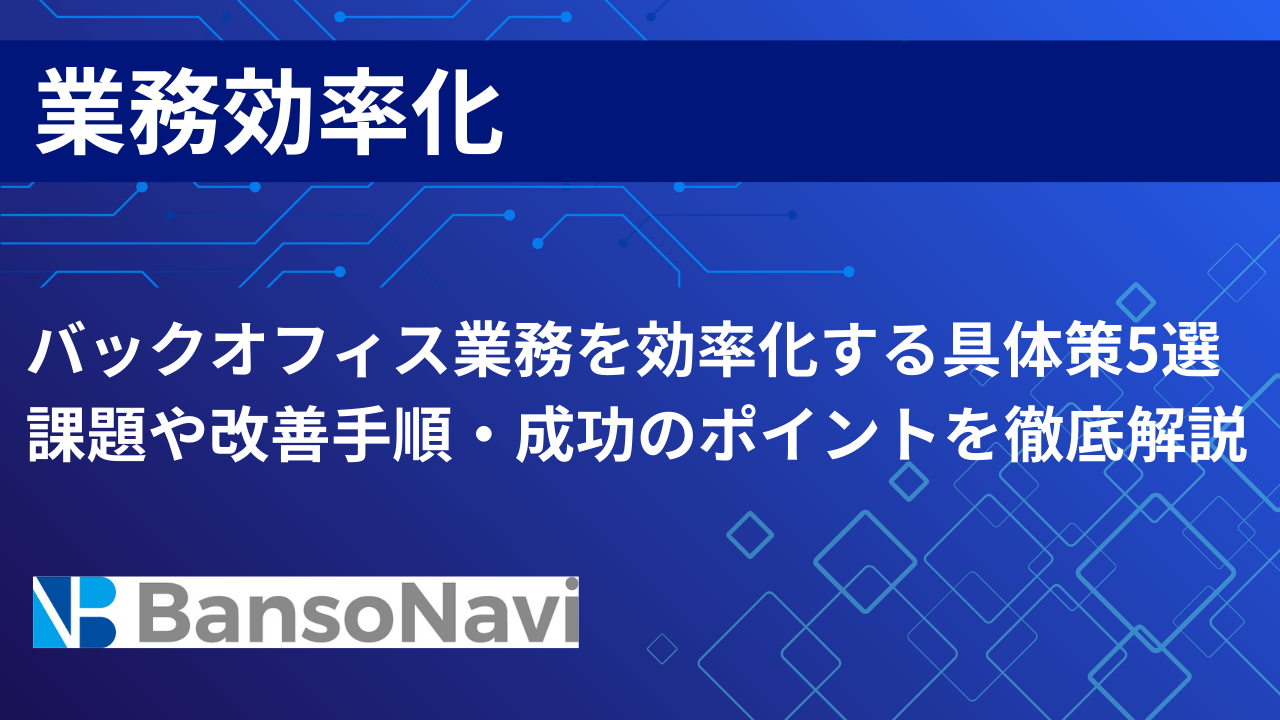勤怠管理ツールのおすすめ10選を比較|選ぶ際のポイントや費用相場も解説
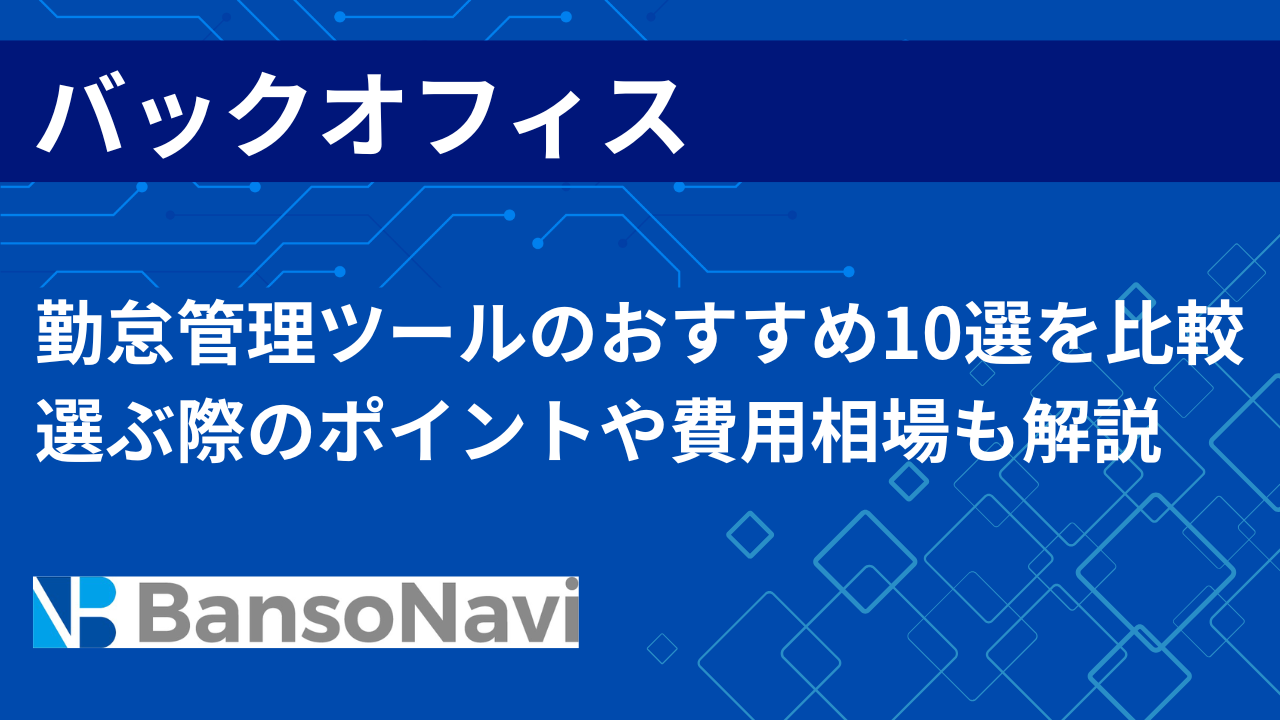
承認作業や締め処理が滞り、紙や表計算の限界を強く感じていませんか。
人事の現場では、以下の悩みがよく挙がります。
「勤怠管理ツールのおすすめを知りたい」
「選び方や費用相場の目安を知りたい」
本記事では、中小企業向けと大企業向けのおすすめの勤怠管理ツールの特徴・打刻方法・サポート・料金を比較します。また、選ぶ際に確認すべきポイントも解説しているため、参考にしてみてください。
また、勤怠管理ツール選びでお悩みの企業・人事担当は、伴走ナビに相談へご相談ください。
目次
【中小企業向け】勤怠管理ツールのおすすめ5選を比較

紙や表計算からの卒業を急ぎたい中小企業向けに、導入しやすさと運用の安定性を軸に比較します。
まずは今回取り上げる5製品の見出しを一覧で確認してください。
- kintone
- ジョブカン勤怠管理
- マネーフォワード クラウド勤怠
- KING OF TIME
- ジンジャー勤怠
ここからは各ツールの強みと相性を詳しく解説します。
自社の勤務形態や申請フローに照らし、導入後の運用を具体的にイメージしながら読み進めてください。
kintone|勤怠管理以外にも利用可能

kintoneは、社内の業務アプリを自由に組み立てられるため、勤怠だけで終わらず日報や申請のワークフローまで整えられます。
主に、タイムカードのテンプレートを起点に、出退勤入力と勤務時間の自動集計、承認まで一連で扱える点が魅力の1つです。さらに、現場ごとの運用方針に合わせて画面項目や承認経路を変えられるため、導入後の微修正も可能です。
そのため、勤怠データと他の業務データを並べたい企業や、部署ごとに異なる運用を持つ組織におすすめのツールです。
kintoneの利用料金は下記のとおりです。
- ライト月額1,000円/ユーザー
- スタンダード1,800円/ユーザー
※最小契約ユーザー数は10(2024年改定)
ジョブカン勤怠管理|さまざまな業務形態に対応している

ジョブかん勤怠管理は、モジュールを組み合わせて使えるため、勤怠管理からシフト管理・有休管理・工数管理まで段階的に広げられます。
拠点や雇用形態が混在している場合であっても、打刻方法や申請の流れをそろえやすい点が魅力の1つです。
料金は選ぶ機能によって変わるため、必要に応じてコストを管理できます。また、店舗と本社が分かれる体制や、夜間を含む勤務が多い現場と相性が良いです。
そのため、将来的な機能拡張を見据えた上で、まずは勤怠から始めて運用を固めたい企業におすすめのツールです。
マネーフォワード クラウド勤怠|スマホ・ICカードでも打刻できる

マネーフォワード クラウド勤怠は、スマホアプリやICカードの打刻に対応しているため、外出が多いスタッフの記録を現場で管理できます。
さらに、会計や給与と同シリーズで連携できるため、手入力の手間や時間を削減できます。
管理画面は申請と承認が見渡しやすく、締め前の未処理を早めに把握しやすい構造です。そのため、既にマネーフォワードを使う企業は導入の手間が少なく、バックオフィス全体の流れをそろえられます。また、少人数で始めて人数増加に応じて機能を拡張したい企業にもおすすめです。
参考:無料で試せる勤怠管理システム – マネーフォワード クラウド勤怠
KING OF TIME|利用者数410万人以上の実績がある

KING OF TIMEは、クラウド型の勤怠管理ツールの代表格であり、初期費用を抑えつつ必要機能を広く使用できます。
主に、残業管理・有休管理・シフト作成・ログ連携など実運用で必要な機能を一通り搭載している点が魅力の1つです。さらに、使い始めの教育に時間を割けない企業でも、打刻と申請の流れを早く定着させやすい設計になっています。
価格体系が分かりやすく稟議の作成もしやすい点も魅力的です。また、人数が増えても運用が崩れにくいので、成長中の企業や拠点追加を予定する企業におすすめのツールです。
参考:勤怠管理・人事給与システム市場シェアNo.1 KING OF TIME
ジンジャー勤怠|マルチデバイスに対応している

ジンジャー勤怠は、パソコンやスマホに加え、位置情報を使ったタブレットやICカードによる打刻にも対応しています。そのため、現場作業や訪問が多い働き方であっても、所定の場所のみで打刻させたい要望に対応できます。
さらに、画面の構成が直感的になっているため、初めて操作する従業員でも手軽に操作が可能です。また、シリーズ内で人事や労務の機能と組み合わせやすいため、人事データの分断を避けたい企業に適しています。
これから申請フローの見直しと合わせて導入したい場合や、就業パターンが複数ある現場には導入がおすすめです。
参考:クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」|jinjer株式会社
【大企業向け】勤怠管理ツールのおすすめ5選を比較

拠点や雇用区分が多い大企業では、就業規則の分岐や承認の段階が複雑になりやすいです。
人事や給与との連携、監査に耐える履歴管理も欠かせません。
ここでは次の五製品を取り上げ、運用の作りやすさとガバナンスの観点で整理します。
- TeamSpirit 勤怠
- COMPANY
- キンタイミライ
- WiMS/SaaS
- TimePro-VG
ここから各製品の強みと相性を解説します。自社の規程や承認フロー、監査要件に照らし合わせた上で検討してみてください。
TeamSpirit 勤怠|2,000社以上が契約した実績がある

TeamSpirit 勤怠は、勤怠と工数と経費を一体で扱い、部門横断のデータ共有を進められます。
これまでに2,000社以上の企業に導入された実績があり、規模拡大後も運用がぶれにくい点が魅力の1つです。さらに、項目や画面はSalesforce上で柔軟に調整でき、複数の就業ルールにも合わせやすくなっています。
Slack連携で打刻や承認通知を受け取れ、確認の抜けを減らせるため、プロジェクト別の実績集計と原価の把握にも最適です。
参考:勤怠管理・工数管理・経費精算ならTeamSpirit(旧チムスピ)
COMPANY|勤怠管理以外にも人事管理や給与計算などに対応している

COMPANYは、人事と給与と勤怠を同じ基盤で扱い、マスタのずれを抑えることが可能です。さらに、フレックスや裁量労働、在宅勤務など多様な就業に標準機能で対応します。
人事異動や制度改定の際も履歴と承認経路を連続させやすいため、運用にかかる手間が少ないことが特徴的です。また、タレントマネジメントや手続き管理と連携し、採用から退職までの情報の流れを一元化させられます。
キンタイミライ|導入担当者がいるため安心して利用できる

キンタイミライは、大規模法人での採用が進んでおり11年連続で3,000人以上の大企業に選ばれています。
専任の導入支援がついているため、初めて導入する企業でも要件整理から設定までスムーズに進められます。さらに、勤務間インターバルや年休取得の計画、残業予測など現場運用に根差した機能がそろっていることが特徴的です。
個別手当や複雑なルールにも対応しているため、現場の入力と管理者の確認の負担を削減できます。
参考:キンタイミライ/大企業シェアNo.1のクラウド勤怠管理システム
WiMS/SaaS|過重労働アラート機能がある

WiMS/SaaSは、過重労働アラートで長時間労働の兆しを早期に抽出できることが魅力的です。また、三六協定の上限や勤務間インターバルの不足も自動で警告します。
ダッシュボードで労働時間や年休の分布を把握できるため、月次締め前に是正へ動かすことが可能です。さらに、地図オプションで直行直帰の位置情報を記録し、打刻位置の把握や走行距離の可視化にも対応します。
TimePro-VG|中堅企業から大企業まで幅広く利用できる

TimePro-VGは、管理画面が操作しやすい設計になっているため、初めて導入する企業でも扱いやすいことが特徴的です。また、クラウドとオンプレの両構成に対応しており、既存の基盤に合わせた導入も可能です。
残業や年休の状況を段階でチェックし、労働基準法違反の予兆も見込み計算で示します。
PCログと出退勤の乖離確認など監査目線の機能が充実しており、ダッシュボードでの遅刻や欠勤の傾向を長期間で可視化できます。そのため、人員配置や面談の判断で役立てることが可能です。
参考リンク:勤怠管理システムならアマノ「TimePro-VG」
勤怠管理ツールを選ぶ際に確認すべき4つのポイント

勤怠管理ツール導入前に見るべき軸を最初に決めると、候補の比較が進みます。
ここでは意思決定で迷いやすい四点を整理しました。これから勤怠管理ツールの導入を検討している企業は、参考にしてみてください
- 導入実績を確認する
- 操作性を確認する
- サポート体制を確認する
- 初期費用や運用費用を確認する
導入実績を確認する
勤怠管理ツールを選ぶ際は、公開されている導入社数やアクティブユーザー数、稼働年数を確認するのがおすすめです。特に、自社規模に近い事例と同業の事例が多いものであれば、自社との相性がいいツールになります。
導入後の失敗を避けるためには、担当部署へヒアリングを行い、利用部門が求める要件と過去の課題を数値で並べることが大切です。
操作性を確認する
操作性を確認するのも、勤怠管理ツールを導入する際に大切なポイントの1つです。
例えば、打刻は一分以内で完了・申請は三手順以内。承認は一覧から即判断などの基準を作成し、ツールを比較・評価すると、最適なものを選びやすくなります。また、スマホとパソコンの切り替えやICカードによる打刻読み取り精度などを確認するのが大切です。
また、「承認者の手作業が五分短縮×二十申請で月百分の削減」などの目安を決めておくと、社内説明が通りやすくなり、導入までスムーズになりやすいでしょう。
教育に使うマニュアルの量と動画の有無も確認します。
サポート体制を確認する
初期設定のサポート範囲や問い合わせの窓口、応答の平均時間などのサポート体制も確認しておきましょう。また、オンボーディングの回数や運用相談の可否、法改正時の設定変更サポートが含まれるかも確認するのが大切です。
この時、管理者向けの手順書やヘルプの充実度も評価対象に入れておくと、より導入や運用がスムーズになります。また、障害発生時の連絡経路や復旧の見込み提示、事後の報告書の提供があるかを確認するのも重要です。
運用を支える体制が明確になっている場合、担当者が交代してもスムーズな引き継ぎができます。
初期費用や運用費用を確認する
勤怠管理ツールにかかる初期費用と運用費用も、欠かさずに確認しておきましょう。
費用感を計算する際は、「ユーザー単価×人数×36ヶ月」に、打刻機器やICカード、システム連携の費用を考慮します。
例えば、1人月300円で50名で運用する場合、月額15,000円で3年(36ヶ月)で54万円になります。また、必要に応じてモジュール追加やアカウント追加の単価、最低料金の有無も加えることもおすすめです。
導入初年度は設定や教育に時間や手間がかかるため、社内工数も稟議に含めておくと適切な判断ができます。
勤怠管理ツールの費用相場

勤怠管理ツールの費用は、主に初期費用と月額費用の2つがあります。
まずは、相場の目安を押さえた上で、自社の人数や必要機能に合わせて総額を試算しましょう。
費用相場は下記のとおりです。
- 初期費用:数千〜数万円
- 月額費用:ユーザー1人あたり100〜400円
例えば、1人300円で50人の場合は、月1万5,000円で3年で54万円になります。この時、初期費用を1万円とすると合計は約55万円です。
計算式は「ユーザー単価×人数×36か月+初期費用」です。
ただし、実際の金額はユーザー数の増減やシフト・工数などの追加モジュール・他システムとの連携・サポート範囲などで変動します。そのため、導入前に必要機能の優先順位を整理し、複数社から同条件で見積を取り、3年総額で比較するのがおすすめです。
勤怠管理ツール選びでお悩みなら「伴走ナビ」へご相談ください!

勤怠管理ツールは、打刻や申請をリアルタイムで可視化し、勤怠管理の効率化や労務のリスクを早期発見に貢献します。また、勤怠管理ツールを選ぶ際は、業種や勤務形態、拠点数を考慮しておくことが大切なポイントです。
勤怠管理ツールの比較ポイントまとめ
- 導入実績と自社規模の近さ、同業の有無
- 操作フローの体験と教育の負担
- サポート範囲と法改正時の対応
これから勤怠管理ツールの導入を検討している企業は、判断を急がず、慎重に比較・検討するようにしましょう。
伴走ナビは要件整理・比較表作成・トライアル設計・社内説明の準備までサポートしています。さらに、見積の前提をそろえて、3年総額での比較もサポートしています。
勤怠管理ツール選びで悩んでいる企業は、「伴走ナビ」へご相談ください。