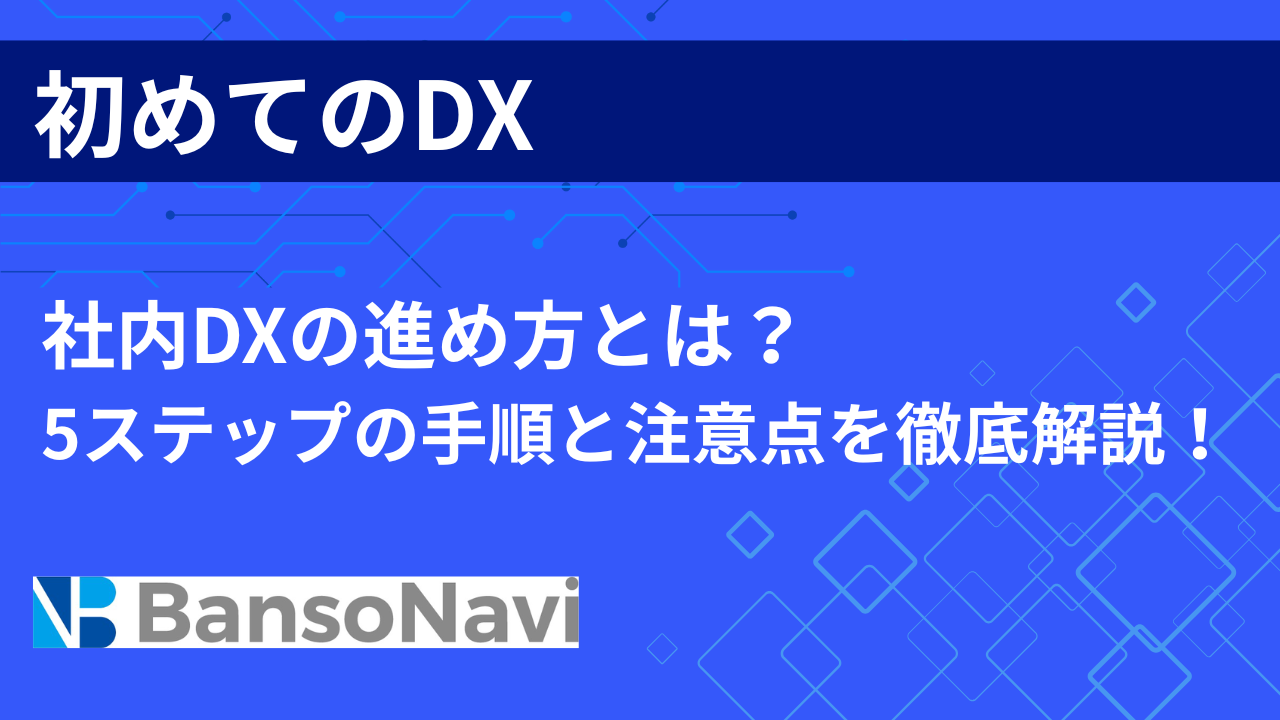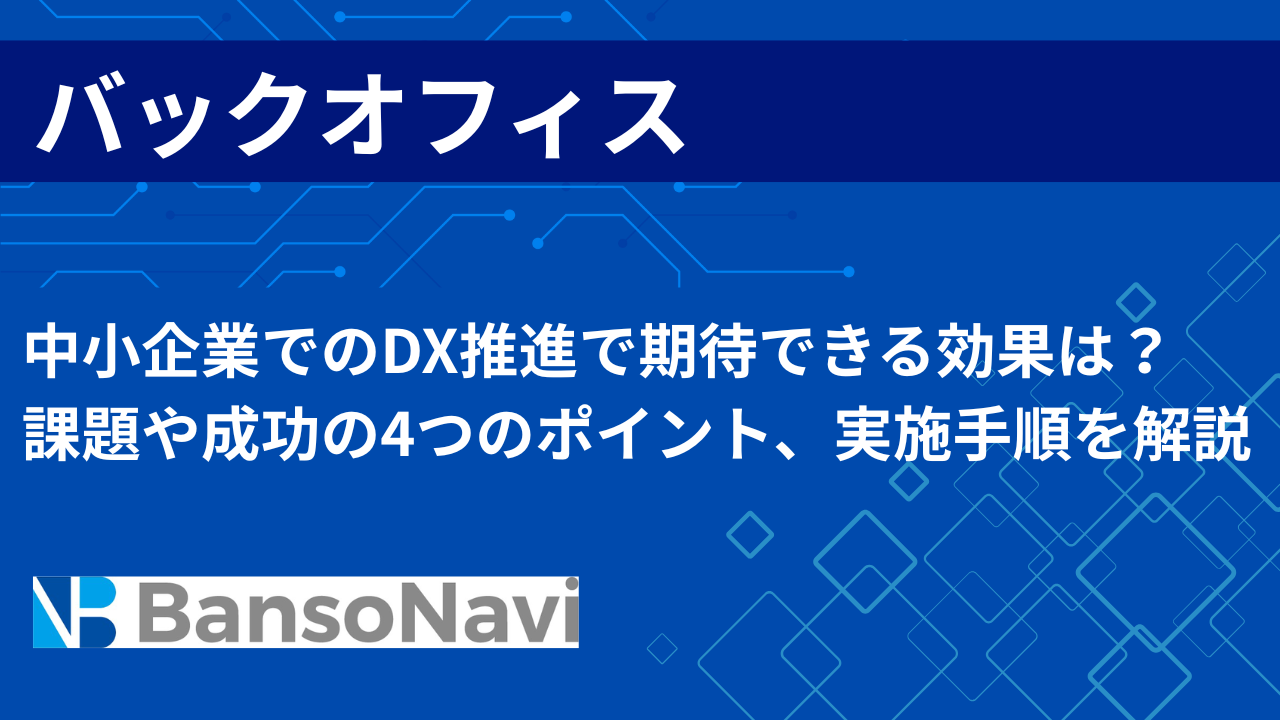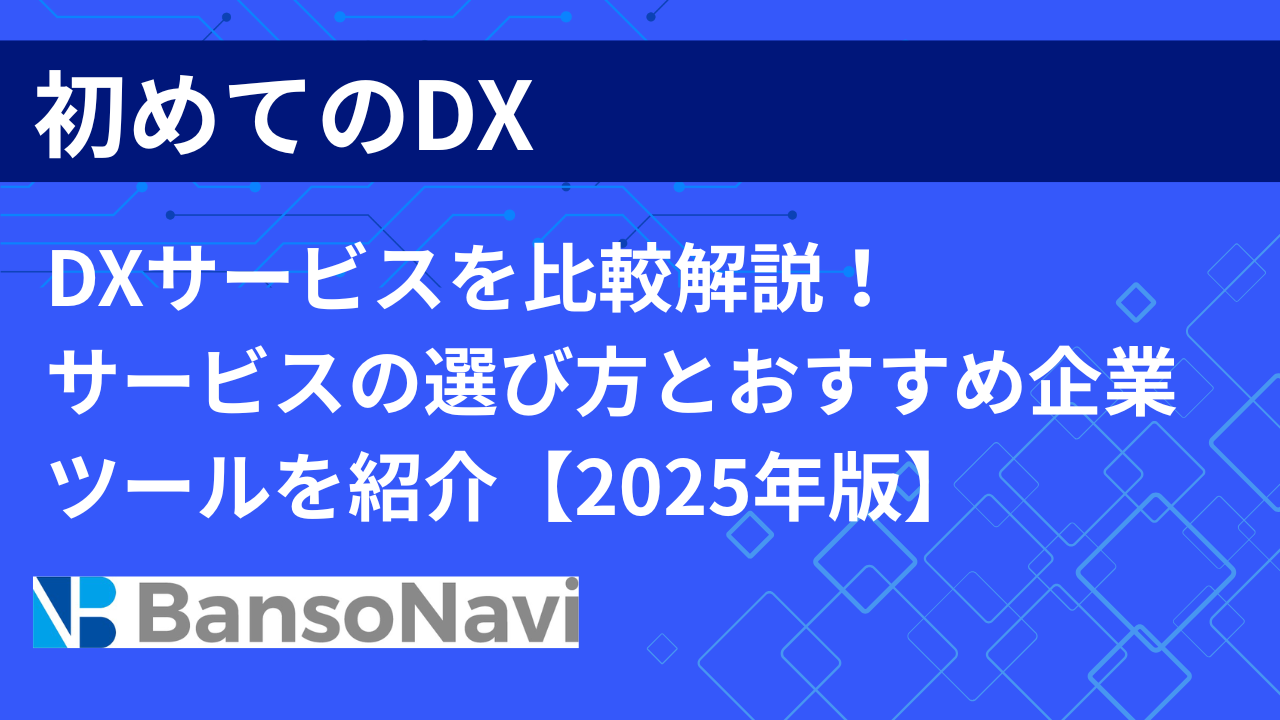DXは何から始める? 初心者でも分かる 7ステップと成功のポイントを徹底解説

「自社のDXを何から始めればいいのかわからない」
「DX推進の最初に行うべきことや、具体的な手順を知りたい」
このような悩みを抱えている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。
DXを進めることで、業務の効率化や新たな価値創出、企業の競争力向上につなげることが可能です。
本記事では、DXとは何かという基本的な知識から、具体的な推進ステップ、成功に欠かせないポイントまでを体系的に解説します。
DX推進の全体像を理解し、自社で何から着手すべきか判断するためにも、経営者や管理職、DX推進を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
また、DXを何から始めるべきか迷っている場合は、ぜひ「伴走ナビ」にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な一歩をご提案します。
目次
DXとは何から始めるか確認する前の基本知識

DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術を使ってビジネスの仕組みを根本から変え、新しい価値を生み出すことです。
単にITツールを導入するだけでなく、製品やサービス、業務プロセス、さらには企業文化までを変革し、競争で勝ち抜くための取り組みを指します。
この変革が求められる背景には、古いシステムが企業の成長を妨げる「2025年の崖」という問題や、顧客のニーズの多様化、デジタルを武器にする新規参入企業との競争などがあります。
多くの企業がDXの重要性を認識していますが、全社的な経営戦略として実行できている企業はまだ少ないのが現状です。
なぜ今、企業がDXを推進する必要があるのか、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
今、企業がなぜDXを推進するのか? やらない企業は生き残れない? – 伴走ナビ-DX人材の育成を実現するメディア
DX推進の具体的な始め方【7STEP】

DXを成功させるためには、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。ここでは、DX推進の具体的な始め方を7つのステップに分けて解説します。
- 経営層の理解とコミットメントを得る
- DXの目的を明確に設定する
- 推進組織・体制の構築を行う
- IT資産や業務の現状分析を行う
- スモールスタートでデジタル化を行う
- ビジネスモデルや業務フローの変革を実行する
- 継続的なPDCAを回す
この手順に沿って着実に進めることが、DX成功への近道です。
1.経営層の理解とコミットメントを得る
DXを始める際には、まず経営層がその重要性を深く理解し、全社で取り組む姿勢を示すことが重要です。
DXは部署単位の改善ではなく、会社全体を巻き込む長期的な変革です。経営層の強力なリーダーシップがなければ、必要な予算の確保や部署間の調整が難航します。
経営トップがDXの旗振り役となり、変革の明確な方向性を示すことで、従業員の理解と協力を得やすくなり、組織全体に変革の文化が根付きます。
2.DXの目的を明確に設定する
DXはあくまで手段であり、目的そのものではありません。
そのため「DXによって何を成し遂げたいのか」という目的を具体的に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままツールを導入しても、期待した効果は得られません。
会社のビジョンや経営戦略と結びついた目的を定めることで、各部署の取り組みに一貫性が生まれます。「顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」を明確にすることが、DX成功の土台となります。
3.推進組織・体制の構築を行う

DXは通常の業務と並行して進めるのが難しいため、専門の推進チームを設置することが重要です。
IT部門や事業部門が主導する形、あるいは独立した専門組織を立ち上げる形など、自社の目的に合った体制を選びましょう。部署を横断した連携体制を築くことで、会社全体の課題解決やデータの一元管理がしやすくなります。
特定の部署に任せるのではなく、全社的な協力体制を作ることがスムーズなDX推進につながります。
4.IT資産や業務の現状分析を行う
次に、自社の現状を正確に把握しましょう。
現在使用しているITシステムが古くなっていないか、あるいは特定の担当者しか仕様を理解できない状態でないかを確認します。部署ごとにバラバラのシステムが乱立している場合は、全社的な視点での再構築が必要です。
現状のIT資産の運用コストや効果を把握することで、将来のIT投資に関する的確な判断がしやすくなります。まずは足元をしっかりと見つめ直すことが重要です。
5.スモールスタートでデジタル化を行う
いきなり大規模な変革を目指すのではなく、一部の業務からデジタル化を始める「スモールスタート」が有効です。
例えば、請求書の電子化やペーパーレス化など、効果が見えやすい業務から取り組むことで、現場の混乱を抑えながらDXを進められます。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の従業員の協力も得やすくなります。
少しずつデジタル化の範囲を広げていくことで、最終的に会社全体のDX化の成功につながります。
6.ビジネスモデルや業務フローの変革を実行する

業務のデジタル化がある程度進んだら、ビジネスモデルそのものを見直す段階に入ります。
変化する顧客のニーズや市場の状況に対応するため、新しい収益モデルを検討することが重要です。これまでのやり方にとらわれず、部署の垣根を越えて業務プロセス全体を改革する必要がある場合も珍しくありません。
他社の成功事例なども参考にしながら、自社に合ったビジネスモデルの変革を考えましょう。
7.継続的なPDCAを回す
DXは一度実行して終わりではありません。
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを継続的に回していくことが不可欠です。経済産業省の「DX推進施策」などを活用し、定期的に進捗を確認して課題を整理します。
成果が出るまでには時間がかかることも多いため、状況に応じて柔軟に計画を修正できる体制を整えましょう。成果の評価と改善を繰り返すことで、DXの目的達成に近づきます。
DX推進を始めるために必要な主要技術

DXを推進するためには、さまざまなデジタル技術の理解と活用が欠かせません。ここでは、DXの基盤となる主要な技術を紹介します。
- クラウド
- AI・ロボット
- IoT
- 5G
- ビッグデータ
これらの技術は、それぞれが持つ特徴を活かし、組み合わせることで大きな変革を生み出します。
クラウド
クラウドとは、インターネット経由でソフトウェアやデータ保存などのサービスを利用する仕組みです。
自社でサーバーを持たずに済むため、場所を選ばず利用でき、テレワークにも対応しやすいのが特徴です。初期投資や運用コストを抑えられ、必要に応じてサービスを拡張することもできます。
多くの拠点でリアルタイムに情報共有ができるため、DXを推進する上で欠かせない土台となる技術です。
DXにおけるシステム選定のポイントについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事:DXにおけるシステム選定のポイントは?DXの基礎や事例も解説
AI・ロボット
AI(人工知能)は、データから学習し、人間のように作業や判断を自動化する技術です。
画像認識やチャットボットなど、ビジネスでの実用例が急速に増えています。最近では、文章や画像を生成する「生成AI」も登場し、より高度な処理が可能になりました。
AIを搭載したロボットは、工場の自動化だけでなく、受付対応や介護支援など、さまざまな分野で人手不足を補う活躍が期待されています。
IoT

IoTは「Internet of Things」の略で、さまざまなモノをインターネットに接続する技術です。
工場の機械や家電などからリアルタイムでデータを収集・分析可能です。これにより、遠く離れた場所から機械を監視・操作できるため、農業や製造業といった幅広い分野で活用されています。
従来は人の手で行っていた作業を自動化し、生産性の向上やコスト削減に直接つなげられます。
5G
5Gは、従来の4Gに比べて「高速・大容量」「低遅延」「多数同時接続」という特徴を持つ通信技術です。
大容量のデータを瞬時に送受信できるため、IoT機器から送られる大量のデータを遅延なく処理できます。
遠隔医療や自動車の自動運転など、リアルタイム性が求められる新しいサービスの技術基盤として、企業のDXを支える重要な通信インフラです。
ビッグデータ
ビッグデータとは、企業が蓄積した膨大で多様なデータのことです。
このデータを分析することで、これまで見えなかった市場のトレンドや顧客の隠れたニーズなどを可視化できます。
データ分析の結果をグラフなどで分かりやすく示すことで、勘や経験に頼らない客観的な意思決定が可能です。
DX推進を始める際に直面する4つの課題

多くの企業がDXを推進する過程で、いくつかの共通した課題に直面します。ここでは、代表的な4つの課題を解説します。
- 経営層のDXへの無関心や誤解
- IT人材の確保と育成不足
- サイロ化・ブラックボックス化されたシステム
- 社内文化・風土の変革への抵抗
これらの課題をあらかじめ認識し、対策を講じることがDXの成功につながります。
経営層のDXへの無関心や誤解
経営層がDXの重要性を十分に理解していないと、DXの推進は困難を極めます。
必要な予算や人材を確保できず、プロジェクトが停滞する原因にもなりえます。また、DXを単なる「システムの入れ替え」と誤解し、ビジネスモデルの変革といった抜本的な改革に踏み出せないケースも少なくありません。
経営トップ自らがDXのビジョンを明確に発信しなければ、変革は社内に浸透せず、現場からの抵抗感も増してしまいます。
IT人材の確保と育成不足
DX推進には、高度なITスキルやデータ分析能力を持つ人材が不可欠ですが、市場全体で慢性的な人材不足が続いています。
そのため、外部からの採用は難しく、自社での育成が重要になります。しかし、技術革新のスピードが速いため、社内教育だけでは追いつかないという課題もあります。
単なる技術者ではなく、ビジネス課題を発見し解決できる人材が求められており、その育成は多くの企業にとって急務です。
DX人材に必要なスキルについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:DX人材になるにはどんなスキルが必要?求められるマインドセットや課題も紹介
サイロ化・ブラックボックス化されたシステム
多くの企業では、部署ごとに最適化されたシステムが乱立し、全社的なデータ連携が困難になる「サイロ化」が起きています。
また、古い基幹システムは、担当者以外には仕組みがわからない「ブラックボックス化」に陥りがちです。
担当者の退職によって運用ノウハウが失われるリスクも大きく、この状況を放置すると「2025年の崖」に直面し、事業継続そのものが危ぶまれる可能性があります。
社内文化・風土の変革への抵抗
DXを進める上で大きな壁となるのが、社内の抵抗です。
「今のやり方に慣れている」として、新しいやり方への変化を拒むケースは少なくありません。また、失敗を恐れる文化や、前例を重視する思考も、デジタル技術の活用を妨げます。
経営トップが率先してDXの価値を発信し、社内に「変化を受け入れる文化」を醸成することが不可欠です。DXを単なるIT導入ではなく、「企業文化の変革」として位置づける必要があります。
DX推進を始める際に成功するための3つのポイント

DXを成功に導くためには、押さえるべき重要なポイントがあります。ここでは、特に重要となる3つのポイントを解説します。
- DXビジョンの明確化と共有を行う
- 他部門と連携し全社を巻き込んで推進する
- DX人材を戦略的に育成する
これらのポイントを意識することで、DX推進の成功確率を高められます。
DXビジョンの明確化と共有を行う
DXを成功させる上で最も重要なのは、「DXによって自社をどのような姿に変えたいのか」というビジョンを明確にすることです。
DXは単なるデジタルツールの導入ではなく、経営戦略そのものの変革です。このビジョンは、プロジェクトを進める上での判断基準となり、道しるべの役割を果たします。
経営トップがこのビジョンを全社員に向けて繰り返し発信し、共有することで、組織全体が同じ方向を向いて進む推進力が生まれます。
他部門と連携し全社を巻き込んで推進する
DXは、IT部門だけでは成し遂げられません。
部署単位で最適化を進めると、システムがバラバラになり、全社的なデータ活用が妨げられます。部門の垣根を越えたプロジェクトチームを作り、現場の課題やニーズを集約することで、組織全体の変革につながります。
IT部門だけでなく、事業部門や経営層、現場の従業員を巻き込んだ推進体制を構築することが欠かせません。DXの目的や意義を社内全体で共有し、理解と協力を得ることが重要です。
DX人材を戦略的に育成する
DXを推進するには、ITスキルだけでなく、データ分析能力や課題解決能力など、多様なスキルを持つ人材が必要です。
日本ではDX人材が不足しており、外部からの採用だけに頼るには限界があります。そのため、自社でDX人材を育成する環境を整えることが重要です。
経営層がDXの知識を深め、現場社員が変革を受け入れるマインドを持つことも組織全体の推進力となります。研修などを通じて、社内人材の育成を戦略的に実施する必要があります。
DX研修の進め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:DX研修の目的と方法とは?DX推進の成功には人材育成がカギ
DXを何から始めるかお悩みなら「伴走ナビ」にご相談ください

DXを実現するためには、自社に合った戦略とツールの導入が欠かせません。
クラウドやAI、IoTなどのデジタル技術を活用することで、業務プロセスの効率化や新たなビジネスモデルの創出が可能になります。自社だけで推進が難しい場合は、専門的な知見を持つパートナー企業に相談し、伴走支援を受けることも検討しましょう。
DXを進めることで、企業は生産性の向上、コスト削減、さらには競争力強化を実現できます。ぜひ、自社に最適なアプローチを見極め、一歩ずつDXを推進してください。
もし、DXを何から始めるべきか、自社だけでの推進に不安がある場合は、ぜひ「伴走ナビ」にご相談ください。