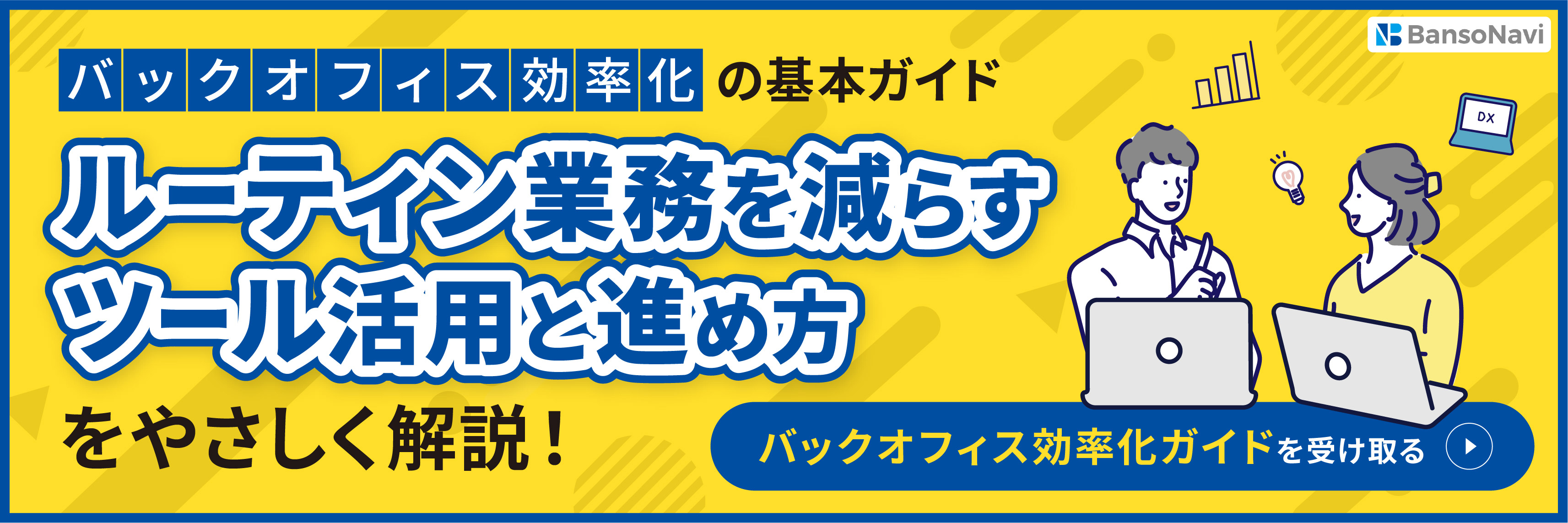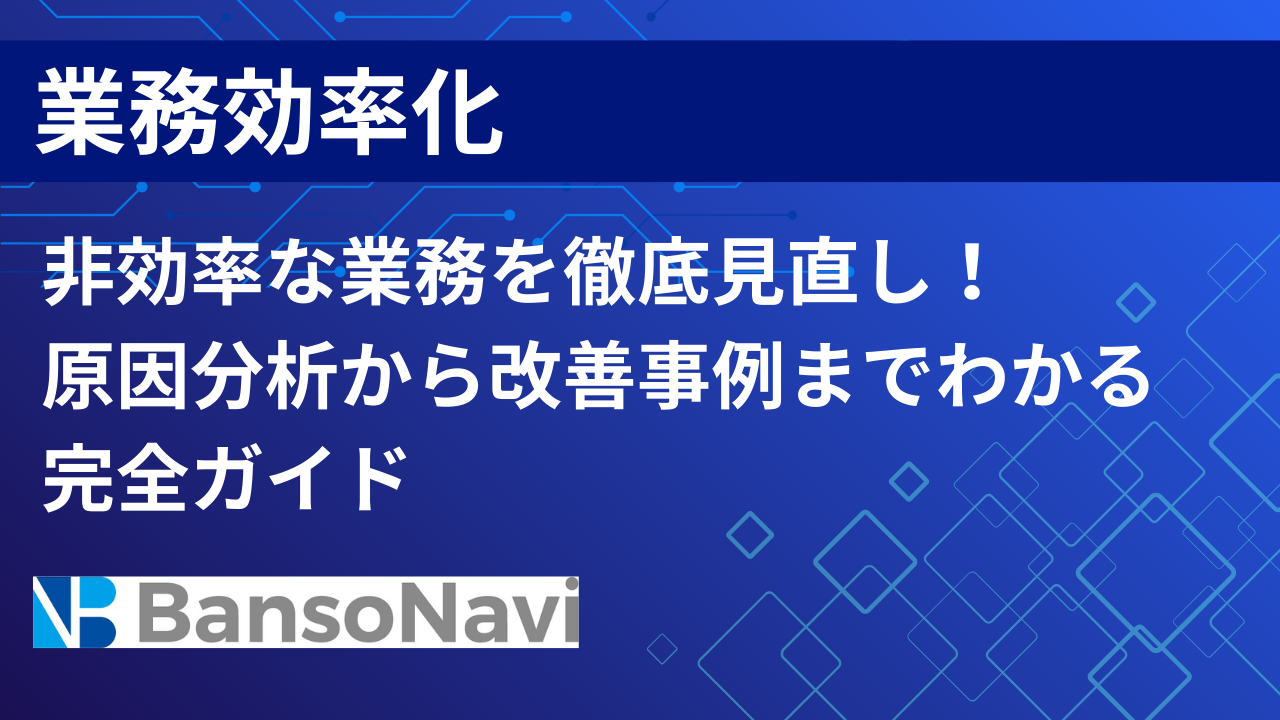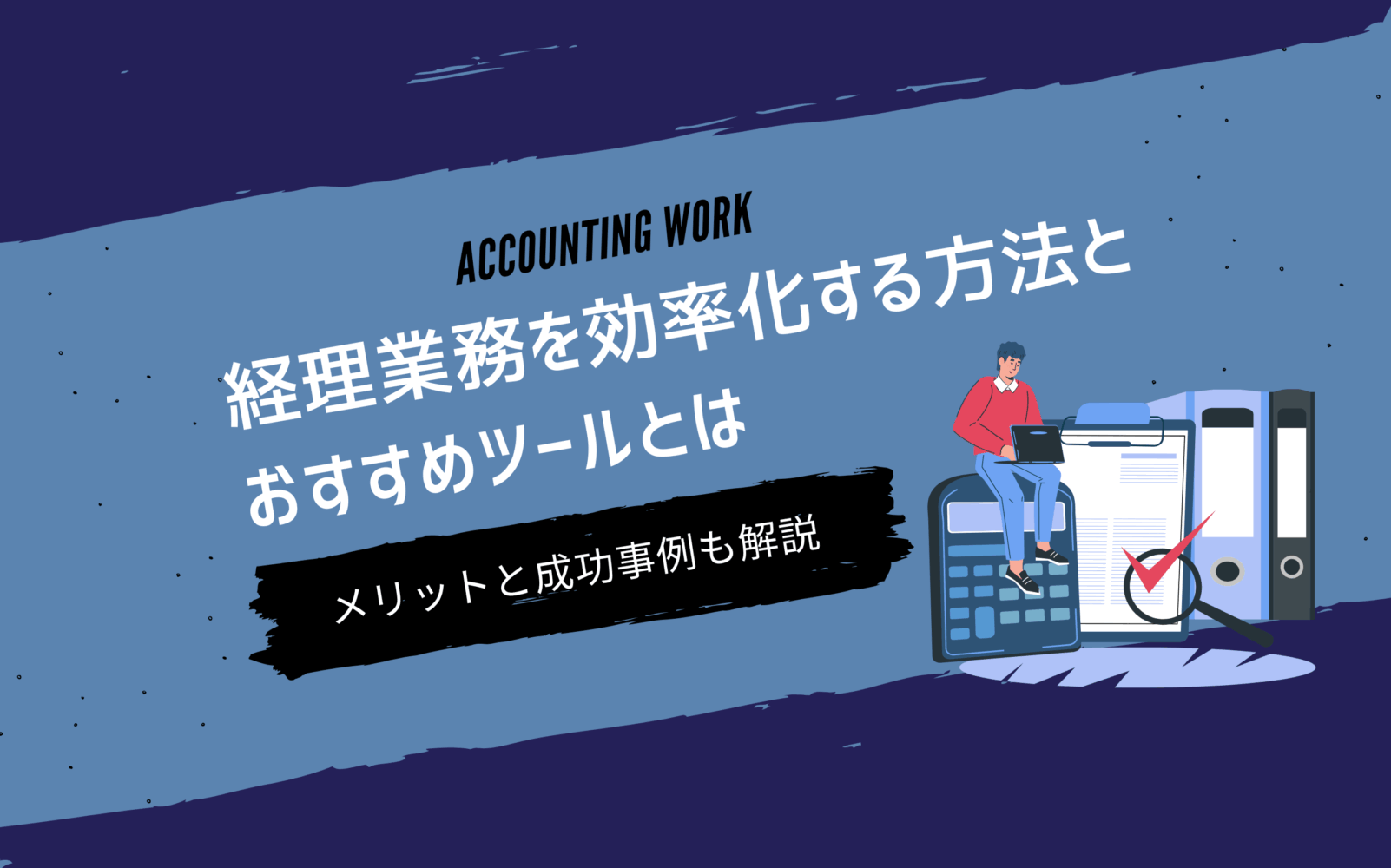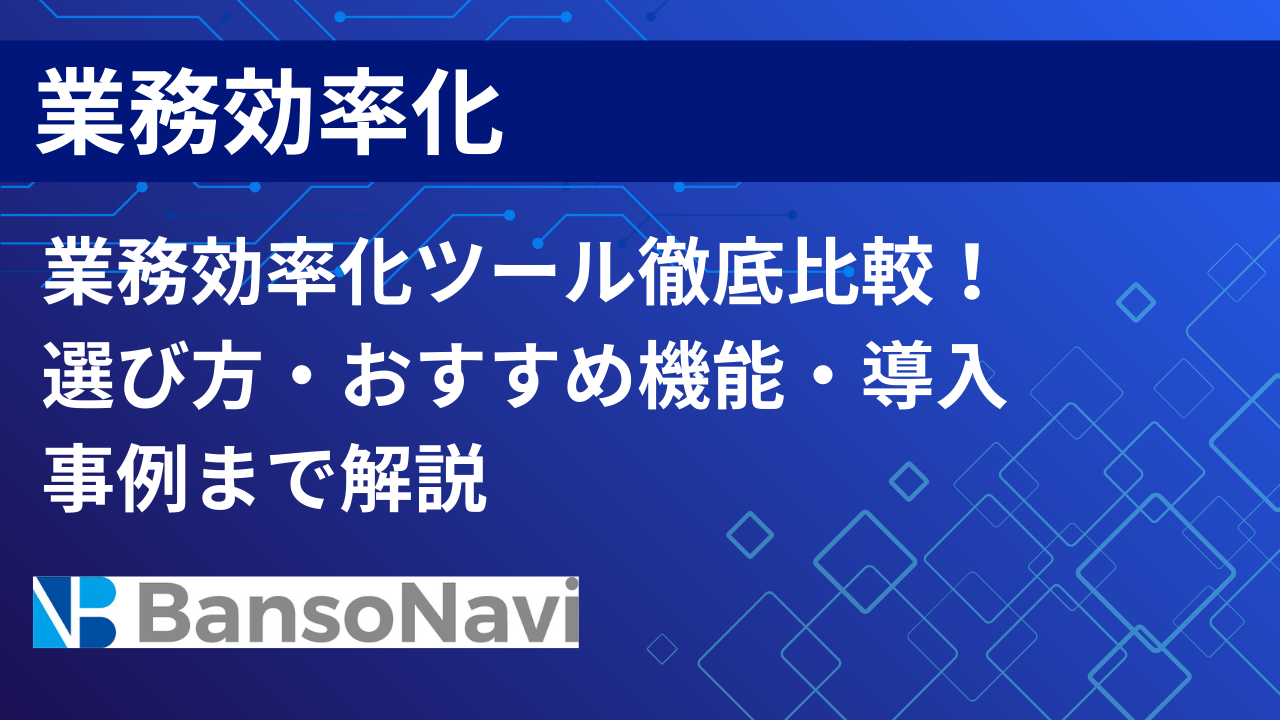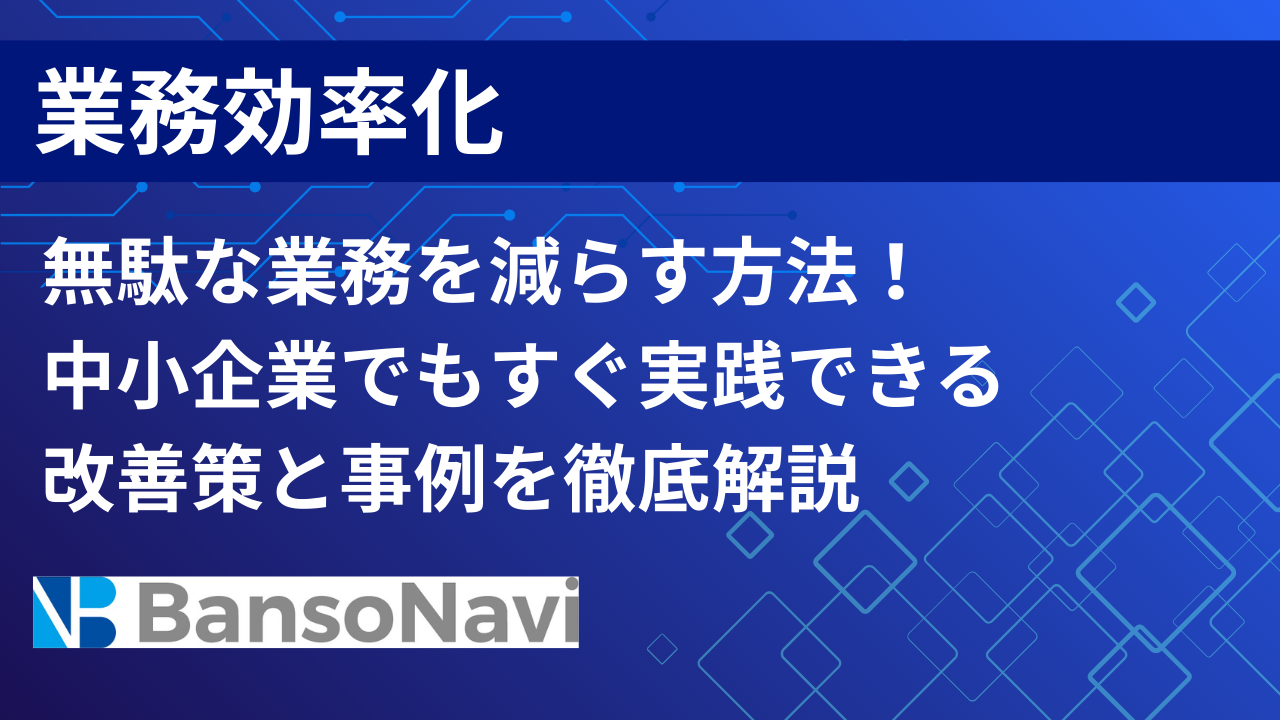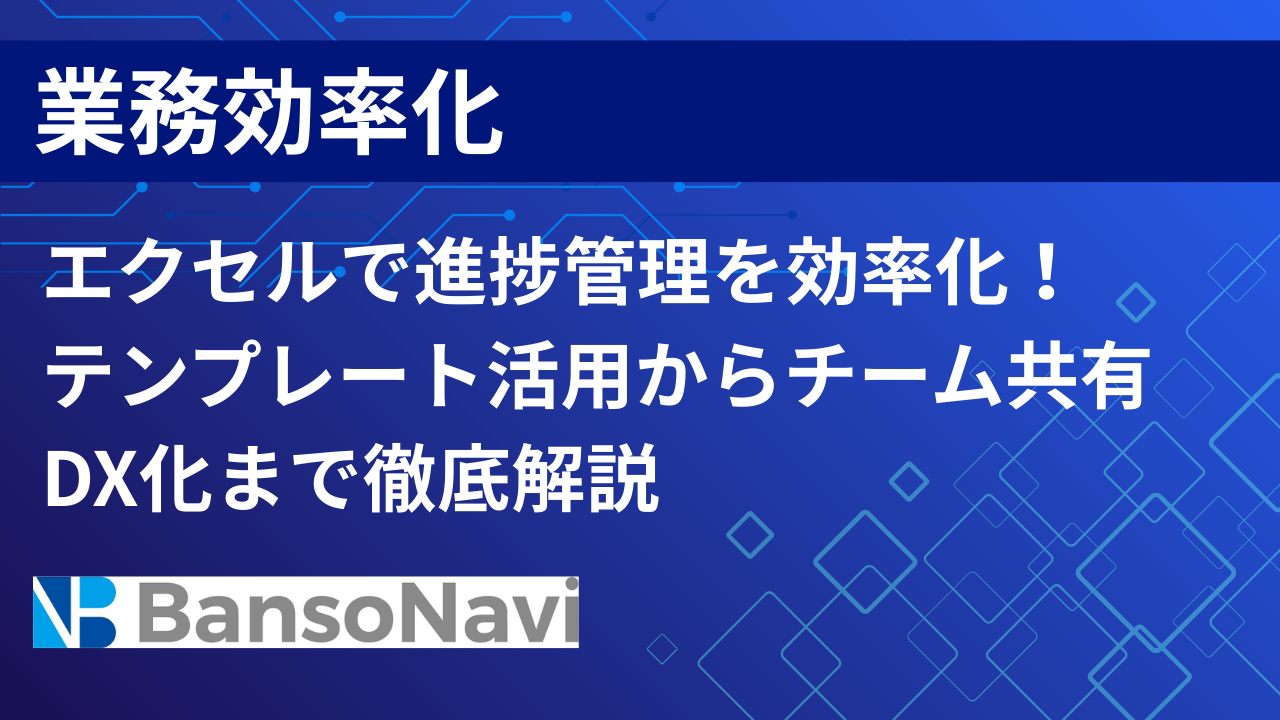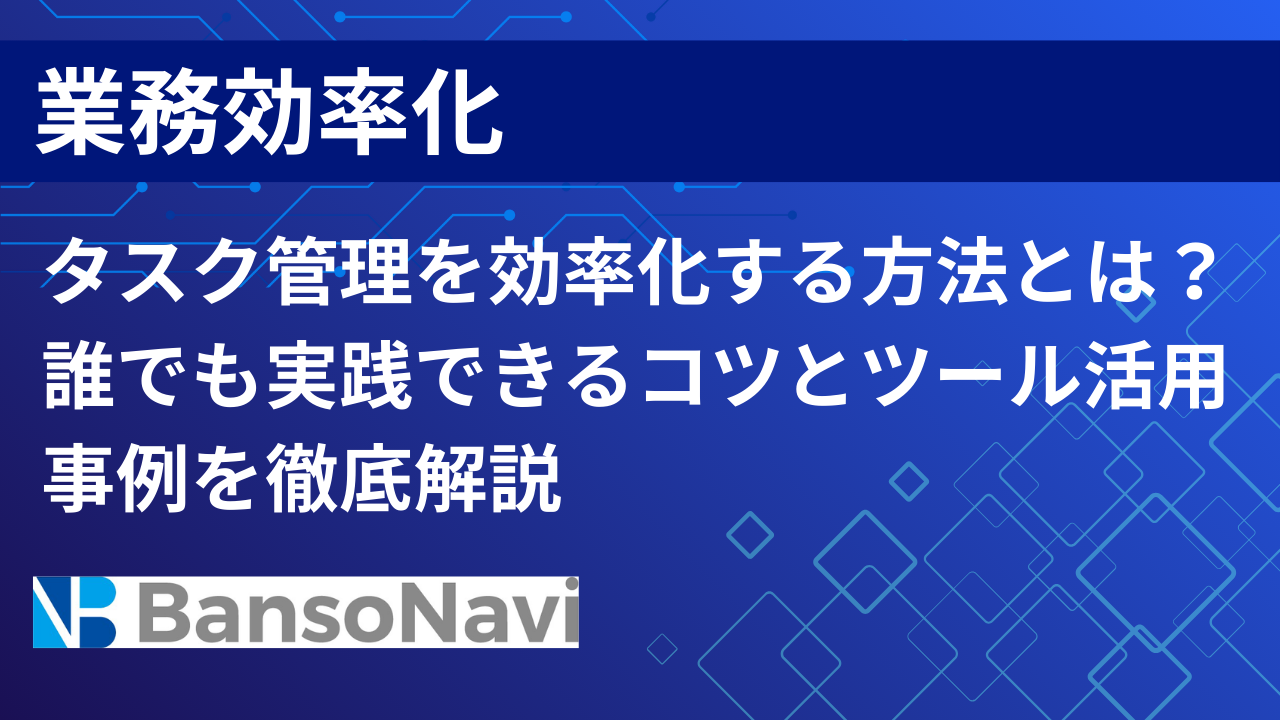経理業務の効率化で残業ゼロへ!中小企業でもすぐ始められる具体策と事例
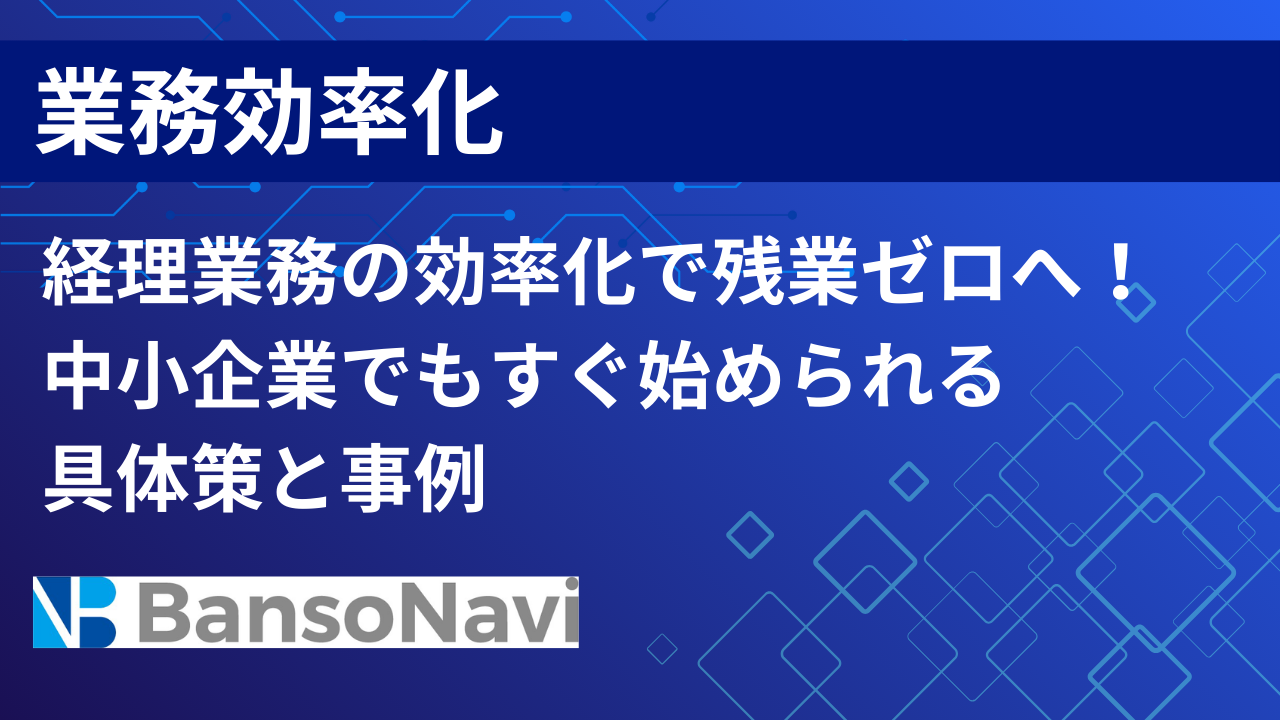
経理業務は毎日のデータ入力、請求書や領収書の処理、月次・年次決算など、細かい作業が多く時間がかかる部門です。「気づけば残業続き」「担当者しか分からない業務が多すぎる」といった悩みは、多くの中小企業で共通しています。
しかし、業務の見直しや適切なツール導入によって、その負担は大きく減らせます。
本記事では、経理担当者や経営者がすぐに実践できる効率化の方法と、実際に成果を上げた事例を紹介し、明日からでも改善に踏み出せる具体策をお伝えします。
目次
経理業務が非効率になる原因と、その放置リスク

経理業務が非効率になる背景には、長年の慣習や社内ルールの固定化があります。
例えば紙ベースの伝票や領収書の運用は、1件ずつ手作業で確認・整理が必要となり時間がかかります。また、担当者が長く同じ方法で作業していると、業務のやり方が暗黙知化し、他の社員が引き継ぎにくい状況も生まれます。
これらの問題を放置すると、作業時間の増加だけでなく、ミスや不正リスクの高まり、さらには人材不足による業務停滞にもつながります。
手作業・紙文化による時間ロス
経理業務では、請求書や領収書を紙で受け取り、1件ずつ手入力で会計ソフトに登録するケースが今も根強く残っています。
例えば月末の支払い処理では、数百件に及ぶ伝票を一枚ずつ開封し、金額や日付を確認しながら入力する作業が発生し、その工程だけで丸一日、場合によっては数日を費やすこともあります。さらに、紙書類は保管スペースが必要で、過去の書類を探す際にも多くの時間を要します。
紙のやり取りや郵送は物理的な移動時間が伴い、急ぎの確認や修正が必要な場合に対応が遅れる原因となります。こうした非効率は、電子化やクラウド管理に切り替えることでほぼ解消できるにも関わらず、慣習的に紙運用を続けている企業も少なくありません。
業務の属人化による引き継ぎ困難
経理業務は特定の担当者が長年同じ方法で行うことが多く、作業が暗黙知として個人に依存しがちです。
例えば、エクセルの独自関数や複雑な集計方法、会計ソフトの入力順序、フォルダ構造やファイル名の付け方などが担当者の頭の中だけにあり、正式なマニュアルとして共有されていないケースです。このような属人化は、急な退職や長期休暇時に業務が滞る大きな要因となります。
さらに、新しい担当者が着任しても業務を覚えるまでに時間と教育コストがかかり、その間はミスのリスクも増大します。結果的に、経理全体の効率や正確性が「その人頼み」になり、組織としての柔軟性や持続性が損なわれてしまいます。
データの二重入力や確認作業の増加
経理業務では、同じ情報を複数のシステムやファイルに入力する「二重入力」が頻発します。
例えば、営業部門が作成した請求データを経理部が再び会計ソフトに手入力したり、エクセル管理と会計ソフトの両方に同じ内容を登録するケースです。これにより、作業時間は単純に倍増し、入力ミスやデータ不一致が発生する可能性も高まります。その結果、突合や差異確認といった余計なチェック作業が増え、経理担当者の負担が膨らみます。
根本原因はシステム間の連携不足や紙・メールベースの情報共有にあり、この構造的な問題を解消しない限り、いくら頑張っても本質的な効率化は実現できません。
経理業務効率化の主な方法と具体例

経理業務の効率化には、大きく分けて「ITツールの導入」「業務プロセスの見直し」「社内ルールの改善」という3つの方向性があります。特に近年はクラウド会計ソフトや電子化サービスの普及により、少人数の経理部門でも大幅な時間短縮が可能になっています。
ここでは、実際に効果が高い具体的な方法と、その活用例を紹介します。
クラウド会計ソフトの導入
クラウド会計ソフトは、インターネット環境さえあれば社内外を問わずアクセスでき、複数人で同時編集が可能なため、経理業務のスピードと柔軟性が飛躍的に向上します。銀行口座やクレジットカード明細と自動連携でき、入出金データを取り込むだけで自動仕訳される機能は手入力の手間を大幅に削減します。さらに、過去の仕訳パターンを学習してくれるため、繰り返し発生する経費や売上処理は数クリックで完了します。
例えばfreeeやマネーフォワードクラウドは中小企業でも導入事例が多く、月末締め作業を従来の半分以下に短縮できた例もあります。また、税理士や顧問会計士ともオンラインでデータ共有でき、資料送付ややり取りの時間も削減できるのが大きな魅力です。
請求書・領収書の電子化とペーパーレス化
紙の請求書や領収書は、発行や受領、保管、検索、郵送といったプロセスの中で膨大な時間とコストを生みます。電子化することで、受領から保存までをワンストップで完結でき、業務効率は格段に向上します。
例えば、スキャナーやスマホアプリで撮影すると、OCR機能が日付・金額・取引先名などを自動読み取りし、会計ソフトに直接取り込めます。また、電子帳簿保存法に対応したサービスを利用すれば、紙で保管する場合と同等の法的効力を持ちながら安全にデータ保存できます。
これにより、保管スペース削減や紛失・破損リスク低減、さらには検索時間の大幅短縮も実現可能です。
ワークフローの自動化(kintone活用事例あり)
経理業務では、経費精算や支払申請、請求書承認など、申請から承認、処理までの流れが頻繁に発生します。こうしたワークフローをkintoneなどの業務改善プラットフォームで自動化すると、承認遅延や書類の滞留を防げます。
例えば、経費精算フォームをkintoneに作成し、社員が申請すると自動で承認者へ通知、承認後は会計ソフトにデータが自動連携されます。この仕組みにより二重入力は不要となり、手作業のチェック時間も削減できました。
伴走ナビの支援事例では、これを導入した企業が経費精算処理の所要時間を70%短縮しました。
さらに、進捗状況がリアルタイムで可視化されるため、業務全体の透明性も向上します。
効率化を成功させるためのステップと注意点
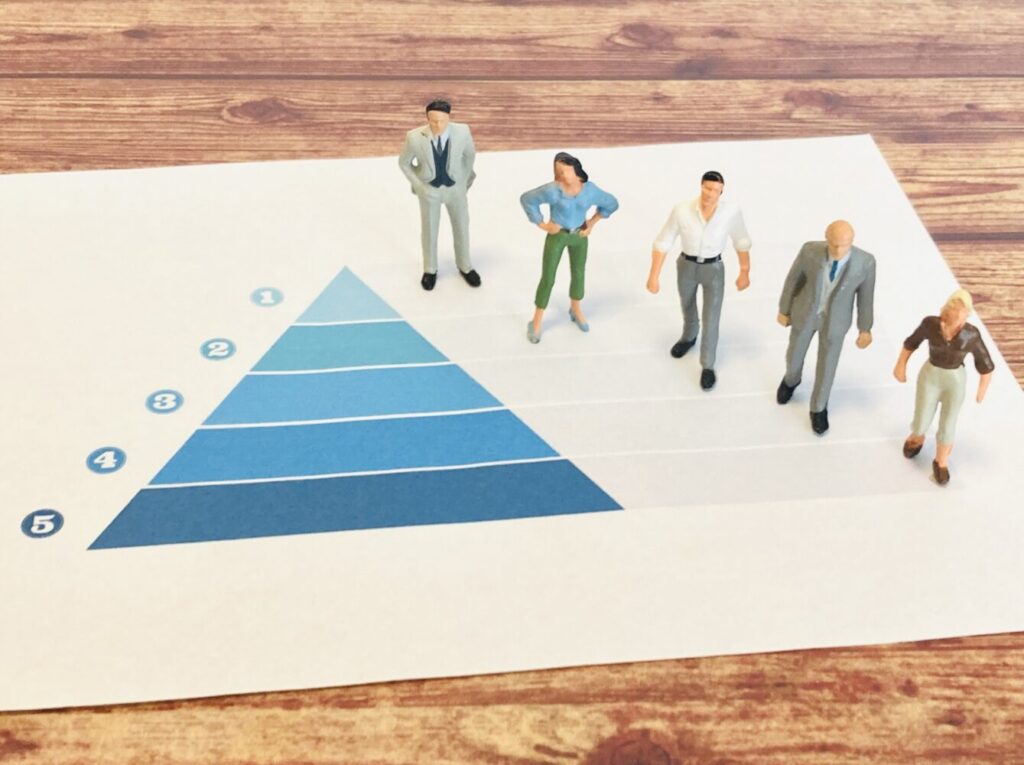
経理業務の効率化は、単にツールを導入するだけではうまくいきません。
現状の業務内容や課題を正確に把握し、改善の優先順位をつけることが重要です。また、効果を測定できる指標を設定しなければ、改善が進んでいるのか判断できません。さらに、社内での浸透を促すためには、社員への周知や教育も欠かせません。
ここでは、効率化を確実に成功させるためのステップと注意点を紹介します。
現状業務の棚卸しと課題整理
効率化の第一歩は、今どの業務にどれだけ時間と労力がかかっているかを正確に把握することです。
例えば、経費精算の処理に1件あたり何分かかるのか、請求書発行や入金確認に要する日数、伝票整理にかかる時間などを詳細に記録します。これらを部署ごと、業務ごとに一覧化すると、負担が大きい工程やムダな作業が明確になります。
課題が見えれば「紙で受け取っている領収書を電子化する」「二重入力をなくす」「承認ルートを簡略化する」など、改善策を具体的に立案可能です。逆に棚卸しを行わず感覚だけで効率化を進めると、効果が薄い部分にコストや時間を費やす危険があります。改善は、現状把握から始まることを肝に銘じるべきです。
効果測定の指標設定(時間・コスト削減)
経理業務の効率化を成功させるためには、成果を定量的に測る指標が欠かせません。
例えば「経費精算処理時間を月30時間削減」「請求書発行までのリードタイムを3日短縮」「紙書類保管スペースを半分に削減」といった、具体的かつ測定可能な目標を設定します。
こうした数値目標があれば、進捗状況を客観的に把握でき、経営層への報告や改善施策の効果説明がしやすくなります。また、指標は一度設定したら終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。業務改善が進むと新たな課題が見えてくるため、指標を更新し続けることで継続的な改善が可能になります。
社内周知と定着のための教育・マニュアル化
新しいツールや仕組みを導入しても、現場が使いこなせなければ効率化は実現しません。そのため、導入時には操作方法やルールを分かりやすく説明し、紙やPDF、動画など複数形式のマニュアルを用意しておくことが大切です。
また、新入社員や部署異動者にも同じ水準で運用できるよう、定期的な教育の場を設けましょう。例えば、月に一度の業務改善ミーティングで実際の操作画面を見せながら共有すれば、理解度が高まります。さらに、運用ルールやマニュアルを社内ポータルに常時掲載しておくと、困ったときにすぐ参照でき、業務定着がスムーズになります。
実際の導入事例:経理業務の効率化で得られた成果

効率化の効果は、実際の企業事例を見ることでより具体的にイメージできます。
ここでは、異なる業種・規模の3社が経理業務を効率化した事例を紹介します。いずれも業務時間の削減だけでなく、社員の負担軽減や精度向上といった副次的な効果も得ています。
中小製造業A社:残業時間80%削減
A社では、月末月初に集中する請求書発行業務が完全に属人化しており、経理担当者は連日深夜まで残業を強いられていました。作業は紙の伝票とエクセルを併用し、販売管理システムのデータを手作業で会計ソフトへ入力していたため、膨大な時間がかかっていました。
改善策として、クラウド会計ソフトを導入し、販売管理システムとの自動連携を構築。これにより請求データの手入力が不要になり、作業時間が大幅に短縮されました。結果として残業時間は80%削減され、請求漏れや金額ミスも減少。取引先からの問い合わせも減り、経理部全体のストレスが軽減されただけでなく、繁忙期でも定時退社が可能になりました。
サービス業B社:請求処理スピードが2倍に
B社は全国に営業拠点を持ち、各拠点から請求データをメールで経理部に送付し、集計・入力を行うフローを採用していました。この方法は手間がかかり、請求書発行までに最長で1週間かかることもありました。改善のため、オンライン請求書発行サービスを導入し、各拠点が直接クラウドシステムに入力できる方式へ移行。入力されたデータは自動で集計・整形され、経理部門は内容確認と承認だけを行えばよくなりました。
これにより請求処理スピードは従来の2倍となり、発行遅延による入金遅れも解消。加えて、各拠点の入力ミスもシステム側で事前チェックされるため、経理の修正作業も激減しました。
伴走ナビ支援事例:kintoneで経理データ集約と自動計算を実現
伴走ナビが支援したある企業では、売上・経費・支払データが複数のエクセルファイルに分散しており、月次集計だけで数日を要していました。
担当者は手作業で各ファイルを突き合わせており、ミスやデータ重複も多発。そこでkintoneを導入し、すべての経理データを一元管理できるアプリを構築しました。入力と同時に自動計算・自動仕訳が行われるため、二重入力が不要となり、集計作業時間は90%削減。さらに、リアルタイムで集計結果を経営層が確認できるため、意思決定スピードも向上。担当者は分析や改善提案など、付加価値の高い業務に時間を充てられるようになりました。
ツール導入以外でできる経理効率化の工夫

経理効率化というとシステム導入が注目されがちですが、社内ルールや業務フローの改善だけでも大きな効果を得られます。特に中小企業では、コストを抑えながら改善するために、こうした取り組みが有効です。
ここでは、ツールに頼らずすぐに実践できる具体的な工夫と、その効果を高めるポイントについて解説します。
業務ルールの見直しと標準化
経理部門内だけでなく、他部署とのやり取りに関するルールを明確化することは、効率化の基盤となります。
例えば、経費精算の申請期限を「翌月5日まで」と設定し、提出フォーマットや記載項目を統一するだけでも、確認や差し戻しの手間が減ります。
さらに、承認ルートや記入例、添付書類の条件などを社内ポータルや共有フォルダに掲載しておけば、新入社員や他部署の社員も迷わず正しい手順で申請できます。こうした標準化は業務の属人化を防ぎ、担当者が変わっても同じ品質で処理できる体制を作ります。また、標準化ルールは年1回程度の見直しを行い、現場の実態に合わせて柔軟に更新することが重要です。
無駄な承認ステップの削減
承認者が多すぎたり、承認順序が複雑だと、経理処理全体が滞りやすくなります。
特に少額経費や定型的な支払いまで複数人の承認を必要とする場合は、申請から処理完了までのリードタイムが無駄に延びます。改善策として、一定金額以下は自動承認に切り替える、定型支出は承認ステップを1回に短縮する、などのルール変更が有効です。
これにより経理部門は重要度の高い案件に集中でき、全体の処理スピードが向上します。また、承認プロセスを見直す際は、過去の処理履歴を分析して「承認のためだけに時間が浪費されている領域」を特定し、優先的に改善すると効果的です。
定期的な業務改善ミーティングの実施
経理業務の効率化は一度の改善で完結せず、継続的な見直しが必要です。そのため、月1回程度の業務改善ミーティングを設定し、「最近時間がかかった事例」や「不要だった手順」などを社員同士で共有することが効果的です。
こうした場を設けることで、現場の小さな不満や改善点が集まり、すぐに反映できる仕組みが作れます。また、他部署のメンバーも参加させると、経理部門だけでは気づけない非効率ポイントが明らかになり、会社全体の業務改善につながります。
さらに、改善した内容や成果を社内で共有すれば、モチベーション維持や全員の当事者意識向上にもつながります。
まとめ|経理効率化で残業ゼロと業務の質向上を実現するために
経理業務の効率化は、単なるツール導入にとどまらず、業務フローや社内ルールの見直し、情報共有の仕組みづくりまで含めた総合的な取り組みです。現状の業務を棚卸しし、時間やコストの削減効果を測定しながら改善を続ければ、残業時間の削減、入力ミスや請求漏れの防止、意思決定の迅速化といった確かな成果が得られます。
また、効率化によって生まれた時間を分析や経営サポート業務に充てることで、経理部門の存在価値もさらに高まります。
伴走ナビでは、現状分析からツール選定・導入、kintoneによるワークフロー自動化まで、一社ごとの課題に合わせた支援を行っています。これまでの豊富な成功事例とノウハウを活かし、経理の負担を減らしつつ、業務の質とスピードを両立する環境づくりをサポートします。今こそ、経理業務の在り方を見直し、組織全体の成長を後押しする仕組みを一緒に作り上げませんか。