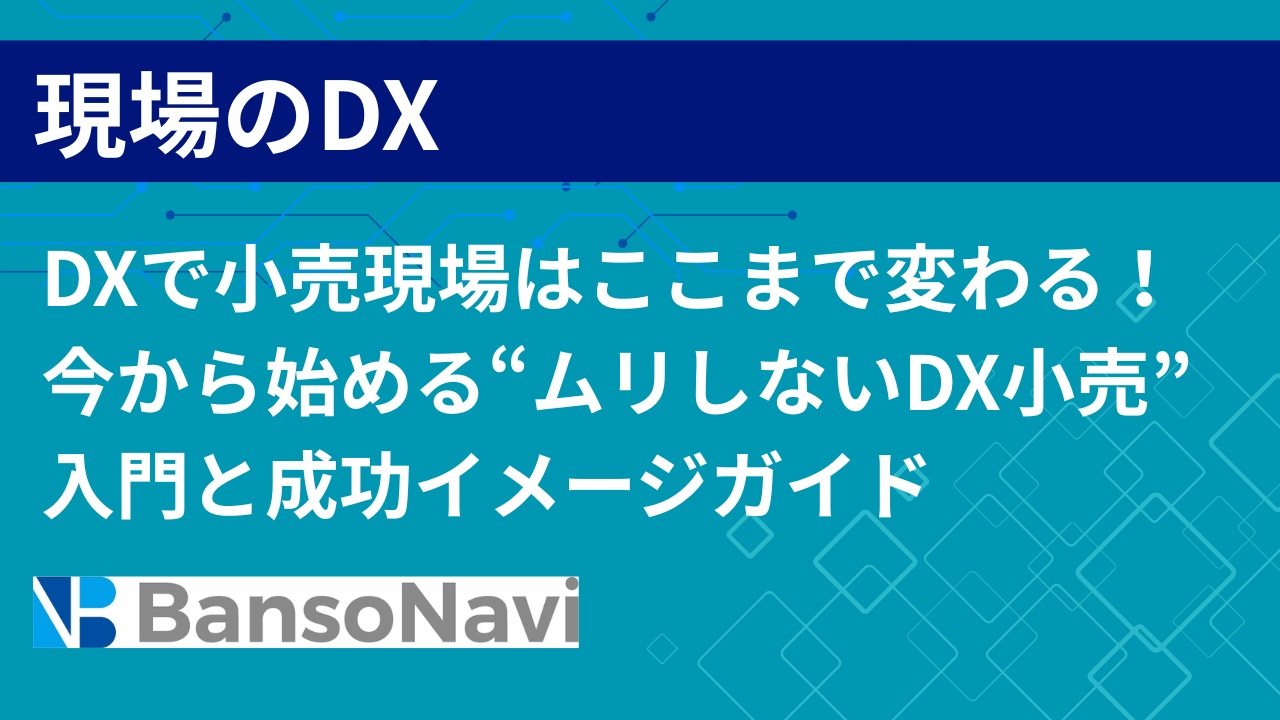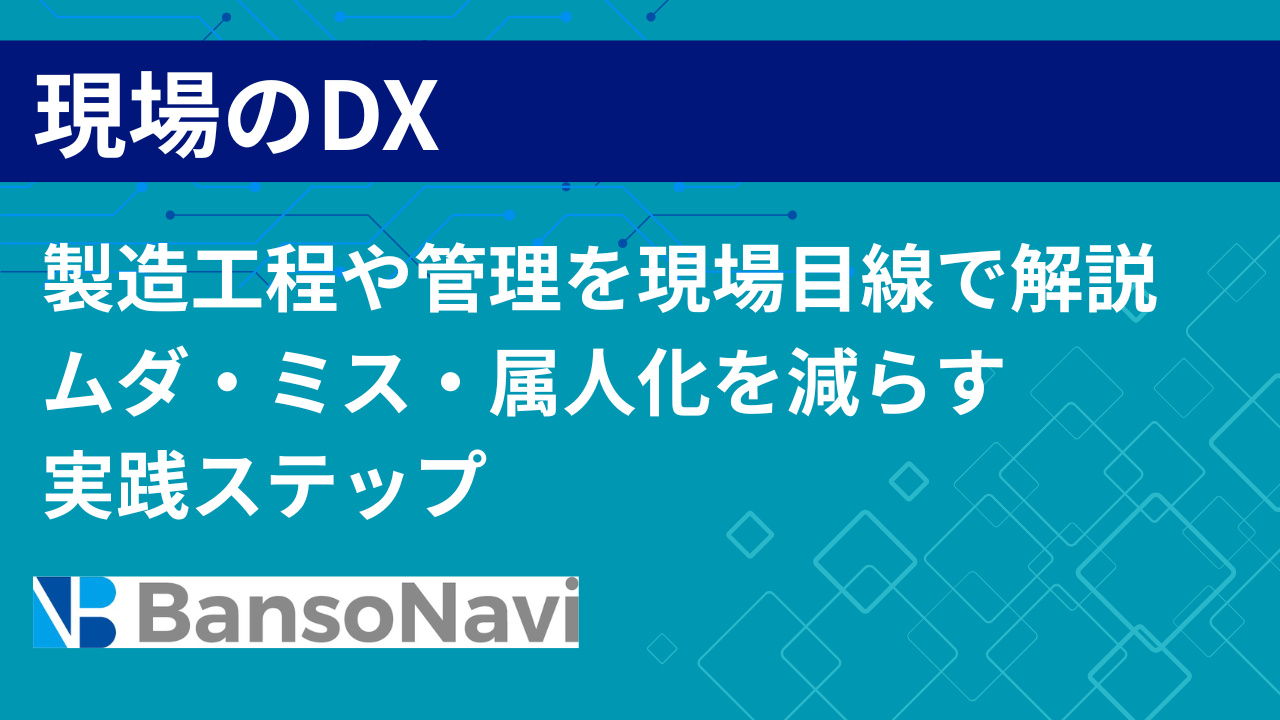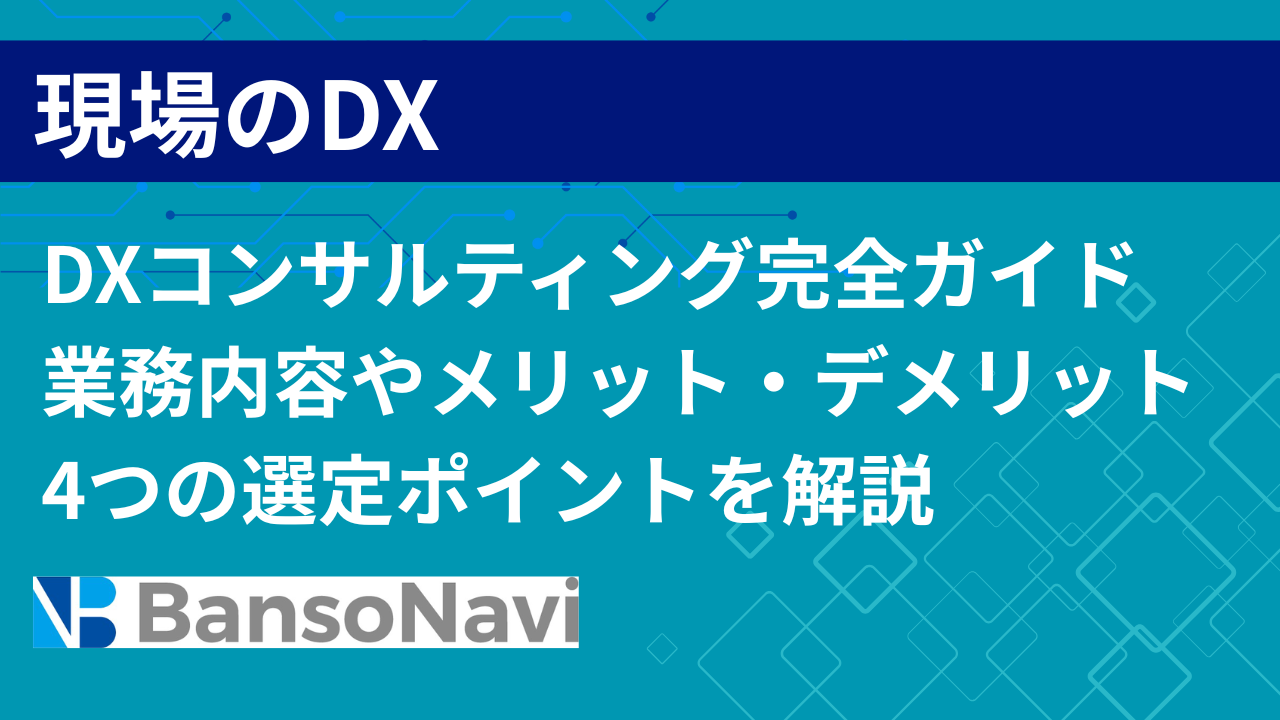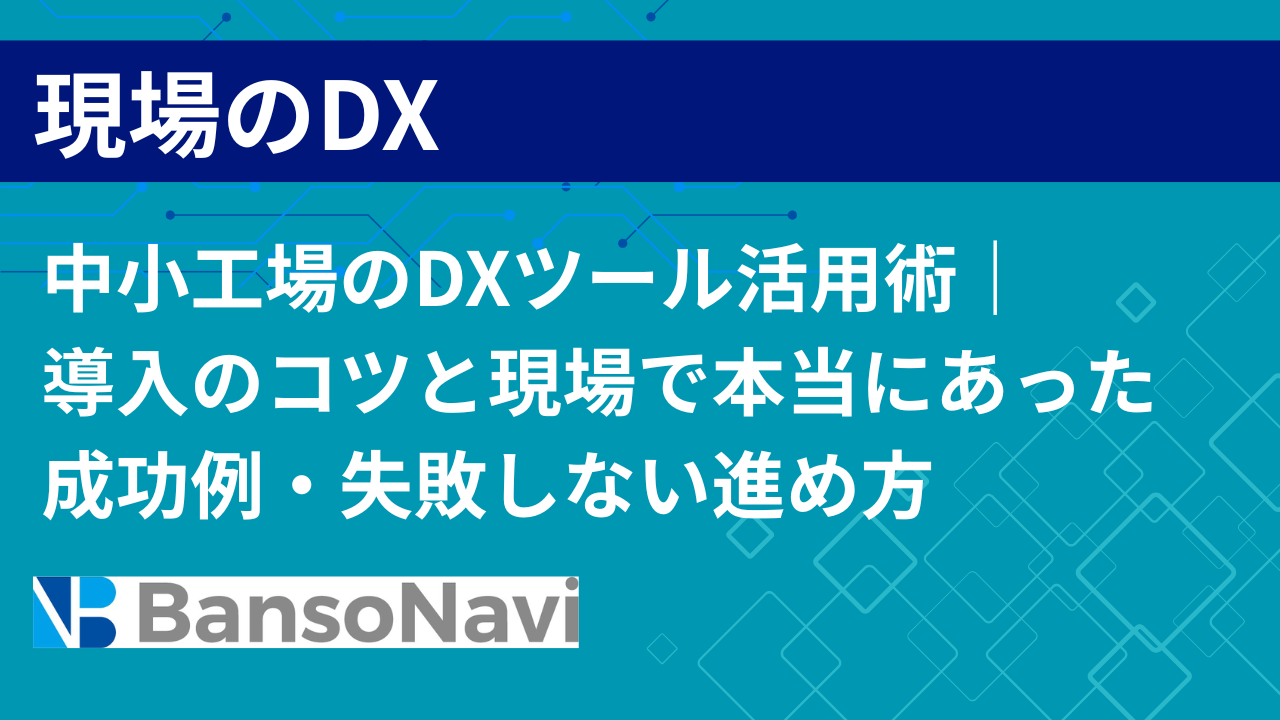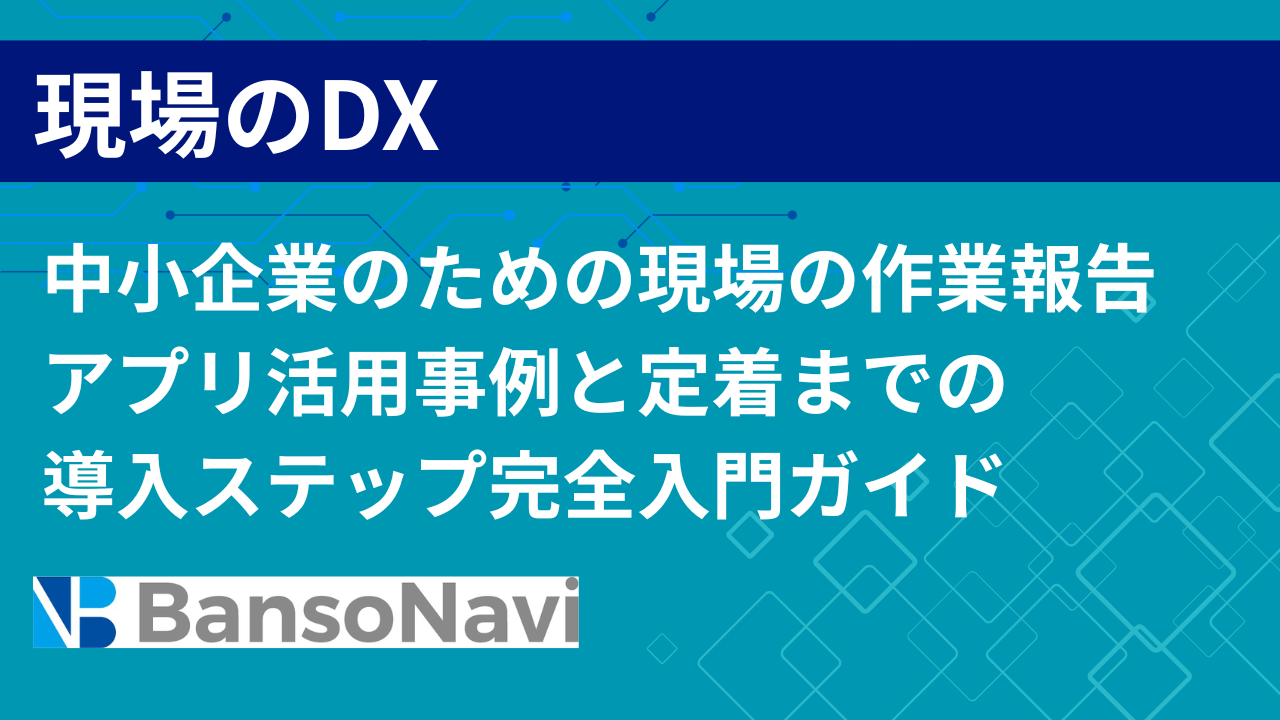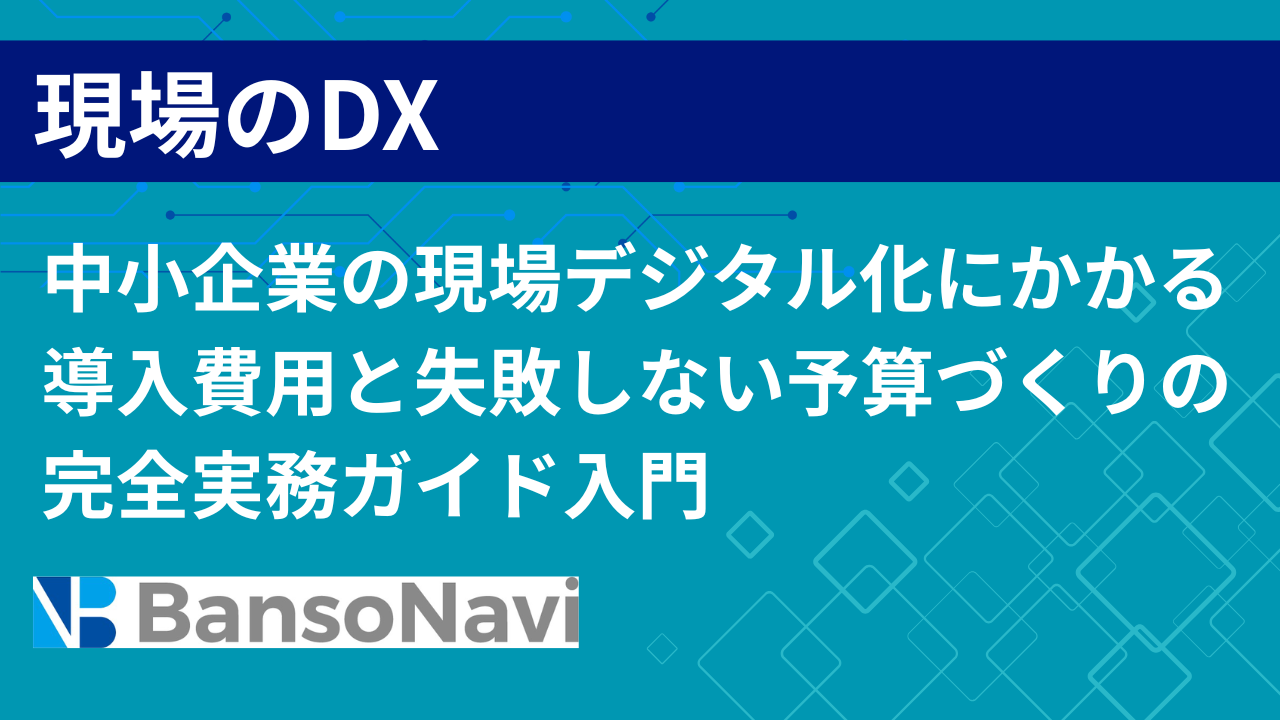中小製造現場のDXを自社で進める伴走支援ガイド|進め方・事例・費用の考え方を徹底解説
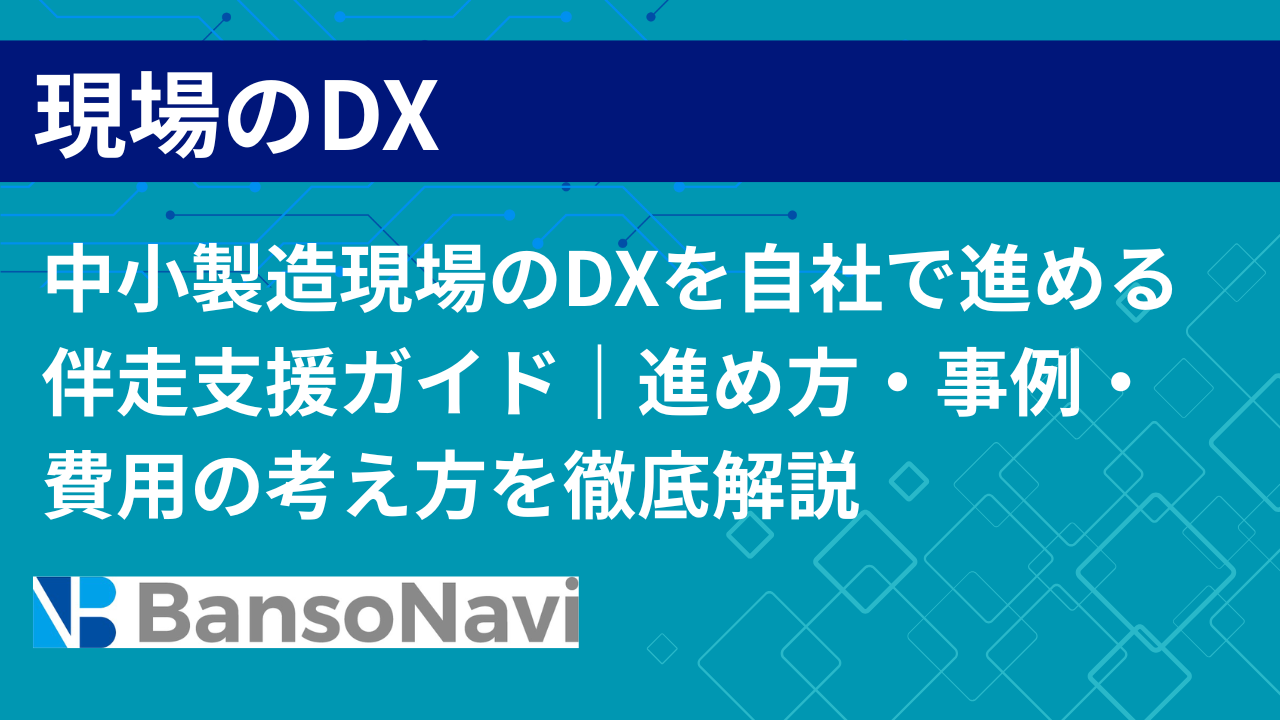
現場では今も、紙とExcel、ホワイトボードと電話をフル活用しながら、毎日の生産を何とか回している会社が多くあります。頭では「そろそろデジタル化しないと」「DXとやらに取り組まないと」と思いつつも、専門用語ばかりでよく分からず、忙しさもあって後回しになりがちです。
一方で、システム会社に丸投げしてシステムを入れてみたものの、「画面が使いづらくて誰も入力しない」「ちょっと直したいだけなのに都度見積もりが出てくる」といった苦い経験をした方も少なくありません。そうなると、「また失敗するくらいなら、紙とExcelのままでいいか……」と、気持ちが止まってしまいます。
この記事では、そんな中小製造業の現場責任者やDX担当の方に向けて、自社で育てていくスタイルのDXと、それを外部が横で支える伴走型の支援について、できるだけ分かりやすく整理します。どこから手を付ければいいのか、どんな業務が対象になりやすいのか、支援会社はどう選べばよいのか、そして費用はどのように考えればよいのか。読み終えたときに、「まずはこの一歩から始めてみよう」と思える状態になることをゴールにしています。
伴走ナビとしての具体的な支え方にも触れますが、押し売りではなく、「うちの状況だとどんな進め方がありそうか」をイメージする材料として読んでいただければうれしいです。
目次
なぜ今、自社主導のDXが必要なのか

製造業の現場は、他の業種に比べてシステムやツールの導入に慎重なことが多く、「これまでのやり方で何とかなってきた」という自負もあります。それでも今、「現場のやり方をベースに、社内で工夫しながら少しずつデジタル化していく」という考え方に注目が集まっています。この流れの背景を押さえておくと、単なる流行ではなく、自社にとっても避けて通れないテーマなのだと腹落ちしやすくなります。
DXが進まない中小工場の典型パターン
中小の工場で「DXがなかなか進まない」とき、表面上の理由はさまざまですが、現場で起きていることをよくよく見ていくと、よく似たパターンに落ち着きます。
一つ目は、「誰のためのDXか」があいまいなまま、ツールやキーワードから入ってしまうパターンです。「クラウドで管理できるらしい」「IoTで見える化できるらしい」といった言葉が先に立ち、現場の具体的な困りごとが置き去りになってしまいます。結果として、導入してみたものの、現場からは「別に便利になっていない」「むしろ入力が増えて仕事が増えた」と見なされ、数か月後には使われなくなってしまうケースが多く見られます。
二つ目は、「一気に完璧を目指すあまり、検討だけ長く続いて動けない」パターンです。頭の中で「生産計画」「品質管理」「設備保全」「在庫管理」など全てを網羅した理想の仕組みを描こうとしてしまい、「全体像が固まるまで動けない」という状態に陥ります。その間にも、現場では相変わらず紙とExcelの転記が続き、忙しい人ほどDXの会議に参加する余裕がなくなっていきます。
三つ目は、「特定の有志だけが頑張って、組織としての取り組みにならない」パターンです。現場にITが得意な人がいると、その人が自前でExcelマクロや簡易ツールを作り、周りもそれに頼り切ってしまうことがあります。一見すると便利なのですが、担当者が異動・退職した瞬間に誰もメンテナンスできなくなり、「結局、元の紙運用に戻る」「壊れるのが怖くて誰も触れない」という状況が生まれがちです。
こうした典型パターンを避けるためには、「カタカナ用語や理想の全体像よりも、目の前の困りごとから小さく着手する」「特定の人に頼らず、仕組みとして育てる」という発想が欠かせません。この後の章で詳しく触れますが、ここに自社で育てていくスタイルと、外部の伴走役の組み合わせが効いてきます。
外注システムが現場に合わない理由
過去にシステム会社やベンダーに依頼してシステムを入れた経験がある方ほど、「また同じ失敗はしたくない」と感じているのではないでしょうか。外部にお願いすること自体が悪いわけではありませんが、任せ方を間違えると、現場に合わない仕組みが出来上がってしまいます。
よくあるのが、「要件定義の段階で、現場の声が十分に拾われていない」という問題です。打ち合わせには管理部門や情報システム部門だけが出席し、現場の細かな流れやクセ、道具の置き場所、紙の書類の回し方といった情報が十分に伝わらないまま設計が進んでしまうことがあります。そうすると、画面上ではきれいに見えるものの、実際の現場では手が足りなかったり、あちこち歩き回らないと入力できなかったりして、「これなら紙の方がまだマシだ」という感想につながってしまいます。
また、「ちょっとした変更や改善が自社だけではできない」ことも大きなストレスになります。例えば、「項目を一つ増やしたい」「チェック欄の選択肢を変えたい」といった小さな修正でも、都度見積もりや発注が必要だと、そのたびに時間とお金がかかります。その結果、「面倒だから、多少不便でもこのままでいいか」と我慢して使い続けるか、「いっそ使うのをやめよう」と投げ出してしまうかの二択になりがちです。
さらに、外注に任せるスタイルだと、「社内にノウハウが蓄積されにくい」という弱点もあります。システムの構造や設計の意図を知っているのはベンダー側だけで、社内には「使い方のマニュアル」しか残らないケースも多く見られます。これでは、事業や現場のやり方が変わったときに柔軟に対応できません。
こうした理由から、最近は「丸投げ」ではなく、「自社で触れる範囲を増やしながら、難しいところだけ外部の力を借りる」という考え方が注目されています。言い換えると、システム会社を「請負先」ではなく「一緒に走るパートナー」として位置づけるイメージです。
内製と伴走支援を組み合わせるメリット
では、自社のメンバーが中心となって仕組みを育て、外部の支援者が横でサポートする形を取ると、どんな良いことがあるのでしょうか。
まず大きいのは、現場目線での微調整を、短いサイクルで回せるようになることです。例えば、日報アプリを作ったあとに「この欄は要らなかった」「ここに写真を添付できると便利」といった声が上がったとします。そのとき、社内で画面を少し変えることができれば、試しに直して一週間動かしてみる、といった柔軟な試行錯誤ができます。伴走役は、その過程で「こういうときは項目を増やすより集計ルールを変えた方がいいかも」といったアドバイスを行い、行き過ぎた複雑化を防ぐ役割を担います。
次に、ノウハウが社内に蓄積されやすいというメリットがあります。最初は外部の力を借りながらであっても、画面を一緒に触り、作り方の考え方を共有していくことで、「このくらいなら自分たちでできる」という範囲が少しずつ広がっていきます。これにより、ちょっとした改善のたびに見積もりを依頼する必要が減り、スピード感もコスト面も楽になっていきます。
また、現場の人たちが「自分たちの道具」として愛着を持ちやすくなるのも重要なポイントです。外部が作ってくれた立派なシステムよりも、「現場リーダーとメンバーが一緒に考えて作った簡単なアプリ」の方が、意外と定着しやすいことはよくあります。「ここはうちの班長が考えた項目なんだよ」といったストーリーがあると、入力が「やらされ仕事」ではなく、「自分たちの段取りを良くするための道具」に変わっていきます。
そして最後に、伴走支援の存在は、「社内だけで抱え込まなくていい」という安心感にもつながります。新しいことにチャレンジするときは、どうしても不安がつきまといますが、「困ったら相談できる相手がいる」「詰まったら一緒に解きほぐしてくれる人がいる」と思えるだけで、踏み出しやすさは大きく変わります。伴走ナビとしても、まさにこの「安心して試行錯誤できる環境」を一緒に作ることを大事にしています。
自社で進めるDXの全体像と進め方

ここからは、実際に現場のデジタル化を社内主導で進めるときの全体像と、ざっくりとしたステップを整理します。難しい言葉や専門的な図はなるべく使わず、「明日から何をしたらいいか」をイメージしやすいレベルでまとめていきます。いきなり完璧な計画を作る必要はありませんが、ざっくりとした地図が頭にあるかどうかで、その後の動きやすさが大きく変わってきます。
着手前に整理したい現場の困りごと
まず最初の一歩としておすすめしたいのが、「現場の困りごと」と「こうなったらいいな」を、紙とペンでざっくり書き出してみることです。いきなりシステムの話をするのではなく、あくまで仕事の中身と流れに目を向けるイメージです。
例えば、次のような観点で話をしてみると、課題が見えやすくなります。
- 毎月、何となくモヤモヤしている作業はどこか
- ミスや手戻りが起きやすいのはどの工程か
- 「この人が休むと回らない」という属人化が強い業務はどこか
こうした話を、現場のメンバー数人と一緒にホワイトボードで書き出していくだけでも、「実は、在庫の場所が分からないのが一番ストレス」「設備が止まったときの情報共有がバラバラ」など、具体的なテーマが浮かび上がってきます。ここで大事なのは、「DXだからといって、いきなり全部を変えようとしない」ことです。
次に、その困りごとごとに、「こうなったらだいぶ楽になるよね」という理想の状態を言葉にします。例えば、「日報の紙を集めるのに毎朝30分かかっている」という困りごとに対しては、「昨日の実績が朝一ですぐに画面で見られる」「紙を回収しに歩き回らなくていい」といったイメージが出てくるかもしれません。この「こうなったらいいな」のイメージが、後でツールの選定や画面設計をする際の判断材料になっていきます。
ここまで来ても、まだツール名や具体的なシステムの話は出さなくて構いません。むしろ、ここを飛ばして「どのツールがいいか」という話から入ってしまうと、DXの目的が「ツールを入れること」になってしまい、本来解決すべき現場の課題がぼやけてしまいます。最初の段階では、「困りごと」と「こうなったらいいな」をことばで整理することに集中するのがおすすめです。
小さく始めて広げる進め方
次に考えたいのが、「どの順番で取り組むか」です。ここでよくある失敗が、「どうせやるなら一気に全部の業務をつなげよう」としてしまうことです。気持ちはよく分かるのですが、一度に大きな仕組みを作ろうとすると、検討が複雑になりすぎて、途中で疲れてしまいがちです。
おすすめは、小さなテーマを選んで試しにやってみて、その経験を次のテーマに活かしていくやり方です。例えば、いきなり工場全体の生産管理を変えようとするのではなく、「特定ラインの日報だけをデジタルにしてみる」「設備の異常停止の記録だけをアプリ化してみる」といった具合です。
小さいテーマを選ぶときのポイントとしては、次のようなものがあります。
- 関わる人が多すぎない(まずは一つの班や一つの工程に絞る)
- 成果が見えやすい(入力するとすぐにグラフや集計に反映されるなど)
- 現場の負担が増えすぎない(紙と二重入力にならないよう工夫する)
こうした小さなチャレンジを一つ成功させると、「あの方式を、今度は別ラインの作業指示にも応用できないか」といった形で、社内の中で自然と横展開のアイデアが出てくるようになります。伴走役として外部の支援者がいる場合は、「次に広げるときは、ここを変えた方がいい」「この設定は共通化しておいた方が後で楽」など、経験に基づいたアドバイスをもらえるので、試行錯誤のスピードも上がります。
現場・情シス・経営の役割分担
最後に、社内のどの立場の人がどう関わると進めやすいかを整理しておきます。ここがあいまいなままだと、「誰の仕事なのか」が分からず、気付けば誰も本気で関わらない、という状態になりがちです。
現場のリーダーや担当者には、「困りごとの洗い出し」と「試してみた感想をフィードバックする」役割が向いています。特に、「このチェック欄は現場では使われていない」「この順番だと入力しづらい」といった細かな気づきは、実際に作業している人にしか分かりません。最初から完璧な仕様を出そうとする必要はなく、「触ってみて感じたことを素直に伝える」ことが一番の貢献になります。
情報システム担当や、社内でITが得意な人には、「技術的なハードルの見極め」と「社内のルールとの整合性をとる」役割が向いています。例えば、「この情報は外部に出さないように設定しよう」「この操作は権限を分けた方が安全」といった判断です。また、ノーコードツールやkintoneのようなプラットフォームを使う場合、細かな設定を覚えたり、テンプレートを用意したりする役割も担いやすいでしょう。
経営層や管理部門には、「方向性を示し、腰を据えて取り組む空気をつくる」役割があります。DXの取り組みは、どうしても短期的には手間やコストが増える部分も出てきます。そのときに、「この期間は試行錯誤に時間を使っていい」「失敗も想定の範囲だから、恐れずにやってほしい」といったメッセージが出せるかどうかで、現場の動きやすさは大きく変わります。
外部の伴走支援は、これら三者の間をつなぐ「通訳役」「調整役」として機能することも多いです。現場の声を整理して経営に伝えたり、経営の意図をかみ砕いて現場に伝えたりしながら、「みんなが同じ方向を向いて進める状態」を作っていくイメージです。
無理なく始められる業務の選び方

どこから手を付けるかがぼんやりしたままだと、いつまでたっても検討だけが続きます。この章では、まず取り組みやすい業務の例を整理しながら、「あ、うちにも似たようなところがあるな」と感じてもらうことをねらいます。そのうえで、ノーコードツールやkintoneのようなサービスを使うとどんな画面が作れるのか、中小製造業でのイメージしやすいパターンを紹介し、最後に実際にあったケースをもとに「現場のちいさな成功」の雰囲気をお伝えします。
最初に取り組みやすい申請・日報・台帳
いきなり生産計画や原価計算といった難易度の高い領域に挑む必要はありません。むしろ、最初の一歩としておすすめなのは、「紙やExcelが多くて、手間は大きいけれど、仕組みとしてはシンプルな業務」です。例えば、残業申請や有給申請、設備の点検記録、作業日報の提出、在庫の持ち出し記録といったものが代表例になります。
これらの業務は、基本的には「誰が・いつ・何を・どれくらい」という情報を残すだけのシンプルな構造を持っていますが、紙や口頭で運用していると、集めるのも集計するのも管理するのも一苦労です。現場からすると、「記入欄が多くて書くのが面倒」「どの紙が最新か分からない」「どこに提出すればいいのか迷う」といったストレスにつながり、管理側からすると、「入力漏れがないか毎回チェックが大変」「Excelに転記している時間がもったいない」という悩みが生まれがちです。
こうした業務を最初の題材に選ぶと、比較的短い期間で効果を実感しやすいというメリットがあります。紙の回収や転記の手間が減るだけでも、担当者の残業時間が目に見えて変わることは少なくありません。また、「紙のこの項目と、この手書きの丸印は、画面ではこう表現しよう」と、既存の運用をそのままベースに考えやすいため、現場との会話も進めやすくなります。
kintoneで作る現場アプリのイメージ
次に、ノーコード系のツール、とくにkintoneのようなサービスを使うと、どんな雰囲気のアプリが作れるのかをイメージしてみましょう。専門的な言葉で説明するより、「日報アプリ」「設備点検アプリ」といった身近な例のほうが想像しやすいと思います。
例えば、日報アプリの場合、「日にち」「担当者」「ライン」「製造数量」「不良の内容」「一言メモ」といった項目を、紙の日報と同じような並びで画面上に配置します。現場の人は、タブレットやPCからその画面を開き、数字や文字を入力し、必要なら写真も添付します。送信ボタンを押せば、その瞬間に管理側の画面には一覧やグラフが表示され、翌朝の紙を回収してExcelに入れ直す、といった作業が不要になります。
設備点検アプリであれば、「設備名」「点検日時」「点検者」「チェック項目ごとの〇×」「異常の有無」「対応内容」といった項目を用意し、チェック項目はボタンやプルダウンで選べるようにします。紙のチェックシートと違い、「異常ありの場合だけ詳細を入力させる」「写真を必須にする」といった条件を設定することもできるので、後から見返したときに情報の抜け漏れを防ぎやすくなります。
ここで大事なのは、「最初から完璧な画面を作る必要はない」ということです。作ってみて、現場から「ここの順番、作業の流れと逆だから入れづらい」「この項目は実は使っていない」という声が出てきたら、そのつど画面を少しずつ直していけばいいのです。伴走役がいると、この“直し方のコツ”を教えてもらえるので、場当たり的に複雑にしてしまうリスクも減ります。
中小工場での小さな成功事例
ここでは、具体的な社名は出しませんが、よくあるケースをもとに「こんな感じで進んでいった」というイメージをお伝えします。
ある工場では、設備の故障や異常が発生したときの記録が、ノートやホワイトボードにバラバラに書かれており、後から原因を振り返るのが大変でした。そこで、まずは「設備トラブル記録アプリ」を作るところから始めました。最初の画面はとてもシンプルで、「いつ」「どの設備で」「どんな症状」「誰が対応したか」だけを入れる構成にして、とにかく現場の人が数十秒で入力できることを優先しました。
数週間使ってもらう中で、「停止時間も入れたほうが良さそうだ」「写真があると交換した部品が分かりやすい」といった声が出てきたため、画面を少しずつ改良していきました。数か月後には、月ごとのトラブル傾向をグラフで見られるようになり、「この設備は月初にトラブルが集中しているから、点検タイミングを変えよう」といった判断につながるようになっていきました。
印象的だったのは、現場リーダーの一言です。「最初は面倒くさいと思っていたけど、自分たちで”こうしたい”を反映していけると、ちょっと楽しくなってくるね」。この「自分たちで育てている感覚」が生まれると、次の内製テーマに取り組むときのハードルがぐっと下がります。伴走ナビの支援でも、こうした小さな成功体験をいかに早く一緒に作るかを、とても大切にしています。
外部の伴走支援の選び方

ここまで、自社主導で仕組みを育てていくイメージをお伝えしてきましたが、「とはいえ、社内だけで全部やるのは不安」「誰かに並走してほしい」という声も多く聞かれます。この章では、外部の支援を受けるときに気をつけたいポイントと、単なる作業代行との違いを整理しながら、どんな観点でパートナーを選べばよいかを考えていきます。そのうえで、伴走ナビとしてどんなスタンスで現場を支えているのかも具体的にご紹介します。
作業代行と伴走支援の違い
まず押さえておきたいのは、外部の支援といっても、そのスタイルは大きく二つに分かれるということです。一つは、仕様書をもとにシステムを作って納品する「作業代行型」。もう一つは、企画や設計の段階から一緒に考え、運用や改善にも継続的に関わる「伴走型」です。どちらが良い悪いではありませんが、自社で仕組みを育てていきたい場合には、後者のほうが相性が良いことが多いです。
作業代行型では、「何を作るか」をできるだけ最初に固め、そのとおりに構築してもらうのが基本です。決まったものを素早く作るのは得意ですが、作っている途中で「やっぱりここは変えたい」「使ってみたらイメージと違った」となったときに、柔軟に軌道修正するのはそれほど得意ではありません。社内にノウハウが蓄積されにくく、「直したいときはまた見積もりをお願いする」という構図にもなりがちです。
一方の伴走型は、最初から完璧な正解を目指すよりも、「小さく作って試し、直しながら育てていく」ことを前提にしています。現場の会話の中で課題を一緒に言語化し、「それなら、この部分を先にアプリ化してみましょう」「この項目は、最初は紙のまま運用して様子を見てもいいですね」といった提案をしながら進めていきます。ポイントは、外部がすべてを決めるのではなく、社内のメンバーがちゃんと意思決定に関わる形になっているかどうかです。
支援会社選びのチェックポイント
では、どんな観点で支援会社を選ぶとよいでしょうか。ここでは、いくつか代表的なポイントを挙げてみます。
まず大事なのは、「製造現場のイメージが共有できるかどうか」です。工場を一度も見たことがない人に話すのと、現場の音や匂い、動きの雰囲気を知っている人に話すのとでは、会話の噛み合い方がまったく違ってきます。打ち合わせのときに、「現場ってこんな感じですよね」と具体的なイメージを交えながら話してくれるかどうかは、一つの目安になります。
次に、「ノーコードでの内製を前提にしているかどうか」も重要です。システム会社の中には、どうしても自社の開発案件を増やしたいあまり、「ここは難しいので、社内で触らないほうがいいですよ」と何でも黒箱化してしまうところもあります。内製を進めたい場合は、「ここまでは現場で触れるようにしましょう」「この部分は危ないので、こちらで守ります」といった、線引きを一緒に考えてくれる支援者のほうが心強いはずです。
また、「現場の人が話しやすい雰囲気かどうか」も見逃せません。どれだけ技術力があっても、現場の人が遠慮して本音を言えない関係性だと、本当に困っているポイントが見えてきません。ちょっとした冗談も交えながら、良い意味で肩の力を抜いて話せるかどうかは、打ち合わせの場の空気感からも伝わってきます。
伴走ナビが現場と並走できる理由
伴走ナビでは、こうしたポイントを踏まえながら、中小製造業の現場に寄り添った支援を心がけています。特徴的なのは、「ツールの話」だけでなく「現場の運用や人の動き」の話をセットで考えるスタンスです。
例えば、「このアプリを入れたら報告が楽になりますよ」で終わらせるのではなく、「その報告を誰がいつ見るのか」「見た結果、どんな判断やアクションにつなげたいのか」まで一緒に整理します。そのうえで、「だったら、ここに簡単なアラートを付けておきましょう」「この集計画面は、朝礼で使いやすい形にしておきましょう」といった具体的な提案を行います。
また、kintoneを使った内製支援の経験が多いことから、「最初のアプリは一緒に作り、二つ目からは現場の担当者が主体になって作る」といった育て方を意識しています。実際に、最初はまったくツールに触ったことがなかった工場の担当者が、半年後には自分で簡単なアプリを作れるようになり、「これなら、ちょっとした改善は自分たちだけで回せそうです」と話してくださるケースも増えてきました。
もちろん、すべての会社に同じやり方が合うわけではありません。だからこそ、「うちの現場だと、どんな進め方が現実的か」「この一年でどこまでできると良さそうか」といった話を、ざっくばらんに相談していただける場として、無料相談や資料請求の窓口をご用意しています。いきなり大きな決断を迫ることはありませんので、「まずは話を聞いてみたい」という気持ちで気軽に使っていただければと思います。
DXでよくある失敗と防ぎ方

最後の内容編として、取り組みの途中で陥りがちな失敗パターンと、その防ぎ方を整理します。「せっかく始めたのに、いつの間にか使われなくなっていた」「結局、一人の担当者だけがツールに詳しくて、後が続かない」といった状態は、決して珍しくありません。この章では、ありがちなつまずきを先回りして知っておくことで、同じ落とし穴にはまりにくくすることをねらいます。
ツール導入だけで終わらせないために
まず代表的なのが、「ツールを導入すること自体がゴールになってしまう」パターンです。導入前は社内で説明会を開き、マニュアルも配り、最初の数週間はそれなりに入力されているものの、気付けば入力する人が限られてしまい、データも偏ってしまう。やがて、集計結果も信用されなくなり、誰も見なくなる……という流れです。
このパターンを防ぐには、導入前の準備として、「入力する人にとってのメリット」と「使う場面」をセットで設計しておくことが重要です。例えば日報であれば、「入力してもらったデータは、翌朝の朝礼でこのグラフとして使う」「不良が多い工程は週次の改善ミーティングで必ず話題にする」といった「使われ方」を具体的に決めておきます。そうすると、現場の人も「自分たちの入力がちゃんと役に立っている」と実感しやすくなり、モチベーションの維持につながります。
また、入力の手間をできるかぎり減らす工夫も欠かせません。同じ情報を二度三度と入れさせない、紙と画面の二重運用期間を必要以上に長引かせない、現場の動線上で自然に入力できる端末配置を考えるといった地味な工夫が、定着の成否を分けます。伴走支援では、実際に入力する人の動きをイメージしながら、「この画面、本当に現場で触れるかな?」という視点で一緒に見直していきます。
属人化とブラックボックス化を防ぐ工夫
次に怖いのが、「詳しい人が一人だけいて、その人がいなくなると誰も触れない」状態です。ノーコードツールは、確かに専門的なプログラミングよりは取っつきやすいのですが、それでも設定画面や用語に慣れていないと、「壊したらどうしよう」と不安になってしまいます。その結果、特定の担当者にすべてが集中し、相談もその人にしか行かず、忙しさが増してさらに属人化が進む、という悪循環にはまりがちです。
このリスクを避けるには、最初から「二人以上で覚える」「必ず手順を残す」というルールを組織として決めておくのがおすすめです。例えば、「アプリの設定を変えるときは、必ず画面のスクリーンショットを残しておく」「変更した内容は簡単なメモでもよいので共有フォルダに保存する」といった、シンプルなルールから始められます。それだけでも、「何をどう変えたか」が後から追いやすくなり、別の人が引き継ぐ際のハードルが下がります。
さらに一歩進めて、「月に一回、内製アプリの勉強会を開く」といった場を設ける会社もあります。現場の担当者が、最近追加した機能や困っていることを持ち寄り、隣の人に教えたり一緒に解決策を考えたりする時間です。伴走ナビでは、こうした場に同席し、技術的なフォローや「別の会社ではこんな工夫をしていましたよ」といった事例を紹介することで、社内に少しずつノウハウが広がっていくお手伝いもしています。
稟議と費用対効果の伝え方
最後に、多くの会社で悩みの種になるのが、「稟議の通し方」です。どれだけ現場が困っていても、投資に対する説明がうまくできないと、あと一歩のところで止まってしまいます。ここで大切なのは、「数字だけで勝負しすぎないこと」と「分かりやすい例えで伝えること」です。
もちろん、「残業時間が月に何時間減りそうか」「紙や印刷物のコストがどれくらい削減できそうか」といった数字を見積もるのは重要です。ただ、現場の実感に近い形で説明するためには、「この仕組みがないと、どんなリスクがあるか」も合わせて伝えると効果的です。例えば、「設備トラブルの記録が残っていないと、同じ故障を何度も繰り返してしまう」「不良の傾向が見えないと、大口クレームのリスクが高まる」といった具合です。
そのうえで、「まずは一年目にここまでできれば成功」「二年目以降は社内での内製比率を高めてコストを抑えていく」といった中期的な見通しを示すと、経営層としても判断しやすくなります。伴走ナビの無料相談では、このあたりの説明資料の組み立ても一緒に考えることが多く、「こういう説明ならうちの役員にも伝わりそうです」と言っていただけるケースも増えています。
まとめ|明日から始める小さな一歩
ここまで、「現場の困りごとを起点に、小さく始めて育てていくスタイルのデジタル化」と、それを支える外部の伴走支援についてお話ししてきました。一気にすべてを変えようとしなくても、現場に合ったテーマを一つ選び、内製しやすいツールを使いながら試行錯誤を重ねていくことで、気付けば会社全体の動き方が少しずつ変わっていきます。大事なのは、「完璧な計画ができるまで動かない」のではなく、「まず一歩、小さく動いてみる」ことです。
最後に、この記事を読んでくださった方に向けて、明日からできるアクションの例をいくつかご提案します。
1. 現場メンバーと一緒に、困りごとを三つだけホワイトボードに書き出してみる
2. その中から、「紙やExcelが多くて、構造がシンプルな業務」を一つ選んでみる
3. 「こうなったら楽になるよね」という理想の姿を、ざっくり会話で共有してみる
4. 社内にツールに強そうな人がいれば、ざっくり相談してみる
そしてもし、「うちの状況だと、どこから手を付けるのが良さそうか」「kintoneのようなツールを使うと、どんなイメージになりそうか」といった点で悩まれたら、一度、第三者の視点を入れてみるのも一つの手です。伴走ナビでは、中小製造業の現場と一緒に試行錯誤してきた経験をもとに、無料相談の場でざっくばらんにお話をお伺いしています。
「まだ具体的に決まっていないのですが」「社内で検討するための材料が欲しいだけなのですが」という段階でも、もちろん問題ありません。まずは資料請求で情報を集めていただき、社内のメンバーと一緒にこの記事の内容とあわせて検討してみてください。そのうえで、「少し話を聞いてみようか」と思っていただけたタイミングで、無料相談をご活用いただければうれしいです。
明日からの一歩は、決して大きなものでなくて構いません。紙とペンを手に取り、「今、一番モヤモヤしているところはどこだろう」と書き出してみる。その小さな行動こそが、現場に根付くDXの、確かなスタートラインになります。