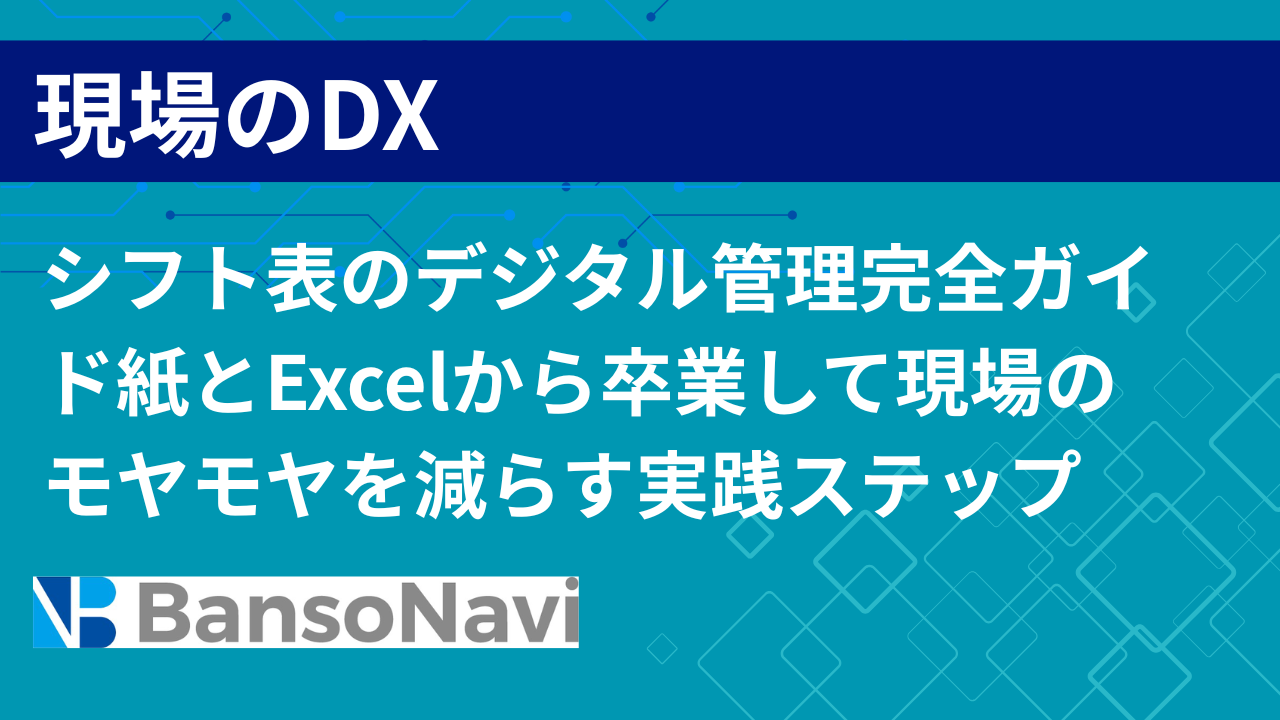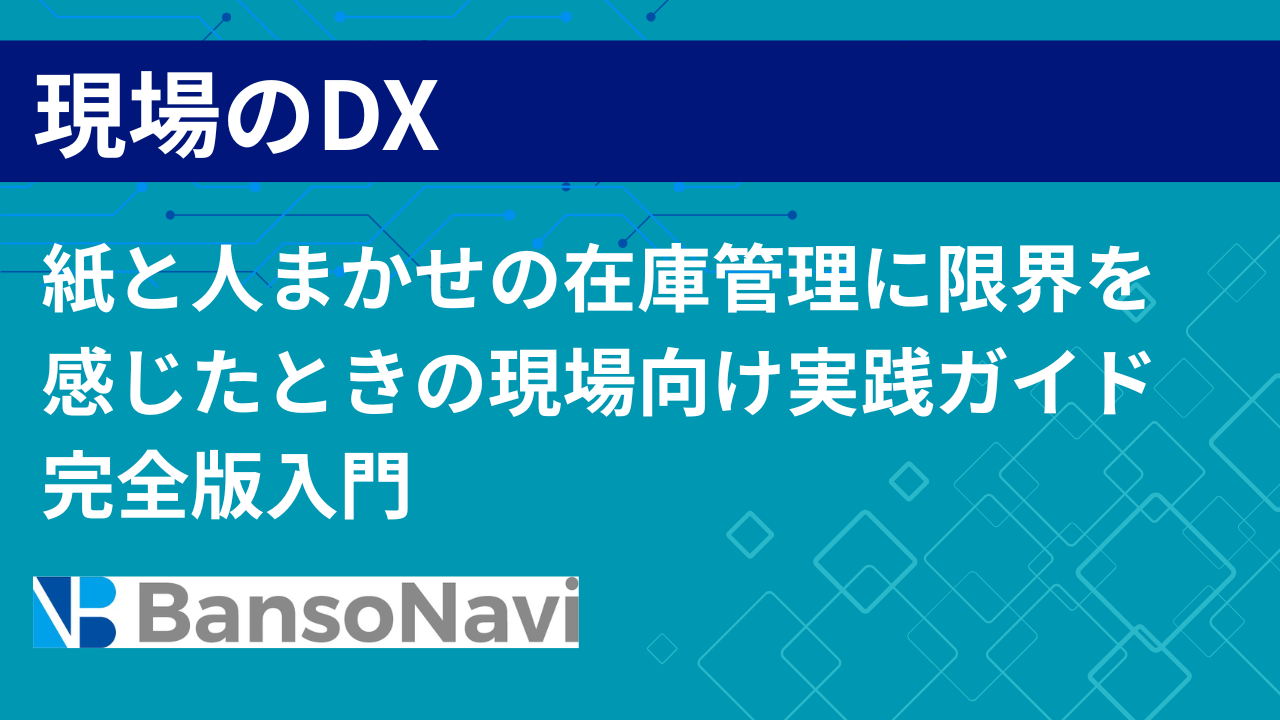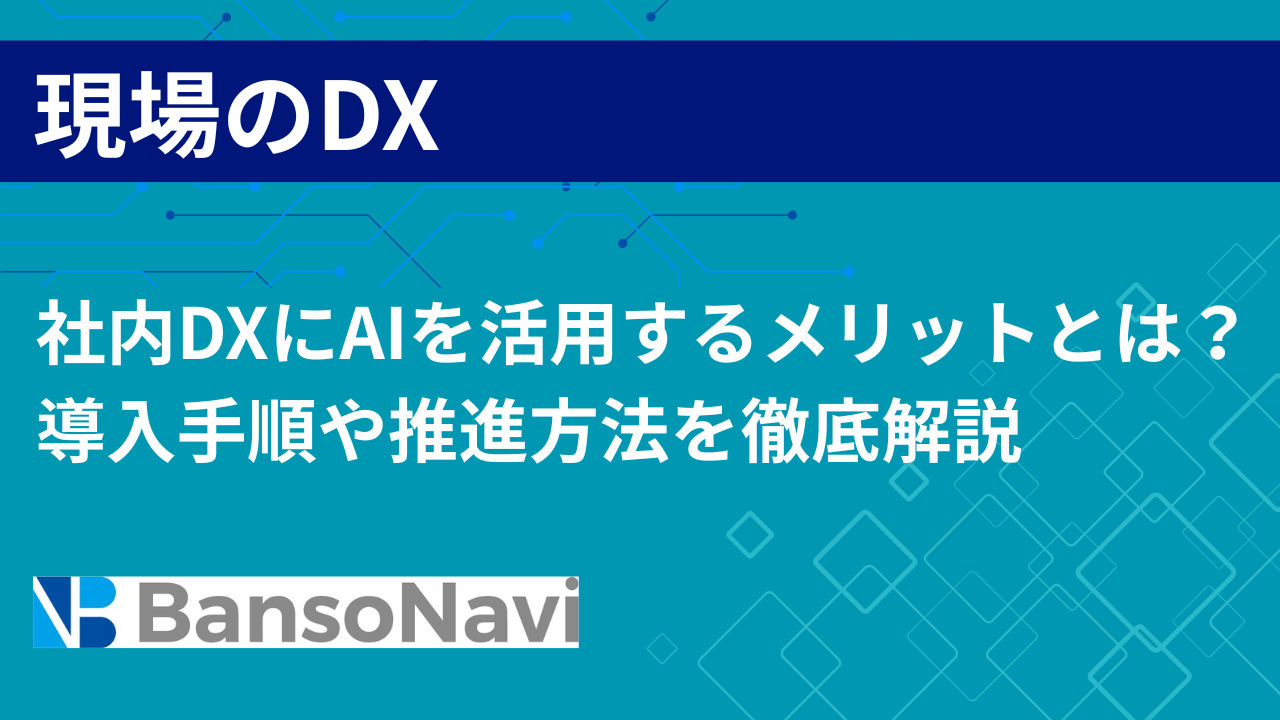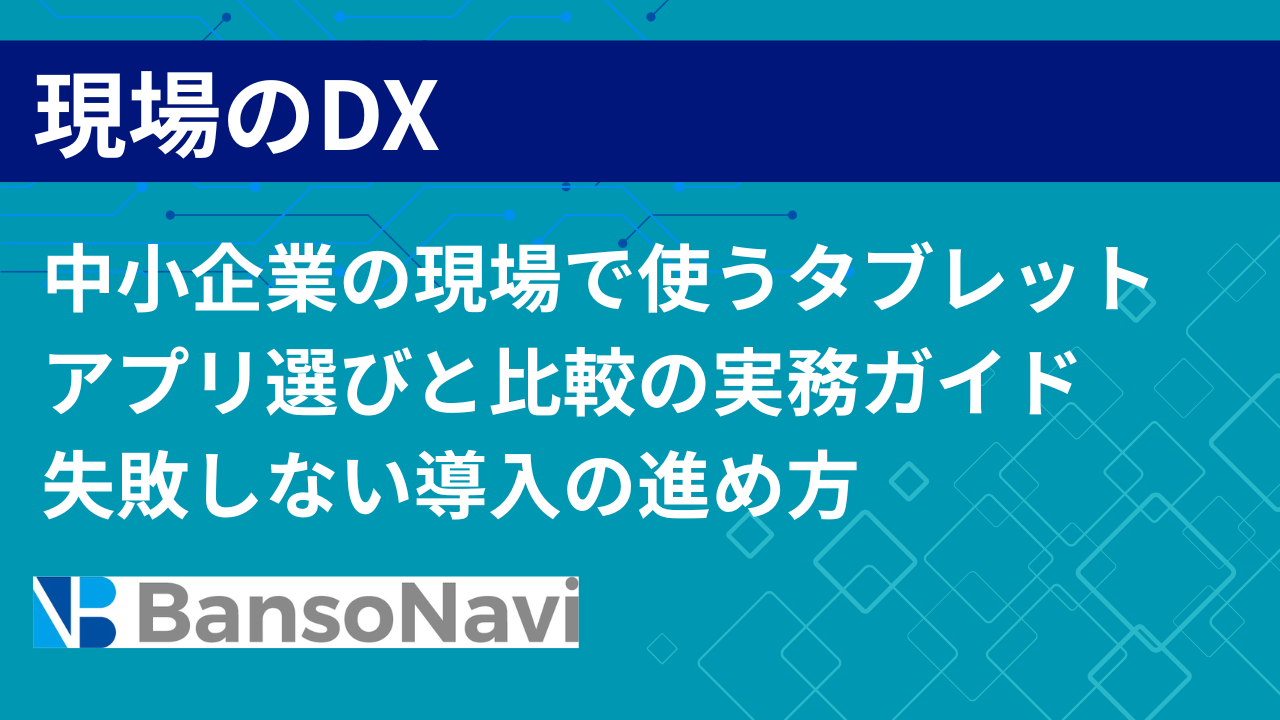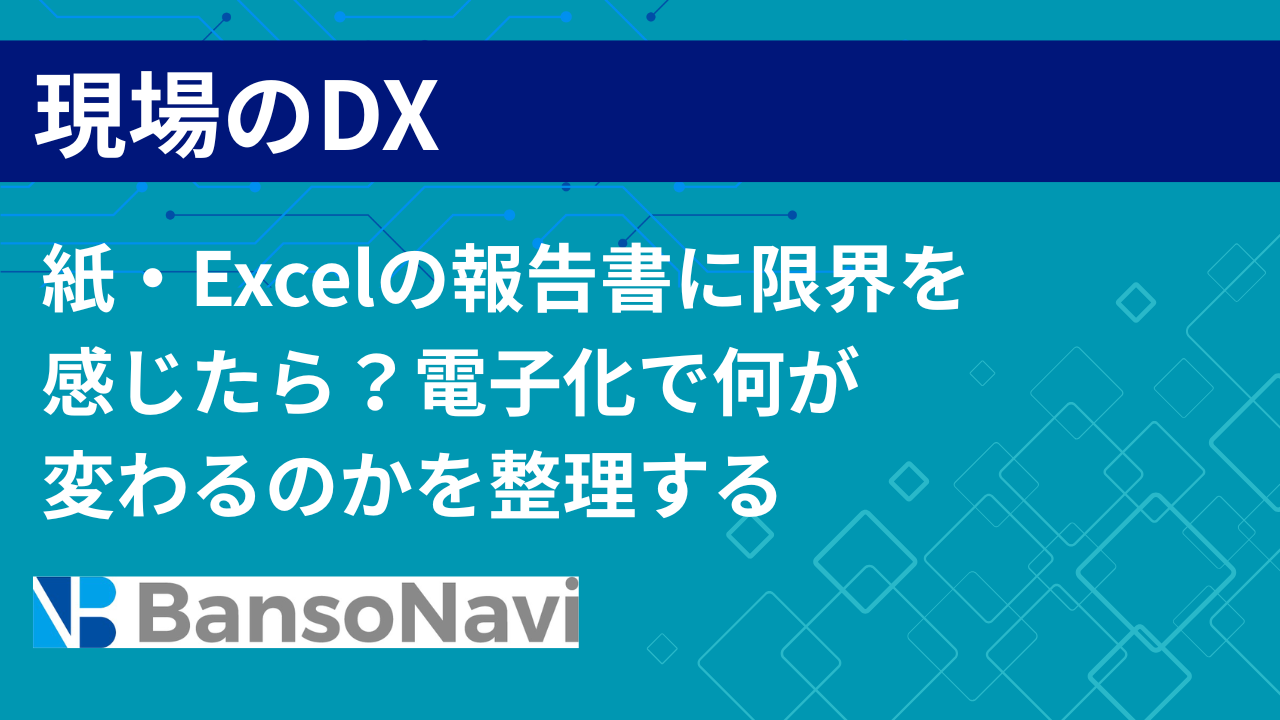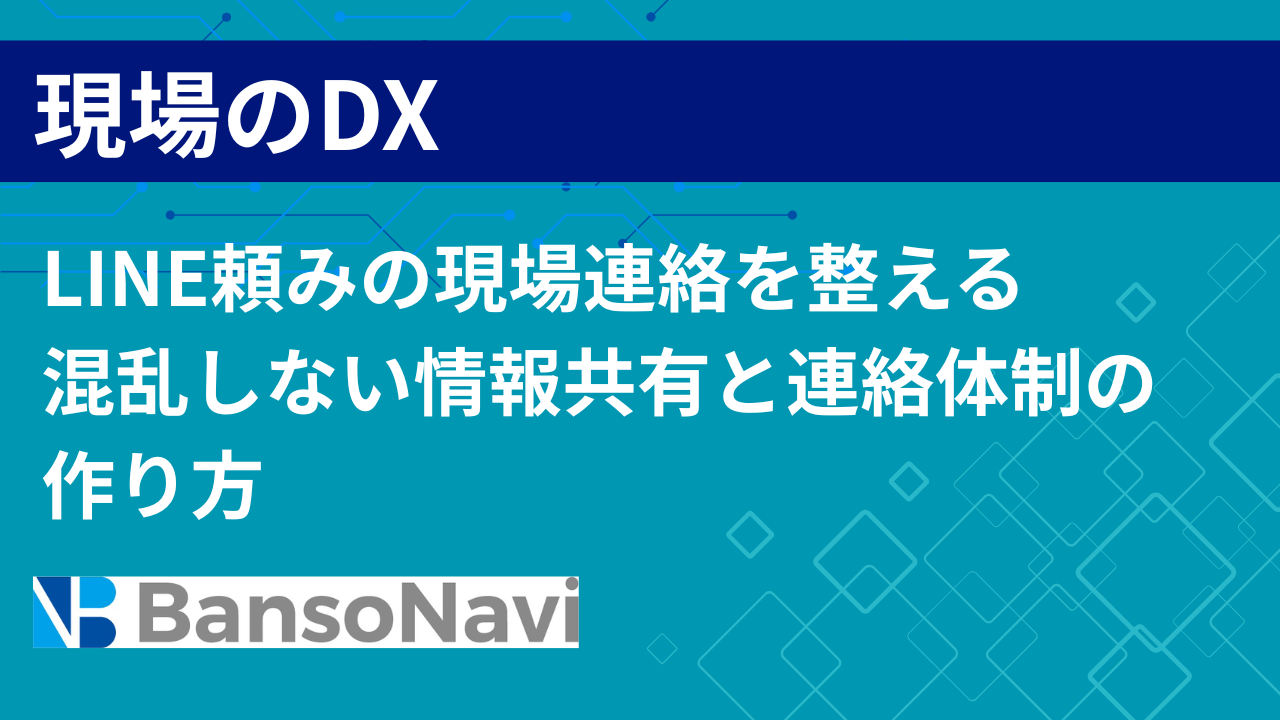現場DX事例をやさしく解説:中小企業の現場がまねできる成功パターンとムリなく進めるステップ
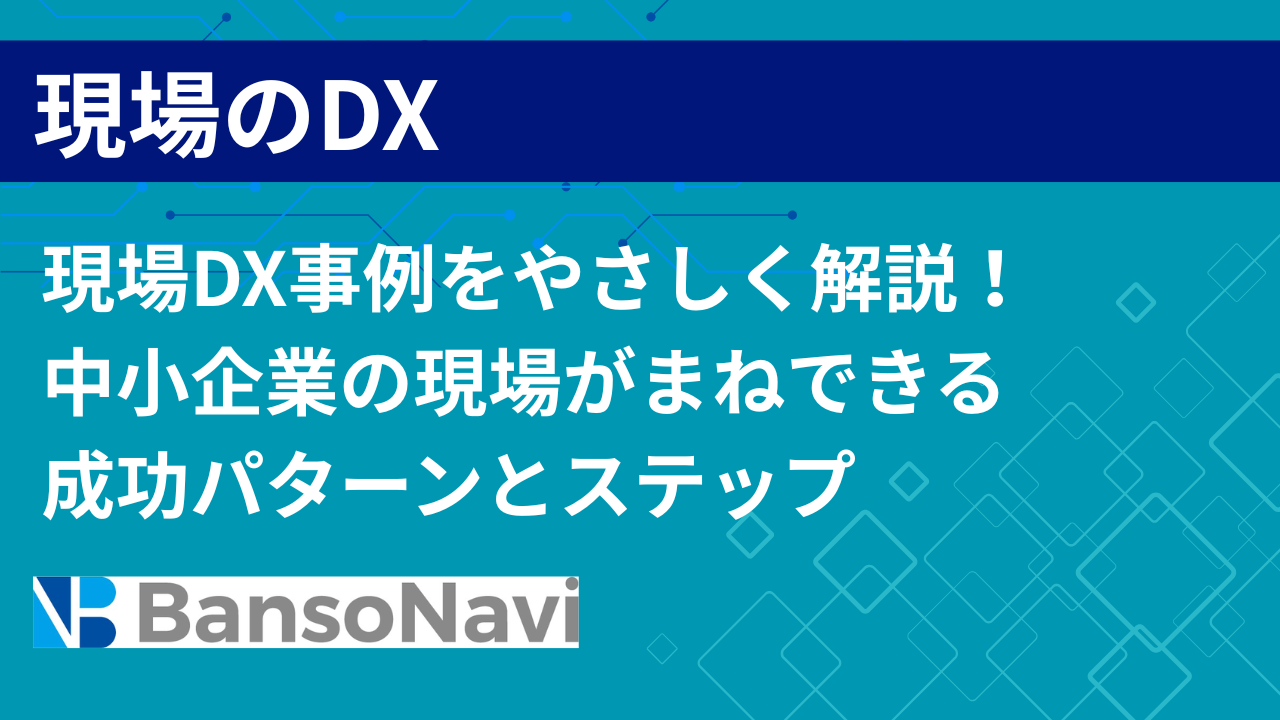
「現場 DX 事例」で検索している方の多くは、
- 「ウチみたいな中小企業の現場でも本当にできるの?」
- 「難しいシステムを入れないといけないのでは?」
- 「そもそも何から手をつければいいか分からない」
というモヤモヤを抱えていることが多いです。
この記事では、そんな不安を少しずつほどきながら、実際の現場 DX 事例をイメージしやすい言葉で紹介していきます。紙の日報・エクセル・ホワイトボード・口頭引き継ぎといった身近なところから、「こう変わるとラクになる」という変化を具体的にお伝えします。
あわせて、
- 現場DXとは何かの基本
- 製造・建設・小売サービスの現場 DX 事例
- ノーコードとkintoneを使ったDX内製化のイメージ
- 自社で一歩目を踏み出すためのステップ
- 失敗しないためのコツと、伴走ナビに相談できること
まで、一気通貫で整理します。読み終わるころには、「まずこの業務から試してみよう」と社内で話せるレベルになることをゴールにしています。
目次
現場DXとは何か?

現場DXという言葉はよく耳にするものの、「IT導入と何が違うの?」「大企業だけの話では?」と感じる方も多いです。最初にここを整理しておくと、後から出てくる現場 DX 事例を自社に引き寄せて考えやすくなります。難しく考えすぎず、「現場の困りごとがデジタルの力でラクになること」くらいのイメージからで十分です。
そもそも現場DXとは何か?
DXと聞くと、「AI」「IoT」「ビッグデータ」など難しい言葉が頭に浮かびがちですが、現場DXのスタート地点はもっと素朴です。例えば、今まで紙とエクセルでやっていたことが、スマホやタブレット、簡単なアプリに置き換わり、「入力の二重三重がなくなる」「探す時間が減る」「誰が見ても同じ情報が分かる」といった変化が起きている状態を指します。
経済産業省や中小企業基盤整備機構の調査でも、DXに期待する効果として一番多いのは「コスト削減・生産性向上」「業務の自動化・効率化」といった、とても現場寄りのテーマです。
つまり、派手な最新技術を入れることが目的ではなく、「今ある仕事のやり方を、デジタルを使ってムダなくスムーズにする」が現場DXの本質です。
もう少し噛み砕くと、現場DXには次のようなレベルがあります。
- 紙の作業をやめて、入力や保管をデジタル化する
- バラバラな表やメモをつなげて、流れとして見えるようにする
- ためたデータを使って、「どこでムダが出ているか」「どの案件がもうかっているか」を見極められるようにする
いきなり三つ目を目指す必要はありません。多くの中小企業では、まず一つ目と二つ目に取り組むだけでも、現場の負担感がかなり変わるケースがほとんどです。
なぜ今、現場DXが必要なのか?
「昔から紙とエクセルで回してきたし、今もなんとかなっている」という会社も多いと思います。それでも現場DXが必要と言われる背景には、次のような変化があります。
- 採用が難しく、人数を増やしにくいのに仕事は増えている
- ベテラン社員の退職が近づき、「あの人しか分からない仕事」が多くなっている
- 取引先や親会社から、データでの報告やスピードアップを求められることが増えている
実際の調査でも、「DXに取り組んでいる、または検討している」企業は全体の4割超まで増えていますが、特に従業員20人以下の小さな企業では、まだ2〜3割にとどまっています。
一方で、DXに取り組んだ企業の8割以上が「何らかの成果が出ている」と回答しているというデータもあり、やった会社とやっていない会社の差がじわじわ広がっているのが実態です。
現場DXは、「かっこいいことをする」ためではなく、次のようなリスクを減らすための取り組みとも言えます。
- 人が増えない中で、現場が疲弊してミスが増える
- 属人化した業務が引き継がれず、突然回らなくなる
- 紙の情報が多すぎて、トラブル時に必要な情報がすぐ出てこない
このような「ちょっと困っている」「この先が不安」という感覚があるなら、規模の大小に関わらず、現場DXに取り組む価値は十分にあります。
現場 DX 事例を見るときのポイント
「現場 DX 事例」を検索すると、たくさんのツール名や専門用語が出てきますが、最初からそこに目を奪われてしまうと、「結局よく分からない」で終わりがちです。事例を見るときに大事なのは、どのツールを入れたかではなく、「現場でどんな変化が起きたか」に注目することです。
例えば、次のような視点で読んでみるのがおすすめです。
- どんな現場の困りごとを、どこまで減らせたのか
- 紙やエクセルで何をしていたのか、それがどう変わったのか
- 現場の人が「ラクになった」と感じた瞬間はどこか
- 数字で見える効果(残業時間、不良率、問い合わせ件数など)はあったか
この視点で見ていくと、「ウチの現場でも似たようなことができそう」「これはうちには合わないかも」と判断しやすくなります。
伴走ナビでも、kintoneなどのノーコードツールを使った現場 DX 事例を紹介するときは、必ず「ビフォー・アフター」と「現場メンバーの声」をセットで整理するようにしています。ツールの名前を覚えるより、「こういう困りごとには、こういう変え方がある」というパターンとしてストックしていくイメージです。
現場 DX 事例を業種別に紹介

ここからは、実際の現場 DX 事例をイメージしやすいように、「製造」「建設・保守」「小売・サービス」の三つに分けて紹介します。あくまで代表的なパターンですが、具体的なシーンを思い浮かべながら読むことで、自社の現場DXのヒントにつながります。
製造業の現場 DX 事例
製造業の現場でよくあるのが、「紙の日報」と「エクセル集計」の二重管理です。現場の作業者が紙に手書きで工程や不良内容を記入し、それを事務担当がエクセルに打ち直して集計する、という流れです。この「転記作業」と「読みにくい手書き」が、ミスや残業時間の大きな原因になっているケースが少なくありません。
ある中小の部品メーカーでは、kintoneを使って「日報アプリ」と「不良記録アプリ」を作り、現場の作業者がタブレットから直接入力する形に変えました。現場では次のような変化が起きました。
- 日報の提出が「紙の回収」から「リアルタイム反映」に変わり、管理者がその日のうちに状況を確認できる
- 不良の種類や原因をプルダウンで選ぶようにしたことで、記載モレや読み間違いが減った
- 月末の集計は、ボタン一つでグラフまで出せるようになり、残業時間が大きく減った
この会社では、導入から数カ月で不良率が目標値を切り、「残業が減ったのに、なぜか前より状況がよく見える」という声が現場から出てきました。
重要なのは、最初から完璧な仕組みを作ろうとせず、「今の紙の日報を、そのままデジタルに移す」くらいの感覚で始めたことです。現場 DX 事例として見るときは、「何を捨てて、何をそのまま活かしたのか」というバランスもチェックポイントになります。
建設・保守現場の DX 事例
建設業や設備保守業の現場では、「現場からの報告がバラバラのチャットやメールで送られてきて、後から追いかけるのが大変」という悩みをよく聞きます。特に写真報告は、
- 誰が、いつ、どの現場の写真を送ったか分かりにくい
- 後から図面番号や工事番号と紐づけるのに時間がかかる
- 証跡として残したいのに、フォルダ構成が人によってバラバラ
という問題が起きがちです。
ある設備保守会社では、現場DXの一環として、kintone上に「現場報告アプリ」を作りました。現場スタッフはスマホから、
- 案件を選ぶ
- 作業前・作業後の写真を撮る
- 簡単なコメントと作業時間を入力する
だけで、本社側の管理画面にリアルタイムで情報が集まるようにしました。
結果として、次のような効果が出ました。
- 現場からの報告漏れがほぼゼロになり、クレーム時の説明がしやすくなった
- 工事別の原価管理がしやすくなり、「どの現場でどれくらい時間がかかっているか」が見えるようになった
- 今まではベテランしか判断できなかった「現場の危うさ」を、写真と履歴で共有し、教育にも使えるようになった
「チャットツールで写真を送る」から「アプリに写真を登録する」へ変えただけに見えますが、情報の整理のしやすさは大きく違います。建設や保守の現場 DX 事例では、こうした「写真+案件+時間」をワンセットで扱える仕組みが、現場の安心感と本社の管理のしやすさを両立させる鍵になっています。
小売・サービス業の DX 事例
小売やサービス業の現場でよくあるのが、次のような「バラバラ管理」です。
- シフトはエクセル、共有は紙の掲示+チャット
- 在庫は店長の頭と、なんとなくの勘で発注
- 顧客メモは担当者のノートや個人PCのファイル
これらが原因で、「情報があるのに共有されていない」「属人化していて引き継ぎが難しい」という悩みが生まれます。
ある複数店舗を持つ小売店では、kintoneを使って、
- シフト管理アプリ
- 店舗別在庫アプリ
- 顧客メモアプリ
を順番に作り、少しずつ現場DXを進めていきました。
最初はシフトから始め、「誰がいつ出勤しているか」「店長不在の日に経験者がどれだけいるか」が一目で分かるようにしました。その後、発注ミスや欠品が多いカテゴリーだけを対象に、在庫アプリを試験導入。最後に、常連さんの好みや注意事項を残せる顧客メモを追加していきました。
この結果、
- 「シフト表を撮ってグループLINEに流す」運用が不要になり、変更もすぐ反映できる
- 欠品や在庫過多の原因が、「どの店舗」「どの時間帯」で起きているか分析しやすくなった
- 顧客メモを見ながら接客できるようになり、指名やリピート率が上がった
という、売上にもつながる効果が見えてきました。
現場 DX 事例として重要なのは、一度に全部をデジタル化しようとせず、「一番困っているところ」から順番に取り組んだことです。小売・サービスの現場では、「シフト」「在庫」「顧客」のどこから始めるかを決めるだけでも、現場DXの一歩になります。
ノーコードとkintoneを活用した「現場DXの内製化」事例
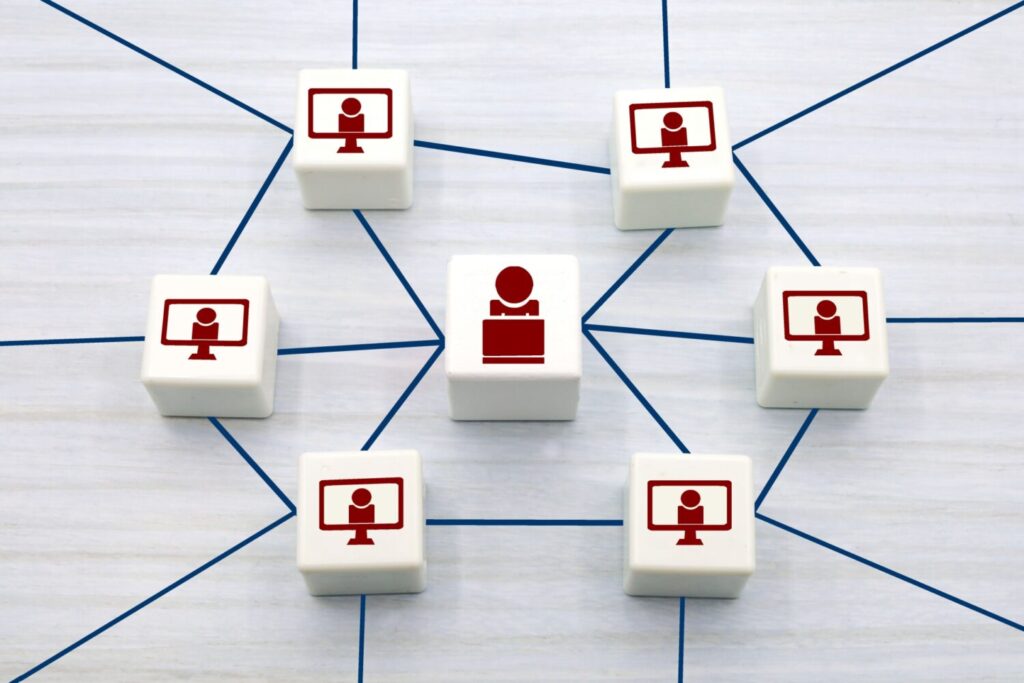
ここまでの現場 DX 事例は、どれもシステム開発会社にフルスクラッチで依頼しなくても、ノーコードツールを使うことで実現できる内容です。特にkintoneのような「業務アプリを自分たちで組み立てられるツール」は、「最初は専門家と一緒に作り、その後は社内で育てていく」DX内製化との相性がとても良いのが特徴です。
ノーコード×kintoneで実現した現場DX
多くの現場では、「台帳」という言葉で呼ばれるエクセルファイルがいくつも存在しています。顧客台帳、案件台帳、設備台帳、売上台帳など、それぞれが別ファイルで管理されている状態です。これをkintone上に移し、「動く台帳」に変えていくのが、伴走ナビがよくお手伝いしているパターンの一つです。
例えば、建設系の会社でよくある構成は次のようなものです。
- 顧客台帳アプリ:会社情報や担当者、過去の工事履歴を管理
- 案件台帳アプリ:見積もり〜契約〜工事〜請求までのステータスを管理
- 現場報告アプリ:先ほどの写真報告や作業内容を紐づけて記録
- 売上・原価アプリ:案件ごとの収支をまとめて確認
これらを「顧客」「案件番号」でつなげることで、
- 過去にどんな工事を、どの単価でやったか
- 現場ごとの粗利率がどう推移しているか
- クレームやトラブルが起きた案件の共通点は何か
といったことが、現場や経営者の目線で確認できるようになります。
ここで重要なのは、最初から完璧に設計しようとせず、「今使っている台帳をそのままアプリ化する」から始めることです。その後、使いながら「この項目はいらない」「この情報も追加したい」と現場の声を反映し続けることで、自社にフィットした「動く台帳」に成長していきます。
外注丸投げにしない進め方
現場DXが失敗しやすいパターンの一つが、「最初から全部、外部の開発会社に丸投げしてしまう」ケースです。要件定義書を作って、数カ月かけてシステムを作り、一度リリースしたらなかなか手直しができない、という流れになりがちです。これだと、現場の業務が変わるたびに「また大きな改修」が必要になり、結果として使われなくなってしまうことも多いです。
ノーコード×kintoneを使った現場DXでは、次のような進め方が現実的です。
- 最初の設計と立ち上げは、伴走ナビのような外部パートナーと一緒にやる
- 現場メンバーの中に「ちょっと触れる人」を1〜2人育てていく
- 小さな改善(項目追加、画面並び替え、集計の追加)は、社内で回せるようにする
こうすることで、現場DXのスピードと柔軟性が大きく変わります。現場で新しいアイデアが出たら、その場で画面を見ながら「この項目足しましょうか」「この条件で一覧を絞り込みましょう」といった会話ができるようになるからです。
伴走ナビでは、単にアプリを作るだけでなく、「社内でアプリを育てていける人」を一緒に育てることを大事にしています。これが、DX内製化の一番のポイントです。
現場DXを自社で進めるステップ

ここまでの現場 DX 事例を読んで、「うちもやったほうがいいのは分かったけれど、具体的にどう動けばいいか分からない」という方も多いと思います。明日からできるレベルに分解したステップとして、シンプルに二つの流れに絞って整理します。
ステップ1:現場の困りごととムダ時間を書き出す
いきなりツール選びから入ると、ほぼ確実に迷子になります。最初にやるべきことは、現場の「困っていること」と「ムダになっている時間」を、できるだけ具体的に書き出すことです。ここでは難しいフレームワークは使わず、シンプルに次のような観点でヒアリングしていきます。
- 毎月・毎週・毎日、「正直ちょっとしんどいな」と感じている作業は何か
- 紙やエクセルへの転記作業、二重入力が発生しているところはどこか
- 「あの人がいないと分からない」情報はどこに隠れているか
- トラブルが起きたとき、「過去の情報を探すのが大変」な場面はないか
現場ヒアリングが苦手な方は、次のような質問から始めると話しやすくなります。
- 一日の中で「これさえなければなぁ」と思う作業はありますか?
- 最近一番ヒヤッとしたミスやトラブルは何でしたか?そのとき、どの情報がすぐ出てこなかったですか?
- 「紙じゃないほうがいいよな」と感じている帳票はありますか?
この段階では、「解決策」まで考える必要はありません。とにかく現場の言葉で困りごとを並べ、その中から「似ているもの」「影響が大きいもの」をグルーピングするのがポイントです。伴走ナビでも、最初の打ち合わせではツールの話より先に、この「困りごとマップ」を一緒に作るところから始めています。
ステップ2:スモールスタートで「最初の現場 DX 事例」を作る
困りごとが見えてきたら、次は「どれから着手するか」を決めます。ここで大切なのは、いきなり全社横断の大きなテーマを選ばないことです。最初の現場DXは、「範囲が小さくても、現場がすぐ変化を感じられるテーマ」を選ぶのがおすすめです。
例えば、次のような観点で候補を絞り込んでいきます。
- 関わる人数が多すぎない(最初は1部署、1店舗、1チームくらい)
- 成果が出るまでの期間が短い(1〜3カ月で手応えが見える)
- 紙やエクセルが多く、デジタル化による効果が分かりやすい
候補が決まったら、ノーコードツールやkintoneを使って、簡単なプロトタイプ(試作品)を作ります。このときのコツは、次の通りです。
- 最初は「必要最低限の項目」だけで画面を作る
- 紙の帳票にある項目を、いったんそのまま移す
- 現場に触ってもらいながら、「この項目は不要」「ここは選択式にしたい」と少しずつ調整する
こうして「最初の現場 DX 事例」ができると、社内で話がしやすくなります。数字としての効果ももちろん大事ですが、現場のメンバーから「前よりラクになった」「ミスが減った」という声が出ると、それ自体が次の現場DXの推進力になります。
伴走ナビでは、この最初の事例づくりを一緒に行い、うまくいったパターンを社内で展開できるよう、「どういう順番で話をしたか」「どの画面を見せると伝わりやすかったか」といった、実務寄りのノウハウもセットでお渡ししています。
失敗しない現場DXのコツとよくあるつまずき

現場DXは、やみくもにツールを入れればうまくいくものではありません。よくあるつまずきと、それを避けるためのコツを整理します。「ここを外さなければ、大きく失敗しにくい」というポイントだけをぎゅっと絞ってお伝えします。
よくある失敗パターン三つ
現場DXの失敗事例を振り返ると、内容は違っても、根っこにある原因は意外と似ています。代表的なものを三つ挙げると、次の通りです。
- ツールありきで話が始まり、「何のためにやるか」がぼやけてしまう
- 会議室のメンバーだけで決めてしまい、現場の声が十分に入っていない
- 情熱のある一人に全部任せてしまい、その人が忙しくなると止まってしまう
一つ目の「ツール先行」は、営業資料やセミナーを見て、「このツールを入れればDXできそうだ」と感じたときに起こりがちです。ツール自体は悪くなくても、現場の課題と結びついていないと、使われないアプリが量産されてしまいます。必ず「どの業務の、どんな困りごとを減らすのか」を一枚紙で言語化してから、ツール選定に入るようにしましょう。
二つ目の「現場不在」は、現場DXでは致命的です。実際に使う人の意見が入っていないと、「画面はきれいだけど、入力するのが大変」「紙のほうがまだマシ」という状態になってしまいます。最低でも、各現場から一人ずつ「代表」を決めて、検討の場に参加してもらうのがおすすめです。
三つ目の「担当者一人に丸投げ」は、どの会社でも起こりがちなパターンです。最初は熱量で進められても、その人が別のプロジェクトで忙しくなったり、異動したりすると、一気に止まってしまいます。小さくてもいいので「チーム」として進めることが、現場DXを続けるうえでとても重要です。
まとめ|現場 DX 事例から学んだポイントを自社の一歩目につなげる
最後に、本記事でお伝えしてきた内容を振り返りつつ、「じゃあうちは明日から何をするか」につなげるための一言を整理しておきます。
現場DXを進める前に確認したいチェックリスト
ここまでの現場 DX 事例を通じて見えてきた共通点は、次のようなものです。
- きっかけは「紙とエクセルがしんどい」「属人化が怖い」といった、身近な困りごとから始まっている
- 最初から大掛かりなシステムを入れるのではなく、小さな業務からスモールスタートしている
- ノーコードやkintoneを使い、「外部と一緒に立ち上げ、社内で育てる」DX内製化の形を取っている
これを踏まえて、今の自社の状況をざっくりチェックしてみてください。
- 現場の「困りごとリスト」は言葉にできているか
- 「この業務からなら始められそう」という候補は一つあるか
- 社内でDXや業務改善に興味のある人を、2〜3人思い浮かべられるか
もし一つでも「まだはっきりしていないな」と感じるところがあれば、そこが現場DXのスタート地点です。全部を整えてから始める必要はなく、「まず話をしてみる」「一つだけ試してみる」ことが何より大事です。
伴走ナビでは、
- 自社に近い現場 DX 事例のご紹介
- 現場ヒアリングや困りごと整理の壁打ち
- kintoneを使った「最初の一つのアプリ」の設計相談
といった内容について、オンラインでの無料相談を受け付けています。また、社内検討に使える資料もご用意しており、資料請求いただければ、稟議や社内説明の場でも使いやすい形でお渡ししています。
「うちの規模でもできるのか」「どの業務から手をつけるべきか」を一緒に整理するところからで構いません。もし少しでも現場DXに可能性を感じていただけたら、ぜひ一度、伴走ナビの無料相談や資料請求を通じて、自社の現場 DX 事例づくりの一歩目をご検討ください。