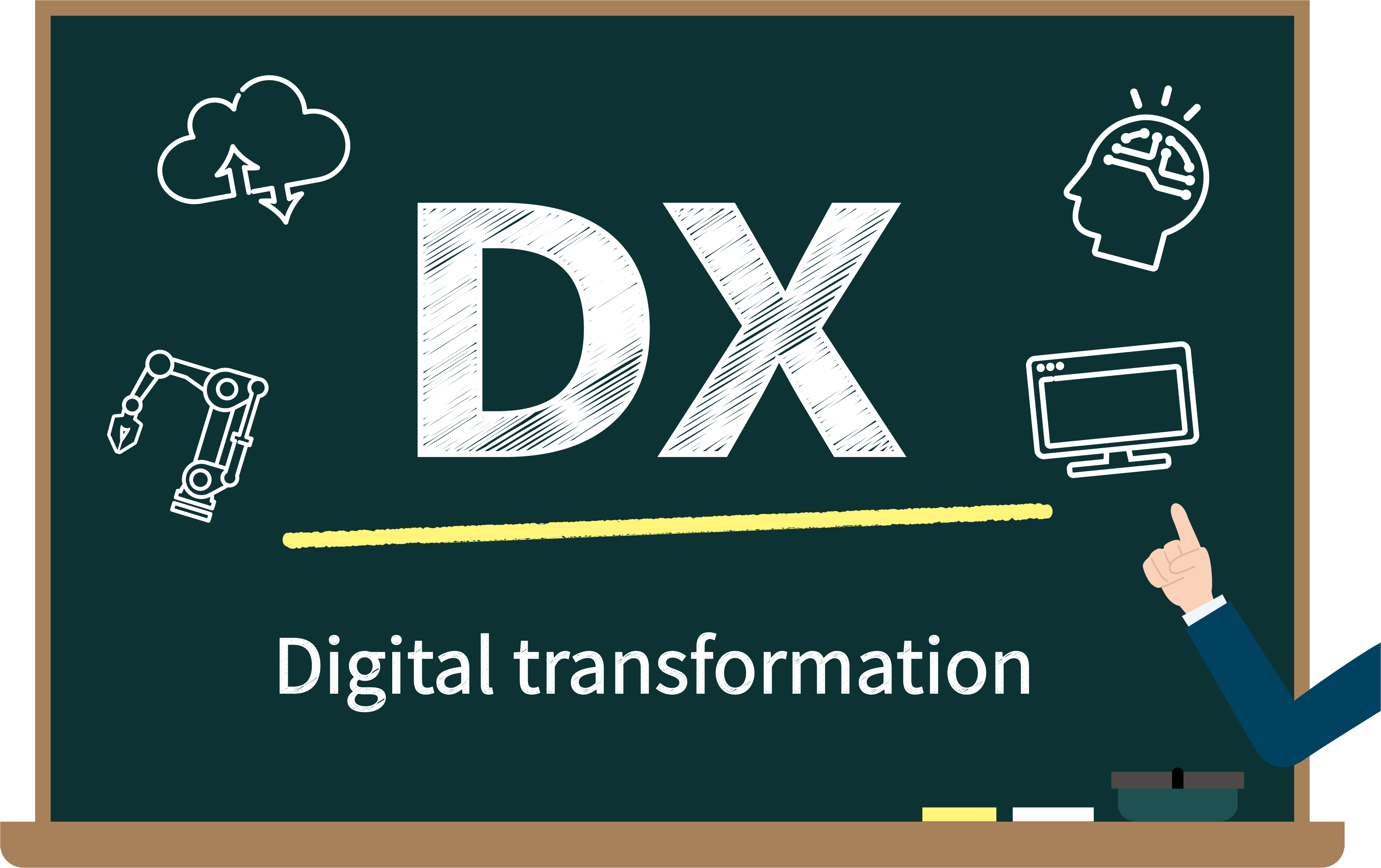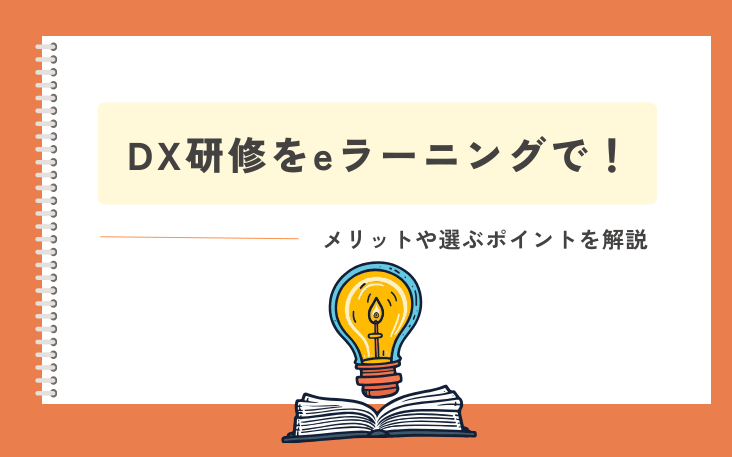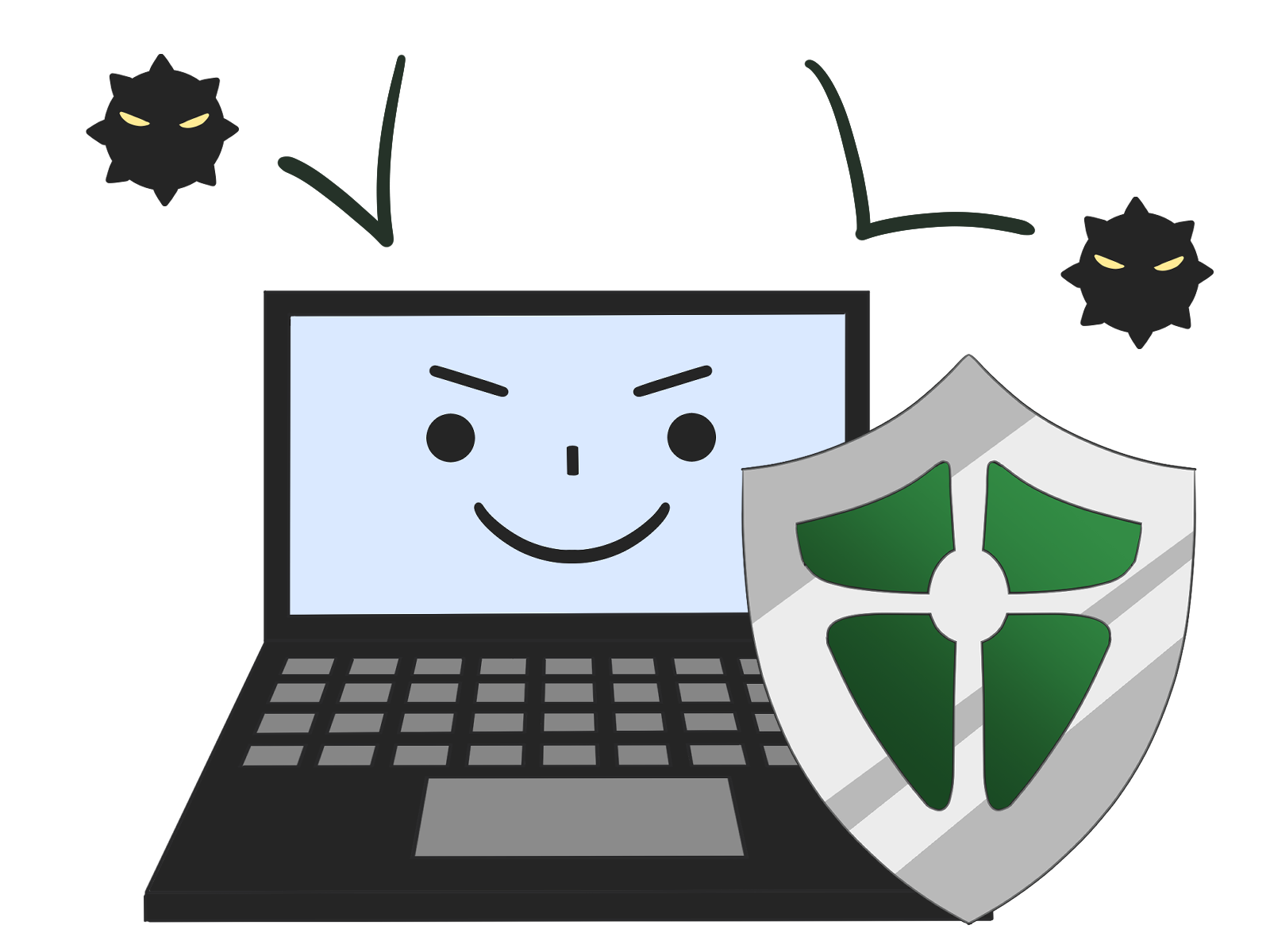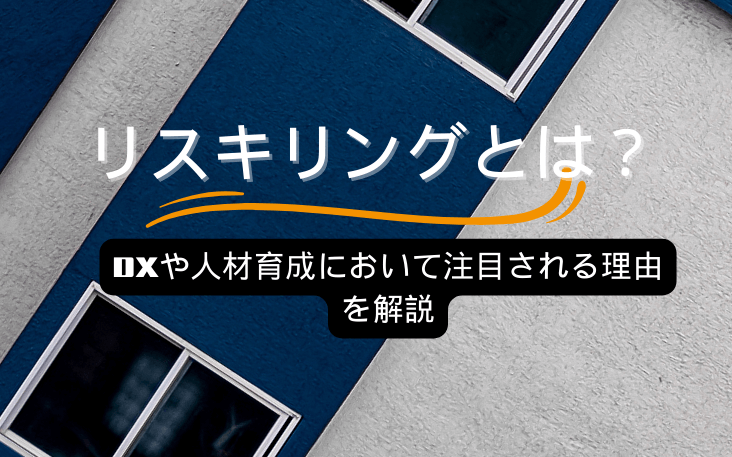医療DXとは?解決が期待できる3つの課題やメリット・デメリット、成功のポイントを解説
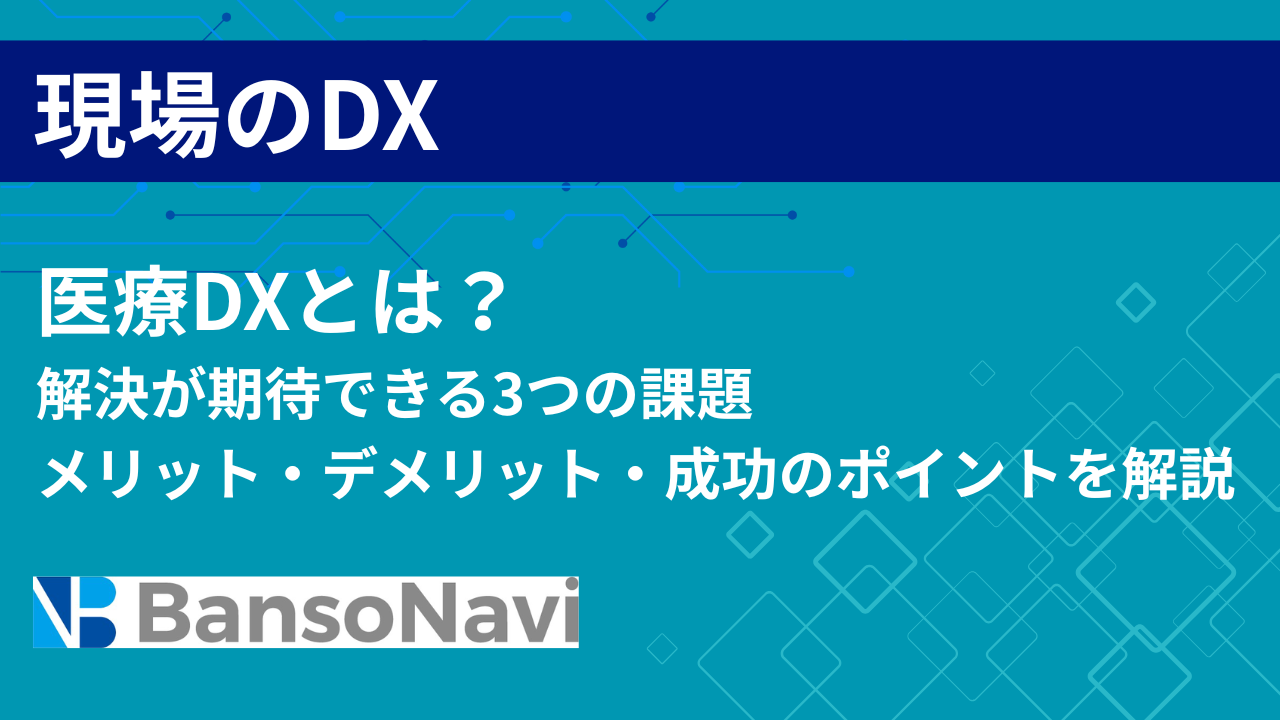
「医療DXの全体像がわからない」
「医療DXで解決できる課題や取り組み例、メリットとデメリットまで一度に知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、医療DXの意味を整理し、現場で着手しやすい領域や導入の手順、成果を測定する指標まで順を追って解説します。さらに、人手不足や待ち時間の長さ、紙中心の運用をどう改善できるかを具体的に紹介し、実務で役立つ注意点もまとめました。
医療DXを進めることで、院内の効率化や患者サービスの向上など多くのメリットを得ることが可能です。医療機関の経営者や管理職、現場担当者の方など、医療DXに関心がある方はぜひご覧ください。
医療DXに関するお悩みは「伴走ナビ」にご相談ください。要件整理から小さな実証、横展開、運用と教育まで並走します。
目次
医療DXとは?

医療DXは、保健、医療、介護の現場で生まれる情報をクラウドなどの共通基盤へ集約し、業務とシステムを標準化して、医療の質を高めながら予防を進める取り組みです。
全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準仕様への統一を軸に、病院やクリニック、薬局で生まれる記録を安全に共有し、研究や地域連携へ二次活用します。
超高齢社会では、限られた人員で診療を維持する設計が欠かせません。重複作業の削減、待ち時間の短縮、人材の有効活用を同時に進め、持続可能な医療提供体制を形にします。
全体像の整理と初期の進め方を短時間でつかみたい読者は、基礎解説も活用してください。
DX化に関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連:DX化とは?中小企業がDX化するステップを具体的に解説!
医療DXの推進で解決が期待できる3つの課題

医療DXの推進で解決が期待できる3つの課題は以下の通りです。
- 人材不足
- 長時間労働
- 紙媒体の業務フロー
各項目を解説します。
人材不足
医療需要が膨らむ一方で生産年齢人口が縮み、限られた人員で外来や入院、在宅の山場へ備える必要があります。
厚生労働省の将来推計では、2070年に総人口が8,700万人、65歳以上の高齢者は3,367万人で比率が38.7%へ上昇すると予想されています。
診療やケアを充実させるため、予約と問診の電子化、記録の自動取り込み、定型作業の機械化が求められます。
長時間労働
長時間の勤務が医療業界で解決が求められる課題です。
カルテ入力は定型文を部品化して使い回し、音声入力を取り入れることで効率化できます。検査や処置は一度に集中させず、院内の移動が少なくなるよう順番を調整すると待ち時間が減ります。
会議や引き継ぎは短い定型フォーマットに揃え、要点と決定事項のみを共有しましょう。当直明けの勤務は回数や連続勤務時間を制限し、心身の回復を優先することが大切です。
さらに、残業時間の内訳を毎月確認し、原因ごとに改善を続けることで、残業時間の削減につながります。
紙媒体の業務フロー
紙の台帳や伝票は、探す手間と書き直しの手戻りを生みます。まず紙の種類を棚卸しし、診療記録、検査依頼、処方、会計、地域連携へ分けましょう。
電子カルテと連携する受付や問診の仕組みを導入し、患者の基本情報と症状の要点を自動で取り込みます。処方や指示は標準のひな形へ置き換え、入力の揺れを減らします。
検査機器と結果を自動で連携することで、転記の手間を省けます。紙媒体の業務を段階的に減らすことは、業務の遅延や資料紛失のリスク低下に効果的です。
医療DXの4つの取り組み事例

医療DXの4つの取り組み例は以下の通りです。
- オンライン予約・問診の導入
- オンライン診療・服薬指導
- カルテや処方箋の電子化
- ビッグデータやAIの活用
各項目の詳細を説明します。
オンライン予約・問診の導入
予約と問診を事前に済ませると、受付の混雑が下がり、診療までの待ち時間が短くなります。予約枠は診療科や検査の所要時間で調整し、初診と再診を分けましょう。
問診では、症状の発生時期、痛みの強さ、既往と内服、アレルギーをあらかじめ作成したフォーマットの項目で集めます。入力内容は電子カルテへ自動で反映し、重複入力を避けます。リマインド配信で未受診を防止し、無断キャンセルの抑制に効果的です。
オンライン予約・問診の導入後は受付の滞在時間、問診入力の完了率、無断キャンセルの率を追い、枠の配分や設問の順番を調整が必要です。
オンライン診療・服薬指導
通院が難しい患者に対しても、オンライン診療・服薬指導で支援が可能です。診療は映像と音声で行い、本人確認と保険情報を事前に確認します。
症状の変化や検査結果に基づき治療を継続し、処方は電子的に薬局へ送る仕組みです。薬剤師は服薬状況や副作用の有無を聞き取り、生活の工夫も合わせて助言します。
再診や慢性疾患の継続ケアで効果が出やすく、通院負担の軽減や中断の抑制が期待できます。
カルテや処方箋の電子化
記録の電子化は、情報の一元管理と検索の速さに直結します。診療録は構造化した項目と自由記載を並べ、検索に強い形へ整えます。
処方は標準のセットを用意し、投与量や日数の誤りを減らします。検査結果は機器から自動で取り込み、画像はビューアで参照しやすくします。監査対応や保管の負担も軽くなります。電子化の段階では、紙との二重運用を最小に抑えます。
入力支援や音声入力の活用で、記録の質を保ちながら時間を短くします。権限と監査の仕組みを整え、安心して運用可能です。
ビッグデータやAIの活用
ビッグデータやAIを活用し、診療、検査、投薬、会計、地域連携に散らばるデータを整理して、判断に役立つ形へまとめましょう。再入院の予測や検査の優先度づけ、読影の支援など、現場の負担を減らす目的で活用可能です。
また、AIを活用した需要予測や医薬品の在庫最適化、人員配置の最適化など、経営面での意思決定の効率化も期待できます。臨床で得たデータを、研究開発や公衆衛生での二次利用に活用することで、社会全体の健康増進にもつながります。
医療DXを進める4つのメリット

医療DXを進める4つのメリットは以下の通りです。
- 現場の業務効率化
- 患者体験や医療サービスの質向上
- コスト削減と経営改善
- 災害時対応の強化
各メリットを詳しく説明します。
現場の業務効率化
医療DXを進めることで、現場の業務効率化が大きく期待できます。ワークフロー化やシステム間の連携により、診療や事務の流れをスムーズにし、無駄な作業を削減できます。
さらに、カルテや処方箋の記載を自動化することで、データの転記や集計にかかる負担を減らし、入力ミスの防止にもつながります。その結果、医師やスタッフは本来注力すべき診療や患者対応といったコア業務に集中できるようになります。
また、情報の変更履歴や記載内容を追跡しやすくなるため、内部統制の強化や情報の信頼性向上にも貢献します。
患者体験や医療サービスの質向上
医療DXは、患者体験や医療サービスの質向上にも貢献します。情報共有が迅速になることで、診療科や担当者が変わっても適切で切れ目のない医療提供が可能になります。
また、オンラインでの手続きや事前入力、情報共有の仕組みにより、来院時の待ち時間や記入の負担が減り、患者の満足度向上につながります。
遠隔診療を活用すれば、通院が難しい患者でも医療へのアクセスが改善され、継続的な治療や服薬支援を受けやすくなります。
コスト削減と経営改善
医療DXの導入は、コスト削減と経営改善にも直結します。定型業務の自動化や効率化により、システム運用や改修にかかるコストを抑えられます。
また、紙媒体での書類作成や保管、郵送に必要な費用を削減できる点も大きなメリットです。さらに、データを活用することで医薬品の原価把握や収益管理が効率化され、経営状況を正確に把握しやすくなります。
経営判断のスピードと品質が高まり、持続的な経営改善につながります。
災害時対応の強化
医療DXは、災害時の対応力強化にも大きな効果を発揮します。クラウドに医療データを保管することで、システム障害や災害によるデータ消失のリスクを抑えられます。
在宅や遠隔から業務を継続できるため、災害時でも医療提供の中断を最小限に抑えることが可能です。
ライフラインである医療事業においては、DXを活用した事業継続計画(BCP)の強化が重要となり、安定した医療体制の確保につながります。
医療DXを進める4つのデメリット

医療DXを進める4つのデメリットは以下の通りです。
- セキュリティ・個人情報保護に関する懸念
- デジタルツールの導入コストや運用にかかる負担
- 医療従事者のITリテラシー不足
- 患者のデジタル格差
各項目を解説します。
セキュリティ・個人情報保護に関する懸念
医療DXによる災害時対応の強化にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。
医療情報をクラウドなどで集中管理することで、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まる可能性があります。
強固な技術的対策や明確な運用ルールの整備に加え、利用者へのセキュリティ教育を徹底することが欠かせません。また、デジタルシステムを提供するベンダーや、連携先の企業におけるセキュリティ対策の確認も必須となります。
デジタルツールの導入コストや運用にかかる負担
医療DXの推進には、デジタルツールの導入コストや運用負担といったデメリットもあります。
新しいシステムの初期投資や月額費用に加え、移行作業や運用体制の整備にもコストが発生するため、十分な計画が必要です。特に小規模な医療機関では費用回収に時間がかかり、投資判断が難しくなるケースも少なくありません。
補助金制度の活用や段階的な導入を検討し、財務負担やリスクを抑える工夫が求められます。
医療従事者のITリテラシー不足
新しい仕組みは、慣れるまで負担を感じやすいです。学びの場を短い単位で用意し、機能を段階で解禁します。
診療や看護、検査、会計の流れに沿った教材を作り、端末操作の迷いを減らします。質問の窓口を一本にし、同じ疑問が何度も起きないよう記録します。
操作の定着を早めるため、現場のリーダーを育て、困った場面へすぐ駆けつけられる体制を整えます。評価や表彰も取り入れ、学びを日常へ根づかせます。
患者のデジタル格差
端末や通信の環境、年齢や障がいなどで差が生まれます。窓口では紙の申込や口頭での対応を並行し、支援が必要な人に声をかける必要があります。
手順は図と短い文で示し、画面の文字やボタンは大きめにしましょう。代理の申込を認める仕組みを整え、家族や地域の支援者とも連携します。
説明会や動画の案内で、利用の不安を和らげます。苦情や提案の記録を毎月見直し、改善の順番を決めます。
医療DXを成功させるための2つのポイント

医療DXを成功させるための2つのポイントを紹介します。
- スタッフ教育や運営体制の整備
- 段階的なシステム導入
各項目を説明します。
スタッフ教育や運営体制の整備
医療DXでは、スタッフ教育や運営体制の整備が必要です。教育は役割ごとに分け、短い時間で繰り返します。最初は基本の操作と安全の考え方を統一し、次に診療科ごとの工夫を共有しましょう。
相談の窓口と判断の基準を一本化し、迷いが現場で止まらないようにすることも大切です。推進の会議は定例化し、数字と現場の声を並べます。学びの記録を残し、異動や新任へ素早く渡します。
評価や表彰も取り入れ、挑戦が続く雰囲気づくりを徹底しましょう。
段階的なシステム導入
段階的なシステム導入が医療DXでは重要です。予約や問診から始め、次にカルテや検査連携、最後に地域連携や分析へ進む流れが一般的です。
小さな実証でDXの経験を積み、成功の設計をひな形にして展開しましょう。契約や設定は共通の考え方で揃え、拠点が増えても運用が揺れません。導入の前後で指標を計測し、数字で判断します。
医療DXを進めるなら「kintone」の導入がおすすめ

現場の業務を止めずに情報を一元化したい医療機関にとって、kintoneの導入がおすすめです。ノーコードで業務に合うアプリを素早く作成可能です。
受付や問診、検査依頼、会計、職員連絡を業務アプリとして使用可能です。申請と承認の業務フローの効率化が可能で、外出先からの入力や確認にも対応し、当直中の連絡や申し送りの抜けを減らせる点もkintoneのメリットとして挙げられます。
他システムと連携すると、二重入力や記載ミスを防止でき、薬剤や検査の記録、在庫の台帳との連携では、薬剤や機器の在庫を探す時間が減り、業務負担を軽減可能です。
一方で、医療特有の権限設計や院内ルールへの合わせ込みでは壁が出やすい点に注意が必要です。全体設計や移行を見据えた高度な要件は、専門家による支援をおすすめします。
kintone伴走パートナーの必要性に関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連:kintone伴走パートナーの必要性|DX事例集とともに解説
医療DXに関するお悩みは「伴走ナビ」にご相談ください

医療DXは、クラウドや電子カルテ、オンライン診療、AI活用を組み合わせ、紙と転記を減らし、待ち時間や手戻りを縮める取り組みです。
人材不足や長い拘束、紙中心の運用に悩む医療機関でも、段階導入で負荷を抑えながら前へ進めます。反面、情報保護や導入費、職員の習熟、患者のデジタル格差といった論点も避けられません。
医療DXに関するお悩みは「伴走ナビ」にご相談ください。要件整理から小さな実証、横展開、運用と教育まで並走します。